大坂冬の陣後、豊臣方はいかなる条件で徳川方との和睦に合意したのか
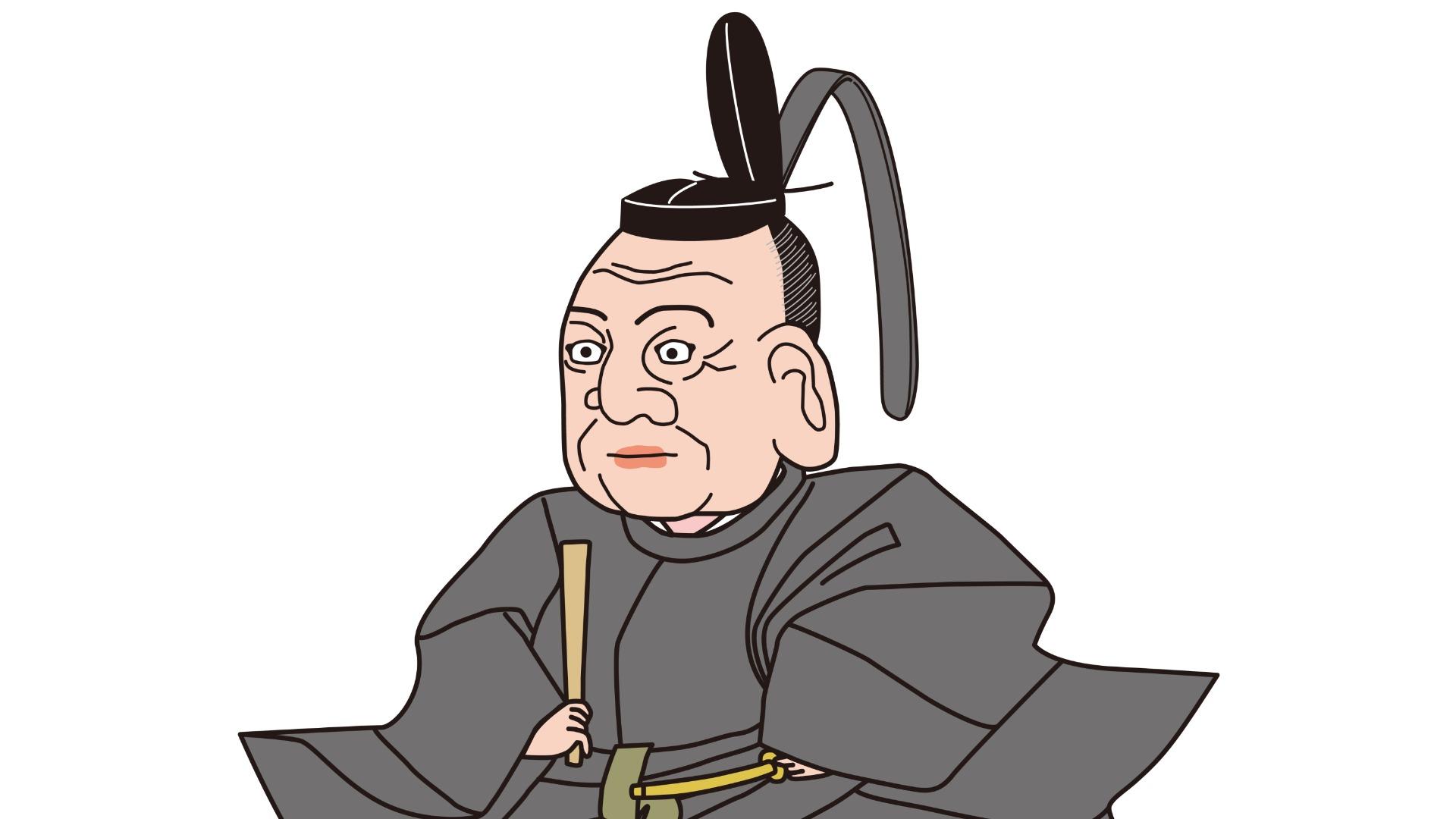
大河ドラマ「どうする家康」では、大坂冬の陣の後の和睦の模様が描かれていた。豊臣方はいかなる条件で徳川方との和睦に合意したのか、詳しく考えてみよう。
慶長19年(1614)、一連の大坂冬の陣の攻防を終えると、両軍から和平の気運が生まれた。豊臣方の交渉役を務めたのは、常高院(京極高次の妻)である。
一方の徳川方の交渉役は本多正純と阿茶局(家康の側室)が務め、交渉の場所は京極忠高(高次の子)の陣となった。以下、『大坂陣日記』をなどの史料を交えつつ、和睦の交渉の過程を確認しよう。
同年12月18日、常高院は高忠の陣中で、阿茶局・本多正純と交渉の場に臨んだが、このときは話がまとまらなかった。その理由は、定かにされていない。
翌19日に再度交渉の席が設けられ、①大坂城の本丸を残して、二の丸、三の丸の堀を埋めること、②織田有楽、大野治長が人質を出すこと(淀殿が江戸に行くのは困難なので)という二案が豊臣方に提示された。豊臣方はこの案を持ち帰り、検討した結果、この条件で和睦に応じることになった。
同月20日の夜に早速、大野治長の子・治徳と織田有楽の子・尚長の2人が、本多正純のもとへ徳川方の人質として送られた。同月21日には、和睦を結んだ証として、茶臼山で徳川方と豊臣方で起請文が取り交わされることになった(『大坂冬陣記』)。豊臣方からは、木村重成、郡主馬と織田有楽、大野治長の使者の面々が交渉のテーブルに着いた。
起請文の内容は、①籠城した牢人たちについては、その罪を問わないこと、②秀頼の知行は、これまでのとおりとすること、③母・淀殿は、江戸に滞在する必要がないこと、④大坂城を開城する場合は、いずれの国であっても、望みどおり知行替えを行うこと、⑤秀頼に対して、表裏(裏切り)の気持ちがないこと、の5点に集約されよう。
①については、のちに問題になるが、実質的には牢人衆を大坂城外へ退去することを求めたと考えられる。牢人衆が大坂城に残っていることは、豊臣家に戦闘を継続する意志があると思われたようだ。
起請文は牛王宝印の裏に誓紙として書かれ、将軍家の血判が捺され、木村重成、郡主馬の両名が持ち帰った。このとき木村重成は、家康の血判が薄いと指摘し、再度指を切らせて血判を押させたという。
これは非常に有名な逸話であるが、史実か否かは検討を要しよう。翌22日、阿茶局と板倉重昌が大坂城に赴き、秀頼と淀殿の起請文を受領した。これにより、両者の和睦は締結されたのである。
しかし、実際の和睦の条件はこれだけに止まらず、大坂城の惣構の破却、堀などの埋め立ても条件となっていた。この点に関しては、改めて取り上げることにしよう。
主要参考文献
渡邊大門『誤解だらけの徳川家康』(幻冬舎新書、2022年)










