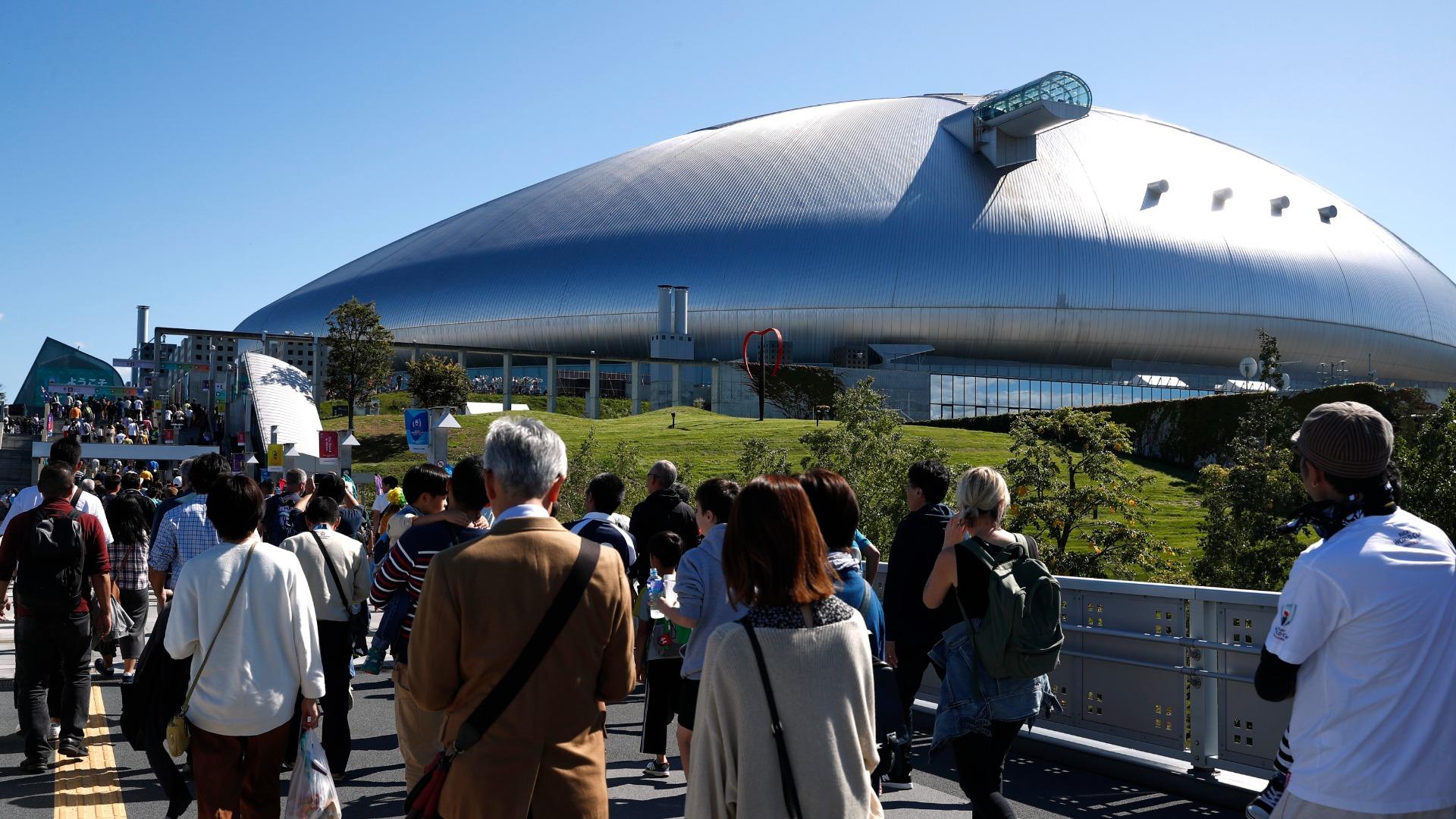広辞苑から消えた名棋士の名

広辞苑掲載の囲碁・将棋関係者は少ない?
「琴棋書画」という言葉があります。「棋」という字は囲碁、将棋、いずれの意味もありますが、この場合は、囲碁のことです。
2018年1月12日に出版された『広辞苑』第7版には、以下のように説明されています。
きんきしょが【琴棋書画】
(キンギショガとも)手を使う四つの芸術すなわち琴・囲碁・書道・絵画。雅人の風流韻事、士君子のたしなみとされ、画題として中国で好んで描かれ、日本でも行われた。四芸。(後略)
出典:(『広辞苑』第7版)
琴(音楽)、囲碁、書道、絵画。これらは四芸としていずれも立派な芸術であるのに、比較すると、現代の日本では、囲碁だけ文化して認められていないのではないか? 囲碁の中山典之七段(1932-2010)は、そう嘆いていました。
ここに一つの例を示そう。岩波書店の広辞苑と言えば、日本を代表するほどの権威のある辞書であるが、その項目に、古今の第一人者とされる本因坊道策の名がなかった。棋聖秀策の名も出ていない。もちろん木谷実の名はない。
ところが、音楽家や書家、画家の名前となれば、私などが聞いたことがない名前まで、ゴマンと出ている。琴棋書画にたずさわる者としては、まことに不公平であるから、事あるごとに岩波さんに抗議してきた。私は岩波新書で『囲碁の世界』(引用者注:1986年刊、岩波新書)という本を書いたことがあり、岩波さんとは多少の縁がある。
出典:(中山典之『昭和囲碁風雲録』[上]2003年、岩波書店刊)
ここで中山七段が嘆いているのは、『広辞苑』第4版(1991年刊)までの話です。
本因坊道策、それから本因坊跡目秀策は、江戸時代の碁打ちで、史上最強を論じる際には、必ずと言ってよいほどに名が挙げられる強豪です。
また木谷實(1909-75)は「昭和の棋聖」と呼ばれた呉清源(1914-2014)のライバルです。本因坊秀哉名人の引退後の相手として、川端康成『名人』にもその対局姿を描かれました。門下からは、大竹英雄、加藤正夫、石田芳夫、武宮正樹、小林光一、趙治勲、小林覚など、現代を代表する数多くの英才が輩出されました。
道策、秀策、木谷ほどの打ち手が『広辞苑』に掲載されていないとは、どういうことか。なるほど、囲碁を愛する人にとっては、腹立たしいことだったのでしょう。
あまりにうるさい、と言うのだろう。1998年に広辞苑が第5版に改まるに際し、私に囲碁の項目を担当して欲しいという依頼があった。私の主張が漸く入れられるのが嬉しいのでお引き受けし、道策、丈和、秀策、秀栄、元丈、知得、道知、秀和、幻庵などなど、名棋士の項目をこしらえて差し出したのだが、許可されたのは、道策と秀策。それと丈和先生をもぐり込ませるのがやっとだった。
広辞苑には、人名の採否を決定する委員会があり、その議決賛同がなければ辞書に登場しないのである。だから、大学者の先生方が碁を知らなければそれまでの話。碁は日本文化、ないし、日本の芸能、芸術として認められていないのである。
しかし、まあ、今回はこれで良しとしよう。たった三人だけだが、棋聖と言われた道策、丈和、秀策が広辞苑に登場した。ゼロと三とでは限りない差があるのだから……。
出典:(中山典之『昭和囲碁風雲録』[上]2003年、岩波書店刊)
囲碁を愛してやまない筆者の、熱い筆致です。近年、こうした一文は、将棋界の方では、なかなか見られなくなったように感じます。
補足をすると、第5版以前の第4版までに、囲碁の棋士の名が一人も掲載されていなかった、というわけではありません。筆者が確認した限りでは、本因坊算砂、安井算哲(やすい・さんてつ)、渋川春海(しぶかわ・はるみ、しゅんかい)、本因坊秀哉の名は、早くから見つけることができます。
渋川春海は碁打ちとしても知られ、広辞苑にもその旨が記されています。しかしそれ以上に貞享暦 (じょうきょうれき)を作った暦学者として有名で、高校の日本史でも、その名を習うことがあるでしょう。最近では、冲方丁(うぶかた・とう)さん作の時代小説のベストセラー、『天地明察』の主人公としても脚光を浴びました。
安井(保井)算哲は、囲碁四家の安井家の人で、江戸時代初期を代表するトップクラスの打ち手。渋川春海は、その長子に当たります。
一方で、将棋の指し手は、どれぐらい『広辞苑』に項目を立てられていたでしょうか? 筆者が調べた限りでは、長い間に渡って、わずかに関根金次郎(13世名人)だけが立項されていました。大橋宗桂(1世名人)などの名もありません。
第4版に至ってようやく、阪田(坂田)三吉が追加されています。将棋史上最も有名な人物といえば、現在は羽生善治かもしれません。しかし以前はおそらく、演劇や映画で取り上げられ、歌にもうたわれた、阪田三吉だったでしょう。そのクラスでもなかなか立項されなかったとなれば、それはいささか、ハードルが高すぎるのではないか、と思われます。
囲碁と将棋は、徳川家康の時代、本因坊算砂と大橋宗桂以来、並び称される分野です。中山七段は、囲碁の打ち手の取り上げられ方が少ないと嘆いていますが、将棋の方はもっと少なかったのですよ……。将棋愛好者としては、そう苦笑したくなります。
中山七段が岩波書店に強力にプッシュしたためか、第5版からは、囲碁に関する人物の掲載が増えました。そして、そのおかげでもあるのでしょう。将棋に関する人物の掲載も増えました。第6版までに取り上げられている人物の一覧は、過去の記事にリストアップしました。
広辞苑にも記された名棋士8人(Yahoo!ニュース 2018年1月8日)
https://news.yahoo.co.jp/byline/matsumotohirofumi/20180109-00080287/
▲大橋宗桂(1555-1634、初代)
○本因坊算砂(1559-1623、「本因坊」の項)
○中村道碩(1582-1630、世襲名「井上因碩」の項)
○安井算哲(1589?-1652、初代)
○渋川春海(1639-1715)
○本因坊道策(1645-1702)
▲伊藤宗看(1706-61、三代)
○本因坊丈和(1787-1847)
▲天野宗歩(1816-59)
○本因坊跡目秀策(1829-62)
▲関根金次郎(1868-1946)
▲坂田三吉(1870-1946)
○本因坊秀哉(1874-1940、「本因坊」の項)
▲木村義雄(1905-86)
▲升田幸三(1918-91)
▲大山康晴(1923-92)
囲碁8人。将棋8人。
第6版から第7版にかけては、筆者がアプリで検索して、確認した限りでは、変化はありませんでした(もし増減あれば、ご教示いただけると幸いです)。囲碁界で「昭和の棋聖」と称された呉清源は、まず確実に追加されるものと予想していましたが、それはハズレだったようです。
消えた名棋士の名
ところで、項目は立てられてはいませんが、地の文において、将棋指しの名が掲載されている個所はあります。まずはこちらです。
いしだりゅう【石田流】
将棋の駒組みの一つ。江戸初期の盲人棋士石田検校の創案。後手の場合、飛車は3筋の四段目、その背後に桂をおき、端1筋の三段目に角をおく構えが正規の組方。
出典:(『広辞苑』第7版)
検校(けんぎょう)とは、「盲人の最上級の官名」(『広辞苑』第7版)のことです。古来、将棋界には、盲目の強豪が存在してきました。石田検校は、それほど強いというわけではなかったようですが、「石田流」の創始者として、その名を永遠に残しました。他には幕末、天野宗歩と好勝負を演じた石本検校などが有名です。
『広辞苑』で「検校」と名のつく人は、筆者が数えた限りでは、15人。そのほとんどが、琴や三味線など、音楽に秀でた人物です。
さて、「石田流」の他にもうひとつ、将棋関係者の名が記されている項目を見つけました。それが第5版(1998年)から立項された「永世名人」です。(以下、引用中、漢数字を算用数字に直した個所があります)
えいせいめいじん【永世名人】
将棋棋士の名誉称号。5期以上名人位を保持した者に引退後贈られる。第14世名人木村義雄以前は一世一代。第15世名人は大山康晴、第16世は中原誠一〇段。
出典:(『広辞苑』第5版)
「中原誠一〇段」(10段)という表記は、正確に記せば「十段」。十段は、九段の上に制度的に設けられた段位、というわけではなく、かつて存在したタイトル戦の名称です。中原誠16世名人は、当時「永世十段」の称号を名乗っていたので、このような表記となったのでしょう。
『広辞苑』では、日本人の場合、どれだけ著名であっても、存命中には項目を立てない、という原則があります。なぜか。初版(1955年刊)の編集中、存命中の文豪の志賀直哉を入れるかどうか、もし入れるとしたら、他にどの文豪も入れるべきか、という議論となり、収拾がつかなくなって、最後は編集主幹の鶴の一声で、日本人は物故者のみと決まったのだそうです。
なるほど、この項の地の文にリストアップされていくという方式を取れば、中原誠16世名人のように、存命中の大棋士でも、『広辞苑』に掲載されます。第6版(2008年)では、そのリストに、谷川浩司現九段の名が加わりました。
えいせいめいじん【永世名人】
将棋棋士の名誉称号。5期以上名人位を保持した者に引退後贈られる。第14世名人木村義雄以前は一世一代。第15世名人は大山康晴、第16世は中原誠、第17世は谷川浩司(襲名は引退後)。
出典:(『広辞苑』第6版)
第6版刊行前の2007年には、森内俊之現九段が18世名人の資格を得ました。時期的には間に合ったと思われれるのですが、第6版ではその名は加えられませんでした。
さらに翌2008年には、羽生善治現竜王が19世名人の資格を得ました。
では、2018年に発行された第7版。「永世名人」の項は、どうなったでしょうか?
えいせい‐めいじん【永世名人】
将棋棋士の名誉称号。5期以上名人位を保持した者に通常は引退後贈られる。第14世名人木村義雄以前は一世一代。
出典:(『広辞苑』第7版)
ああ……。森内18世、羽生19世の名が加えられていません。それどころか、逆に大山15世、中原16世、谷川17世まで削られています。1992年に亡くなった大山15世は、別に項が立てられています。しかし、中原16世、谷川17世の名は、『広辞苑』からは当面、消えてしまった……。将棋愛好者の一人としては、なんとも残念な思いがします。
最近の『広辞苑』は、10年ごとに改訂がおこなわれています。これから10年後は、2028年。もしそのタイミングで、『広辞苑』第8版が改訂されるとすれば、「永世名人」の項は、どう変化しているでしょうか。またそれまでに、新たな永世名人は誕生しているでしょうか。