競馬の仕事を辞めようと考えていた私の気持ちを翻意させた”競馬の神様”の言葉とは……

専門紙に就職も、辞めようと決心
今回は私、平松さとしのお話に少々お付き合いいただきたい。
私は平成になってすぐ、競馬専門紙「ケイシュウNEWS」に就職した。それまでは一競馬ファン。今で言うオタクに近いファンだった。最近のファンには信じられないかもしれないが、私の記憶が正しければ当時、関東地区で関西のレースをリアルタイムで見られるのは重賞かメインレースに限られていた。それ以外のレースはテレビ中継もなかったし、競馬場でも場外馬券売り場(WINSなんていうお洒落な名称もまだなかった)でも見られなかった。そもそも場外馬券売り場での馬券発売は発走1時間前が締め切り時刻。締め切った時点と最終オッズに大きな隔たりがある事も茶飯事だった。
そんな中、私は関西の知人に頼み、テレビで流れる関西のレース映像を録画してもらい、毎週、郵送してもらっていた。
そんなオタクが競馬専門紙に入社したわけだが、私が採用された理由はバイクの中型免許を所持していたから。だからまずは営業として採用された。営業といっても販路の拡大などが業務内容ではなかった。毎週の傾向を見ながらどの販売所に新聞を何部配布するか?などを判断。金曜、土曜の新聞発行日にオートバイのアルバイトの子らにその新聞を配達させる。売り切れそうになれば待機しているアルバイトに新たに持たせて補充させる。そんな業務をこなしていた。
競馬が大好きで就職した自分には正直つまらない仕事だった。そのため「辞めよう」と思っていたから仕事ぶりもいい加減。自ら新聞を競馬場まで配達し、帰社せずにそのまま競馬に熱中し仕事をサボる事もたびたび。自分が上司だったら雇いたくない部下という振る舞いを繰り返していた。
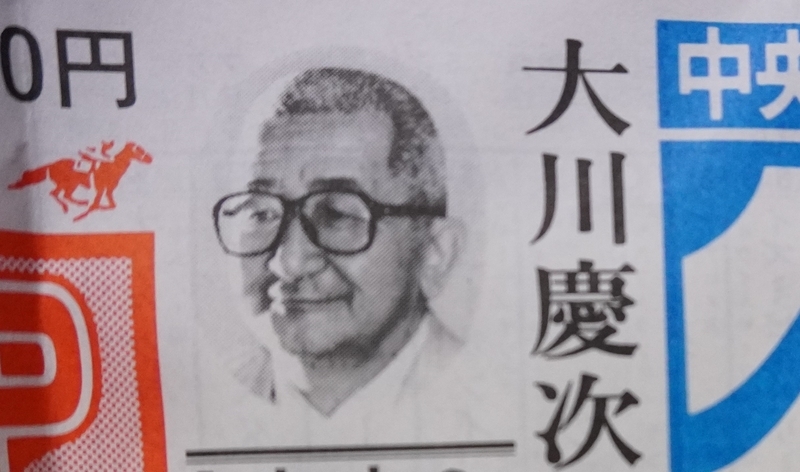
競馬の神様から言われた衝撃的な言葉
ただ、週に1、2日だけそんな会社にも足を運びたくなる日があった。
当時「競馬の神様」と言われていた競馬評論家の大川慶次郎さんが、毎週1日か2日だけ来社。営業部と同じフロア、私から見る事の出来る席に座り、資料に目を通しつつ予想をしていたのだ。
大川さんが亡くなったのは1999年だからもう20年も前。若いファンには大川さんを知らない人も多いだろう。大川さんは毎週、競馬の解説者としてテレビに出演。自分の信念に従った予想は歯に衣着せぬという表現がぴったり。反面、好々爺然とした人の良さそうなおじいちゃんといった出で立ちで、若い競馬ファンからも人気を得ていた。
そんな大川さんと週に1、2回、競馬の話を出来るのが会社での唯一の楽しみだった。しかし、同時にそれが唯一の楽しみなのだから辞めたいと思うようになるのも自然な流れだった。トラックマンや記者と話す機会もほとんどないため「元々競馬ファンだった程度の自分の知識ではそういった先輩方には通用しないのだろうな……」という気持ちもあった。そんな事もあり、いよいよ真剣に退職を考えるようになった。
「会社を辞めてまた以前のようにファンとして競馬を楽しもう」
そう決心した矢先、競馬の神様の口から私の人生を大きく変えるひと言が発せられた。
それは1990年4月下旬の事だった。父トウショウボーイ、母ハギノトップレディの関西馬ダイイチルビーが初めて東京競馬場のレースに出てきた時の事だ。後に安田記念(G1)を制す名牝だが、この時点では3戦2勝。この関西馬について、大川さんが私に向かい、次のように聞いてきたのだ。
「平松君、この馬はどんなタイプの馬なんだい?」
これは衝撃的な一言だった。先述したように自分の知識ではプロには通用しないのでは?と思い、退職も考えていたというのに、まさかの競馬の神様から質問を受ける形になったのだ。当時は関西のレースを見るのも容易ではない時代。そんな中、私が毎週関西からレースビデオを送ってもらっているのを知っていて、そういう質問をしてきたわけだが、これは私にとって大きな自信になった。「大川さんが質問してくるなら、自分の知識でやっていけるのではないか?!」と考えるようになり、辞める気持ちにブレーキがかかったのだ。
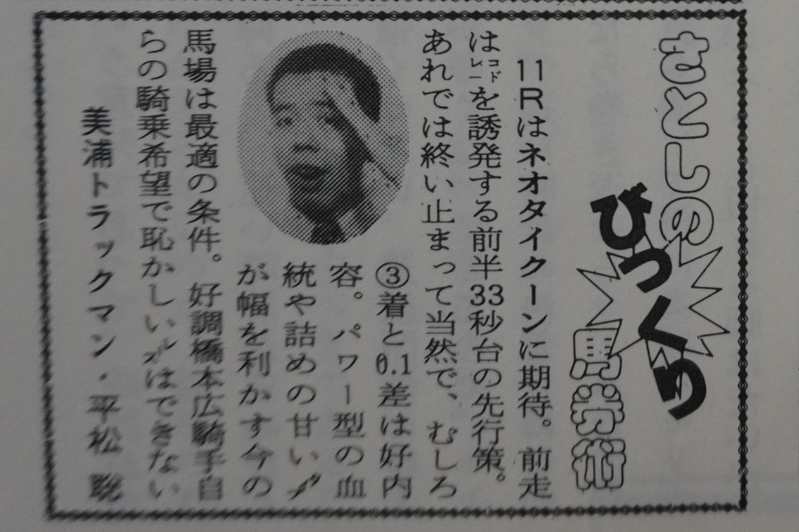
大川さんのお陰で現在の競馬ライターに
その後は大川さんが出掛けるたびにカバン持ちとして指名をしてくれるようになった。一緒に移動しながら競馬の話をするのが楽しかった。そうこうするうち、編集部から声がかかり異動する事になった。更に1年後にはトラックマンとなり、約10年働いた後、フリーになったのだが、編集時代には次のような話があった。
93年3月の毎日杯(G3)。関西本紙の予想印をつけていた私はこのレースで人気薄のメジロモネに◎を打った。すると、大川さんからすぐに電話がかかってきた。曰く「穴を狙い過ぎ」と言われた。結果12着に敗れると多くの編集部員から叱責されるのだが、レース前に言ってきたのは大川さんだけだった。
また、この話には後日談があり、同馬はこの年の暮れのウインターS(G3)で人気薄ながら2着に好走する。するとまた大川さんから電話が入った。
「重い印を打つのが半年、早かったね。僕は平松君の顔が頭に浮かんで印を打てなかったよ」
この時、声をかけてくれたのも大川さん1人だけだった。
私が現在、この仕事を続けていられるのは、助けてくれた沢山の人達のお陰だが、そのうちの1人、それも重要な存在として、大川慶次郎さんがいたのは間違いない。
大川さんが亡くなったのは1999年の12月21日。明日で丁度20年となる。競馬の神様は雲の上でアーモンドアイにどんな印を打っているだろうか……。

(文中一部敬称略、写真撮影=平松さとし)










