これはテレビ界への劇薬、そしてエール。忖度なしにありのままのテレビを映す『さよならテレビ』

常に議論を巻き起こすドキュメンタリー映画を発表し続けている<東海テレビ>。通算12作品目の劇場版となる『さよならテレビ』は、テレビ放送がされた時点から、とりわけ全国のテレビマンの間で瞬く間に噂が広まった1作だ。
東海テレビの開局60周年記念番組として製作された本番組は、同局の報道ディレクターが自社の報道部にガチの真っ向勝負でカメラを向ける。いままでありそうでなかったこの挑発的な試みは、視聴者はもちろん全国のテレビ業界内で話題騒然。東海地方限定の放送ながら、番組を録画したDVDが全国の映像制作者に密かに出回っているとの噂が流れた。
業界内に出回るDVD。それはテレビマンのテレビへの危機感のひとつの現れ
手掛けた(仕掛けた?)のは、『ヤクザと憲法』の土方宏史監督と阿武野勝彦プロデューサー。まず、テレビ放送時の喧騒をこう振り返る。
土方「個人的には驚きはあまりなかったですね。テレビが題材なので、テレビ業界で出回るのは、あることだろうと。逆に、もし他局がこういう作品を作ったら自分もみてみたいと思ったでしょうし。ただ、DVDが『裏ビデオのように出回っている』と聞いたときは、なんだか悪いことしてるみたいで、『自分たちはそんな悪いことしてない』と思いましたけど(笑)、まあテレビマンだったら興味持つだろうな、ぐらいでした」
阿武野「僕は名古屋ローカルの番組が、こんなに広がるのかと、びっくりしましたね。テレビマンの間に、やはりテレビについて危機意識がある。そのひとつの表れかなと。
ですから、この番組をきっかけに豊かな論義をしてもらえるなら、出回ることはいいことだと。ただ、敵失やあらさがし、それを見て嗤う程度なら、ダビングして回すなど悪趣味だと。そうそう、『裏ビデオ』ではなく、僕は『密造酒』と言ってほしいと。一人きりの自慰のためじゃなく、隠れてこっそりみんなで飲んで、ちゃんと酔う、そういう見方なら、どうぞ、ダビングしてください、と。
これは自分たちも含めてですけど、テレビ業界にいる人間たちは、このままでは行き止まりになる、だけれども、どうすればいいかわからないというような閉塞感の中にいるような気がします。
その中で、『さよならテレビ』をどう受け止めるのか。これを契機に、どんどんと意見が出て、テレビの在り方について有効なキャッチボールをできる人がテレビ業界にどれだけいるのか知りたいし、出てきてくれることを期待したい。
僕たちは包み隠さず丸裸になってみましたが、密造酒を飲んだテレビマンが、それをどれだけ真剣に受け止めてくれるか、気になりましたね」
こうした反響がある中、今回改めて劇場版にした理由をこう明かす。
阿武野「『さよならテレビ』の取材対象はテレビですが、今の社会を感じることができるはずです。テレビの内輪話にとどまる内容で終わっていない。テレビマンやメディア関係者を対象として作ったわけではないですしね。映っているのは東海テレビであり、その局員であるわたしたちの日常をおみせするのですが、この時代を考える、これからの時代を模索するための大事な題材でもあると思っています。働き方、組織と個人、階層社会、労働疎外…、時代は進んだのに、どうしたことだろう、ということがあると思います。」
土方「テレビ業界で話題に、という話ですけど、ディレクターとしては、もちろん広く一般の人たちにみてもらいたいという気持ちで作っています。
まず、テレビを含めたいまのメディアがどんな状況にあるのかを知ってもらいたい。
あと、さきほど阿武野が触れた社会構造の点でいえば、会社や学校などなにかしらの組織に入ってる人にとっては身につまされる場面があるんじゃないでしょうか。集団内での立ち位置や役割で悩んでいる人は多いでしょうから。ここ最近、経営サイドと現場の軋轢や、本社とフランチャイズオーナーの間のトラブルなど、組織をめぐるゴタゴタがずいぶん表沙汰になったように思うんです。
なので、みた人が自分の身になんとなく照らし合わせて、働き方や他者とのコミュニケーションについて、少し考える機会になればとの思いがありました」
忖度抜きに自局員にカメラを向け、テレビを斬る
正直なことを言うと、これまでも手ぬるいことはしていない東海テレビであるから大丈夫と思いつつも、ひとつ危惧していることがあった。それはなんやかんやで自己肯定に陥っていないかということだ。きついいい方になるかもしれないが、テレビが「マスゴミ」と揶揄されるのは自分たちのせいじゃないとばかりに保身に走っていないか。自らにカメラを向けることを免罪符にして、自己を正当化してはいまいか。都合の悪いところはカットしているのではないか。でも、それは杞憂に終わっている。土方監督は忖度抜きに、自局員にカメラを向けている。
土方「自分たちに甘くならないようにという点は、今回1番注意したことだったと思います。
この作品は『自画像』を描くことだというのは、取材中ずっとスタッフの間で共有していました。自画像を描く行為ってすごく難しくて、放っておくとどうしても自分を良く見せたくなっちゃうんですよね。でも、ちょっとでもかっこつけたことがバレると、とんでもなく恥ずかしいので、それは絶対にやっちゃいけない。
だからといって、実際よりもかっこ悪く描いてしまうのも、それはそれで嘘になる。事実と異なるわけですから。その辺の塩梅をどうすればいいのかという事は、みんだで徹底的に議論しました。編集でどうにでも料理できてしまうところでもありますし。
最終的には、正直にいまの自分たちの姿、東海テレビや局員の姿をある程度さらけだす事ができたと思っています。ただ、そこは自分たちでは判断できないところもありますから、見た人の中にはかっこつけてんじゃねえよっていう人もいれば、かっこ悪い自分たちを見せることに酔っていて悪趣味だなという人もいるでしょうし。感想はさまざまでしょうね。」
阿武野「取材対象が自分たちであるというのは、手心を加えたと思われたら終わりだと思うんですよ。そこはもう手加減してはいけない、より厳しい題材です。
取材対象に対して斬りこんでいくことが多いドキュメンタリーですから、自分たちに向かうときは、腹を開いて見せるぐらいの気持ちが必要です。日常の取材では相手を傷つけることもあるわけですから、自分たちだけ甘めにするわけにはいかないんです。
そういう作り方をしないと、あらかじめ自己肯定が前提の気持ちの悪いドキュメンタリーになってしまう。これまでの幻想を抱かせる甘口のメディアリテラシー番組になっては、何の意味もない。テレビは崖っぷちなんだと、その崖っぷちから、どう押し戻せるか。冷徹な目で見て、しっかりと自画像を描くことからしか始まらない、そういう思です。ただ、誰も崖っぷちなどと思いたくない。そこに、『さよならテレビ』の表現としての刃がある」
土方「だからみるたびに、嫌な気持ちになるんですよ。これはたぶん画面に映った全員が抱く気持ちかと。たとえ画面に登場してなくても、東海テレビで働いていれば、あまりいい気持ちにはならないんじゃないでしょうか。でも、そういうものにしないとダメだと思ったんです」

できればテレビマンとしても自分としても他人にみせたくない、自分が映っている
この自らにも厳しい刃を向ける姿勢を如実に表しているのが、夕方のニュース番組「みんなのニュース One」の生放送中に誤った映像が流れてしまうシーン。フロア全体が、その取り返しのつかないミスで騒然する一部始終が収められている。
土方「モザイク処理しないといけない映像が、そのまま流れてしまった。実は、そのミスをした編集マンが、今回の『さよならテレビ』の編集も担当しているんです。本人としてはおそらく2度とみたくない。思い出したくもないでしょう。でも、編集という作業を通して自分のミスと再び向き合わないといけなくなった」
阿武野「むごいことかもしれない。あのミスは、深夜まで懸命にやった作業でしたけど、最後にトラブルになってしまった。その日のニュース企画を担当しつつ、彼は、『さよならテレビ』の編集を担うことが決まっていた。
このミスがあって、編集マンは僕のデスクにうなだれてやってきた。『さよならテレビ』の編集は担えません、と。僕はそのとき、『別の人のミスをあげつらうだけでなく、図らずも、自分のミスを映像化しなくちゃならなくなった。自分のミスを自分でどう描けるか、とっても大事なことだ。むしろ、きみにしかこの編集はできないよ』と言いました。
たぶん彼は、僕の発言にズタズタに傷ついたと思います。でも、傷を負ったままスタッフに入ることが特に今回は大切なんじゃないかと。ただ単に他のスタッフをさらし者にするのではなく、自分が一番のさらし者になるという覚悟を持たざるを得なくなった。その意識こそがテレビマンとして大切じゃないかと。
『さよならテレビ』には、そういうシーンまで入り込んじゃっているんです。『わたしがミスをした編集マンです』とどこにも明示してはいないですけど、できればテレビマンとしても自分も、他人にもみせたくない、自分が映っている。そういうものの積み重ねでできている。だから『さよならテレビ』は、自画像なのだと思っています」
襟を正すべきところもある。でも、いいことをしたらテレビも褒めてほしい
観ていくと、テレビ局自体が変わってしまったのか。それとも世間のテレビを見る目が変わったのか、わからなくなってくる。
土方「どっちもあるんじゃないでしょうか。ただ、『テレビ=悪』みたいなイメージがいつからか定着して、それがずっと続いているところはあるのかなと」
阿武野「もちろんテレビ側が襟を正すべきところもあるでしょう。でも、いまは、叩けるものは叩けるだけ叩いてやろうという風潮、極度のバッシング社会の中で、極度にテレビが目の敵にされているようなところもある。
叩ける対象だと思った瞬間、みんなで一斉に攻撃するでしょ。それも最近は、みてもいないのに激しく叩く。ネットの数行だけみて、わかったかのように叩く。参加意識の高揚といえば聞こえはいいけど、尋常じゃないヒステリックな感じがすることがあります。
テレビの状況をお話すれば、経済が衰退していくと、広告を中心にした収入構造の民放テレビは、経営が苦しくなる。これから、民放は、特にローカル局は厳しい時代に入ります。その時、地域の人たちは、自分たちのメディアとして、ローカルテレビをどうしていくのかを考えなくてはならない時が来ると思います。
つまり、たとえば地域に4局ある民放局が、潰れ始めるんです。報道、情報という大事なものを担っている地元局を、どう潰し、どう守るかということが近々起こります。テレビ局は、テレビ局で、このままでいいわけはなく、使命をしっかり果たして、このテレビ局だけ存続してほしいと言われる局にならなくてはなりません。4局5局あるということが、多様性に繋がっているのかというのもかなり疑問ですし、テレビの在り方と、地域の人たちとの関係について、テレビの側も、地域の人たちも、考えた方がいいと思うんです。
僕は『テレビも褒めるときは、褒めてください』と、ティーチ・インなどの機会で言うんです。褒めて伸ばすということもある。メディアも、人間がやっているんですから、みなさんに『頑張れ』っていってほしいときもあるんです。強い支持の声が勇気や希望を与えてくれる。ほんとうに褒めてほしい(苦笑)。
ただ、テレビの側も本気で考えないといけないことがある。ひとつは視聴率。経済が縮小して広告費の取り合いになると、視聴率が指標なので、そこに集中してしまう。その数字の競争が何を引き起こしているのか。そこを考えなくてはならない。伝えたいことよりも、求められるものへのシフト。マス・コミュニケーションとしての変容は大丈夫か。
『さよならテレビ』を見てもらえればわかることですけど、ニュース番組になぜグルメものが入ってくるのか。ラーメンが悪いわけじゃないけれど、知らない外国の情報だとか、そういうものの方が大事じゃないのと思うんですが、マーケティングするとグルメが視聴率が取れる、と。テレビの経営にはお金が必要。だから、視聴率だと。求められているのは遠いワールドニュースじゃなく、ラーメンだと。この国民に、この政治じゃないですが、この視聴者に、このテレビ…。お互いに見くびっちゃ終わりです。テレビと視聴者とニュースの題材の関係など、変わりうるはず…。今のテレビマンの苦悩とジレンマが一筋縄ではいかないこと、作品から見てもらえるんじゃないかなと思います」
土方「求められてること=(視聴率の)数字がとれるものという考え方だけでニュースを作り続けていくと、どんな状況になるのか。ちょっと怖くてあまり考えたくないですよね」

セシウムさん事件の矢面に立ったアナウンサーがみせるテレビマンとしての良心
作品は、契約社員の澤村慎太郎記者、制作会社から派遣社員としてやってきた新人の渡邊雅之記者、入社16年目の福島智之アナウンサーの3人を中心に展開していく。この中で個人的に強く印象に残ったのは、「みんなのニュース One」のメインキャスターを務める福島智之アナウンサーだ。
いわば彼は番組の大きな看板を背負っている。いち視聴者からすると、番組の顔という意味では、冠番組をもつタレントとかわらない。でも、福島アナウンサーは東海テレビの一局員。そう、しがないサラリーマンに過ぎないのだ。
そんな局のアナウンサーがこれほどの孤独とプレッシャーに押しつぶされそうになりながら、番組と向き合っている。恥ずかしながら、ここにはまったく考えが及んでいなかった。
阿武野「作品の中でも触れられていますけど、2011年8月4日に東海テレビはセシウムさん事件という狂ったような放送をしました、そのせいで岩手のみなさんに嫌な思いをさせてしまいました。以後、社長は毎年、岩手を訪問して東海テレビの取り組みを報告し、8月4日には、放送倫理を考える全社集会を開き、みんなでいろいろなことを語り合っている。今後、2度と馬鹿げた不祥事を起こさないように、当時のこと、それに日常のヒヤリハットをスタッフ全体で共有しています。
でも、当時、セシウムさん事件を起こした、その番組の前面に立っていた福島キャスターが、どんな思いで過ごしてきたのか、誰も知らなかった。彼の傷はちっとも癒えていなくて、ときに自分の意見をカメラの前で言わなくてはいけないのに、当たり障りのない話になってしまう。アナウンサー、表現者として、そこまで追い込まれているとは、僕も思っていなかった。
『さよならテレビ』の取材を通じて、福島キャスターの苦悩がみえてくる。これにはとてもショックであり、考えさせられました。メインキャスターはここまでの責任を深く感じるものなんだと。そして、キャスターとしても、東海テレビの局員としても、重い十字架を背負い続けてきた。この彼の思いこそ、テレビマンの良心であり、大事なテーマの一つだと」
土方「しゃべるのが仕事のアナウンサーが、できれば自分を表に出したくないという。これは相当なことでしょうね。本来、前に出たいはずですから」
阿武野「テレビマン、キャスター、アナウンサーとして彼の中にある強い道、何というか倫理観をみたような気がします。同じ局の人間ですけど『すごい男だな』と思いましたよ。放送人の在り様をみせてくれたと思います」

テレビが萎縮していってしまうほんとうの理由
ミスをしてしまった編集マン、福島アナウンサーの姿をみると、テレビが一歩間違うと取り返しのないことを起こしてしまう地点にいることに改めて気づくことになる。善にもなれば悪にもなる。だからこそ高い倫理観や責任が求められる。
とはいえ人間のやることに絶対はない。ときにはミスを犯してしまうことがある。なのに、どこかテレビに絶対を求めていないか。
ときに人はミスを犯す。そのことにもう少し留意して、受け手もテレビと向き合っていいのではないかと思う。
土方「絶対を求められると、萎縮につながると思うんですよね。何か表現をしようとしたときに、もしかしたら問題が起きるんじゃないかという心配が先に立ってしまう。それがいつしか、批判されそうだからちょっとやめとこうかという話に繋がっていく。いまのテレビに限らずメディア全般に起こっている事じゃないでしょうか。」
阿武野「いまは、安心、安全、リスクなしというのが合言葉です。そこで、なにかをやらなければならない。だけど、本来、新しいことは、リスクと隣合わせだと思うんです。冒険には、落とし穴がつきもの。
だけど、安心・安全を第一義としているような組織だと、落とし穴にはまったとき、ボコボコにたたかれる。それは活力ある組織、多様なものを許容できる社会でしょうか…。挑戦する人を簡単に切り捨てない。そうじゃないと、だれも、何もやらなくなります。
でも、いまは叩いて、もう二度と『そいつは表に出すな』みたいな雰囲気がある。相手がテレビ局なら、そんなテレビは潰して失くしてしまえ、みたいな。
もちろんミスを好んでいるわけじゃないですが、もう少し様々なものを許容する力があったらなと。甘いといわれればそれまでですけどね」
そうなのである。もちろんニュースを伝える上で、ダブルチェックをするだとか、ソースの確実性を担保するといったことはテレビ局としてやることは当たり前だ。それを踏まえた上でも、ミスは起こる。それをわたしたちはある程度は引き受けておかないといけない。テレビを必要以上に神格化することももちあげることもしなければ、必要以上に否定もしない。存在意義を認めることがテレビの未来につながっていく気がする。
土方「その話に関係するかわからないんですけど、最近では街頭インタビューをするにも、承諾書をもっていってサインをしてもらうースが多いと聞いています。それが常識になりつつある。
そうなると今度は、許諾を取っていないものは全て画面に出してはいけないとなっていく。最近、街頭インタビューなんかで答えている人の背景が全面モザイクになっている場面をよく見ると思いますけど、これはバックに撮られたらまずい人が万が一映り込んでいた場合を考えてのこと。苦情がくる可能性をつぶすためにやっている。そこまでしてリスクゼロにしないといけない」
阿武野「もう、そんなことも何も考えないで、街頭インタビューのバックはモザイクを掛けるという単純作業化が日常になっている可能性もある。モザイクが一種のマニュアル化している感じ。安易なモザイクの使用は、匿名社会に繋がっているんですけれどね。安心、安全の果てにこういうリスクを恐れるテレビマンが常態して、より奇妙な社会を作っていっしまう。これもいまのテレビの現状ですかね」
土方「マニュアル化といえば自分も考えさせられることがありました。作品内では、報道の使命として、1.事件・事故・政治・災害を知らせる 2.困っている人(弱者)を助ける 3.権力を監視する、という3つが出てきますけど、僕なんかは何度も聞いているうちに、自分の中でもう慣用句のように覚えこんでしまっていたというか、きちんと自分の身に寄せて考えていなかったんですよね。一種の思考停止状態で、文言としてしか認識していなかった。まさにマニュアル化してしまっていたんです。
今回の取材で、『なぜそれが必要なのか』を初めて考えることができたんですが、そういう意味では、当たり前のようになっていたり、言われたりしていることを一度自分の中で吟味することが大切なのだと感じます。」
正直なことを言うと、テレビマンの二人を前にして失礼にあたるが、ここ数年、テレビには幻滅させられることがいくつかあった。それゆえいまの世間一般と同じように、メディアとしてあまりいい印象を抱いていなかった。
だから、本作の冒頭で土方監督が、報道部の局員にカメラを向け、彼らが取材拒否の態度を明確に示したシーンをみたとき、変な話だが少しほっとした。普段、一般人にカメラを向けている彼らだが、自分が撮られるとなるとやはり嫌なことがわかったからだ。
これも失礼になるが、もうテレビマンの感覚は麻痺していて撮られることに無自覚で取材拒否などおきないのではないかと、勝手に予想していたのだ。
でも、明確に拒否する反応をみたとき、カメラが時に暴力になること、時に人の心を操作することをきちんと認識していることを少なくとも東海テレビの局員に見た気がした。ある種、その人の人生までも背負うぐらいでカメラを被写体に向ける覚悟が東海テレビのテレビマンにはまだあることを感じたのだった。
それはテレビの可能性がまだあることを感じさせるものでもあった。
阿武野「僕たちの東海テレビは開局してちょうど60年。人間でいえば、還暦を迎えたわけです。いっぺんゼロに戻って、もう一度生まれ変わるチャンスだと思うんですよね。
そういうタイミングでもあり、この番組のメッセージを局員が心に刻んでほしい。で、メディアなんですから、世の中に自画像として堂々とお見せして、批判は甘んじて受ける。次の時代のテレビになるために、いろいろと意見をいただければと思っています。
その上で、これは希望ですが、やはり東海テレビが必要だよと思ってもらえるようになって行けたら、うれしいんですね」
これは全国のテレビマンへの、厳しい、しかし、愛情に満ちたエール
作品は、全国のテレビマンへの熱いエールが込められている一方で、最終通告を突きつけているようにも思える。
阿武野「厳しい、しかし、愛情に満ちたエールだと思っています」
土方「まだ立ち上がる体力・気力は残っていると思っています。ただ、方向性を間違えると、このまま消えてしまう可能性も十分にある。いまがメディアとして踏ん張りどころなんじゃないでしょうか。まだ信頼を取り戻すことができるチャンスはあると。
そう思うのは「叩かれている」から。叩かれるということは、まだ世の中の人たちの視野に入っている。無視はされていないということ。本当に消えてしまっていたら話題にもなりませんから。その意味では、まだ何かテレビに期待してくれているところがあるんじゃないかとポジティブに考えています」
スポンサーありきであるとか、権力になびくといった、テレビにもたれている負のイメージがあるが、果たしてそうなのだろうか?こちらが色眼鏡で見すぎてはいまいか?このままテレビ離れは加速していくのか?本作は、さまざまなテレビの「いま」を映し出す。
このテレビの「いま」をあなたはどう受け止めるだろう?
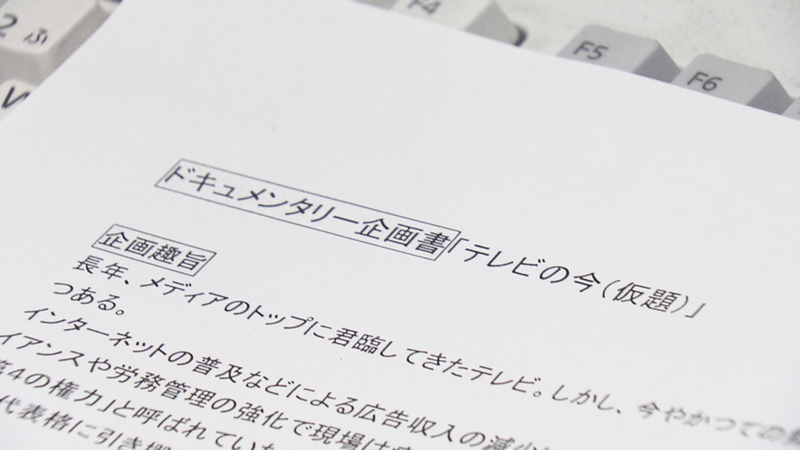
ポレポレ東中野、愛知 名古屋シネマテークにて公開、全国順次公開。
場面写真はすべて(C)東海テレビ放送










