村井邦彦×川添象郎対談【後編】「『キャンティ』もアルファレコードも、梁山泊のような存在だった」

【前編】から続く
フランメンコギターの名手として活躍

――象郎さんはフラメンコギタリストの名手として活躍していましたが、今年3月に発表した象郎さんプロデュースの作品を集めたアルバム『象の音楽~世界に衝撃を与えた川添象郎プロデュース作品集~』のボーナストラックに、1966年の音源「BULERIA/川添象郎with三谷真言」が収録されていて、見事な演奏を聴くことができます。
川添 二人で一発撮りした音源。当時はみんなそういうレコーディングの仕方だった。
――村井さんが書かれた象郎さんの作品集『象の音楽』のライナーノーツの中にも、象郎さんが「キャンティ」の前でギターを弾くシーンが描かれていますが、風景と音を想像できました。
村井 僕もそれをはっきり覚えてるんだよね。
川添 当時はあの辺もまだ静かだったし、弾いていても気持ちよかったことを覚えています。
“ALFA”はスぺル違いだった⁉
――象郎さんは1969年12月に日本人キャストによるロックミュージカル『ヘアー』をプロデュースし、当時の若者に衝撃を与えました。
川添 加橋かつみのレコーディングでパリに行っている時、『ヘアー』のリハーサルを見る機会があって、僕と加橋と友人の美青年のカルロスと、その知り合いのカイゼル髭のおじさんと一緒に観に行って。あまりに素晴らしい舞台だったので、プロデューサーに日本での上演を直談判しました。あとで聞いたら、そのカイゼル髭のおじさんは、実はサルバドール・ダリだったという…(笑)。それでプロデューサーも信用してくれたのかな。同じ頃クニが「象ちゃんがいるなら、初めてだけどパリに行くわ」って来てくれて、このフットワークの軽さもクニの武器。そのときにクニから音楽出版社の構想を聞きました。それでバークレー・レコードというレコード会社で僕はプロデューサーをやっていたので、そこの社長をクニに紹介して、その関係の出版社のところに彼が行って、色々な権利を獲得してきました。
村井 出版社に権利を獲りに行くのに、会社の名前を考えないと、ということになって、それで象ちゃんと考えてたら「イプシロンっていうのはどうか?」って言い出して。「イプシロンって何だよ」「ギリシャ文字のアルファ、ベータのイプシロンだ」と。「だったら最初のアルファにした方がいいよ」って言ったんだよ。
川添 この人「それがいいよ、それ、それ」って簡単に決めちゃうわけ(笑)。それでアルファになっちゃったんだけど、そのとき僕が早とちりして本当は「ALPHA」なのに「ALFA」って書いちゃってね(笑)。
村井 僕も気がつかなくて「これでいい、これ、これ」って(笑)。それで登録しちゃった(笑)。
川添 あの頃はそんな感じで軽く決まったことが、たくさんあってね。それで大当たりしているのもいっぱいある(笑)。やっぱりクニは天才なんですよ。
村井 ミュージカル『ヘアー』に出ていた小坂忠やその友達の細野晴臣もアルファに来て、その追っ掛けだったユーミンも合流するという、不思議な縁で繋がったね。
川添 僕の家に小坂忠が細野さんを連れてきて、ギターを渡したら弾いてくれて、その音がすごくよくて。クニも「これはすごい!」って、それからの付き合い。類は友を呼ぶんだね。クオリティの高いクリエイターと知り合いになると、そういう人たちが集まってくる。それを面白がっていたのか、憧れていたのか、一人の少女がやってきて、それが荒井由実だった。クニは何でユーミンと契約しようと思ったの?
ユーミンとの出会い
村井 加橋かつみのセカンドアルバムを、フィリップス(当時ビクターの一部門)の本城(和治)さんが作っていて、僕も曲を書いていたのでレコーディングに立ち会うために千駄ヶ谷のビクタースタジオに行ったら、本城さんがいい曲をプレイバックで流してたんだよね。「これ、誰が書いたの?」って聞いたらユーミンだって。その日ユーミンもスタジオに来ていたので紹介してもらって、その場で「うちの専属(作家)になりませんか」って言ったのかな。
川添 ユーミンは『ヘアー』のオーディション現場に来たんだけど、当時13歳だったから「若過ぎるから駄目だ」って言って。でもしょっちゅう楽屋に出入りしていて、その流れで「キャンティ」に出入りしていたわけ。
村井 早熟だね。
川添 各界の天才が集まっている梁山泊って感じだったね、「キャンティ」は。
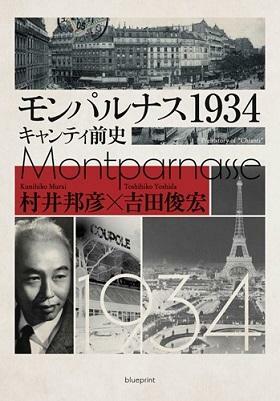
「当時の流行り歌をダサいと思って、もっとかっこいいの作ろうよって始めたのがアルファレコード」(川添)
――アルファが作り上げた音楽は、村井さんも川添さんも生粋の東京人で、それで、どこか都会的な薫りがするものが生まれたきたのかもしれませんね。
川添 クニは慶應(義塾大学)のライト・ミュージック・ソサエティっていうビッグバンドのコンサートマスターだったから、ずっと洋楽に触れてきたし、僕はフラメンコギターをやっていて世界中で演奏していたし。
村井 象ちゃんのお母さん(原智恵子)はクラシックの大家だもんね。
川添 僕たちが何にも囚われなかったからだと思う。当時の日本のいわゆる流行り歌をダサいと思って「もっとかっこいいの作ろうよ」って始めたのがアルファレコード。そういう意味で、最初から普遍性というか世界性を持っていたレコード会社ですよね。そのアルファの作品が最近また再評価されてるって話を聞いたんですけど、本当?
「『ひこうき雲』に当時にお金で1千万円以上かけて作ったのも、YMOの渡米に何千万もかけるのも異例だった。クニは博打打ち(笑)」(川添)
「ただいいものを作ろうと思っていただけ」(村井)
――そうです。昨今国内外で起こっているシティポップブームでもアルファ作品は特に人気を集めています。どのアーティストの作品にも、今もシーンで活躍する凄いミュージシャン達が参加して、丁寧に音を紡いでいるので、音が決して色褪せない、時代を超える作品になっていると思います。
川添 それはうれしいね。確かに“ちゃんと”作ってる。当時どこのプロダクションにも所属していない荒井由実っていう女の子のアルバムを、まず作ろうっていうのが大胆だし、1stアルバム『ひこうき雲』(1973年)は、キャラメルママ(細野晴臣(B)、林立夫(Dr)、鈴木茂(G)、松任谷正隆(Key))をバックに据え、コーラスは山下達郎、大貫妙子、吉田美奈子、山本潤子という今考えるとすごいメンバーだった。このアルバムに当時のお金で1千万円以上かけて作ったのも異例だったし、でも確か3万枚しか売れなかったのかな。もちろん赤字で、でもその後もアルバムを3枚作って大ブレイクしたからよかったけど、すごい博打打ちだと思わない?
村井 ただいいもの作ろうと思っていただけだったね。
川添 YMOもそうだった。日本に来ていたトミー・リピューマ(ジョージ・ベンソン、マイケル・フランクス等数多くのアーティストや、ナタリー・コール『Unforgettable...With Love』等多くの名盤をプロデュースした名プロデューサー/レーベル経営者)という、大物プロデューサーにYMOの作品を聴かせたことがきっかけで、チューブスというロックバンドの全米でのコンサートの前座にYMOが出演することになって、当時YMOはアルバムが3千枚くらいしか売れてなかったのに、何千万円もかけてアメリカに連れていってライヴをやらせるって、博打でしょ(笑)。
村井 あれはすごかったね(笑)。今のレコード会社だと無理だろうね。
川添 そこで撮ったライヴ映像をクニに送ったら、それをすぐNHKに持っていってニュースで流してもらったら話題になって、もう素晴らしい動きだよね。
村井 だってアルファの顧問の古垣鉄郎さんは、前NHK会長だからね(笑)
「ある水準のものがきちんとできる金額を使えるか使えないか、あるいは、それだけのお金を使うに値するアーティストかどうかを見極められるか」(村井)
――ちなみに当時のアルファの制作予算、バジェットはどんな感じで決めていたのでしょうか?
村井 当時1千万か2千万ぐらいは最初から覚悟してるわけ。それが5千万とか1億になることもないし、そこからいくら削ったって半分になることはないんだよ。変にけちなことをやるといいものできないからね。そういう意味でバジェットというのはあんまり意味がないという考えだったね。でも普通のレコード会社だと、損益分岐点をまず考えなければいけなくて、アルファも僕が辞める頃にはそういうことを重視する人が来て細かくチェックしていました。「これは何枚売れるんですか?」と。そんなのわかんないよね、みんな(笑)。だからもちろん無駄使いはいけないけれど、ある水準のものがきちんとできる金額を、使えるか使えないかっていうことだと思う。あるいはそれだけのお金を使うに値するアーティストかどうかという問題。まずそこからだった。
川添 そこから入らないとダメだよね。
村井 例えば小坂忠の『HORO/ほうろう』(1975年)の制作費は2千万くらいかかってる。
川添 でも50年近く売れてるからね。
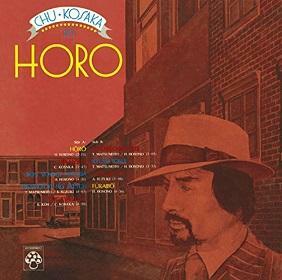
――あの作品を聴いたフォロワーがその後ミュージシャンになって、また新しい音楽を作って。さらに海外からも高い評価を得て、そういう大きな“影響”を与えた一枚ですよね。
村井 そうそう。だから、いいものを作っておくと大きな意味を持つということ。ずっと普遍性を持って、長く売れるっていう。
「アルファレコードの社是は“駄目で元々”“犬も歩けば棒に当たる”“毒も食らわば皿まで”」(村井)

――象郎さんは、当時アルファレコードの制作担当役員でした。社長の村井さんと色々戦略を練って作品作り、アーティストの発掘をやっていたのでしょうか?
村井 何もないね、適当だよ(笑)。
川添 そんなの全くなかった(笑)。
村井 だってアルファの社是が「駄目で元々」「犬も歩けば棒に当たる」と、あと、何だっけ?
川添 「毒も食らわば皿まで」(笑)。僕は感心して、大きく書いて会議室に貼ってた。
――おしゃれなレコード会社のイメージですが、こんな社是だったんですね(笑)。
川添 ほとんど、やけくそだよね(笑)。
村井 でもね、ちゃんと裏の意味があるんだよね。「犬も歩けば棒に当たる」っていうのは、プロデュースするときに色々な可能性を試してみろと。だから、とにかく足を使えと。
川添 街に出て感じろ、情報を拾ってこい、ということだよね。
村井 「毒も食らわば皿まで」は一度信じて動き始めたプロジェクトは、とにかく最後まで、めいいっぱいやらなきゃダメということ。
川添 最初にそのアーティストを信じ込んだ自分を信じて、ともかく行くところまで行っちゃえ、と。
村井 細野晴臣はすごくセンスのいいミュージシャンで、バックバンドとして色々と貢献してくれたので、彼のソロプロジェクトに「好きに作っていいよ」って丸投げしてできあがってきた音楽(アルバム『はらいそ』(1978年)が、電子音のインストゥルメンタルで、当時は誰も売れると思わないよね(笑)。でも売らないといけないから象ちゃんに相談して。
川添 プロモーションを考えないといけないけど、テレビに持って行ってもダメ、ラジオでもかけてくれない。当時ミュージシャンの間では細野君は有名だったけど、世間の反応はそんなもので、音楽専門誌で取り上げられた程度だった。でもなんとかしないといけないので、『アルファ・フュージョン・フェスティバル』というイベントを考えて、当時アルファにはギタリストの渡辺香津美や、フュージョンバンドのカシオペアが所属していたし、契約しているアメリカのレコード会社A&Mにお願いすれば、誰かアーティストがいるだろうと。それで先ほど出てきたトミー・リピューマというプロデューサーにつながったんです。
川添象郎が考えるプロデューサーの仕事
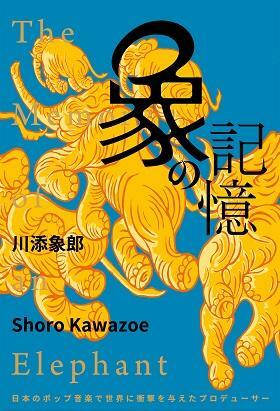
――象郎さんとYMOの関係は、象郎さんの著書『象の記憶 日本のポップ音楽で世界に衝撃を与えたプロデューサー』(DU BOOKS)にも詳しく書かれていますが、象郎さんはプロデュースするときは、とにかく自由に作らせるというのがモットーですか?
川添 ほとんどそう。アーティストを選んで、たまに選曲会議に入ることもあるけど、そこから後は僕より全然耳のいいスタッフが仕切れるから、アーティストには「ちゃんとしたもの作れよ。できたら聴かせろ」って言うだけ。でもそれがプロデュースの基本だと思う。アーティストをセレクトする、制作する環境を作って、あとは専門家に任せて、できあがってきた作品を聴いてプロモーションを考える。それがプロデューサーの仕事。
村井 僕も同じような考え方かな。まず信用する人にしか任せないからね(笑)。それだけ。一回この人でやるって決めたらもう細かいこと言わないで、好きに作っていいよっていう。「ダメで元々」「毒も食らわば皿まで」ですよ(笑)。
YMO結成秘話
――細野さんのお話に戻りますが、1978年のソロ作品『はらいそ』は細野晴臣&イエロー・マジック・バンド名義で、のちにYMOを結成する高橋幸宏さん、坂本龍一さんも参加しています。
川添 細野さんの中にYMOっていう構想があって、ミュージシャンは誰にしようかって色々な人が候補だったと思う。最終的に、幸宏と教授(坂本龍一)になったけど、実はその前は幸宏と佐藤博(Key)が候補だったと聞いています。
村井 そうだったの?
川添 天才音楽家・佐藤博は色々な意味で変わっていて、それで教授になったんじゃないかな。
「また気になる才能を見つけたら、プロデュースしたい」(川添)

――象郎さんがプロデュースした「そばにいるね」(青山テルマ feat. SoulJa/2008年)は当時音楽ダウンロード日本最高記録を樹立する大ヒットになりました。生涯現役で、若い人たちにも受ける音楽を日々研究しているのでしょうか
川添 最近の音楽は全く聴いてないね(笑)。これは、と思う作品がない。ちょっと前の曲だけど例えば森山直太朗の『さくら(独唱)』とか、夏川りみの『涙そうそう』を聴いた時は衝撃を受けたけど、今はそういう曲と出会っていない。かといって昔の音源も聴かないし、うちで音楽を流すとかみさんに「やかましい」って怒られるんだよ(笑)。でもまた気になる才能を見つけたら、プロデュースしたいと思っています。










