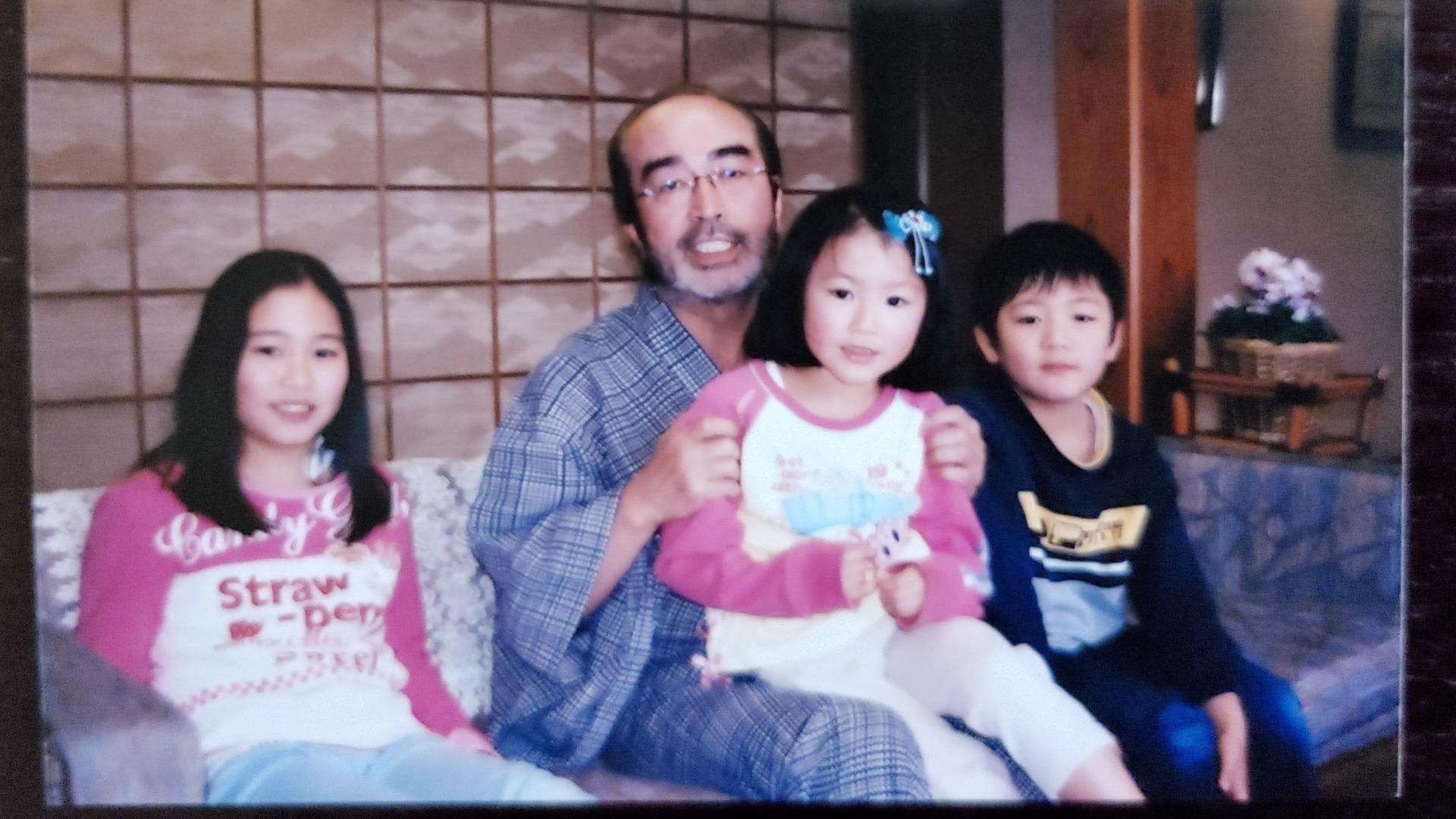吉高由里子『最愛』で増幅する、「オリジナルドラマ」ならではの魅力

気がつけば、もう12月。今期のドラマも、それぞれに最終コーナーへと差し掛かってきました。
そんな中、ますます目が離せなくなっている1本が、金曜ドラマ『最愛』(TBS系)です。
過去と現在、2つの事件の複層性
主人公の女性実業家、真田梨央(吉高由里子)は殺人事件の重要参考人とされます。
被害者の渡辺昭(酒向芳 さこう・よし)は15年前に失踪した息子、康介の行方を捜しており、梨央に接触していました。
この康介、15年を経て、白骨化した遺体となって見つかります。
捜査にあたった刑事、宮崎大輝(松下洸平)は、大学時代に陸上競技の選手でした。
寝起きする合宿所で世話になったのが梨央の父、達雄(光石研)です。
かつて互いに淡い恋心を抱いていた梨央と大輝ですが、15年後、対立する立場での再会。そこに企業弁護士の加瀬(井浦新)がからんでいきます。
失踪した当時、渡辺康介は薬物を使って周囲の女性たちを襲う、卑劣な男でした。梨央も襲われかけましたが、「怖い夢を見ただけ」と当時の記憶を封印してきました。
しかし、父の達雄は病気で亡くなる前に、「私が康介を殺した」という告白ビデオを残しており、それを見た弟の優(高橋文哉)は「違う。刺したの、俺や!」と叫びます。
黒澤明『羅生門』の作劇術も応用
見ていて、ふと黒澤明監督の名作『羅生門』(1950年公開、第12回「ヴェネツィア国際映画祭」金獅子賞)が思い浮かびました。
殺人と強姦(ごうかん)という同じ出来事を、異なる人物による異なる視点で描く、この映画の手法が見事だったからです。
原作でもある、芥川龍之介の小説の題名から、「藪(やぶ)の中」形式とも呼ばれました。
複数の証言が交錯し、真相を求める観客の目はスクリーンにくぎ付けとなったのです。
『羅生門』の作劇術も応用しながら、巧みなストーリーテリングが続く『最愛』。
その大きな見どころは、登場人物たちがそれぞれ自分以外の「誰かを必死で守る」姿です。
自分のせいで脳機能障害を抱えてしまった弟を守りたい梨央。
姉をおびやかす者を排除しようとする優。父の達雄は自分を犠牲にしても子どもたちを守り抜こうとしていました。
そして大輝も加瀬も立場の違いこそあれ、梨央を守ろうとする気持ちは共通しています。
そのために大輝は、刑事という職務からの逸脱と見られ、異動を命じられました。
何としてでも守りたい人、それはまさに「最愛の人」です。
オリジナル脚本と力のある制作陣
ドラマは大別すると2種類あります。小説や漫画などを原作にしたものと、原作のないもの。
原作があるドラマも面白いのですが、その気になれば結末まで分かってしまいます。
一方、先が読めない物語は、オリジナル作品ならではの醍醐味(だいごみ)でしょう。
『最愛』では、提示された情報をもとに考察する楽しさと、ストーリー展開にひたすら身を委ねる快感の両方が味わえるのです。
脚本は奥寺佐渡子さんと清水友佳子さん。2人が組んだ作品では、湊かなえ原作の『夜行観覧車』(2013年)や『リバース』(17年)が印象深い。
どちらもプロデューサーは新井順子さん、ディレクターが塚原あゆ子さんでした。
新井P&塚原Dといえば、秀作『アンナチュラル』(18年)や『MIU404』(20年)の名コンビであり、この『最愛』も彼女たちが手掛けています。
吉高さん主演のサスペンスとしては、昨年の東野圭吾原作『危険なビーナス』が記憶に新しい。
しかし物語の緊迫度、そして吉高さんの演技と美しさは、今作のほうが断然勝っています。
それを支えているのが、よく練られたオリジナル脚本と力のある制作陣です。
梨央を執拗に追っていた、フリー記者の橘しおり(田中みな実)も前回の終わりで不可解な死を遂げました。
15年前の「真相」と15年後の「真実」。謎はさらに積み重なってきました。残りの数回、やはり目が離せません。