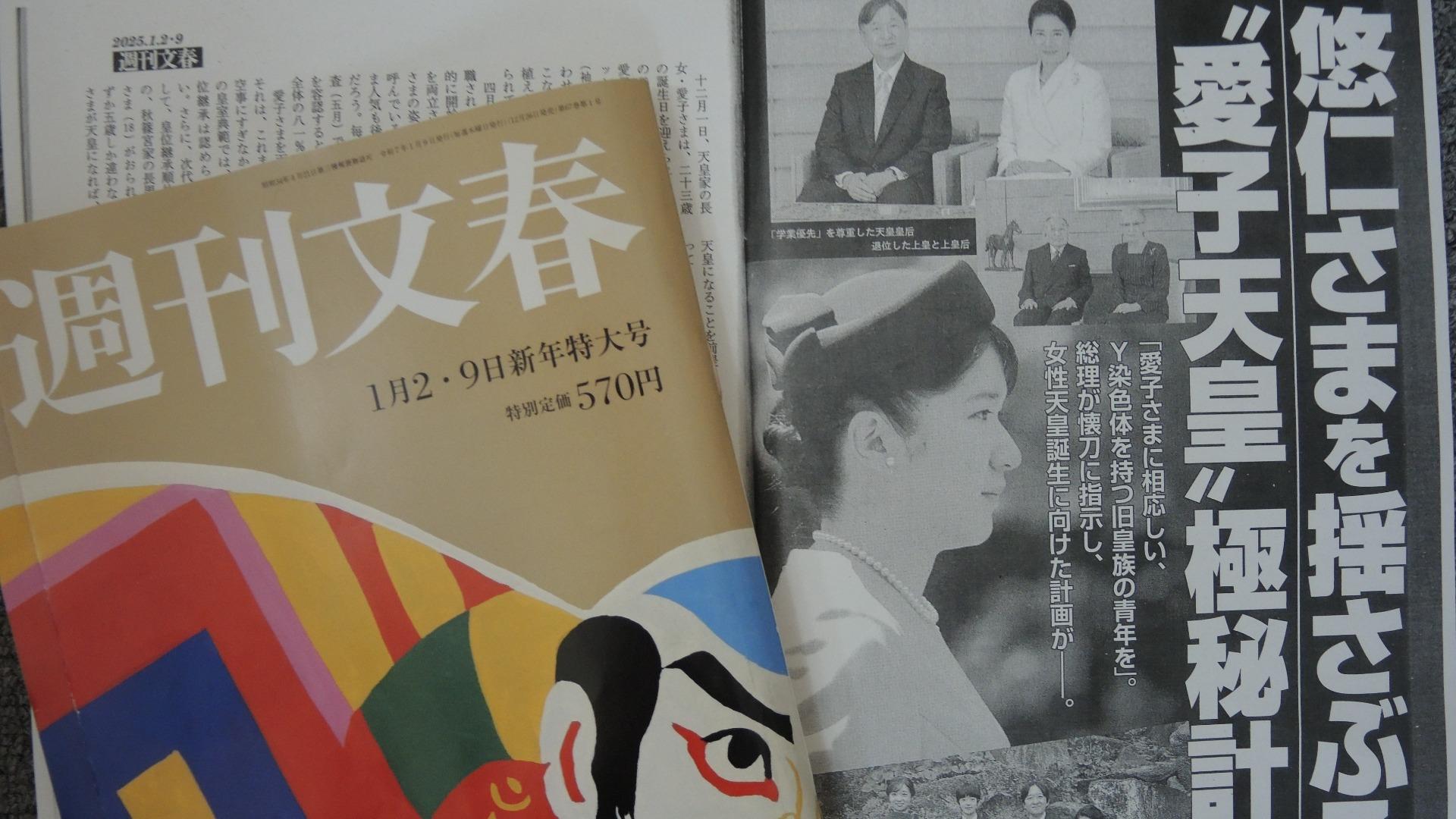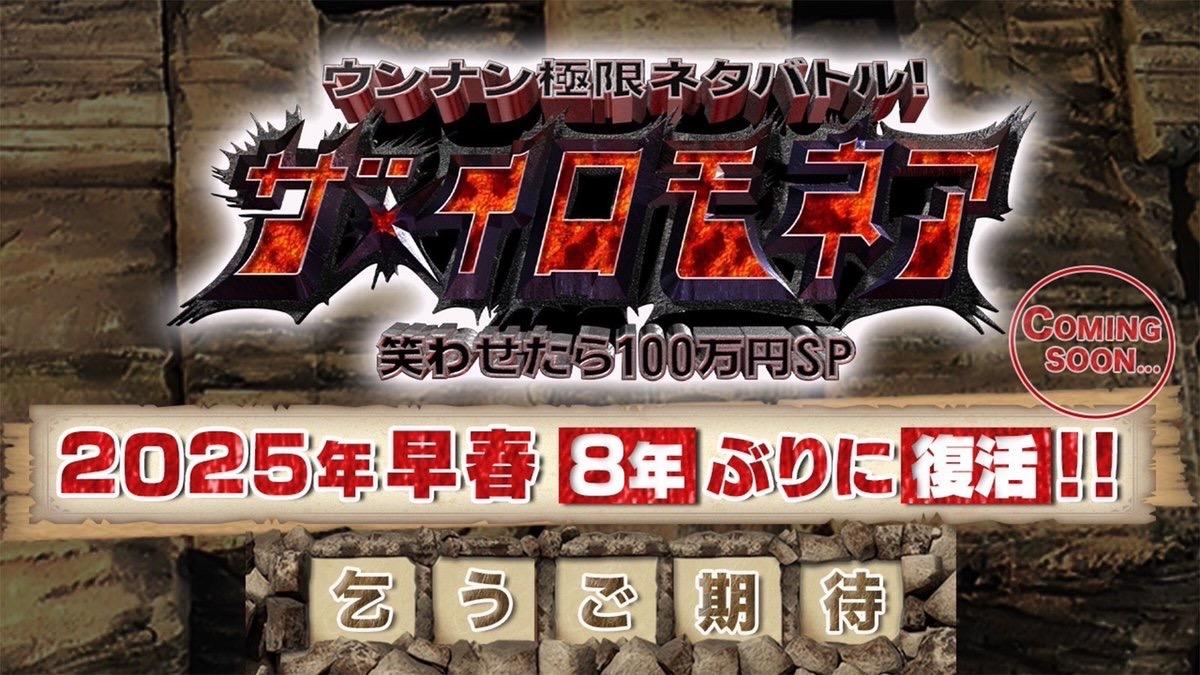「出版の灯を絶やさないための反撃」を唱える作家・今村翔吾さんの最近の活躍はすごい

報道・情報番組が次々とこのテーマを
全国で街の書店がどんどん消えていっている現状について、このところテレビが相次いで取り上げている。その中でゲスト出演して発言を重ねているのが直木賞作家の今村翔吾さんだ。この1~2週間だけでも、TBS系「NEWS23」、日本テレビ系「ウェークアップ」、そしてフジテレビ系「ワイドナショー」など次々と出演、「書店の大切さ」を訴える作家として発言している。

ちなみにここに掲げた写真は「ワイドナショー」に出演した今村さんだが、このコーナーのタイトルは「“書店”減少で全国の4分の1が『書店がない』自治体に」だ。この4分の1というのは、2022年9月に発表されたJPIC(出版文化産業振興財団)のデータに基づいたもので、正確に言えば26・2%なのだが、今年3月に新たな調査データではそれが27・7%になったと発表されている。つまり今や「全国の4分の1」どころか3分の1に近づきつつあるわけだ。
さて周知のように今村さんは4月27日に東京・神保町に「ほんまる」というシェア型書店をオープンさせた。その時の様子やシェア型書店についての今村さんの見解については、下記記事で紹介した。
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/f9eff1b6a98eec9b5a6c5a46688c8e8c91b10fd2
作家・今村翔吾さんのシェア型書店「ほんまる」がオープン、そこで本人が語った決意とは…
今村さんが語った「きょうここから、出版の灯を絶やさないための反撃に出ようと思っています」という言葉がとてもいい。
ここで取り上げたインタビューは4月に行ったもので、今村さんには「ほんまる」の話だけでなく、そもそもそれ以前から行っていた2店の書店経営についての話も聞いている。以下、その部分を紹介しよう。
東京堂書店2階で本屋さんをめぐるブックフェア
ちなみに街の書店が消えてゆく現実についてはこのところ新聞・テレビの報道も増えて社会的関心もかなり高まっている。神保町の東京堂書店2階では、書店をめぐる本のフェアを開催しているので、関心のある方は行ってみてほしい。このフェアは本屋さんについて書かれた本を集めているのだが、書店が急速に減ってゆくという最近の話題についてまとめた本の出版もこの1カ月ほど相次いでいる。創出版『街の書店が消えてゆく』だけでなく、プレジデント社『2028年街から書店が消える日』(小島俊一著)、blueprint社『ルポ書店危機』(山内貴範著)など、次々と関連書が出版されている。

街の書店が消えてゆく流れに抗する動きも次々と現れている。この6月14日には東京駅八重洲口、以前、八重洲ブックセンター本店のあった一角に八重洲ブックセンターグランスタ八重洲店がオープンとなる。
八重洲ブックセンターは、今年初め、阿佐ヶ谷駅前の書店「書楽」が閉店した時にも八重洲ブックセンター阿佐ヶ谷店を開店したし、書店界をめぐる状況に対してある種の方向性を示そうとしているように見える。
さて以下は今村さんへのインタビューだが、最初の書店「きのしたブックセンター」の開店を決めた時のエピソードがとてもいい。本屋さんがなくなっても電子書店があるからいいじゃないかと言う人が時々いるが、ここで今村さんが語っているおばあちゃんと孫娘の話は、リアル書店の本質を象徴するエピソードだ。
書店は思い出とともにある存在
――4月27日オープンの神田神保町のシェア型書店「ほんまる」で、今村さんの書店経営は3店目ですね。まず、これまで書店経営に取り組んできた経緯を教えていただけますか。
今村 2021年にオープンした最初の書店は大阪府箕面市にある「きのしたブックセンター」でした。
僕の同級生が事業承継のサポートをする会社をしていて、「大阪に事業承継を望んでいる書店があるんやけど興味ある?」みたいなことを言ってきたのです。作家が書店を経営するなんてほとんどないことなので、同じ業界とはいえかなり遠いぞと思いながら、ちょっと気になって行ってみたんですね。というのも、その書店がなくなると、箕面のその駅から歩いていける書店がゼロになってしまうと聞いたからです。
行ってみたらやっぱり本の数も少なくて、その書店の方も先代から受け継いだもので、いずれ閉店せざるを得ないみたいなことをおっしゃっていたんです。
だから正直、迷ってたんですけれど、最終的にやろうと決めたのは、おばあちゃんと小学校2~3年生ぐらいの女の子が買いに来ておられて、お客さんもまばらやったんですけど、絵本か何かを買ってたんです。僕自身も祖父と一緒に書店に行って本を買ってもらった思い出がいっぱいあります。やっぱり書店ってそういう思い出と一緒にあるものなので、この子が大人になった時に、この書店がなかったらおばあちゃんと行った思い出の場所がなくなるんかなと、ふとそんな思いがよぎったのです。
その時に、僕でできるんやったらやろうかなと思ったんですね。とはいえ、僕はその時点でスタッフも雇っていたので、わざわざ危ない橋を渡るのはどうかとも考えました。でも幸い、僕が以前、ダンスのインストラクターをしていた時の教え子とかがスタッフとしてやってくれていて、僕がやりたいと思っていることを何となく感じ取って、後押ししてくれたのですね。それで、その1店舗目を継ぐことになりました。
全国の書店を回って現状がいろいろわかった
今村 それから2022年に僕が『塞王の楯』で直木賞を受賞した後、全国47都道府県の書店や図書館280カ所くらいを4カ月ぐらいで回ったんですけど、その中で日本の書店の現状がいろいろわかったのです。いろんな縁とかもできた中で、「事業承継をうちもしてくれませんか」みたいな声がすごくいっぱい来たんです。あと年齢的な問題もあって、年配の方が跡取りもいなくて引き継げる人を探している、という声もありました。アドバイスが欲しいという声もあって、僕より皆さんのほうがプロでしょと思うこともありました。
一応、会社の財務状況なども見させてもらって、正直そういうところの8割9割ぐらいはきついなというのも目の当たりにしました。
その中の1人に「佐賀之書店」の本間店長もいまして、彼女が自分で書店をやろうとしてる、もしくは引き継ごうとしている。ただ、書店の現場の経験と経営の経験は全く別物で、「私は書店員としてはそれなりに学んできたけど経営は全くわからないから」ということで、誰かに相談したら「今村さんに聞いてみたら?」ということで僕のほうに来たんです。
僕自身が佐賀での賞でデビューしたということもあるので、佐賀には何か恩返しをしたいなと思っていたのですが、調べたら2回の台風で書店の本が水没し、それを契機に積文館さんが撤退されて駅から本屋が消えたということなんですね。
やっぱりなくなってから書店のありがたさとか良さに気づく人が多いみたいで、佐賀新聞の記事でも、駅が再開発されてるのに書店が戻ってきてないみたいな記事があったんです。なので、ここでやってみようかということで佐賀のJR九州さんとも話したら、すごく喜んでもらえて、これを機に、ということで、恩返しも兼ねて「佐賀之書店」の経営をすることになったのですね。ここまでが2店舗目です。
作家の仕事だけでは実感できなかったことも
――書店業界全体を見渡して行動しているというのはすごいですね。
今村 いやいや。作家をやってただけじゃなかなか知れなかったことがたくさんあります。例えば書店が厳しいとか言ってるけど何が厳しいんだろうとか、そういうことが肌でわかりますよね。世の中の物価の上昇に対して本の価格が追いついてないんじゃないかとか、物流費の高騰であるとか、特に地方の場合は発売日から数日遅れて本が届くのでインターネット書店に負けてるとか、挙げだしたら切りがないんです。そういうことが肌で実感できて、そこからですかね。
別に作家がやる必要はないのかもしれないけど、知ったからには少しでもプラスになることをやり続けていきたいなと思いました。それと、のっぴきならないぐらい業界が疲弊しているのも感じたので、まずはやってみようと。ほかにもいろんな人がいろんなアプローチでやっているので、どこかで結実し、出版文化の復活、書店の復活につながればいいなと思っています。
――基本的に2つの書店は店長さんに任せているんですね。
今村 そうです。でも名義貸しみたいなのではなくて、具体的に数字を見ながら経営をやっています。毎日、日報をちゃんと読んだり、指示も出しています。本当にそこはもう、作家というより社長としてやってますね。人件費の管理からいわゆるキャッシュフロー、お金の管理まで、全部数字を見て会議を開いてやっています。
――書店経営はいま厳しいとよく言われますが、実際にやってみて、やっぱり厳しいですか。
今村 「きのしたブックセンター」で何とかトントンか、赤字の月もあったり黒字の月もあったりみたいな感じなんですけど、一方で佐賀の方は今のところオープンからずっと黒字なんです。
どうしてかと考えて一つ思ったのは、人の流れのあるところに本屋があるというのが必要かなということです。わざわざ本屋に行くという動機は減ってしまっているのかもしれないけれど、通りかかった生活動線の中に本屋があれば、入ってしまうだけの魅力はあると思います。
本の売れ行きが全体的に下がっていっているからこそ、いわゆる良い立地で書店を出すことができなくなって、生活動線上にない書店の場合は目的来店になります。ショッピングモールとかにない限りはその本をインターネットで買ってしまうということもあるし、そのあたりバランスが悪くなってきてるんでしょうね。
以下、インタビューはシェア型書店の話に入るのだが、その部分は前述した記事で紹介している。