同情と共感的理解の違い。(傾聴とは何か?)
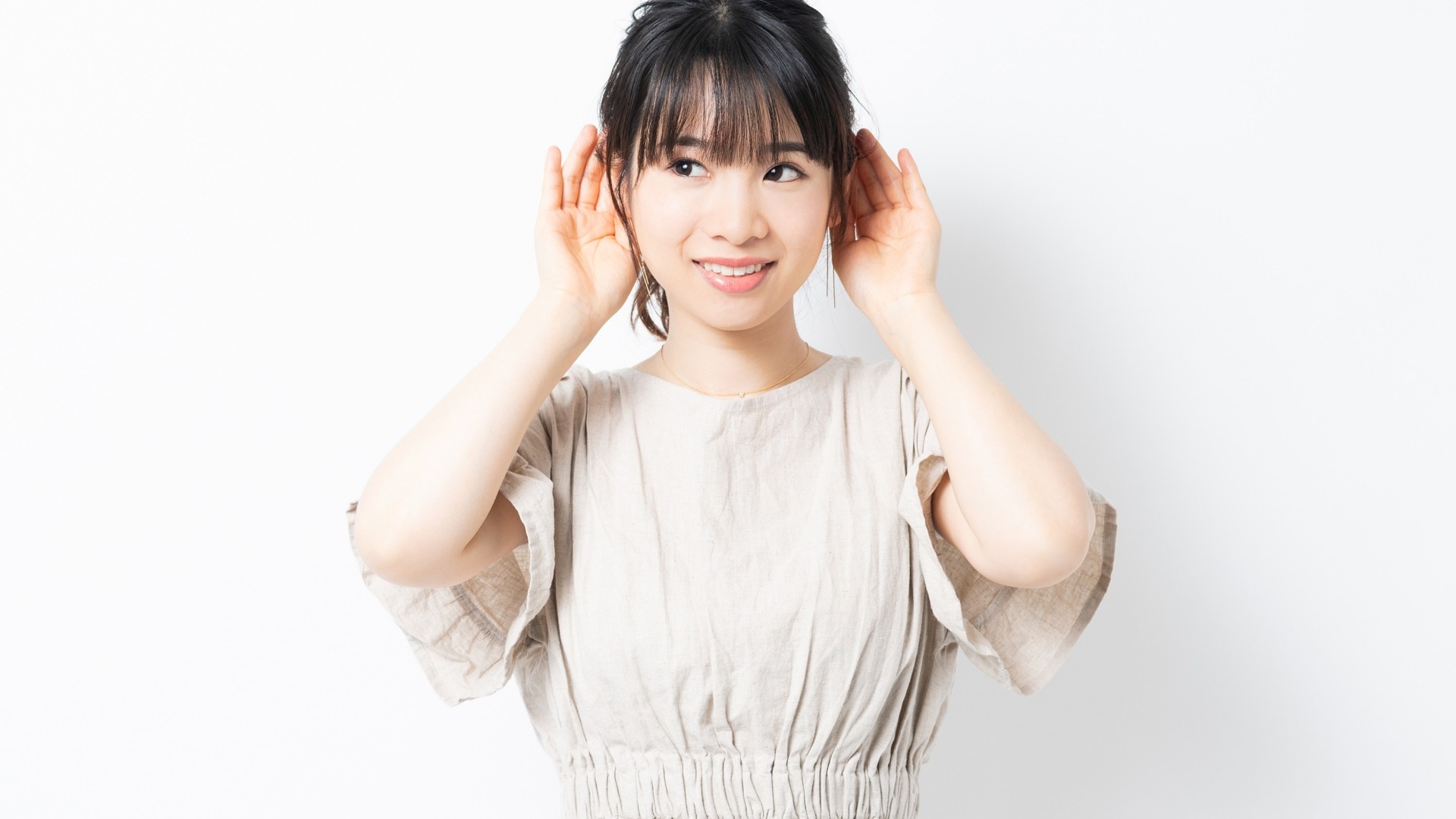
こんにちは。
精神医学と性格心理学に詳しい
心理カウンセラー(公認心理師)の竹内成彦です。
「同情と共感的理解の違い」を説明するのは難しいです。
グーグル先生に訊いても、なかなか腑に落ちない…ってな感じです。
※「グーグル先生に訊く」というのは、グーグルで検索して調べることを言います。
グーグル先生は、次のように教えてくれたりしています。
同情は、他人の状況を思いやり、支援する能力であるのに対して、共感は、他人の状況や感情を読み取って共有し、効果的かつ適切な方法で対応する能力のこと。
うーん、「よくわからない」と言うか、私的には、ちょっと違和感を覚えたりします、
また、
グーグル先生は、次のようにも教えてくれたりしています。
同情とは、相手の感情を追体験することなく、その人の痛みや不幸に対して心配や哀れみ、悲しみを感じたり表現したりすること。共感とは、相手と同じ状況に、自分が置かれたらどう感じるのかを想像する能力のこと。
やっぱり、よくわからないですね。
で今日は、
私(竹内成彦)が、別の切り口でお話したいと思います。
同情や感情移入は、馬鹿でも阿呆でも出来ます。
同情や感情移入は、基本、しても疲れません。
けれど、
共感的理解は、馬鹿や阿呆では出来ません。
共感的理解は、すると、かなりエネルギーを消費します。
一般の方が、カウンセリングの真似事をすると、同情になってしまいます。
もしくは、同情できないという事態に陥ります。
何故かというと、共感的理解は、スキル(技能)やマインド(心)を必要とした、非常に高度な技(技術)だからです。
熟練カウンセラーは、同情しません。
共感的理解をするだけです。
と、ここまでお読みいただくと、
同情と共感的理解は、どうやら全然違うものらしい…
ということが、あなたにも、薄ぼんやりご理解いただけるのではないかと思います。
私たちが、映画やテレビドラマを観て、感動したり涙したりするのは、同情したり感情移入しているに他なりません。共感的理解とは、全く違います。
同情や感情移入というのは、基本、自分より不幸な人か、自分と価値観が似ている人にしか起きません。それが、同情や感情移入の大きな特徴です。
ちなみに、カウンセリングで同情や感情移入を行っても、クライアントには、変化が起きません。起きたとしても、ごく小さな変化か、「惨めな気分になる」等の良くない感情の変容だけです。
さて、
東山紘久 先生が、ご自身の著書「来談者中心療法」において、共感的理解とは、次のようなものだとおっしゃっています。
1.カウンセラー自身が、自分の価値観をしっかり持つこと。持ち続けること。
2.カウンセラーが、カウンセラーとクライアントの間に、クライアントよりの自分を作ること。
3.カウンセラーが、カウンセラーである自分と、クライアントである相手の2人を観察する、もうひとりの自分を作り、カウンセラーとクライアントの間(横の位置)に立たせること。
4.カウンセラーが、クライアントの話を、医学的・脳科学的・性格心理学的に見る自分を作り、カウンセラーとクライアントの間(横の位置)に立たせること。
以上です。
共感的理解とは、上記の4つの条件を満たしてこそ起こるものだ、ということです。
2は、クライアントの良き理解者であり、クライアントの絶対的味方です。
3は、カウンセラーとクライアントの観察者であり、常に、「カウンセリングが円滑に運ばれているかどうか?」という観点から、冷静にカウンセリングの場を見る役割を担っています。4は、データマンです。「クライアントは、医学的みてどうか? 脳科学的に見てどうか? 性格心理学にみてどうか?」を、観察する役割を担っています。
上記は、私(竹内成彦)の解釈です。微妙にズレていたら御免なさい。ちなみに、東山先生は、「馬鹿」とか「阿呆」だなんて、そんな乱暴な言葉は使っていません。
※上記の「データマン」のデータとは、 データムの複数形で、「論拠・基礎資料、実験や観察などによって得られた事実や科学的数値」などを意味します。
つまり、共感的理解は、同情や感情移入と違って、
自分以外の、クライアントよりの自分と、ふたりを見る観察者である自分と、医学的・脳科学的・性格心理学的に見る自分、3つの自分を同時に作らなければならないため、たくさんの気力や体力を消費する、大変な作業だということです。
いっぽう、同情や感情移入は、価値観を持っている自分が、クライアントに近付いていっているだけの行為であり、2も3も4も作っていないので、疲れないということです。
おわかりいただけたでしょうか?
御免なさい。ちょっと難しいですか?
その他、私は、東山先生に習って、
カウンセリングが終わったあと、またはカウンセリングの最中に、私のスーパーバイザーなら、私の面接を見て、そして見終えて、「何て言うかなあ?」と考えたりします。
さらに、私は、東山先生に習って、
カウンセリングが終わったあと、またはカウンセリングの最中に、私の守護霊とクライアントの守護霊を、頭の中で話し合わせています。守護霊である2人は、高次元にいる人たちなので、互いに物分りがよく、仲良く話し合うことが可能です。
では、今日のまとめです。
同情は、別の自分を作る必要がない。
共感的理解は、別の自分を、同時に幾つも作る必要がある。
これが、同情と共感的理解の最大のの違いです。
もうひとつ。
傾聴についても言及させて頂きます。
世の中には、「傾聴は、同情や感情移入だ」と思ってらっしゃる方が少なくないのですが、少なくとも、深い傾聴は、同情や感情移入とは別次元のものであり、限りなく、共感的理解に近いものだと言えましょう。よって、深い傾聴が堂々巡りになるようなことは、基本ありません。
今日も最後までお読みくださって、どうもありがとうございます。
心から感謝申し上げます。
この記事を書いた人は、心理カウンセラー(公認心理師)の竹内成彦です。










