将来認知症になったら困る人の性格5選。こんな人が危ない!?【介護福祉士が見た老後の現実】
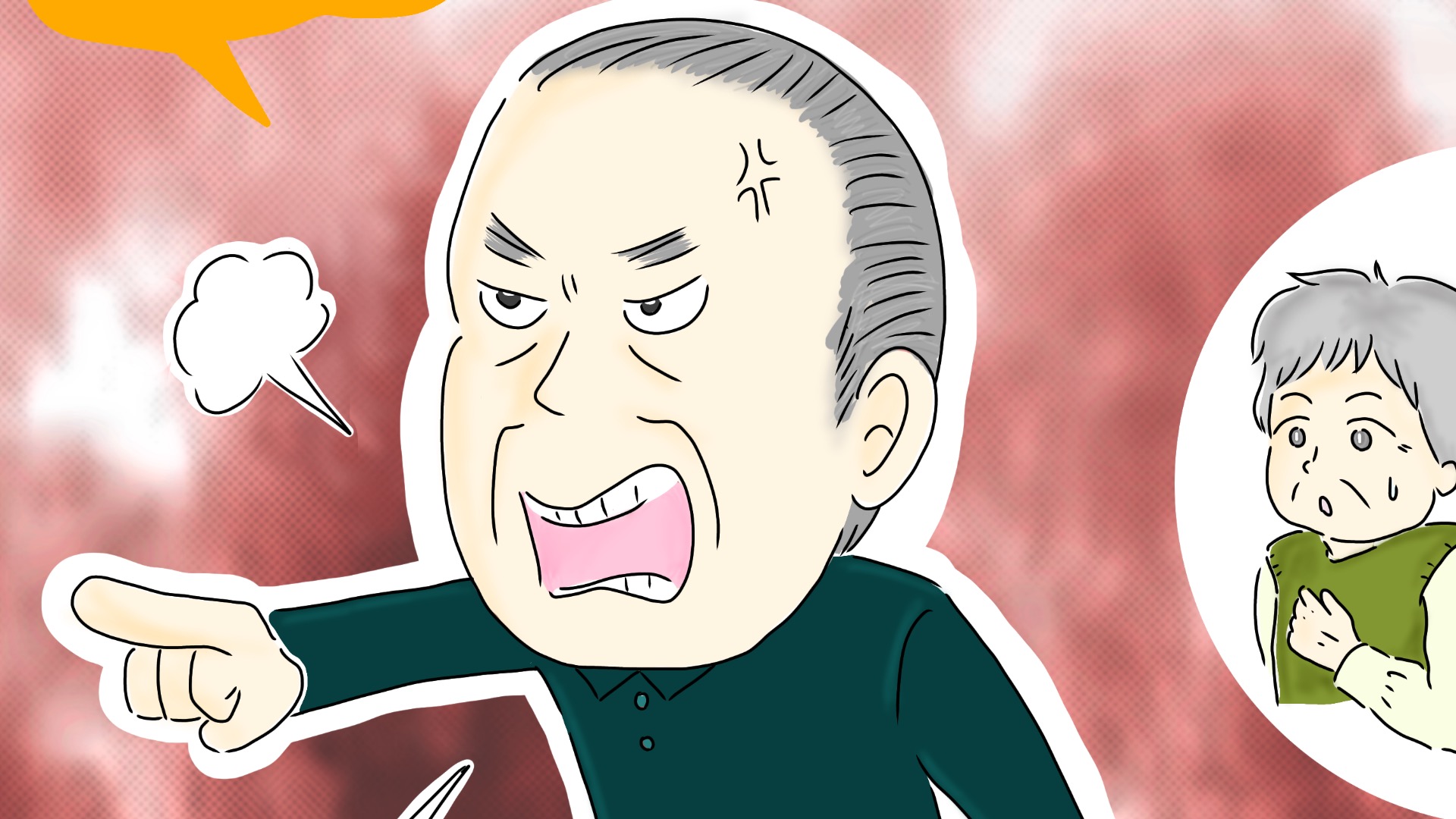
↓YouTubeでは、音声付きの解説動画を見られます。
超高齢社会となった日本では、長寿の人が圧倒的に増えています。
それに従って、認知症の人も急激な増加傾向にあります。
人ごとではない認知症
あなたも、わたしも、誰もが認知症になる可能性を持っています。
わたしは介護福祉士として、介護現場で様々なタイプの認知症の方と関わらせていただきました。
その実体験の中で感じた、将来、認知症になったら困るだろうなと思われる性格やタイプをピックアップしてみました。
性格は、なかなか変えることが難しいものですが、若いうちから少しずつ心掛けることで、認知症になっても、周りの人との幸せな関係を築けるかもしれません。
最後まで読んでいただくと、認知症を予防するヒントも見つかるかもしれませんよ。
わたしの体験が、あなたの将来のお役に立てば幸いです。
それでは始めましょう。『介護福祉士は見た!認知症になったら困る性格 5選』です。
1. 小さいことを気にする人

あなたは、ささいなことでくよくよしてしまうこと、ありませんか?
気持ちが不安定な人は、小さなことでもストレスや不安を感じやすく、常に周りの目を気にしてしまいます。
介護を受けることになっても、人や自分の言動一つ一つが気になって、介護者と楽しい関係を築くことができません。
それで、引きこもりがちになったり、人とのコミュニケーションが少なくなったりすると、さらに脳の働きが鈍くなってしまいます。
また、不安な気持ちが長期間継続することで、うつ状態に陥る危険があります。
うつ病から認知症へ移行するケースは少なくないといわれていますので、注意が必要です。
2. 怒りやすく、短気な人

怒りやすい人や短気な人は、他者とトラブルを起こしがちです。
コミュニケーションがうまくいかず、まわりから敬遠されることも多いでしょう。
そうして社会的に孤立し、人との関わりが減ることにより、脳の刺激も減って、認知症が進行してしまうこともあります。
3. 誠実でない人、協調性のない人

不真面目で責任感がなく、自己中心的な人も、人との交流が自然と減り、脳への刺激が少なくなってしまいます。
人との関わりがなく、自分の世界だけで生活してしまうので、生活に新鮮さがありません。
考える機会が減ることで脳の働きが弱って、認知症が進行する恐れがあります。
4. 生活習慣が乱れている人

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣の乱れが引き起こす病気は、生活習慣病と呼ばれています。
がんや心臓病、脳卒中などです。
この生活習慣病が認知症の発症に関与しているといわれています。
生活習慣の乱れは、体だけではなく脳にも大きく影響するのです。
認知症にならないため、また認知症を悪化させないためにも、規則正しく、健康的な生活を心掛けることが大切ですね。
5. 自分で全部してしまう人

人に頼らず、自分で何でもこなせるということは、素晴らしいことのように感じられますね。
しかしその反面、他者との関係を築けず、自分だけの世界にこもりがちであることも確かです。
自分で何でもできる人は、もともとプライドが高く、ほかの人の意見を聞き入れることが苦手なために、孤立しがちです。
そのため、必要なタイミングで援助を受けられず、気付いたときには病気が進行していたというケースも少なからずみられます。
『自分でできると思っても、人に任せてみる』そんな心がけが、若い時から必要なのかもしれません。
まとめ
いかがでしたか?
今日の話を読んで、自分の性格全てを無理やり変えようと思う必要はないですよ。
自然体でいることも大事です。
決して無理せず、自分に合った生き方を取捨選択していくことで、幸せな老後を迎えましょう。
元気に、楽しく歳をとっていきましょう。
わたしが介護福祉士として介護現場で働く中で、認知症になっても幸せな人に、何人も出会いましたよ。
またの機会に、そんな幸せな認知症の人のお話ができればと思っています。










