「やすらぎの郷」 倉本聰は何が言いたかったのか
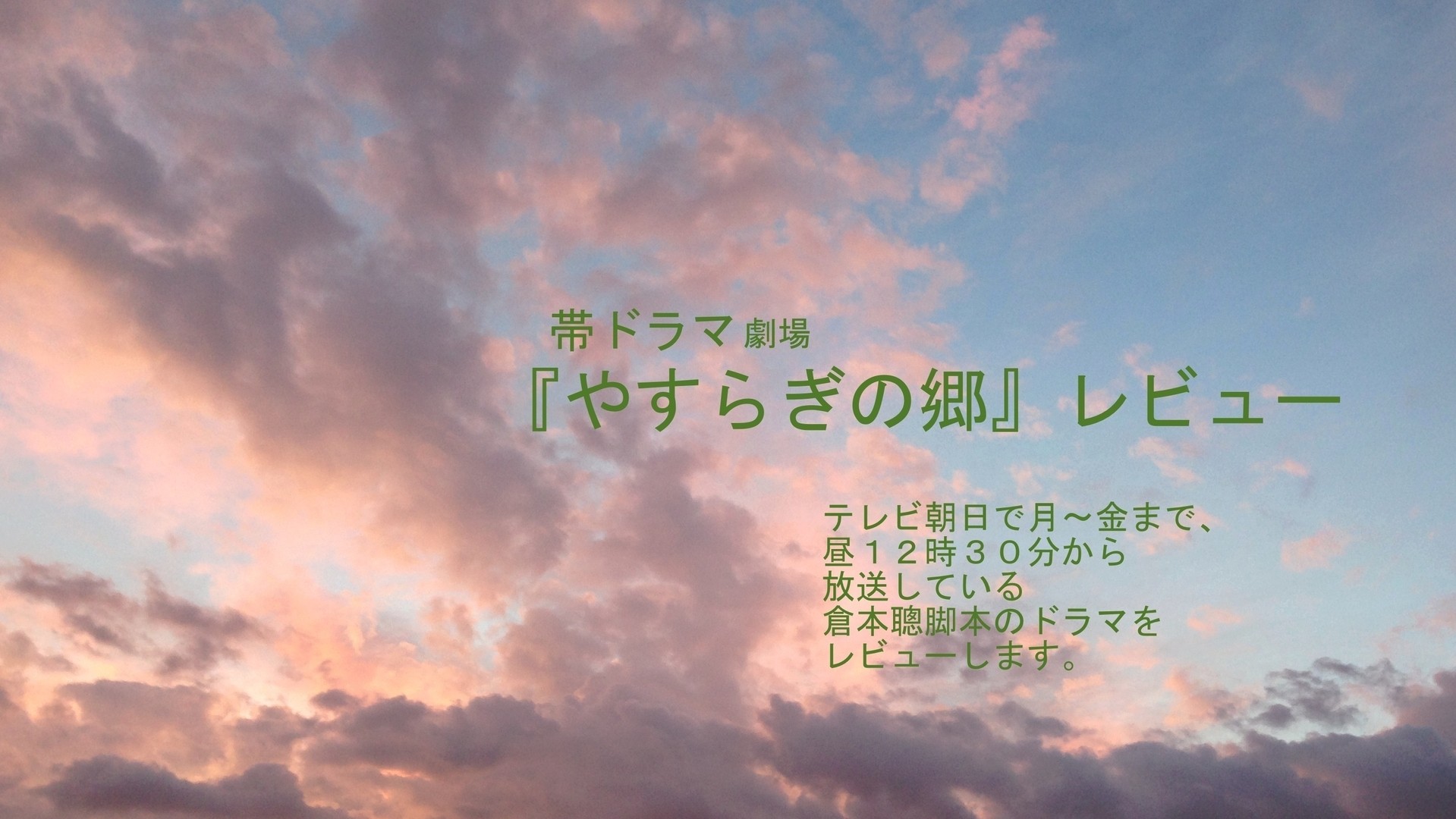
70過ぎて人生をはじめようとする男の話
またも、冨士眞奈美劇場。
15分中の後半5分ほど、彼女が演じる犬山小春がひとり語りをして、それを聞く菊村栄(石坂浩二)や姫こと九条摂子(八千草薫)が深い感慨に浸る。
小春の歓迎パーティーは、彼女を嫌う欠席者も何人かいて、やや寂しい状況で行われた。
小春は、挨拶代わりに、ニューヨークで出会った「70過ぎて人生をはじめようとする男の話」をする。
概要はこうだ。
ふつうのサラリーマンだった男が、50歳過ぎてから観たアーサー・ミラーの『セールスマンの死』に感激し、俳優を目指した。
まずお金を貯めるために懸命に働き、社長にまでなってしまうが、60歳で会社をすっぱり辞めて俳優修業をはじめる。そして70歳で、アクターズユニオンに入り、ついに念願の『セールスマンの死』の主役を演じるまでになる……というもの。
小春は、そこに何も、意見や感想をつけくわえず、ただ、老人の話をしただけ。だが、菊村は「なんだかいきなり涙が噴き出した」とモノローグで語り、ほかの出席者たちもスタンディングオベーションをするほどだ。
「小春は何が言いたかったのか。すでに人生をあきらめた我々に何が言いたかったのか」と菊村がモノローグで語るが、それはそのまま、「倉本聰は何が言いたかったのか」と入れ替えることができそうだ。
『セールスマンの死』の作家アーサー・ミラーが、マリリン・モンローの夫であることは、小春の台詞で説明されている。
『セールスマンの死』はピューリッツァー賞を受賞している名作で、映画化もされている。44話で小春が、スターになっても勉強していて「ぶったまげた」俳優として例に挙げた、ダスティン・ホフマンも舞台でも映画でも主演している。日本では、仲代達矢が主宰する無名塾による上演などが有名だ。
懸命にセールスマンとして働いてきた男が、晩年、行き詰まってしまう話で、ふたりの息子も、人生がうまくいっておらず、とくに長男は父との確執を抱えている。タイトル通り、主人公はやがて死ぬが、死んだ後、何を遺したのか……という話。労働は、国や個人(家族)の幸せのためだったはずが、なぜ、こうなってしまったのか……というのは、現代日本にも当てはまる。
このエピソードを観て思い出したのは、かつて、演出家・蜷川幸雄(倉本のドラマ『6羽のかもめ』に俳優として出ていた)がイギリスで『タンゴ・冬の終わりに』(作・清水邦夫、主演・平幹二朗)を上演したときの話だ。俳優である主人公が45歳にして突如引退、故郷に帰ってしまう。彼の鮮烈な過去を懐かしむ場面が詩的で美しいが、イギリスの観客は、なぜ日本人は45歳で人生を諦めるのかわからないという反応をしたというのだ。日本では「人生50年」と戦国時代のような感覚が現代にもあるが、欧米では、50歳過ぎても人生はまだまだこれからと前向きな人が多いらしい。実際、いまや、70歳過ぎても人生まだまだという状況になっている。
そんな彼らの財産は、『セールスマンの死』や、小春が語る老人の話の中で語られた、ユージン・オニールの『楡の木陰の欲望』やテネシー・ウイリアムズの『欲望という名の電車』などの名作の数々だ。
『欲望〜』もピューリッツァー賞受賞作で、過去の栄光にすがる落ちぶれた女が、新しい時代にふみにじられていく悲劇である。
『セールスマンの死』『欲望という名の電車』という名作は、『やすらぎの郷』のメインターゲット、シニア層にはわかるだろうが、次第に知らない人も増えているところだろう。
ドラマの中で、40年ぶりに復活するらしい伝説のバラエティー番組『しのぶの庭』のモデルと思われる『光子の窓』(58〜60)も、『イグアノドンの卵』(60)という、原子力とテレビを批判する社会派視点で、芸術祭奨励賞を取ったほどの先鋭的な作品を生み出したが、いま、それを知る人はどれだけいるだろうか。
小春の語りから、倉本聰が何を言いたかったのか、ドラマの中では明確には語られない。だが、『やすらぎの郷』は、消えかかりそうな歴史や記憶を遺そうとする渾身の叫びに見えてならない。
帯ドラマ劇場「やすらぎの郷」(テレビ朝日 月〜金 ひる12時30分 再放送 BS朝日 朝7時40分〜)
第10週 47回 6月6日(火)放送より。
脚本:倉本聰 演出:池添博










