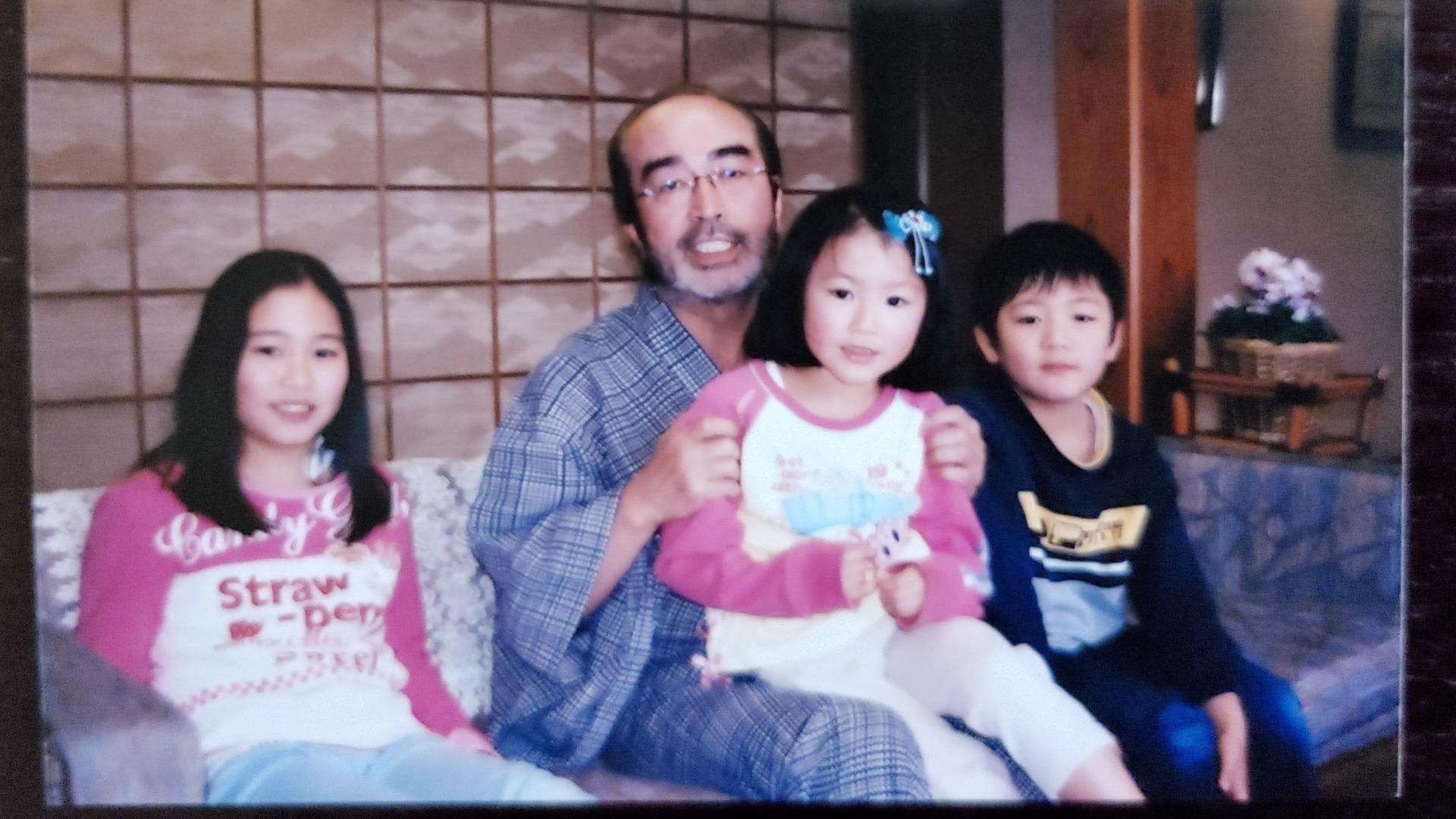樋口尚文の千夜千本 第171夜【生誕90年】篠田正浩監督インタビュー(後篇)

「日本のヌーベル・バーグ」の旗手として1960~70年代の日本映画を牽引し、80年代以降は異色の話題作、問題作を連打する娯楽映画の名匠として活躍した篠田正浩監督。90歳を迎えた今年、42年間「封印」されていた泉鏡花原作の大作『夜叉ケ池』の4Kデジタルリマスター版公開を目玉にした回顧特集上映も開催され、改めて知的遊戯に満ちた作品群のモダニズムが注目を浴びる。その篠田監督独特の映画術についてインタビューを試みた。
――(承前)確かにロックンロールも「融合」の産物ですね。篠田監督は二作目の『乾いた湖』でも、脚本に寺山修司さん、音楽に武満徹さんといった映画界の外部にいた才能の積極的な「融合」を図っておられましたね。
篠田 寺山は早稲田の同窓だったんですが、武満は以前から目をつけていて彼が病気で鎌倉で療養していた頃から訪ねて行ったりしていました。そう言えば、武満は佐藤勝とともに黒澤明作品で知られる作曲家の早坂文雄の弟子をやっていたわけですが、師の早坂さんは『羅生門』のテーマを書いた時に黒澤監督からどうしてもラヴェルの「ボレロ」ふうにしてほしいと言われて忸怩たる思いであったと聞きました。そして『羅生門』はヴェネツィアでは金獅子賞をもらって世界的評価を受けたのに、なぜか当時の国内評は辛口でキネマ旬報ベスト・テンでも五位に留まり、早坂さんの音楽もこの後で溝口健二の『雨月物語』などに付けた和楽器を使った音楽のほうが優れているとされた。でもその頃、大学生だったぼくらには『羅生門』のほうが断然ベストワンだった。あれは日本的な自然主義リアリズムとは切れた形而上的な、クールな観念の映画で、あの「ボレロ」ふうの音楽もクレオールの魅力を放っていたと思うんです。
――現在の観客ならまるでそこに異論はないでしょう。もっとも黒澤監督はシェイクスピアで『乱』を撮る時も武満さんにマーラーを注文して怒らせたようですが(笑)。でもまさに武満さんは篠田監督の近松物『心中天網島』をバリ島のガムランで始めてトルコの笛で終わらせていて、しかも不思議と絶妙にはまっている。あれこそクレオールの面白さですね。
篠田 僕が撮影所に入った頃には早坂さんは亡くなってしまって、監督になった時には次世代の武満とともに始めたわけです。僕はもともと世代的に武満と波長が合って信頼しているから、黒澤さんのように名曲のレコードを聴かせて「こうしてほしい」と言うようなことはなくて(笑)、むしろ「篠田は何も言わないね」とさえ言われていましたが、うまく行きました。僕はそういう年の近い横のつながりを存分に活かそうと試みていましたが、監督として軌道に乗った頃からは逆に大ベテランのキャメラマンの宮川一夫さんにぜひ僕の作品を撮ってくださいとお願いした。それもまた温故知新の「融合」かもしれませんね。実は宮川さんは古巣の大映も倒産してしまったし、もうキャメラマンは引退しようと考えていたようなんですが、ちょうどその頃から『沈黙』『はなれ瞽女おりん』と僕の映画を次々に撮ってくださった。
――篠田監督はそういった世代、ジャンルの枠にとらわれない人的「融合」をたくらむ一方で、古臭い映画人ならアレルギーを起こしそうな特撮技術、それも『夜叉ケ池』のようなアナログ特撮から『梟の城』『スパイ・ゾルゲ』のようなデジタル特撮まで果敢に最新のテクノロジーを導入されていて、こうした技術的「融合」ないし「越境」がまた篠田作品のクレオール性を形づくっている気がします。
篠田 それにかかわることで印象深かったのは、戦前からの映画界の大先輩でもあり、伝統的な映画技術の鑑ともいうべきくだんの宮川一夫さんに、『舞姫』の時に当時注目され出したハイビジョン合成を見てもらったら、前向きに肯定してくださるわけです。そういう進取の精神というのは本当に尊敬するし、自分もそういうものを大事にしたいと思ってきました。『夜叉ケ池』の特撮監督の矢島信男さんは、実はもともと松竹の大船撮影所の特殊技術課におられた先輩なんですが、僕が監督になる前年には東映に移籍された。あの矢島さんの特撮の凄さは緻密な手仕事でホリゾントやミニチュアを作ったり、繊細な光学合成で独特なリアルさをつくる凄さです。それに対して後の『写楽』『梟の城』『スパイ・ゾルゲ』などで使ったCGは予算とスケジュールで諦めざるを得なかった大がかりなセットや難しいカメラワークをコンピュータ上で全部可能にしてしまう。
――とはいえ、CGはあくまで絵なので、それが現実にあるものの実写の映像になじんでゆくものなのか、不安ではありませんでしたか。
篠田 でもそこでたとえば伊藤若冲のことなどを思うわけです。若冲は京都の錦市場の八百屋のせがれで、毎日動植物を眺めていた。市場で鶏は料亭などの食材になっているけれど、少し前まで生きていた鶏はもう自然そのもの、もっと言えば宇宙そのものとして生きている。だから若冲は鶏の羽を物凄く克明に、高精細に描いた。そんな絵が屏風のなかにあると、もう生きものがそこにいるかのように見えた。あれはデジタルではないけれども、発想としてはCGにつながるものではないか。僕は若冲の描いた絵具の一点一点をピクセルに置き換えたのがCGだと思う。
――なるほど。逆に言えばデジタルの絵筆を執っているのは、やっぱり人間ではないかということですね。
篠田 そのCGを使った部分が1989年の『舞姫』ではせいぜい10数カットくらいだったけれども、10年後の『梟の城』の時は40数カットくらいを占めていて、僕はその時、「ああ、フィルムありきの古い映画の作り方は終わったな」と実感しました。実際、それから20年余りを経た今はすべての映画館がデジタル上映になってしまった。でも、人間が技術に支配されてはだめなんだけれども、こうしてクラシックな映画技術の不変の部分と、新技術の未知なる部分がぶつかり合うところには何か面白いものが生まれると思うんです。それは、先ほどもふれましたが、森鴎外から大江健三郎まで日本文学と外国文学のはざまで生まれる文体の面白さにもつながる。泉鏡花だって江戸の戯作文学の後継という印象が強いけれど、実は大変熱心にドイツ文学を読んでいた。だから『夜叉ケ池』の面白さも、そういう異文化のアマルガムの産物ではないでしょうか。
――こうしてうかがって来ると、篠田作品はひじょうに多彩に見えますけれども、“クレオール美学”という一本の基調が貫かれているように思います。
篠田 そういう人にせよ言語にせよ技術にせよ、異物が刺激的に「融合」するところに立ち合っていたいという気持ちはずっとありましたね。『夜叉ケ池』は設定としても人間と妖怪が渾然一体となって登場する映画ですが、これもそういった別のことわりをもって生きるものがぶつかり合う物語に惹かれたのかもしれません。
(了)