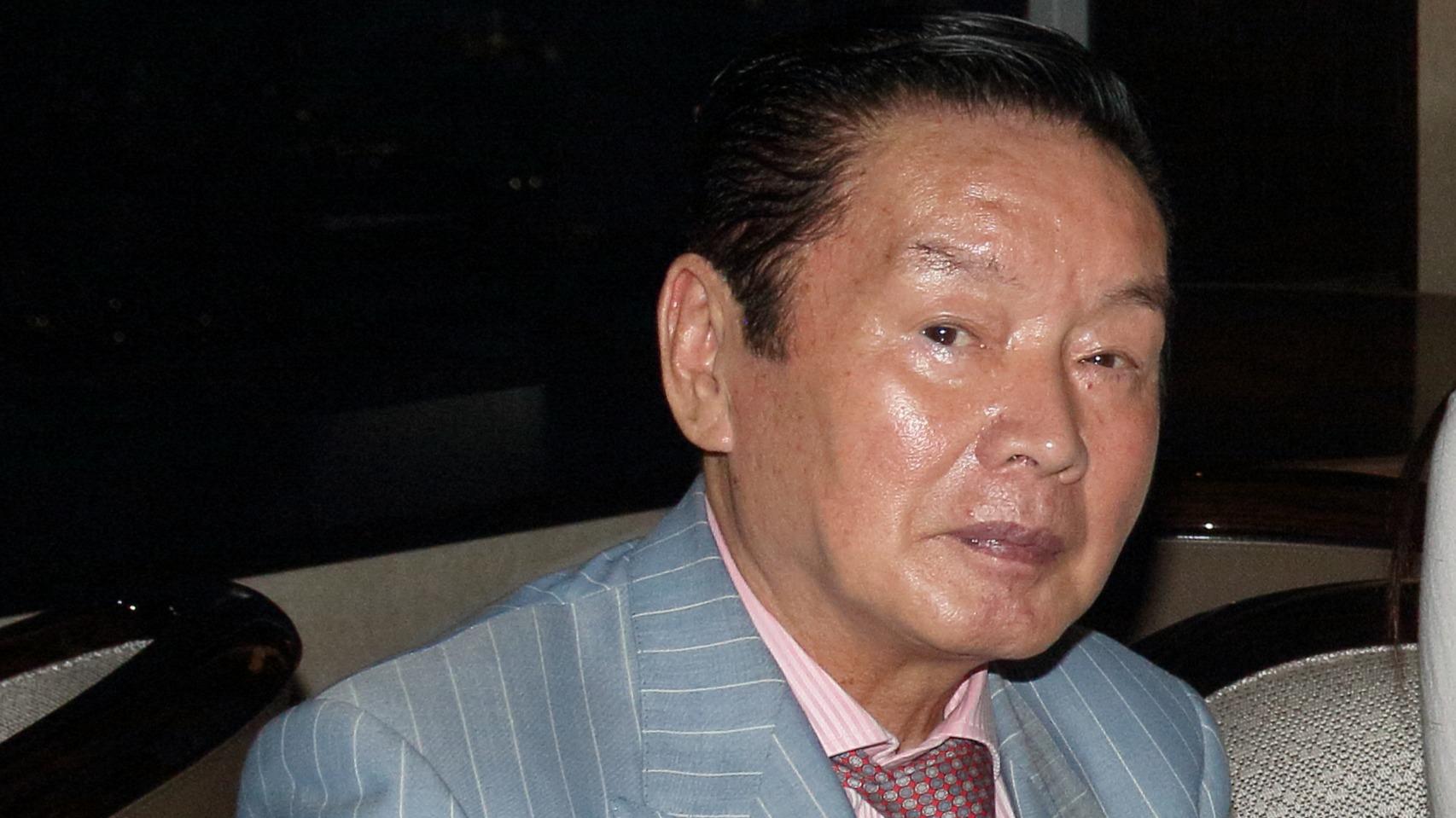画期的!「同性パートナー」の姓の変更が認められる~姓や名前を変える条件とは

名古屋家庭裁判所が、今年3月、同性パートナーと暮らす愛知県の男性に対し、「婚姻に準じる関係」として、パートナーと同じ姓(名字)への変更を認める決定を出していたことが次の記事で報じられました。
同性パートナーの名字変更認める 名古屋家裁「婚姻に準じる関係」
そこで、今回は法が定める姓を変えるための条件についてお話しします。
姓の変更には許可が必要
法は、「やむを得ない理由」がある場合には、氏の変更ができると定めています。そして、戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です(戸籍法107条1項)。
戸籍法107条1項【氏の変更]
やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
やむを得ない事情とは、氏(法律で姓や名字のことを「氏」といいます)を変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
氏の変更が許可されたケース
実際に、次のようなケースに許可が下りています。
・珍奇・難解な氏
例えば、狼→坂田、赤鬼→赤木、井戸端→古屋 などがあります。
・内縁関係で長年、相手方の氏を通称として使っていた場合
・元暴力団員として周知されている者が更生するのに必要と認められる事情がある場合
・離婚に際し婚氏続称の届出期間を超えた者の婚氏(結婚していたときの氏)への変更
・婚氏続称した者の婚姻前の氏への変更
名の変更
一方、名の変更は、「正当な理由」があれば、家庭裁判所の許可を得て変更することができます(戸籍法107条の2)。
戸籍法107条の2【名の変更】
正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
変更許可の一般的基準として、名の変更についての「正当な事由」は、次のように考えられています。
・同姓同名の者があって社会生活上多大の差支えをきたす場合
・社会生活上著しい支障を生じる程度に珍奇ないしは著しい難解難読の文字を用いた場合
・通称名として定着している場合 等
なお、正当な理由とは、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
以上ご覧いただいたとおり、氏の変更の許可は名の変更の許可に比べてハードルが高いと考えられます。
氏名は社会生活を送る上で重要な役割を持ちます。氏名でお悩みの方は、一度専門家や家庭裁判所に相談してみてはいかがでしょうか。