横浜-明徳義塾 「あれが魔物」2人の名将が語る大逆転劇の真相
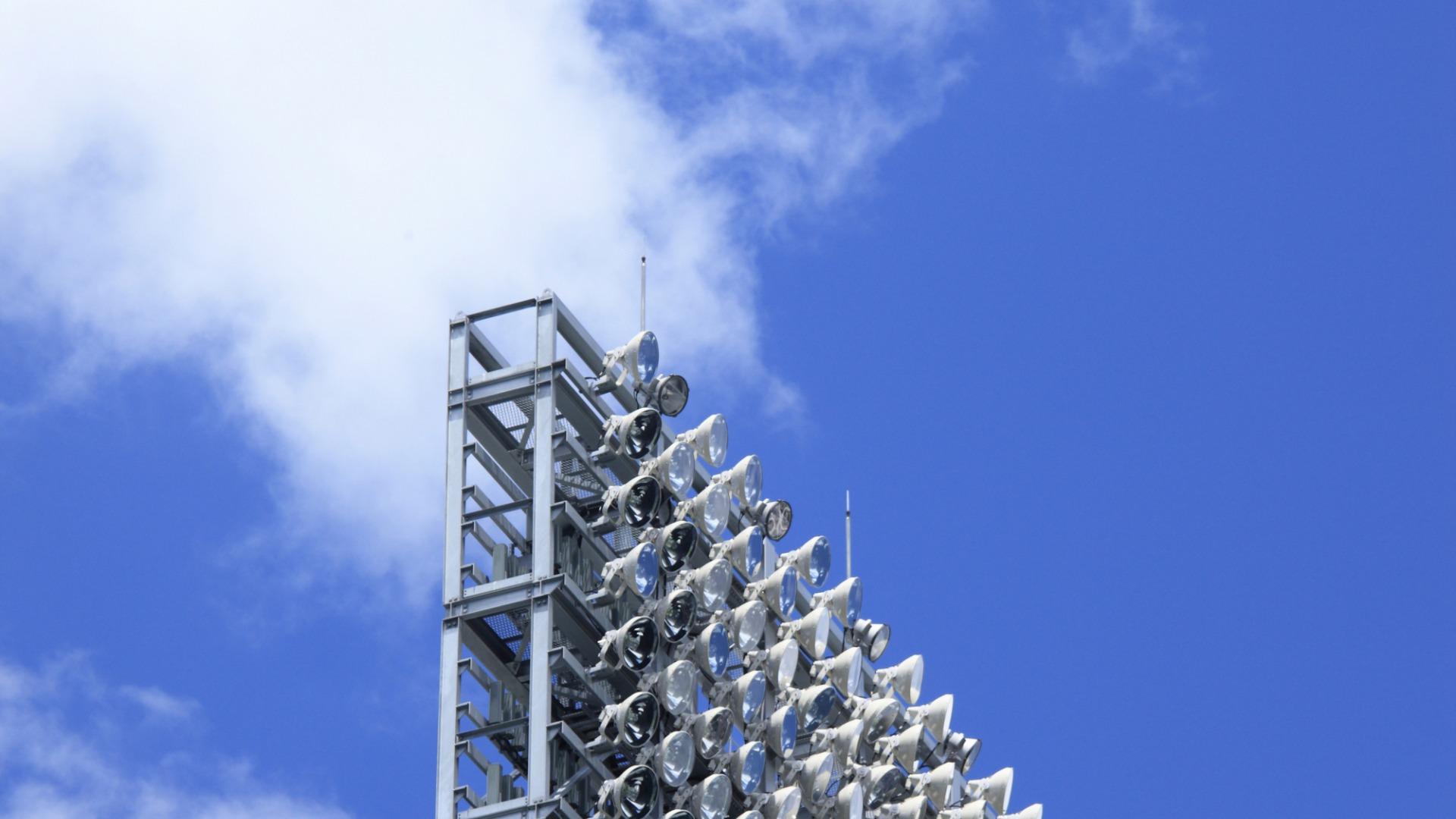
サヨナラヒットが二塁手の後方にポトリと落ちた瞬間、守備についていた選手が、一斉にグラウンドに崩れ落ちた。
1998年8月21日、第80回全国高校野球選手権記念大会の準決勝、第1試合。
そのラストシーンは、今年で生誕100周年を迎えた阪神甲子園球場の長い歴史の中でも、最も印象的な場面の一つとして、多くの野球ファンの心に刻み込まれているのではないだろうか。
「三塁側ベンチにいて、風を感じました」
優勝候補の横浜(東神奈川)に、明徳義塾(高知)が挑んだ一戦だった。
ぼくは甲子園球場バックネット裏にある記者席から、この試合を観戦していた。その後も朝日新聞の記者として、横浜・渡辺元智(もとのり)監督と明徳義塾・馬淵史郎監督を何度も取材し、当時の話を聞く機会にも恵まれた。
「風を感じましたね」
渡辺監督は、しみじみと話してくれた。
「三塁側ベンチにいて、風を感じました。すごい風圧というか、そういうものがグワーッと押し寄せてきました」
横浜は「平成の怪物」こと松坂大輔投手を擁し、この大会で春夏連覇を達成することになる。しかし、この準決勝は明徳義塾に、8回表まで0-6と一方的にリードされていた。
松坂選手はマウンドでなく、レフトを守っていた。
前日の準々決勝でPL学園(南大阪)を相手に、延長17回を戦い、250球を投げたからだ。

「ああ、松坂が甲子園を去ってしまう…」
高校野球担当キャップだったぼくにとっても、松坂選手と横浜を追い続けた1年だった。スポーツ記者として冷静に取材するよう努めていたが、記者席で何とも言えない寂しさを感じていた。
きっと、球場に詰めかけた観客も、似たような感傷に浸っていた人が多かったのではないだろうか。
そんなとき、松坂選手がブルペンに走り、投球練習を始めた。
それまで静かだった大甲子園が、突然震え始めた。
「千両役者がとうとう出てきた。そうなると…」
「実は負けてもいいと初めて思った」と渡辺監督は言う。
「最後は松坂をマウンドに上げて、最高のメンバーで甲子園を去ろう」
覚悟を決めたら、風向きが変わったというのだ。
一塁側の明徳義塾ベンチでは、馬淵監督がその風圧に耐えていた。
「千両役者がとうとう出てきたでしょ。そうなると、俺なんか桔梗(ききょう)屋さん(時代劇の悪役)よ」
明徳義塾にも、寺本四郎、高橋一正という左右の好投手がいた。寺本選手は同年秋のプロ野球ドラフト会議でロッテから4位指名、高橋選手もヤクルトから6位指名を受けている。
しかし、好投を続けてきた寺本投手が8回裏につかまり、高橋投手にスイッチしたら傷口が広がった。この回、4失点。
「実はいらんことを言うたんよ」と馬淵監督は苦笑する。
「横浜はこのままでは終わらせてくれんぞ」と選手を鼓舞したというのだ。
「監督があんなことを言うからですよ、と後から選手に叱られたよ」
右腕のテーピングをはがして松坂投手が9回表のマウンドへ。空振り三振、四球、二塁ゴロ併殺で明徳義塾を抑える。
すると、その裏、横浜が2点差を追いついた。
なお、2死満塁。横浜は途中出場の7番・柴武志選手が左打席へ。明徳義塾のマウンドは再登板した左腕の寺本投手。
そして、冒頭の印象的なシーンが生まれた。
「人の心に棲んどるのか」
試合後のインタビュー。横浜・渡辺監督の第一声は「信じられない」だった。
「4点取った後、何が起きたのか分からない」とぼくの取材メモは続く。
反対側の取材スペースでは、明徳義塾の馬淵監督が「なにがどうなったのか、ようわからん」とうなだれていた。
渡辺監督は「あれが魔物。うちの逆転というより、明徳が魔物にのしかかられたのだと思います」と当時を振り返る。
一方の馬淵監督は「魔物がいたのなら、それは人の心に棲んどったのかもしれんな」と首をひねった。

百戦錬磨のベテラン監督でも想像できないようなプレーや、想像を超える試合がときに生まれる。うまく説明ができないから、いつからか誰かが言い始めた。
甲子園には「魔物」が棲んでいる――。
ぼくは10年前の2014年7月下旬、この試合の後日談などをまとめ、「甲子園の魔物をたどって」と題した連載企画を執筆し、朝日新聞夕刊に掲載した。
この年は石川大会の決勝で星稜が0-8と大量リードされた9回裏に一挙9点をとって大逆転勝ちするなど、例年にも増して劇的な試合が多かった。いや、この年や、この試合が特別なわけではない。昨年も東東京大会決勝で9回に一挙7得点による大逆転劇が起きるなど、毎年、全国各地で多くのドラマが生まれている。
もちろん、高校野球に限った話ではない。筋書きのないドラマこそ、スポーツ最大の魅力の一つなのだから。










