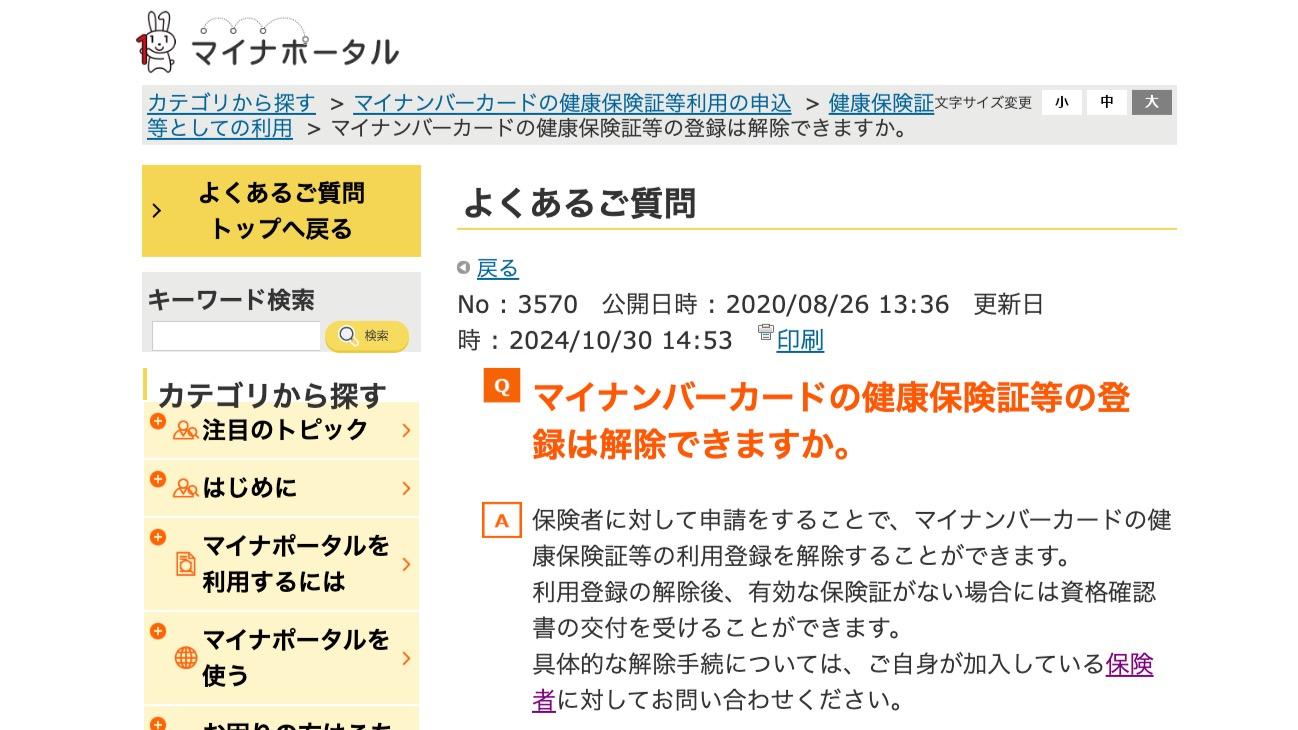【深掘り「鎌倉殿の13人」】お友達政権か!?源頼朝が優遇した源家一門と有力御家人

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」はいったん休憩で、座談会となった。今回は源頼朝が優遇した源家一門と有力な御家人について、詳しく掘り下げてみよう。
■東国の支配者・源頼朝
源頼朝は奥州の覇者である藤原秀衡に送った書状の中で、秀衡を「奥六郡の主」と称える一方で、自らを「東海道惣官」と表現した。子の実朝は征夷大将軍に任じられたとき、自身を「関東長者」と述べた。
頼朝は東国を支配し、自らがその頂点に立つだけの地位と権力を保持していることを自負していた。それゆえ、頼朝は弟の義経らが無断で朝廷から官職を得たとき激昂し、墨俣以東への下向を禁止したのである。
頼朝は、御家人と強い主従関係で結ばれていた。頼朝が反平家の挙兵をしたとき、衣笠城で三浦義明が戦死した。三浦氏は源家累代の家人であり、源家という「貴種」の再興を喜んでいた。
つまり、有力御家人は頼朝の貴種性に着目しており、その貴種性こそが頼朝の権力、権威、地位の源泉となったことが明らかである。こうした体制が鎌倉幕府の基礎になったといえよう。
■源家一門・御家人の扱い
いかに頼朝が貴種とはいえ、源家一門や御家人の扱いには慎重だった。たとえば、関東知行国が設置された際、受領に選ばれたのは弟の範頼などの源家一門に限られていた。和田義盛は上総を希望したが、それは却下された。
源家一門はその貴種性から、頼朝およびその子孫に代わって、「鎌倉殿」になる資格があった。弟の義経や範頼が殺害されたのは、不穏な動きが警戒されたからである。将軍として擁立されそうになった武田有義、平賀朝雅も同じだったので、諸刃の剣だったといえよう。
源家一門の次に優遇されたのは、頼朝の外戚だった。北条一門はその代表であり、時政は源家以外で初めて受領(遠江守)に任じられた。以降、子の義時、時房も受領となり、北条一門の繁栄が約束されたのである。
■まとめ
いかに頼朝が権勢を誇っていたとはいえ、1人では政権の運営はできない。そこで、まず源家一門を優遇し、次に外戚を登用した。ところが、それは頼朝の強力なカリスマ性があったことで実現したのであり、その死後はうまく機能しなかったのである。