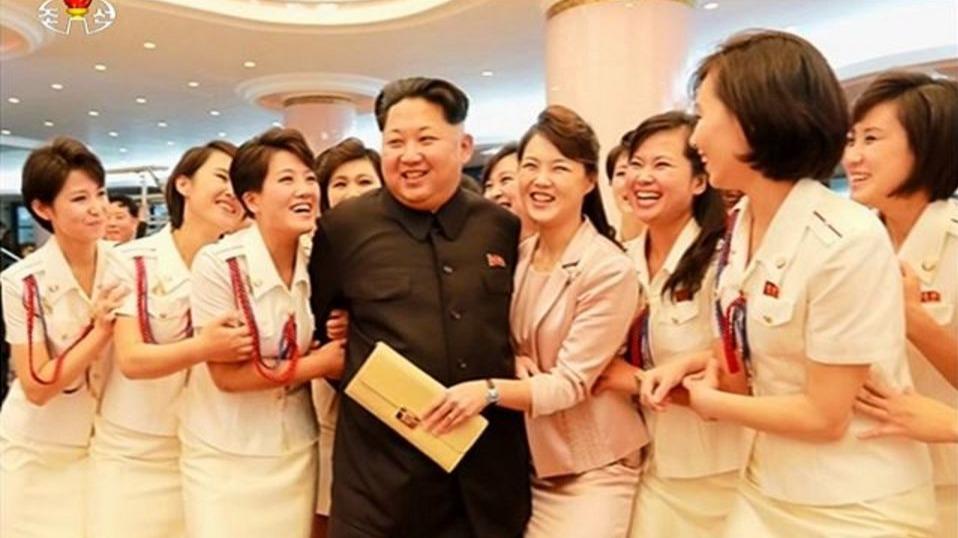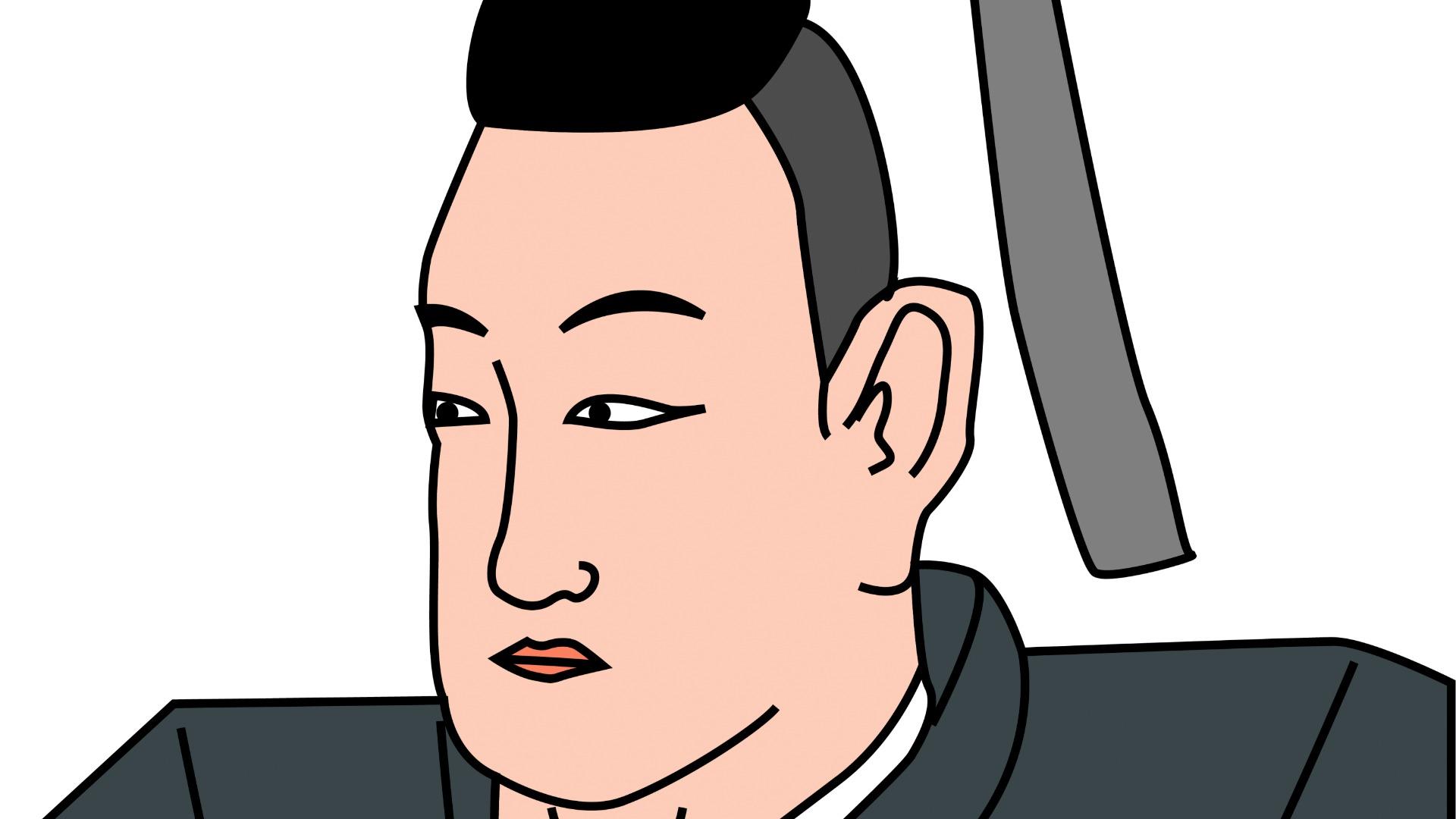児相への通報で「通告」は必要? 元児相職員が語る本当の現場

「もしかしてあの子虐待されているかも・・・」そんな子どもがいたら、ためらわずに児童相談所に連絡して下さい。
“ネットで話題になった「通告Q&A」”
ネットで話題の「通告」は本当に必要?
児童相談所に通報する際に、冒頭に「通告」という一言が必要、ということがネットで話題になっています。ですが、児童相談所に子どもが虐待されているかも、と電話をする時に、「通告」という言葉は必要ではありません。私が児童相談所に勤務していた時も一般の方が「通告です。」と電話をしてくることはほとんどありませんでした。専門用語は必要ありません。「もしかしてあの子、虐待されているかも・・・」そんな子どもが身近にいたら、ためらわずに児童相談所に連絡して下さい。
児童相談所には児童虐待に関する色々な情報が入って来ます。児童相談所は、冒頭に「通告です」という一言がなくても、児童虐待が疑われる内容であれば、「虐待通告」として受け、緊急の会議を開き、どの様な方法で子どもの安全を確認するかを検討します。児童虐待への対応は48時間以内に子どもの安全を確認するのが原則ですから、出来る限り早く動かなくてはなりません。地域による各児童相談所のルールの違いはあるかもしれませんが、「通告」という言葉で即録音、というのは少なくとも東京ではやっていませんでした。録音機能はありますが、どうしても録音が必要、と判断した時しか使っていませんでした。
警察からの連絡は全て「通告」です。これはルールとして徹底されています。児童相談所と同じく、地域の子ども家庭課や子ども家庭支援センターからの情報の場合は、役割分担として、児童相談所がすぐに動く必要があるのか、しばらくは地域で見守るので、あくまで情報提供なのか、という確認をすることはあります。学校や保育園からの虐待に関する相談も、児童相談所がすぐに動く必要があるのか確認することはありますが、いずれも内容による、と言えます。児童相談所が動くか動かないかは、児童相談所が決定出来るのです。
児童相談所は虐待の「疑い」の段階から動く
児童相談所は子どもが虐待されている「疑い」の段階から調査をする権限を持っていますし、それが職務です。「通告」という言葉がなければ虐待として対応しない、となると児童相談所は職責を果たせません。
一般の方は「通告」という言葉を知らない方も多いですから、「ちょっと心配な子どもがいて、相談したいんです。」というお電話もたくさん受けますが、その内容から虐待が疑われれば、「相談」という言葉であっても児童相談所は調査します。「子どもの通っている保育園で、お迎えの時にお母さんが子どもを叩いているのを見て、心配で。」という連絡を頂けば、保育園に連絡を入れ、親子の様子を聞いたり、お迎えの時間に合わせて保育園を訪問して、実際に叩かれているのか、親子の様子を確認したりもします。「小学生の子どもの同級生が『お父さんに毎日叩かれる』と言っているみたいなんです。」というお電話があった場合は、学校に直接子どもの話を聞きに行ったりもします。もちろん、事前に親には連絡は入れません。学校も虐待が疑われる子どもについては、児童相談所に積極的に協力してくれます。後から、子どもが親に児童相談所の人が来たことを話して、苦情を言ってきても、児童相談所には親の許可がなくとも子どもから話を聞く権限があるので、問題ありません。そして、子どもの話の内容次第では、親の許可なく、学校から子どもを保護する権限も児童相談所は持っています。「毎日のように叩かれる。」「夕飯を食べさせてくれない。」「朝まで正座させられて寝かせてもらえない。」などの子どもの言葉は保護を検討すべきです。私は実際、学校に子どもの話を聞きに行き、子どもが「お父さんに毎日叩かれる。」と言ったので、その場で子どもを即一時保護した、という経験もあります。関係機関ではない、一般の方からの相談にも、保護が必要な子どもが含まれているということなのです。子ども達は助けて欲しくても、誰に相談すればいいのかわからないでいたり、相談したらお父さんやお母さんにもっと叩かれる、と思っていて、相談出来ずにいる場合が多いので、身近な大人が子どもの様子や発言から、児童相談所につないであげる必要があるということです。
子どもの泣き声、大人の怒鳴り声
また、私が勤務していた東京都内の児童相談所では、近隣の方からの「激しい子どもの泣き声が聞こえる。」「大人が怒鳴っている声が続いている。」などのご相談もたくさん受けました。みなさん、「子どもが虐待されているのではないか、心配で・・・。」と電話して来て下さいました。虐待されている心配というお電話も、児童相談所は虐待通告として受けることが原則です。出来るだけ早く、子どもの姿を確認する方法を検討します。保育園や幼稚園、学校など、子どもが通っている所があれば、すぐにそこに電話をするのも調査方法の一つです。児童相談所が直接子どもの姿を確認する必要がある、と判断すれば、保育園や学校に出向いて、子どもから直接話を聞く、ということも児童相談所は行います。また、子どもがどこにも通っていなければ、家庭訪問をして、子どもの姿を確認し、親御さんからも話を聞きます。タワーマンションでどこの部屋か、はっきりと分からないという電話の内容や、「マンションの駐車場で叩かれているのを見た。」という電話の内容でも、住基確認をし、該当しそうな年齢の子どもがいるご家庭全てを家庭訪問します。昼間に訪問し、不在だったら、児童相談所のパンフレットとお手紙をポストに入れ、夕方以降に再度訪問します。何らかの形で子どもの安全が確認出来るまで続けます。
大人の怒鳴り声は夫婦喧嘩の時もありますが、今は、子どもの目の前で夫婦喧嘩をすることも心理的虐待に該当しますから、児童相談所が関わる必要がある、ということになります。
もちろん、児童相談所への連絡は匿名で大丈夫です。児童相談所は情報源は秘匿します。だから「私が電話したってわかってしまうかも・・・」と相談をためらわなくともいいのです。
虐待の判断は児童相談に任せる
虐待が疑われるお電話全てが、本当に親が虐待している訳ではありません。「激しい子どもの泣き声がする。」というお電話を受け、訪問してみたら「子どもの具合が悪くて、ずっと泣いていましたので、その時のことだと思います。」と、虐待ではなかったことが判明するなど、虐待ではなかった、という結果に終わる事も少なくありません。ですが、大事なのには確認です。虐待ではなかった、ということが判明するのは良いことです。また、程度は軽くても、親が子どもを叩いている、という事実を把握したら、児童相談所は親に指導をし、繰り返す場合には、児童相談所が子どもを保護する場合もある、ということを伝えるので、虐待の抑止になるのも間違いありません。加えて、本当は子育てに困っていて、つい、怒鳴ってしまうことが増えていたけれど、相談出来なかった、というお母さんを見つけ、子育てのサポート体制を整える、ということにもつながるのです。
また、一般の方は児童相談所に連絡を入れる際には、虐待の程度を判断して頂く必要はありません。虐待の有無、程度を判断するのは児童相談所の役割です。「子どもの同級生の子の洋服がいつも汚れているし、うちに遊びに来る時は、必ずお腹を空かせていて・・・。心配なんですけど、この程度で相談するのもどうか、ってずっと迷っていて・・・。」というお電話での相談が、子どもへの虐待の発見につながったこともあります。「このくらい、虐待とは言えないかも」と考えずに、まずは児童相談所に連絡を入れて下さい。
また、夜間に小さい子どもが外に閉め出されている、街を1人でウロウロしているのを見かけた時は、私は110番通報をお勧めしています。絶対に放置してはいけない状況ですが、24時間365日で動ける体制を整えている児童相談所はまだ多くはありません。電話はつながっても、職員は動けない、という自治体が多いので、すぐに対応してもらうには110番通報の方が確実と言えます。
児童虐待件数は年々増え続けていますが、それは、一般の方からの電話が増えていることも一因です。児童虐待の件数が増え続けていることは悲しい現実ですが、親から子どもへの虐待が早期に発見されて、救えている子どもが増えているのも事実です。
児童虐待防止法改正
2020年4月には児童虐待防止法が改正され、親や監護権者からの体罰は禁止になります。
・口で3回注意したが言うことを聞かないので、頬を叩く
・大切なものにいたずらをしたので長時間正座させる
・友達を殴ってケガをさせたので、同じように殴る
・他人の物を盗んだので、罰として尻を叩く
・宿題をしなかったので、夕ご飯を与えない
親から子どもへの、こうした体罰を、厚労省は具体例として示しました。今後はしつけであっても、禁じられるのです。厳し過ぎるのではないか、という意見もありますが、体罰というのはエスカレートする危険性を孕んでいます。学校や保育園など、子どもに毎日関わる組織だけでなく、一般の方達も目撃したら児童相談所に連絡を入れて下さい。それが子どもを救うことにつながるのです。「通告」という言葉は必要ありません。「心配」「相談」で構わないのです。
ここに書いたのは、あくまで私の東京都内児童相談所での経験に基づいているので、自治体や児童相談所によってルールの違いはあるかもしれません。ただ、児童虐待防止法の改正によって、さらなる児童虐待に関する相談件数の増加が見込まれます。児童相談所の機能強化もさらに進めてゆく必要があると言えます。
*一部記事を加筆・修正しました。