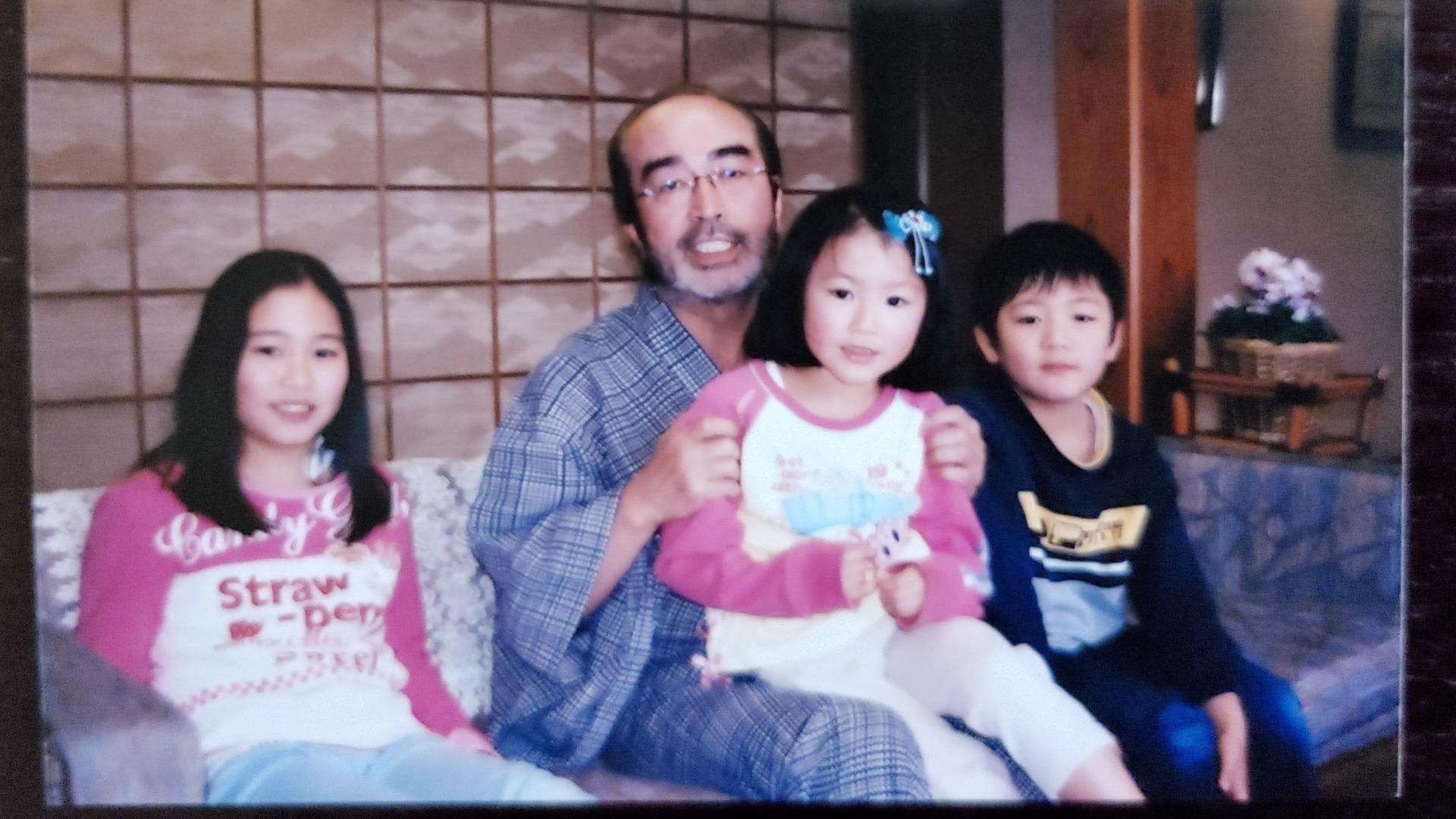ウクライナでの戦争や国内の抗議行動で注目のイランで「イスラーム国」が暴れる

2022年10月26日、イラン南部のシーラーズにあるシーア派の廟が襲撃され、数十人が死傷した。この事件について、「イスラーム国 イラン」名義の犯行声明と、「イスラーム国」の自称通信社である「アアマーク」の短信が出回った。報道やイラン当局の発表によると、現場に現れた襲撃犯は3人でうち2人が逮捕された由だが、「イスラーム国」の主張では特攻要員1人とあるだけで、他に何人が関与したのかはよくわからないし、特攻要員の生死もわからない。襲撃犯が生きて逮捕されると、敵方の当局のプロパガンダに利用されたり、その後の取り調べ・裁判でこれらの者たちが「カリフの兵士」としての資質をどうしようもないくらい欠いているのが明らかになったりするので、この種の事件では実行犯がきっちり死んでくれないと「イスラーム国」としては犯行声明が出しにくい。にもかかわらず、早々に犯行声明が出回ったということは、長期間にわたり政治的反響の大きい戦果を上げられていない「イスラーム国」としてはよほどうれしかったのか、ぼろを出さない自信があるかのいずれかということだろうか。
イランと言えば、最近はウクライナでの戦争でのイラン製の無人機の使用や、ヒジャーブの着用に関する取り締まりに端を発する抗議デモについての報道が多い。そうした中での今般の襲撃事件なので、「悪の独裁政権」の一種であるイランの政治体制に打撃を与えるものとして「自業自得」や「ざまあみろ」といった反応も出てきかねない。ただし、「イスラーム国」について考えるのならば、国際情勢ともイラン人民の自由や尊厳とも全く無関係に、単なる「シーア派殺し」として作戦を実施しているということを忘れてはならない。「イスラーム国」が発信する情報は日に日に単調かつ独善的になっており、今や同派は人殺しをする理由を「マトが異教徒だから」としか説明しなくなりつつある。「イスラーム国」の認識では、外敵よりもイスラーム共同体を内部から蝕む者たちの方が重要な敵である。その結果、「イスラーム国」が広報で言及する敵対者は、同派とは異なるイスラーム解釈・実践をするスンナ派の者(=背教者)と、やはりイスラーム教徒(ムスリム)のふりをして共同体を破壊するシーア派(=ラーフィダ)の件数が外敵よりも圧倒的に多くなる傾向だ。「イスラーム国」にとって、政治的にはイランとその仲間によって象徴されるシーア派は十字軍やユダヤよりも有害な敵であり、優先的に殺すべき存在だ。今般の事件についての声明や短信でも、シーア派はシーア派であるが故に殺す、という意識が強く感じられる。
そのような経緯もあり、イラクやシリアにおいては長年イランとその同盟者が「イスラーム国」との戦闘の最前線に立ち続けている。無論、イランがそうするのは同国なりの外交・安全保障・政治的な目標があってそうしているのだろうが、「イスラーム国」がイランと熱心に戦い、同国の政治的目標の達成を邪魔することによって受益する者たちは、「イスラーム国」とそのファン・支持者以外にもたくさんいる。アメリカ、イスラエル、ヨーロッパ諸国などは、「イスラーム国」の攻撃の矛先が自分たちではなくイランに向いている限り、「イスラーム国」の討伐に真剣に取り組むつもりはないだろう。その結果、「イスラーム国」は現世的な利害得失を計算した上で攻撃対象を選択するようになった。この計算を経て中東地域で「イスラーム国」が選んだ攻撃対象が、背教者やラーフィダということだ。イスラーム過激派とイランとを勝敗がつかない程度に争わせて両者を消耗させるという発想は、2010年代前半のアメリカの政策決定者の周辺で「燃えるがままにせよ」という論理として唱えられていたが、このような発想は現在もいろいろなところで生き続けているように見える。
イランとアメリカなどが国際関係や安全保障上の敵対関係を乗り越えて「イスラーム国」対策で手を携えることは考えにくいし、それはそれでなんだか気持ち悪い光景ともいえる。とはいうものの、「イスラーム国」を含むイスラーム過激派の取り締まりは複数の国連安保理決議を通じて各国が取り組むべきものであり、個別の都合でまじめにやったり手を抜いたりしては成果が上がらない。イスラーム過激派の影響力は著しく低迷しており、それは「イスラーム国」についてもあてはまる。しかし、どんなに破壊と殺戮の規模が大きくても世界中の誰からも関心を寄せてもらえない、サヘル地域の諸国、コンゴやモザンビークのようなところでは、イスラーム過激派が「猛威を振るっている」と言ってもよい状況だ。経験的に、イスラーム過激派の活動や影響力は5年周期で高揚と低迷を繰り返しており、それに鑑みると現在は低迷から高揚へと向かう期間である。これまでイスラーム過激派の活動が高揚した際には、それを促進するかのような各国の振る舞いがあったように思われる。イスラーム過激派を二度と栄えさせないためにも、何かの都合で彼らの活動を黙認したり奨励したりしてはならない、という点を今般の事件を契機に再確認すべきではないだろうか。