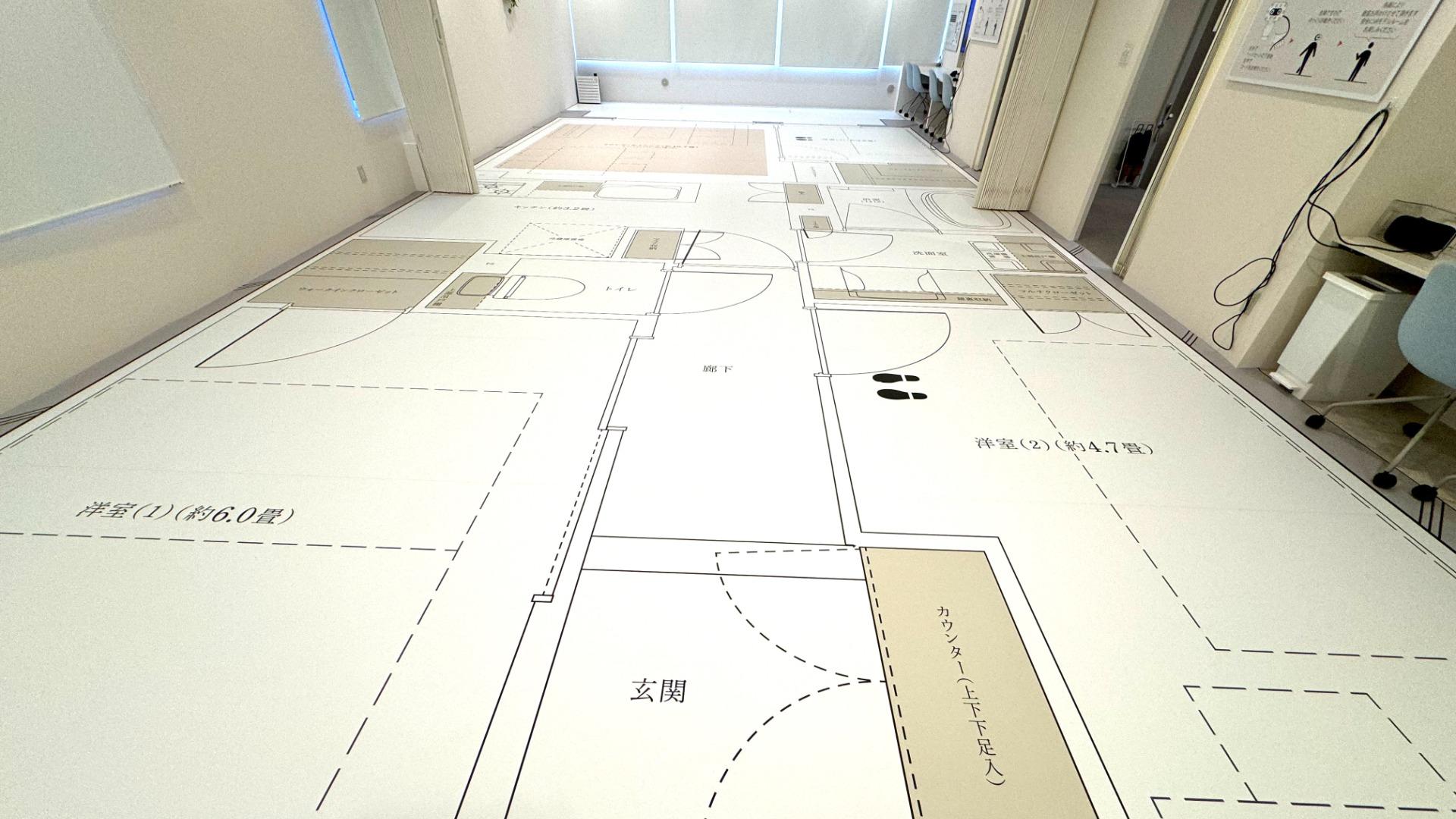快挙まであと6人でなんと降板を直訴……石井一久、ヤクルト時代の逸話(その2)

1996年12月、アメリカで左肩の手術を受けた石井一久は、そのまま現地に残ってリハビリに取り組んだ。
「すごくいい経験になったのは、メジャーとルーキーリーグ、両極端のレベルをこの目で見たことです。相撲でいえば横綱と十両、いや、それ以上の差があるわけ。そこで感じたのは、体格とか技術はそんなに変わらなくても、メジャーの人というのは活躍するための考え方、機転みたいなものを持っているんですよね。それがないと、いくら技術がすぐれていてもモノにならないんじゃないか……」
野茂英雄が海を渡ったのが95年である。当時の日本選手は、メジャーに対する理解が十分ではなく、尺度も持ち合わせていなかった。リハビリの過程とはいえ、その空気をじかに吸い、レベルを体感したことは、石井にとっては確かに大きな経験だったに違いない。
地道なウエイト・トレーニングに汗を流し、左手の指先で子どものように粘土をこね、ようやくボールを握れるようになったのは、手術から100日近く経過した3月の終わりだった。そうこうするうち、日本からはプロ野球が開幕したニュースが届く。焦りはなかったのか。
「その場にいられない悔しさはありました。でも、リハビリの年だと割り切ってしまえば、戻るまでにチームがいい位置にいてくれればいい、と思えました。自信もあったんです。みんなが見ていないところで、自分はこれだけやっているという自信……正直いえば、弱気も顔を出しかけました。とくに、ピッチングをした次の日に肩の痛みが引かなかったりすれば、ドクターはいくら"大丈夫"といってくれても、ね。でも自信があるから、弱気にどっぷりは浸からないですみましたね」
やせ我慢かもしれないが
悲壮感なく、ひょうひょうと振り返るのはやせ我慢かもしれない。そもそも石井は「きついランニングを終わってみんながへたり込んでいても、僕は平気な顔で鼻歌でも歌っていたいタイプ」なのだ。だからだろう、97年5月にようやく帰国し、6月4日の巨人戦で復帰後初登板を果たしたあとも、とりたてて特別な感慨はないように装った。そして、ノーヒット・ノーランを達成した9月2日の横浜戦のように、節目節目の試合で石井は白星を重ねていく。驚くのは、奪三振の多さだ。この年が終わった段階で、石井の成績を6年間通算すると、投球回数とほぼ同数の三振を奪っているのだ。
「三振を取れないと、投げていてもおもしろくないでしょう。打たせてアウトを取るより、三振を取るピッチャーのほうが力を認めてもらえる。1年目は、三振を取りたいから、古田(敦也)さんのサインに首を振っていましたね。ただ監督が"なにも考えていないんだから、首を振るな"。それからは、考えるのが面倒なこともあって(笑)、首は振りません。理想は27アウトすべてを三振で取ることですけど、まさかそうもいかない(笑)」
ノーヒット・ノーランにこだわらなかったのと同様、三振の数自体には興味がない。いくら三振を取っても、試合に負けたら意味がないからだ。石井は2002年、ドジャース入り。その年にいきなり14勝を稼いだのは、手術からのリハビリ中に獲得した米国での耐性と、そして本人いうところの"活躍するための機転"があったからなのだろう。
それにしても……高校出たての1年目から、球史に残る名捕手のサインに首を振っていたとはね(もっとも古田は現役時代、「キャッチャーには、ピッチャーに首を振らせることも必要」と断言していたが)。それだけ、大物だったということだろう。