自民党の政治資金パーティー巡る「裏金疑惑」 議員の立件あるか、捜査の焦点は
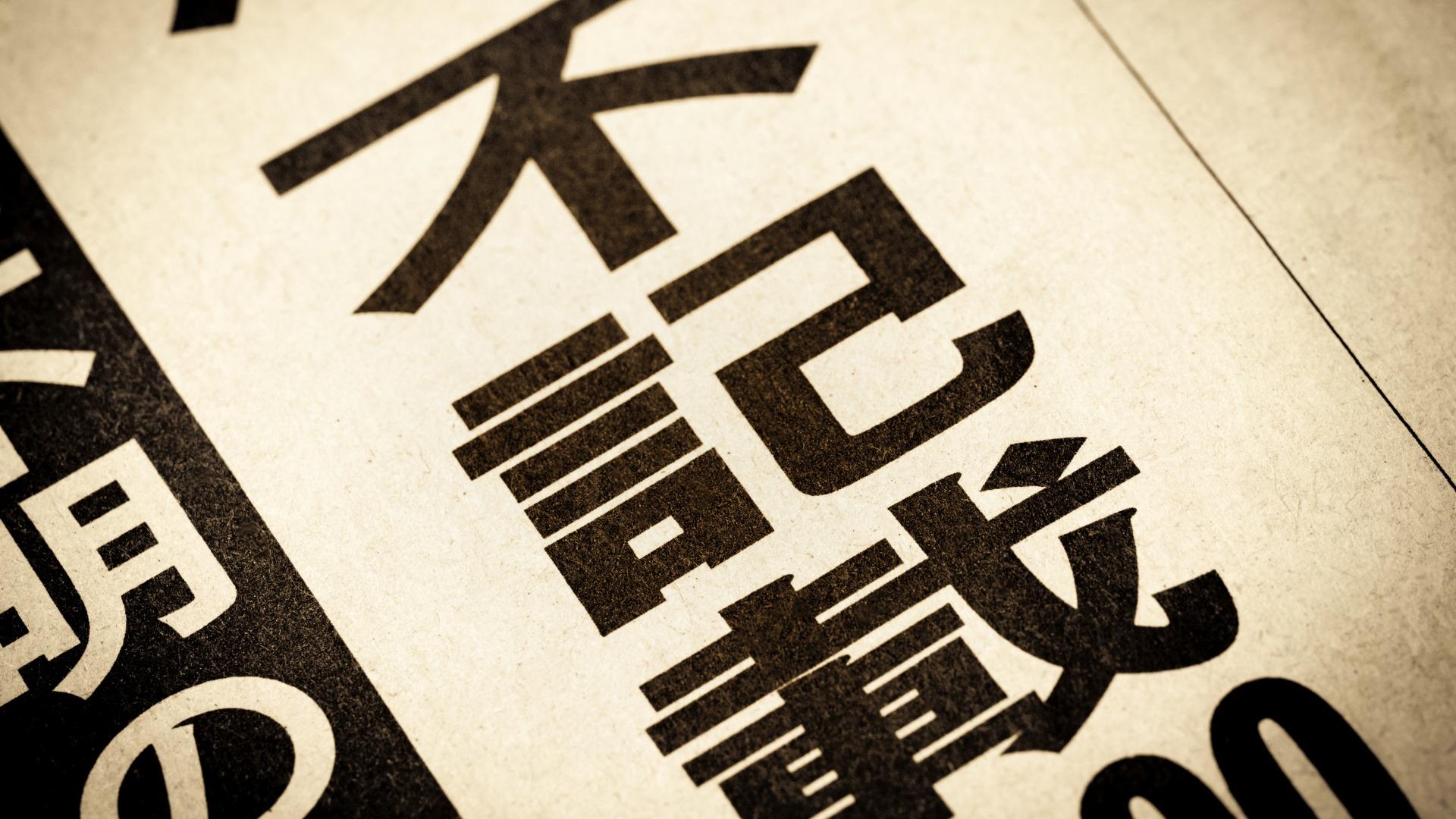
自民党の政治資金パーティーを巡る裏金疑惑について、東京地検特捜部は全国から応援検事を集め、100人規模という異例の態勢で捜査を進めている。焦点は派閥の幹部や所属議員らの立件の有無であり、来年1月下旬とみられる通常国会の開会に向け、これから大きな山場を迎えそうだ。
どのような事案か
この事件では、次のような疑惑が取り沙汰されている。
【安倍派(清和政策研究会)について】
・所属する衆参議員のパーティー券の販売ノルマ超過分を議員側に還流するとともに、参院選の年に開催したパーティーでは改選参院議員の販売ノルマを免除し、その販売分を議員側に全額還流か
・これらの収入と支出について、派閥の政治資金収支報告書に不記載か
・還流を受けた議員も、この収入について、自らの政治団体の政治資金収支報告書や選挙陣営の選挙運動費用収支報告書に不記載か
【二階派(志帥会)について】
・パーティー券の販売ノルマ超過分の収入を派閥の政治資金収支報告書に不記載か(ただし、超過分を議員側に還流するも、安倍派と違って支出として記載し、議員側も収入として記載か)
両派閥は、こうしたやり方で派閥や議員らが自由に使える多額の裏金を得たとみられている。その総額は、不記載の公訴時効にかからない直近5年間で安倍派が5億円規模、二階派が1億円超に上るという。金額こそ少ないものの、ほかの派閥でも同様の疑惑が浮上している。
何に使ったのかも重要となる。もとの収支を偽装していることから、領収証の受け渡しを要しない表に出せない使途に充てることもできるからだ。特捜部は、政治資金規正法違反の容疑で両派閥の事務所を捜索するとともに、派閥の幹部議員や事務担当者、還流を受けた議員、その秘書らの取調べを進めている。
裏金作りができる「カラクリ」
議員らがこうした大金を得られるのは、その収支を規制する政治資金規正法が「ザル法」だからだ。企業や団体の議員に対する寄附は禁止されているものの、政党や支部には寄附できる。政党が得た寄附を「政策活動費」といった形で議員側に寄附すれば、議員は使途の報告義務がない大金を手にできる。金額が億単位に上る議員もいる。その延長線上にあるのが、政治資金パーティーを巡る裏金疑惑にほかならない。
というのも、パーティー券の購入は企業や団体などでも可能だし、年間で20万円を超えなければ誰がいくら購入したのか明らかにする必要がなく、何枚売れたのかも議員側の自己申告だからだ。ノルマ超過分を「中抜き」して派閥に納めなかったり、いったん全額を納めた上で還流を受けたりすることも可能となる。後者だと議員側の認識も「政策活動費」と大差がない。
それでも、派閥や議員らがその政治団体の収支報告書に収入や支出として適正に記載していれば「合法」だ。今回はこれを欠いていたことから、捜査の対象となった。
一方で、政治資金規正法には自主的な「訂正」に対する規制がない。不記載は最高で禁錮5年、罰金だと100万円以下だし、有罪になれば選挙権や被選挙権が停止されるものの、収支報告書の提出後に収支額などを自由に訂正できる。何か問題があればあとで訂正すればよいというのが議員の発想であり、現に訂正が常態化している。
さらに、議員は政党支部のほか、資金管理団体や複数の政治団体を抱えており、どこに対する収入として記載するか選べるし、手持ち資金と混和するので、使途についても様々な弁解が可能となる。個人的な用途に使っていても、政治活動で使ったと言い張り、経費分の控除で議員の「雑所得」課税も回避できる。
不文律の「立件基準」も
こうした背景もあって、検察や裁判所は政治資金規正法違反を「形式犯」として軽くみる傾向にある。億単位でも逮捕せず在宅のまま略式起訴し、罰金で終わらせるケースが多いし、公判請求をしても、不記載だけで実刑になることはない。特捜部も、不記載の背後にある贈収賄や選挙違反といった実質的な悪質性の掘り起こしを重視することになる。
では、これが見込まれず、あるいは難点があって事件化に至らず、不記載の事件にとどまった場合、検察はどうするか。例えば脱税事件の場合だと、起訴して刑事責任を問うケースと修正申告で済ませる「申告漏れ」のケースを区別する際、3年分で総額1億5千万円以上、1年平均だと5千万円以上といった脱税額が一つの基準となる。これと同様に、国会議員絡みの政治資金規正法違反事件では、不記載の総額が「1億円」を超えなければ収支報告書の訂正に委ね、議員や秘書を起訴しないという不文律の「立件基準」が長らくあった。
ただ、検察の判断も、幹部の意向やそのときの情勢に左右される。自民党の派閥事務所が捜索されるのは、当時の橋本派(平成研究会 )への日歯連ヤミ献金事件以来、19年ぶりの事態だ。いまの最高検刑事部長は森本宏氏だから、最高検が事件を潰すという懸念もない。強気の姿勢が際立ち、特捜部長や東京地検次席検事などとして文部官僚、4大ゼネコン、企業トップ、国会議員らを次々と立件してきた人物である。
議員絡みの政治資金規正法違反事件の場合も、立件基準が「3000万円程度」にまで下がってきている。安倍晋三元首相の後援会が主催した夕食会の補填費などを巡る事件では、不記載の総額が約3000万円でも後援会の代表者を略式起訴したし、2年後の2022年には、パーティー券収入などの不記載の総額が約4900万だった自民党の薗浦健太郎元衆院議員を秘書とともに略式起訴している。
こうした立件基準の引き下げは、検察審査会の存在が影響しているものと思われる。議員は清廉潔白であるべきだという素朴な国民感情が議決に反映されるからだ。従来の「1億円」基準で議員のみならず秘書らまで不起訴にすると、「起訴相当」や「不起訴不当」の議決が下り、再捜査を余儀なくされる。特捜部としても、検察審査会を意識した捜査や刑事処分が求められる時代となっている。
安倍氏が不起訴になり、薗浦氏が略式起訴されたのは、検察の政権中枢に対する忖度という面もあるだろうが、「共謀」を裏付ける証拠の有無が大きかった。前者は秘書が全責任をかぶるという構図で否認され、覆す証拠もなかったが、後者では秘書が薗浦氏に報告し、薗浦氏も了承していたという事実を両者が認め、メールや資料などの物証でも裏付けられた。
今後の捜査の焦点は?
そこで、今後の捜査では、特捜部は次のような点を見極めることになるだろう。
(1) 派閥での不記載
・誰が、いつ、どのような形で還流の仕組みを考え、誰の判断で、なぜこれをその後も続けてきたのか
・誰から、どの議員に、いつ、どのような形で、いくら還流し、これまでの還流全体の総額はいくらだったのか
・各年度で政治資金収支報告書の不記載に関与したのは誰か
・不記載は誰の判断で、その経緯や動機は何だったのか
(2) 還流を受けた議員の不記載
・誰から、いつ、どのような形で、いくら還流されたのか
・各年度で政治資金収支報告書の不記載に関与したのは誰か
・選挙時の選挙運動費用収支報告書の不記載に関与したのは誰か
・不記載は誰の判断で、その経緯や動機は何だったのか
・還流された裏金を何に使ったのか
(1)については、両派閥の会計責任者が不記載の容疑を認めており、還流額などを一覧表の形で記録していたという。収支報告書の正確性について第一義的に法的責任を負うのは会計責任者だから、彼らの立件は不可避だ。過去の同種事例だと、在宅のまま起訴されるのが通常だが、金額の大きい安倍派の会計責任者の場合、捜査の展開次第で逮捕の可能性もある。
問題は、それ以外の関係者との共謀だ。歴代会長の安倍氏と細田博之前衆院議長は死去しており、刑事責任を問えない。そこで、この5年間に事務総長を務めた高木毅前国対委員長、西村康稔前経産大臣、松野博一前官房長官や、座長の塩谷立元文部科学相のほか、高木氏や西村氏、松野氏とともに「5人衆」と呼ばれる萩生田光一前政調会長、世耕弘成前党参院幹事長の関与が焦点となる。
ただ、たとえ自らも還流を受けるなどし、派閥における還流の事実を分かっていたとしても、派閥の収支報告書に収入や支出として記載されていれば問題ないので、不記載の認識があったことまでが必要だ。会計責任者の報告やそれに対する指示、了承の有無、その際の具体的なやり取りの解明が求められる。
特捜部は高木氏ら派閥幹部からも事情聴取を進めているが、不記載の認識を否認し、会長と会計責任者で決めていたなどと供述しているという。一方、会計責任者が事務総長に還流を報告したと供述しているとの報道はあるものの、肝心の不記載まで報告し、了承を得ていたのか否かは明らかでない。会計責任者が事務総長に報告し、事務総長から会長に報告されて了承を得るという構図だったとしても、安倍氏と細田氏から裏付けを取ることはできない。「キーマン」である会計責任者の供述に加え、事務総長らの指示を裏付けるメモやメールなどの物証が不可欠だ。
そうした中で注目されるのは、安倍派が2022年5月のパーティーの1カ月前である4月にいったん還流をやめると決め、議員側にも伝えられたものの、反発を受け、7月の安倍氏の死去後、8月にその方針を撤回したとされる点だ。還流や不記載が長年の慣習で行われてきたとしても、やめるか続けるかという重大事項を会計責任者の独断で決められるはずがない。還流をやめると決めたときの事務総長は西村氏、その方針を撤回したときの事務総長は高木氏が務めている。
重要な「ターニングポイント」だから、いかなる形でやめ、あるいは続けるのか、収支報告書の記載をどうするのか、会長や事務総長らに相談し、その指示を仰いだと考えるのが自然だ。還流の取りやめは会長である安倍氏の意向だったとされるが、だとすると異を唱えられるのは安倍氏にものを言える派閥の重鎮議員ということになる。
特捜部としても、こうした経緯を踏まえ、事務総長経験者に狙いを絞り、共謀立証に向けた証拠収集に重点を置くことになるのではないか。それでも、供述と物証が必要であることに変わりはなく、立件のハードルはなお高い。代替わりする事務総長の場合、会計責任者と違って刑事責任を問いうる不記載の金額も5年分ではない。2023年3月に提出された2022年分の収支報告書の不記載だけだと、逮捕を見送ることも可能となる。
還流を受けた議員の立件は?
(2)の議員に関する不記載についても、同様の捜査が必要となる。還流分の不記載が疑われる議員の数が多く、その金額も議員ごとに数万~5000万円超と幅広いから、例えば3000万円を超えているか否かにより、まずは立件するケースと収支報告書の訂正で済ませるケースとを区別することが考えられる。
その上で、議員が抱える複数の政治団体のうち、どこの収入とすべきだったのか特定し、会計責任者と議員との共謀を裏付ける供述や物証を収集することになる。2022年の薗浦氏の事件のようにこれが十分にそろえばまだしも、議員側が否認を貫き、物証などで崩せなければ、会計責任者だけが罪に問われて終わりということになりかねない。関係者の取調べとともに、関係先の捜索でどれだけ客観証拠を確保できるかが重要となる。
ただ、参院選の年に開催したパーティーで改選参院議員の販売ノルマが免除され、議員側にその販売分が全額還流された件については、別の問題を検討する必要がある。参院選の選挙資金としての還流ということになれば、自らの選挙陣営の選挙運動費用収支報告書に寄附収入として記載しないと、公職選挙法違反になるからだ。
最高で禁錮3年、罰金だと50万円以下と政治資金規正法違反よりも刑罰は軽いが、有罪になれば公民権が停止されることに変わりはない。第一義的な法的責任は出納責任者に課せられているので、ここでも議員との共謀の有無を見極める必要があるが、議員が還流分を直接受け取っていれば、選挙運動費用の寄附収入としての計上を出納責任者に指示する必要があるから、議員本人を立件しやすくなる。
それこそ、仮にこれを原資とし、2022年の参院選に際して候補者である改選議員から地方議会の有力議員らに支援要請の趣旨で現金がばらまかれたということになると、それも複数の議員・選挙区にわたる買収ということになると、さらに大規模な公職選挙法違反事件に発展する可能性もある。
特捜部としては、まずは派閥での不記載の問題を精査し、次に同時進行的に捜査を進めている個々の議員の不記載を見極める流れとなるはずだ。ただ、国会開会中は国会議員に不逮捕特権があるし、国会が始まれば予算審議などに大きな影響を与えないような配慮も求められる。通常国会までの期間をめどとし、急ピッチで詰めの捜査を進めることになるだろう。(了)
【この記事は、Yahoo!ニュースエキスパートオーサー編集部とオーサーが内容に関して共同で企画し、オーサーが執筆したものです。】










