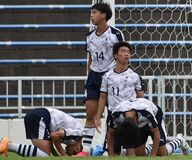関係の質を高めて成果を出そう

前回は、チームの健康診断をするうえで私が重要だと思う6つのチェック項目をお伝えしました。また、組織にとっての万病の元は「偽りの平和」であり、それを改善するための処方箋として「心の安全」という概念についても簡単にご紹介しました。
今回は、「心の安全」から生まれる好循環についてお伝えしていくこととします。

「偽りの平和」を脱却しよう
人は皆それぞれ違う価値観、思考、行動様式を持っています。
正解のあった時代には、その「違い」が邪魔となっていました。
そして、それを束ねる方法としてリーダーによる威嚇や権力を用いてきた時代もありました。
リーダー1人の価値観に全員をはめ込むことで「違い」を取り除き、統率を保ってきたわけです。
現代は劇的な変化が連続し、唯一の正解がない時代と言われていますので、時代背景も大きく変わりました。
1人1人が意見を押し殺して黙っている状態(偽りの平和)ではイノベーションが起こらず、ビジネスも停滞してしまいます。
偽りの平和は表面的には問題がないように見えますが、メンバーの納得感は低く、心の中はストレスでいっぱいの状態です。
「もっとこうしたら良くなるのに…」
「こんな計画、うまくいくはずがない…」
そんな不信感や疑問を持ったメンバーたちを権力や威嚇で黙らせているようでは、いつまでたっても主体的に仕事をしてくれる日は訪れません。
怒られないため、保身のためだけに仕事をし、予定調和で無難な行動しか起こさない組織は活気を失い、衰退の一途を辿ります。
そんな「偽りの平和」から脱却するための処方箋として「心の安全」という考え方があるのです。

「心の安全」とは
「心の安全」とは、「こんなことを言ったらみんなからどう思われるだろう」「こんなことを言ったら評価を下げられるかも」「余計な提案して責任を負わされたらどうしよう」という不安のない状態のことを指します。
私たちは、自分と意見の違う人に対して、(攻撃や防御など)ある種のアレルギー反応を起こすことがあります。
「心の安全」が担保されていれば、率直かつ建設的に議論ができるため、意見の食い違いを人格否定へとつなげず、「違いこそ武器」「違いこそ豊かさ」と捉えられるようになります。
「違い」に対して寛容になると、職場が安心・安全な場となって対話や議論が活性化します。
そして、多くのメンバーが議論に参加した末に重要事項が決定していけば、「自分も意思決定に関与した」という思いから責任感も湧いてきます。
仮に発言をしなかったとしても、「決定のプロセスを見届けた」という思いがあれば、高い納得感で仕事に向き合えます。
ましてや、自分の意見が採用されていればなおさら責任感は湧くことでしょう。
ここからは、そういう好循環を生み出すために必要なことをまとめていきます。

「北風マネジメント」
繰り返しになりますが、「心の安全」を担保するためには「人は皆それぞれ違う」という極めて当たり前のことを理解し、「違い」を武器にしようとするマインドが大切です。
つまり、権力や威嚇によるマネジメントを手放すことです。
ただし、「偽りの平和」は組織の生活習慣病のためすぐには改善できません。長期にわたる地道な取り組みで組織の体質改善を目指す以外に道はなく、緩やかに組織風土が変わっていくのが自然でしょう。
ここで「北風と太陽」の寓話をご紹介します。
北風と太陽が力比べをするため、どちらが旅人のコートを脱がすことができるかを勝負する。まずは北風が精いっぱいの強い風でコートを吹き飛ばそうとしたが、寒さを感じた旅人は逆にコートを強く押さえ込み、脱がすことはできなかった。いっぽう、太陽のほうはジリジリと旅人を照らし続けた。すると暑さによって、旅人は自らコートを脱いだ。結果として太陽に軍配が上がった。
この寓話から得られる教訓としては、「力で人をねじ伏せようとすると逆に反発を生みかねない」「自ら進んで行動を起こしたくなるような方法(仕掛け)を模索することが大切」ということです。
権力と威嚇で従わせるマネジメントのことを私は「北風マネジメント」と呼んでいます。
この手法では短期的に成果を上げることはできますが、メンバーが疲弊してしまうリスクがあります。
では、どうしたらメンバーの自立を支援できるのでしょうか。
人それぞれの違いを武器にするマネジメント手法を身につけることで、会社組織全体が自由闊達な風土になり、リーダーだけでは思いつかないようなアイデアに溢れた職場になることでしょう。
成功の循環モデル
リーダーは常に結果を求められる立場であるため、すべてを自分の管理下に置きたいと思ってしまいがちですが、それはメンバーの意欲を削ぐことにもなりかねません。
メンバー1人1人の違いや個性、すなわち多様性を生かすことでリーダーの想定を上回る成果が期待できます。
ここからは、「心の安全」が担保されたチームについて、「成功の循環モデル」に私の解釈を加えて解説していきます(図1)。

「心の安全」が担保されていて【①関係の質】が良好なチームでは、様々なアイデアが歓迎されるため、【②思考の質】が高まります。
仮に、メンバー間で意見が食い違ったとしても、両者納得の第3案を生み出そうと前向きなディスカッションをします。
そうやって決定した事項には納得感が高く、やり遂げようとする強い意志が備わり、【③行動の質】が高まります。
ポジティブで挑戦的なプロジェクトにワクワクしているメンバーたちは、少々の困難に直面しても粘り強く取り組むため【④結果の質】も向上します。良い結果を手に入れたメンバーたちは、お互いの努力を讃え合い、ますます【①関係の質】が良好になります。

「目標の質」の重要性
最近私がスポーツ現場で強く感じていることは、もう1つの「質」の重要性です。それは、【目標の質】です。
これについては、「チームづくりの教科書」(高野俊一著)にも書かれていました。
従来の「成功の循環モデル」は「関係の質」から始まるですが、そのサイクルのスタートは、「真に合意の取れた共感できる目標の存在」ではないかと気付いたのです。
なぜなら、目標の質によって関係の質も変わるからです。
それほど高くない目標であれば、ほどほどの関係性でも達成できるかもしれませんが、達成困難な高い目標に立ち向かうチームであれば、厳しいことも言い合える関係性でなければなりません。
特に、成果を出すことが義務付けられ、各部門のエース級が集められた短期プロジェクトチームなどは、目標の質からスタートし、どんな関係性で在りたいかを確認するほうが良いと思います。

衰退するチームが陥るバッドサイクル
次に、「心の安全」が脅かされたチームが辿る衰退(バッドサイクル)を考えてみましょう。
「心の安全」が担保されておらず【①関係の質】に不安を抱える組織では、周囲の目が気になり、思考は委縮します。
【②思考の質】低下が常態化すると、チャレンジすることよりも失敗しないこと(怒られないこと)を優先する臆病な組織体質になり、無難な行動ばかりを選択するようになってしまいます。
そのため、すべてのことがリーダーの想定以下でしか起こらなくなります。
良い提案も出てこず、言われたことだけを淡々とこなす職場になり、活気を失っていきます。まさに、【③行動の質】が低下している典型的な症状です。
予定調和で消極的な行動ばかりでは大きな成功は期待できず、【④結果の質】まで低下してしまいます。
結果の質が下がれば責任転嫁や犯人探しが始まり、ますます【①関係の質】は悪化します。
業績ばかりを求めるのは危険
バッドサイクルは、【結果の質】を重視することが原因となることもあります。
正しいプロセスを経ずに結果(業績)ばかりに執着するリーダーのもとでは、結果が出ないとメンバーは居場所を失います。
すると、チーム内で犯人探しや責任転嫁が始まって【関係の質】が低下し、バッドサイクルがまわり始めるのです。

まとめ
「成功の循環モデル」を読み解くと、結果(業績)を高めたいならば「合意の取れた真の目標」と「心の安全」が担保された人間関係の構築が最重要だとわかります。
組織にとっての万病の元、「偽りの平和」から脱却するためには、「北風マネジメント」による管理を見直し、メンバーの自由な発言を歓迎する風土を作ることが重要です。
仮にメンバーがリーダーの考えと異なる意見を提案したとしても、それはリーダーを否定したことにはなりません。
提案してくれたメンバーを反逆者のように扱わず、むしろ感謝を示すことでリーダーの意識改革・組織変革の覚悟を強く印象付けるメッセージとなるでしょう。
リーダーとメンバーの間で意見交換のできない状態は血流の悪い組織と言えます。
積極的に意見を求め、互いの考えを尊重しながら納得度の高い案を生み出せば、それはメンバーの “やる気” に変わります。
「自分の意見も採用された」「採用されなかったけど、十分に検討してもらった」「決定のプロセスを見届けた」そんな小さなことで「結果の質」に大きな影響をもたらすのです。
今回は、万病のもとである「偽りの平和」から脱却するための処方箋として「心の安全」「目標の質」というキーワードをもとに、成功の循環モデルについて解説しました。