『芋たこなんきん』が描いた「笑い」「友情」「老い」
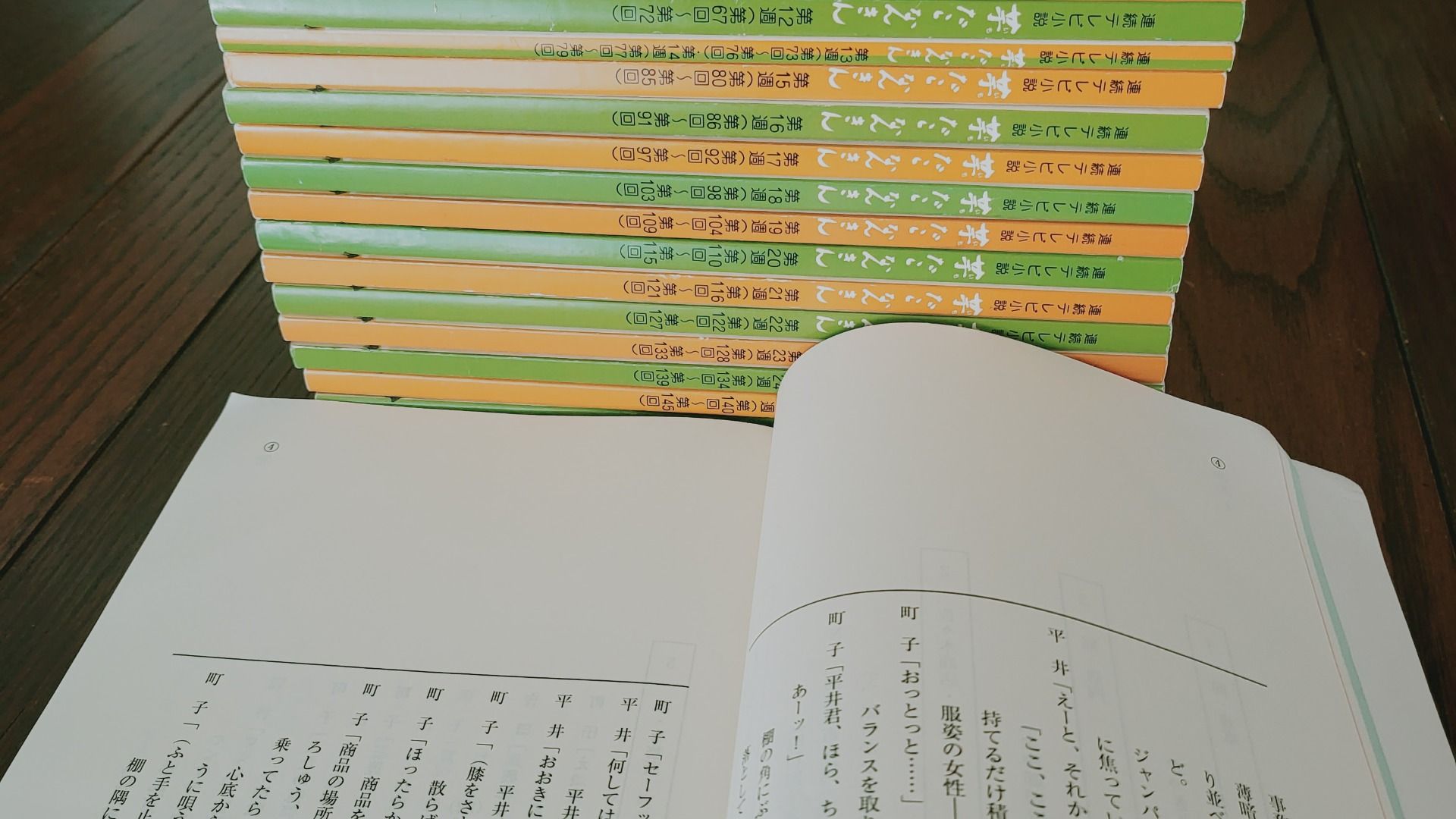
台本を作った上でセリフに「笑い」をプラスする手法
BSプレミアムでの再放送がとうとう最終回を迎えた『芋たこなんきん』。
朝ドラで常に最も難しいと思うのが、「笑い」の表現だ。なぜなら、15分の中で様々な感情を描くために、「笑い」の部分ではコテコテやドタバタ展開が浮いてしまったり、大げさなBGMに視聴者がノレなかったりすることが多々あるためだ。
その点、笑いのお手本とも言えるのが、本作である。脚本家の長川千佳子さんは言う。
「私はもともと芸人さんをすごく愛していることと、もともと大阪でバラエティの仕事もしていたこともあって、できればクスリと笑えるように、台本を作った上でセリフの時点で少々手を加えているんです」
本作の企画協力で外部プロデューサーの尾中美紀子さんが、こんな具体例を挙げてくれた。
「例えば、ツチノコ研究家・田村駒蔵(石橋蓮司)が東京土産を渡して、『あのーこれ、浅草の人形焼です』と言って、こっそりと『こしあんです』と付け加えるところに、あの人の奇妙なこだわりが見えてきますよね。あれは台本通りなんですが、そういったセリフのセンス。また、石橋蓮司さんが完全に役を理解して言っていただいている。その言い方がまたおかしくて」
いしだあゆみ演じる矢木沢純子も、笑いの要素として重要な役割を担っている。例えば、第40話で、町子(藤山直美)が逆上がりの練習をする清志にアドバイスしようと熱くなり、物干し竿でお手本を見せようとして腰を強打し、取材で来ていたカメラマンに写真をおさえられてしまったシーン。純子は「すっころばれたときのお写真は、今回は載せていただかないようにお願いしておきました」と言い、「良かった。そうかて、パンツちょい見えなんやもん」と町子が安堵すると、一言。
「イエ、丸見えでございました」
「いしだあゆみさんの『丸見えでございました』のセリフは台本を確認しましたが、現場で追加されたものでした! 台本では町子の『丸見えやったもんね……』を『ちょい見えやったもんね』にとどめておき、『丸見え』を純子さんに言わせるというナイスアイデア。このように、演出・出演者の方々がふくらませてくださった笑いのシーンもいくつもあります」(尾中さん)

「泣きながら笑う」「笑いながら泣く」が1番面白い
また、健次郎(國村隼)の亡き妻・澄子の手料理の漬物を子どもたちに食べさせようと、ぬか床探しをする展開が第72話で描かれた。
徳永家のぬか床は去年の夏にダメになってしまっていたため、たこ芳のりん(イーデス・ハンソン)が澄子に漬物を教わっていた話を聞き、訪ねる。しかし、りんが澄子から分けてもらったぬか床も、去年の夏にカビさせてしまって、もうないと聞いた純子のセリフ「んもう、去年の夏が目の前にいたらひっぱたいてやりたいです~!」によって、落胆する展開が一気に笑いに変わる。
「ああいう上品なぼけ方をするキャラクターは、なかなかいませんよね(笑)」(尾中さん)
「あれはキャラクターの笑いというよりも、『言わなくても良いことを言う』ギャグに近い笑いですね。大真面目なシーンや、シリアスなシーンほど、笑いって入れやすいんですよ。気が張っているときこそ、緊張と緩和で、ふと笑いが起こりますから。シリアスなシーンでの笑いは一歩間違えると場を台無しにする恐れもありますが、そこはキャラクターが愛されているから許される、笑ってもらえる部分も大きいと思います」(長川さん)
「『泣きながら笑う』『笑いながら泣く』みたいなことがやっぱり1番面白いなと思ってやっていましたね」(尾中さん)
16年ぶりに再確認された「カモカのおっちゃん」の魅力
長川さんは、脚本を作る立場からのキャスティングとして、藤山直美が重要であることはもちろんのこと、同様に大事だったのが「カモカのおっちゃん」だと語る。
「町医者として、一家の長としての役割を果たしながら、堅さと柔軟さ、ユーモアを併せ持ち、なおかつ、田辺作品に登場する『可愛げがある男』で大阪弁を操る……何というハードルの高さ(笑)。私の中では國村隼さん以外にはあり得ませんでした。それまでに何度か作品でご一緒させていただいていたり、藤山さんとの息の合った過去の作品を何本か拝見していたりしたこともあって、國村さんには絶大の信頼を抱いていました。お引き受けいただいたのは、本当に幸せなことでした。完璧な徳永健次郎が、そこにいました」(長川さん)
16年ぶりの「再会」となった今回も、「健次郎さん」の名前が何度もトレンド入りし、大反響を呼んでいる。
「16年ぶりに見た今回の再放送でも、新たに國村さんの、脚本へのアプローチの繊細さ、表現の深みを発見し、何度も変なうなり声が出ました(笑)。病に倒れた健次郎の体から発する光が徐々に薄く見えていくところなども、カメラのエフェクトなしで自然に出ていることに本当に驚きます。夫婦間の絶妙なイキはもちろん、昭一、晴子との兄弟、兄妹の、さらに、ツチノコ研究家の駒蔵、米春師匠たちとの、どのシーンも忘れられません。どの球が来るか読めず、しかしどれもが美しくストライクゾーンに入っていく……おかしみも悲しみも自然と湧き上がる……健次郎というキャラクターに何倍もの厚みを与えてくださいましたし、ツイッターの皆さんに、『カモカの色気ダダ漏れ』(笑)と、その魅力を愛されるのも当然ですよね」(長川さん)
非常に高度な笑いとなったのは、第78話。
お正月に作家・加藤舞子(岡田茉莉子)や編集者(もたいまさこ)らが徳永家に遊びに来て、ワイセツ談義で盛り上がるくだりだ。
永井荷風の作と言われる『四畳半襖の下張』について、「性的毒性がない分、ワイセツじゃないと思うんですけど」と編集者が言えば、町子が「毒なんかありませんもんね」と応じ、舞子が「そもそもワイセツとは何でしょう」と言い出し、男性のいる前でとたしなめられると「何言うてんの! 男性の前で、なんで遠慮せないかんのよ」と怒る。それに対して健次郎が「ご婦人方の前ですが、ワイセツと言うと、僕の場合は『忠臣蔵』なんです」と意外な見解を語り始め、なぜか舞子と下ネタで意気投合するのだ。
「田辺聖子さんがモデルの今作で、田辺さんは女性の作家さんとしては珍しく下ネタもエッセイなどでよく書かれていて、それらの下ネタが下品にならず、面白くて上手いという評価があり、これはハードルが高いけれど、小説家・エッセイストとしての作風をどこかでぜひ入れたいということは話していました。それで、佐藤愛子さんモデルの岡田茉莉子さん演ずる加藤舞子さんがいて、しかもお正月という空気感の中だったらできるだろう、ここしかないと(笑)」(尾中さん)

「更年期障害」「シスターフッド」を描いた理由
後半で、純子の更年期障害を描いたことも挑戦的だった。
「医師の健次郎さんも含めて、男の人は気がつかないけど、晴子さんは気づいていて。当時、まだ更年期障害に関する情報がなかったかと言うと、そんなことはないんですね。私の周りにも、少し上の世代の人たちでその時期を乗り越えてこられた方が何人かいて、日常的にそんな話をしていました。女の人たちの場ではたまに語られることですが、ドラマで描かれることは少なかったかもしれません」(長川さん)
また、仕事の失敗で町子に迷惑をかけたくないからと、秘書をやめようとする純子と、引き留めるために手紙を書こうとしても書けず、「経歴書」を渡し、そこに二人の出会いが書かれていた……という、町子とのシスターフッド的展開にも泣かされた。
さらに忘れられないのは、最終週の町子と純子の結びつきだ。
健次郎の悪性腫瘍が発覚したとき、本人に本当のことが言えない町子に対し、純子は今までどんなことでも話してきた夫婦だから、大切なことはちゃんと伝えるべきだと諭す。それにより、町子が健次郎と一緒に病気と闘う覚悟ができたのだ。
「実は私自身、シスターフッドとして描いたわけではなく、『シスターフッド』という言葉もSNSの反響などを見て、改めてみると、『あ、これって、そうなんだな』と気づいたくらいでした(笑)」(長川さん)
「ドラマに登場する人物たちは、会社や事業のようなものだと思っているんですよ。男性もいるし、女性もいるし、年配の人もいるし、子供もいて、みんなそれぞれの役割を持っている。そんな中、朝ドラの大多数は女性が主人公の物語なので、女性同士の友情などを描くことが割合として多くなるのは、自然な流れでした。ただし、友情でも、若い女性同士とは違い、年齢を重ねたからこそ共通項となる経験もたくさんあって、つながっていく関係もありますよね」
そう言って尾中さんが挙げたのが、終盤において、純子が編集者・北野(RIKIYA)からの交際の申し込みを断り、後に北野が他の女性と結婚することになった報告を受けたくだり。純子は笑顔で祝福した後、路地裏で一人、北野との出会いと交流の数々を思い出す。しんみりと切なく、しっとりしたシーン。ところが、その直後に飛び出してきたネズミに悲鳴をあげ、飛び出してきたアムールのママに「どないしはったん?」と聞かれて「大きいネズミ」と言うと、こう言われる。
「何を言うてんの? もう! 一人で生きてる女がネズミごとき怖がってたら世の中生きていかれまへん!」
ちゃっかりがめつくて、下世話キャラに見えるアムールのママが、ロマンチックで切ない恋の顛末を蹴散らし、空気を一気に笑いに変えたうえ、一人で生きる純子の背中を押すのもまた、シスターフッド的である。ちなみに、徳永家でもたこ芳でもダメにしてしまった澄子のぬか床をしっかり守っていたのも、アムールのママだった。
「大阪の下町って、実際にあんな感じだったと思うんですよ」(長川さん)
「商売人もみんなたくましくて、そもそもこの物語の中、仕事していない女性はほとんどいないですからね。全く働いていないのは小学生くらいじゃないですか。その小学生も学校に行かないなら仕事を探せといわれてるし(笑)」(尾中さん)
また、「不倫」がさりげなく描かれている作品でもあった。
「田辺先生の小説の中で、不倫をしている男女の話があるんです。それは、ドラマの中ではあまり上手に描けなかったんですが、季節ごとに会うたびに美味しいものを一緒に食べるという共通の喜びを持って、頑張って仕事をしていくっていう、男女の恋愛だったり友情だったりというのも、先生の小説にはたくさん出てくる要素の一つです」(長川さん)
「お母ちゃんにも明日への期待いうもんがあるの。未来があるの」
夫の死後、奄美大島に帰ることを決意する健次郎の母・イシ(岩本多代)と、結婚を決めた息子に同居しようと言われ、断り、高層団地に住む町子の母・和代(香川京子)の「老い」と「人生の選択」にも称賛の声が多かった。
特に印象的だったのは、一人暮らしをすることを決めた和代の「毎日お稽古でお友達とも会えるし、行きたいとこもいっぱいある。新しいとこ引っ越したら『お部屋どないしよう? どんなカーテンにしよう? 何飾ろう?』って、もう楽しみで。寂しいなんかしてる暇あれへん。これからの楽しみ取り上げんといてちょうだい。お母ちゃんにもね、明日への期待いうもんがあるの。未来があるの」というセリフ。
「奄美大島に帰るお母さんはオリジナルで作ったエピソードです。田辺先生の小説には年配の方が登場するものが多いんですが、1人暮らしをしていて、近所の青年が来てくれて、お料理を作ってという日常を楽しんでいる描写がたくさんあるんですね。それを1つのモデルとして、お母さんには後に同居される前、一人暮らしする段階ではその理由を、ちょっと新しいぶっ飛んだものにしたかったんです」(長川さん)
そんな和代は、町子が健次郎の病状について医師に聞きに行く際、純子に同行を頼む。また、町子が健次郎と共に病と闘っていくと決意した矢先、足をねん挫してしまうが、町子の負担を心配した弟・信夫(西興一朗)が和代を引き取ると言っても、悲しむ町子のそばを離れないと主張。それも、町子の前ではあくまで町子のためと言わず、年寄りのわがままと言って飄々と縫物をしながら。何歳になっても母親は母親なのだと改めて感じ、泣かされた視聴者は多かったことだろう。
「田辺先生のお母様には直接お目にかかったことはないですが、『芋たこなんきん』の企画がスタートし、撮影に入る頃に入れ替わりのように亡くなられているんです。ご長命でした」(尾中さん)

「あえて書かない」部分への思い
本作には数々の名ゼリフがある一方で、高く評価されているのは「あえて書かない」部分も多いこと。「省略」に対する思いについて、長川さんは言う。
「イシさんが奄美大島に帰る時の最後のご飯のシーンでは、晴子さんにイシさんが料理をあんたも覚えなさいよみたいなことを言って、あのしっかり者の晴子が母との別れにこらえきれず台所に立ち、皆には背を向けて静かに1人で泣いている、みたいなところですね。あの場面で親子で何か言い合い、抱き合って泣いてもつまらないと思いますし、そこは役者さんに委ねることにより、さらに1つ上の表現をしてもらえる楽しみもあります。今は全部ト書きで説明する脚本が多いようですが、心情などを全て書いてしまったら、役者さんもたぶん面白くないでしょうし。実際、役者さんの楽しみっていうのもそこにあると私は思うんですね。脚本に何でもかんでも書いてしまうと、盛り上がっているつもりに現場ではなるけど、実は視聴者には何も伝わらない。離れたところでそっと泣いている人がいて、それに気づいている人と気づいてない人がいて、その両方を見られる視聴者というのが、一番贅沢な視点だと思うんですよ。せっかく晴子のキャラクターがあるのだから、みんなの前で涙を流すなんてしたくないわけです」(長川さん)
「そしてそして、この作品が世に出ることができたのは、誰が何と言おうと、ヒロインをドンと引き受けて下さった藤山直美さんがあってこそ。直美さんの女優としての凄さは、いくら書いても書ききれないと思います。でも、いくら字数を重ねても、ドラマをご覧になっている方には言わずもがなでしょう。かえって野暮なことのようにも思えてしまいます。我々としては、ひたすら決まっていた舞台を止めて『芋たこなんきん』というドラマ企画を信じて半年間を預けていただけたことが、今でも奇跡のようなことだったと思います。あらためて感謝しかありません。いつまでもチャーミングな女学生みたいな直美さんに魅了され続けた半年間でした」(尾中さん)
ちなみに、現在は石垣でバーを営む傍ら、小説を書いているという長川さん。尾中P×長川脚本作品の新作を望む声も多いが……と問うと、こんな返答があった。
「10年のブランクを簡単に超えられるほど簡単な仕事ではないですからね……ただ、そうした言葉をたくさんいただけるのは、本当にありがたいです」(長川さん)
「今こうして再び半年にわたり視聴者の皆さんとつながり続けられたことは、やはり『NHK連続テレビ小説』という特別な枠だからこそ。作品に関わったすべての方々は、2006年の秋を一緒に闘った同志だったと、振り返って改めて思います」(尾中さん)
さらに尾中さんは、こっそりこんな思いを語ってくれた。
「長川さんは芋たこの最終週を書き上げたとき、まだあと半年くらいは書けそうです、と言ってました。登場人物がまだ生き生きと動いていたんですね。本人はどう思っているのかわかりませんが、私はできれば長川さんには大型時代劇ドラマを書いてほしかったんです。長川さんは骨太のダイナミックな世界が書ける作家だと思います。もうフル充電なんじゃないかと(笑)」
(田幸和歌子)










