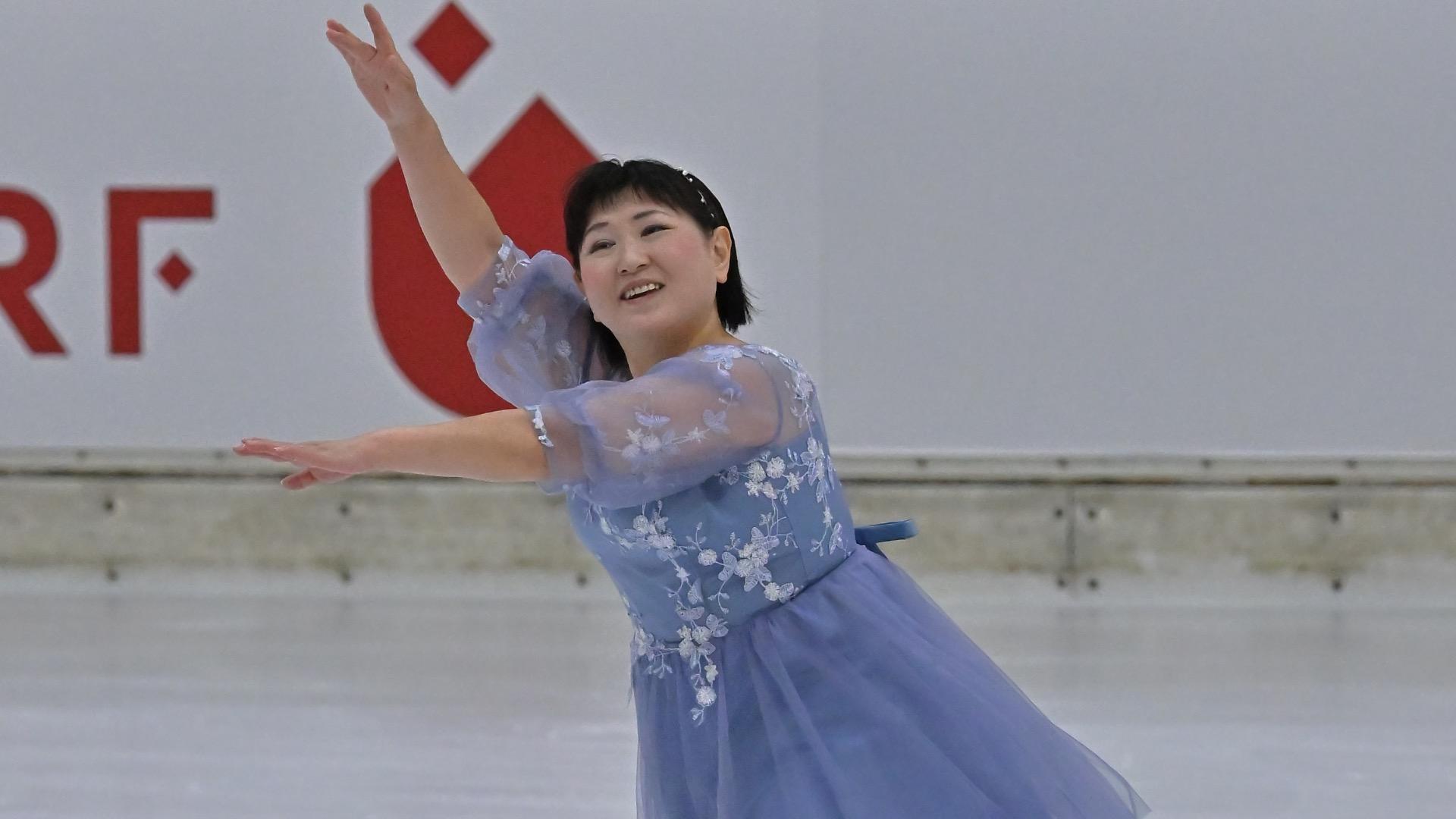前編2019年のEUを振り返る。ブレグジット・汎欧州支払システム計画・ユンケル退任ー2020年への道

もうすぐ2019年が終わろうとしています。
今年、ヨーロッパと欧州連合(EU)を観察していて筆者の目についたことを、前編・中編・後編に分けて書いていきたいと思います。今、欧州中央時間で大晦日の13時半くらい。日本では21時半くらいです。なんとか日本で年明けの前に終わらせたいです。
<前編>ブレグジットについて
ブレグジットに関しては、もう説明するまでもない。あまたの情報が流布している。
それでも筆者の問いは続いている。「なぜ、イギリスだけが」。
「なぜイギリスだけが」を考える
グローバル化の疲れは、イギリス以外のEU加盟国でも起きている。EUに関係ない日本でもアメリカでも起きている。そもそもEUがどんどん強くなっていったのは、グローバル化する世界で団結する意味が強いのだ。なぜEU離脱する必要があるのだろうか。
説明は色々考えられる。
◎EU=にっくきグローバル化の象徴、となった。
◎ヨーロッパ大陸の国々よりも、言語と歴史を共有する英連邦(コモンウエルス)の国々(=旧植民地)のほうが近い存在である。
イギリスは、EU域内の移民を受け入れるよりも、英連邦の人々を受け入れるほうを好んだ。そして、イギリスに住むそういう移民(起源)の人達も、EUよりも英連邦のつながりを望んだ。
この問題を、もう少し詳しく考えてみる。
英連邦には、正確には2種類ある。
一つは、「英連邦王国」。君主がエリザベス女王となっている国々である。カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ジャマイカ、パプアニューギニア、ソロモン諸島、ツバルなど、全部でイギリスを入れて16カ国ある。イギリスの旧植民地で、小さな島国が圧倒的に多い。
もう一つは、単純に「英連邦」。全部で53カ国。こちらもほとんど全部がイギリスの旧植民地である。前述の「英連邦王国」の16カ国に加えて、エリザベス女王が国家元首ではない国が37カ国となっている。
ゆるやかな連邦で、どのくらいの力があるかは判断が分かれる。一般的には、インドなどのように自国の力が強くなればなるほど、旧宗主国=旧支配者との距離は離れていく傾向がある。何よりも、イギリスそのものに昔日の力がない。
イギリスでは、特に英連邦王国から来る移民が優遇されているし、多いと思う。彼らは英語を話すし、旧宗主国の責任もあるのだろう。白人ではなく、肌の色の異なる人々が多い。
そして、歴史的には第2次世界大戦における連帯が重要である。ノルマンディー上陸作戦で、独伊日の枢軸国に対抗した軍隊は、イギリスとアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド等の英連邦王国や、旧植民地の国々からやってきた人達の軍隊であった。彼らが欧州大陸に「自由」の勝利を導いたのだ。
筆者はそれほど長い期間ではないが、イギリスに住んでいたことがある。そのときに、お墓からミュージアムまで、この大戦の歴史はイギリスに深く刻まれていることがわかった。
彼らは、ヨーロッパよりも英連邦の団結を支持している傾向が強い感じる。当然といえば当然だ。想像してみてほしい。イギリスには、例えばインド起源のイギリス人がたくさんいるが、彼らはEUの連帯と英連邦の連帯のどちらを支持するだろうか。南アフリカ起源、ジャマイカ起源などの人々も同じである。
(ちなみにスコットランド独立投票のときも同じだった。このような移民(起源)の人々は、独立よりもイギリス残留を支持していた)。
不思議な感じはする。人種対立や人種差別は、それほど昔の話ではない。改善され進化してはいるが、今でも現在進行系だ。肌の色だけではなく、さらに宗教問題が加わる。英連邦の国には、イスラム教徒が多い国もあるので、イスラム教徒の移民も多い。
それなのに、同じヨーロッパ人で白人でキリスト教の文化を共有しているポーランドEU域内移民よりも、肌の色の異なり、時には宗教の伝統すら異なる英連邦の人々のほうが良いということになるのだろうか・・・。
それとも、これからのイギリスは、排外的な空気が高まって、肌の色の異なる移民も排斥するような空気が高まっていくのだろうか。英連邦の絆を強調するのは、カナダやオーストラリア・ニュージーランドなどの先進国に限られていくのだろうか。
さらにもう1点。この議論には反論もできる。「フランスだって同じである」と。
現在、フランスが正規移民として受け入れるのは、圧倒的にフランス語圏(=旧フランスの植民地)の人々が多い。第2時世界大戦で、フランスの旧植民地からやってきた人々の軍隊が、フランス解放に貢献した歴史も、イギリスとほぼ同じである。
でも、フランスではEU離脱の動きはない。イギリスとフランスはどう違うのか。
おそらく、イギリスの旧植民地がカナダ・オーストラリア・ニュージーランド(英連邦加盟国)、そしてアメリカ等と先進国が存在するのに対して、フランスの旧植民地にそのような国はないことが挙げられる。
スコットランドと北アイルランドの変化
今後を占うので大事なのは、スコットランドと北アイルランドの動向だろう。
スコットランドで、スコットランド国民(民族)党が、議席数を35から48へ大幅に伸ばしたのは、日本でも報道されている。
党首のニコラ・スタージョンは、スコットランド独立の是非を問う2度目の住民投票実施を公約に掲げ、議席数を伸ばしたのだ。
彼女は、この成功によって住民投票への信任を得たと語った。
前回の投票は、キャメロン元首相が許可をして行われたが、ジョンソン首相は許可しない旨を表明している。もし投票を強行するのなら、カタルーニャ問題と重なる所が出てくるだろう。
ただ、カタルーニャは独立しなくてもEUにいられる。スコットランドは、独立しないとEUに残れないのだ。
それと北アイルランド。日本語ではほとんど報道されていないが、総選挙の結果、北アイルランドの強硬イギリス派である「DUP党」(北アイルランド民主統一党)は、10議席をもっていたのに、2議席を失って8議席になったのである。
この議席はどこにいったのか。
1議席は、アイルランド強硬統一派である「シン・フェイン党」へ、もう1票は、中立的な立場である「北アイルランド同盟党」にいった。
今まで北アイルランド議会では、イギリス派とアイルランド派が完全に拮抗しており、話し合いで議会が成り立たず対立したままで、無地方政府状態が続いていた。
しかし、この英総選挙でこの拮抗が崩れてしまい、アイルランド派に傾いてしまった。
強硬イギリス派は、2つの打撃に肩を落としているという。一つはこの議席減、もう一つは、保守党の大勝利により、イギリス中央政府は、北アイルランドの「DUP党」の言うことなど聞かなくても、政治を進められる状況になったことだ。
今までは保守党は過半数に届いておらず、「DUP党」と閣外協力をすることで、政権の安定をはかろうとしていた。これは保守党政権のあしかせとなった一方で、北アイルランドの親イギリス派の意見を中央の政策(特にEUとの関係)に反映させる効果があった。
やはりアイルランド島は、どんどん統一され、イギリスは北アイルランドを失う方向に行くのだろうか。
二つの「連合」が重なる時
もともとイギリスというのは、アメリカと同じで「コミュノタリズム=コミュニティ主義」の国である。
各コミュニティが独自の文化を守って、コミュニティ単位で生きる。そのためには、特に学校で公立ではなくて私立が必要になる。
これは、例えば「ロンドンの中のインド・コミュニティ、ポーランド・コミュニティ、あるいはイスラム教徒コミュニティ、パキスタン・コミュニティ」等々というような形もとるし、もっと大きくは「イングランド・ウエールズ・スコットランド・北アイルランド」という形にもなる。
これはフランスと大きな対象をなしている。フランスは「革命旗」を中心とした超中央集権国家である。そのために「ライシテ」と呼ばれる、公共の場や公共の職での非宗教性が極めて大事となる。宗教の自由は「個人の自由」の範囲なのだ。
民主主義とは、自由と平等が必須である。しかしこの二つを完全に両立することは不可能である。自由を追求すれば、不平等が生じる。平等を追求すれば、不自由さが増していく。アメリカとソ連の対立は、自由と平等の対立でもあった。ソ連は自由を殺しすぎて、民主主義の範囲を逸脱して崩壊した。
いわば、民主主義の範囲で、アメリカとイギリスは「平等より自由を重んじる国」、フランスは「自由よりも平等を重んじる国」である。
それでもイギリスやアメリカで一つの国が成り立つのは、どちらも島国だからである(筆者の持論は「アメリカは、ほとんど巨大な島国である」)。
欧州大陸では、ハプスブルク家のオーストリアが「連邦制」という形で各民族、各コミュニティを包括していたが、革命と共に崩壊して消滅してしまった。
統一するために、アメリカは星条旗を掲げて「アメリカは自由の国」「我々はアメリカ人である」と叫び続け、イギリスはユニオンジャックを掲げ「God Save the Queen」を歌う。
しかし地理的に比較的孤立しているアメリカと異なり、イギリスは目の前の欧州大陸で「欧州連合」が進んでしまった。
大小二つの「連合(ユニオン)」が重なる時ーー小さい方の連合は、遠い将来には大きいほうの連合に吸収されて解体されていくのかと思いきや、そうではなかった。大きい連合に反発して離脱して、一つのnation(国家)を守ろうとした結果、解体の危機を迎えるとは、未来はなんて想像不可能なのだろうか。歴史というのは、だれも想像ができなかった大きなうねりによってつくられていくのだろう。
中編と後編に続く