中国・清朝末期の壮大なドラマにタカラヅカが挑む、雪組『蒼穹の昴』
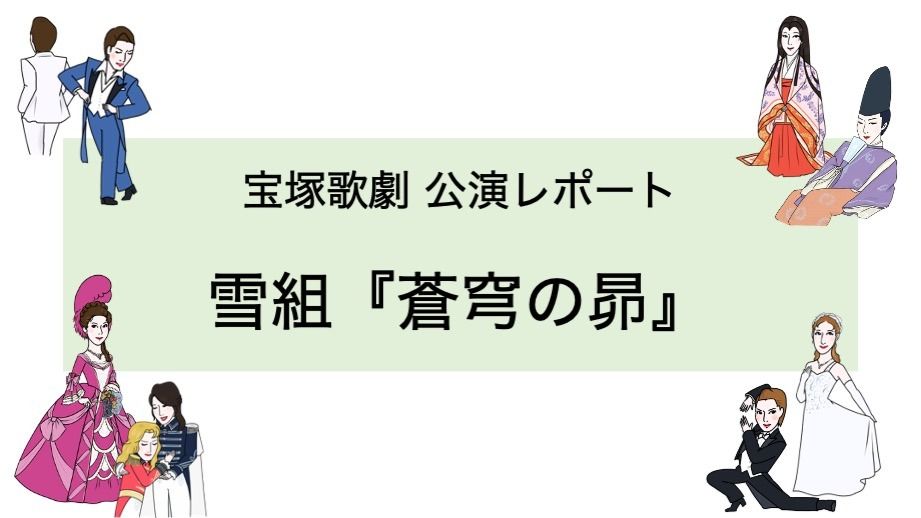
雪組公演『蒼穹の昴』が、初日の幕を開けた。
原作は、浅田次郎の人気長編小説である。事前に原作小説を読み始めたところ、あまりの面白さに全4巻をあっという間に読破してしまった。しかも、発表されているキャストが皆、適役だと思った。これは見応えのある舞台になるのではと、高まる期待の中で迎えた初日だった。
いつもと違って縦書き・右開きのプログラムからも、こだわりのほどが感じられる。洋物とは一味違う衣装の色使い、箏や胡弓、銅鑼の音色の加わった音楽、何もかもが新鮮で、大階段をうまく使った紫禁城の場面には思わず息を呑んだ。フィナーレのパレードでもいつもの羽根は背負わず、中国風の豪華な衣装で通して作品の世界観を守っていた。
何より、幕が下りた後も激動の時代を生き抜いた人々の姿がしみじみと思い出され、心地良い余韻に浸ることができたのが良かった。
物語の舞台は19世紀末の中国・清朝の末期、西欧列強の脅威が迫る中、保守派と改革派が対立する時代である。世界史の教科書では次のように説明されている。
日清戦争敗北の衝撃のなかで、中国では、日本の明治維新にならおうという意見が台頭し、国会開設や憲法制定による、立憲君主制に向けての改革をおしすすめようとした。康有為を中心とした改革派は1898年、光緒帝を説得して政治の革新を断行させた(戊戌の変法)。しかし、保守派は西太后と結んでクーデタ(戊戌の政変)をおこし、光緒帝は幽閉され、康有為や梁啓超らは失脚して日本に亡命し、改革は3カ月あまりで失敗に終わった。
(山川出版社『詳説世界史B』の記述を筆者要約)
こうした時代背景の中、物語は改革派のひとりとして奮闘する梁文秀(リァン ウェンシウ・彩風 咲奈)と、宦官の頂点に上り詰めて西太后の信を得る李春児(リィ チュンル・朝美 絢)の二人を軸に展開する。同郷に生まれ、深い絆で結ばれながらも、真逆の道を歩むことになる二人の物語である。
主要キャラクターが、みんなハマり役
彩風演じる梁文秀は、科挙の試験に一位で合格する秀才だが、元来は次男坊らしい自由奔放な性格だ。改革派の一員だが、現実を誰よりも冷静に見据えている。バランス感覚あふれるその中に、国の未来のため、貧しい人々のために尽くそうという確かな志が伝わってくる人物だ。
とかくバランスの取れた人というのは魅力的な主人公になりにくいが、それをやってのけられるのが彩風咲奈というスターの持ち味だと、改めて思った。
朝美演じる李春児も、これまたハマり役だ。たとえ衣装はボロボロでも、不思議に人を惹きつける煌めきがある。その天真爛漫さで、誰もが応援せずにはいられなくなる存在だ。貧しさに喘ぐ生活の中で「宦官になるしかない」という痛ましい決意をするまでの芝居にも、説得力を感じた。師匠・黒牡丹(ヘイ ムータン・眞ノ宮るい)との京劇の場面は、この作品ならではの見どころの一つになるだろう。
今回、娘役に見せ場が少ないのは残念なところだが、これは原作の主な登場人物に女性が少ないため致し方ないのかもしれない。それでも、中国物らしい華やかな衣装で娘役が居並ぶ様は目に楽しい。
その中にあって、李玲玲(リィ レイレイ・朝月希和)のシンプルで可愛らしい衣装が逆に目を引く。それがまた、玲玲の純粋さを際立たせているようでもある。だが、その胸の内には譚嗣同(タン ストン)への温かい愛情と文秀への特別な想いが複雑に交錯する。今回が卒業公演となる朝月が、集大成としてのこの役柄をいかに繊細に深めて見せてくれるかも楽しみだ。
にわか原作ファンの私が圧倒されたのは、順桂(シュンコイ・和希そら)が先祖から受け継いでいる「ある使命」を果たす場面だ。順桂は寡黙でクールな雰囲気をまとう人物だが、内に秘めた熱い思いと、それを支える満州旗人としての誇りが、歌とダンスから切々と伝わってくる。「舞台で見ることができて本当に良かった」と実感できる場面の筆頭である。
時代が違えば名君と言われたかもしれない悲運の皇帝・光緒帝 載湉(ツァイテン・縣千)。辛抱役だが、大階段にしつらえられた豪華な玉座がよく似合う。ミセス・チャン(夢白あや)は、紫禁城の女性たちとは一味違う現代的な美貌とふるまいで、少ない登場シーンの中、キーパーソンとしての存在感を見せた。
作品に重厚感を加える専科の6人
今回、専科から出演している6人が、それぞれ重要な役柄を演じている。
文秀と春児の運命を左右する占い師・白太太(パイタイタイ・京三紗)の温かみ、まるで本物が蘇ったかのような伊藤博文(汝鳥伶)、改革派の支柱としての楊喜楨(夏美よう)の信頼感、権力欲に振り回される栄禄(悠真倫)の滑稽さ、武人の鑑のような李鴻章(凪七瑠海)の威容、そして、落日の帝国を支える女帝・西太后 慈禧(ツーシー・一樹千尋)の深い孤独と哀しみ…その手堅い布陣が作品に重厚感を加えた。
対する雪組メンバーも健闘している。「ペンで闘う者たち」の芯としての岡圭之介(久城あす)の佇まい、裏切り者・袁世凱(真那春人)の一筋縄ではいかないコンプレックス、涙なしでは見られぬ優しい譚嗣同(タン ストン・諏訪さき)の決断、皇帝を扇動する康有為(カン ヨウウェイ・奏乃はると)の賢しさ、我が道を行く王逸(ワン イー・一禾あお)の一途さ、そして、スチール写真からして度肝を抜かれる安徳海(アン ドーハイ・天月翼)の役者魂…など、とにかく個性あふれる登場人物が多く、印象に残る場面は枚挙にいとまがない。
回を重ねて凄い舞台になる予感が…
宝塚歌劇の歴史を振り返ってみると、中国物の一本物は『虞美人』(1951年)、そして『紫禁城の落日』(1991年)以来、久しぶりの上演になる。しかもこのご時世、乗り越えなければならない障壁も多かったに違いない。カーテンコールでの彩風の挨拶からは、ようやく無事に初日を迎えられた安堵感と、今後さらに作品を進化させていく決意が入り混じって感じられた。
そもそも、あの壮大な原作を、3時間の舞台でも描き切るのは至難の業だ。今回の舞台は基本的に原作に忠実な作りだが、その分ダイジェスト的になり、登場人物の重要なバックグラウンドや複雑な人間関係など、どうしても描き切れない部分が出てくる。それ故のわかりにくさはあるかもしれない。
だが、出演者の一人ひとりから、短い見せ場の中に各キャラクターの抱えているものを全力で出し切ろうという貪欲さが、初日でさえ伝わってきた。もともと、どの登場人物も深い業を抱え、宿命を背負っている物語である。回を重ね、それらが各キャストの芝居に凝縮されていけば、これは凄い舞台になっていくのではないか…そんな予感がする、これからが楽しみな作品である。










