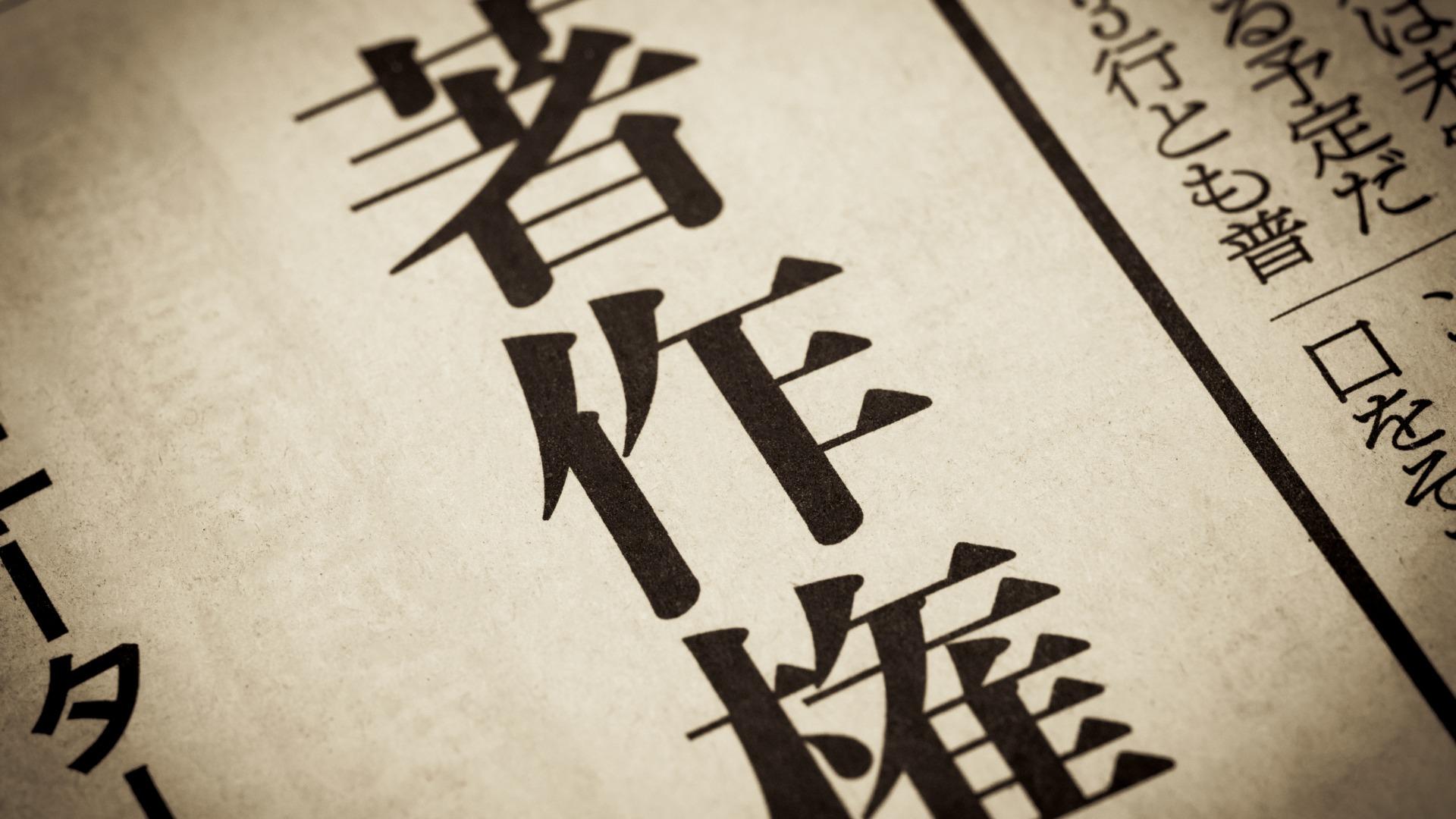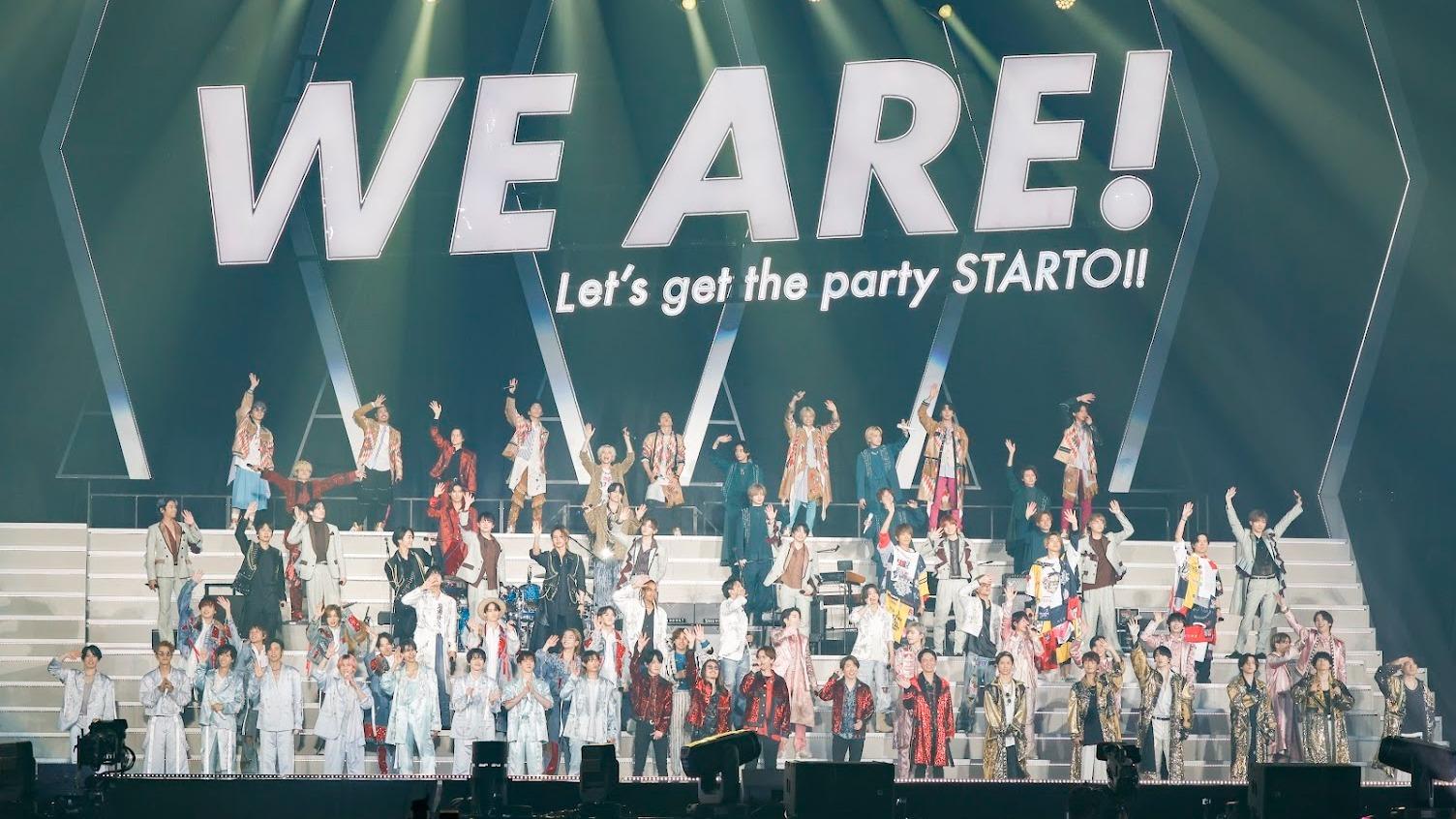米国での銀行からの資金流出とその行き先

米国では3月にシリコンバレー銀行(SVB)とシグネチャー銀行が相次いで破綻し、金融不安が燻るなか、預金保険の上限額の25万ドルに焦点が当たり、大口預金者がMMFになだれ込んでいる。
MMFとはマネー・マネージメント・ファンド(Money Management Fund)の略称である。主要な投資対象を国債など国内外の公社債や譲渡性預金(CD)、コマーシャル・ペーパーなどの比較的安全性の高い短期金融資産とするオープン型の公社債投資信託である。
預金金利よりもMMFの運用利回りのほうが高いことも、資金シフトにつながっている。米連邦預金保険公社(FDIC)が集計する1年物の譲渡性預金(CD)の金利は1.5%程度。また、貯蓄口座の全米平均の金利は0.3%台にとどまっている。
一方、主要MMFの平均利回り(1か月物)は3月、4.5%になった。米2年債利回りは3月8日に一時5%台に上昇していた。
米国債の利回りはいわゆる逆イールドとなっている。これはつまり中短金利のほうが長期金利よりも高い。
FRBが急激な物価上昇を受けて、利上げを急ピッチに進め、FF金利を引き上げた結果、中短金利が大きく上昇した。それに対して長期金利の上昇は抑えられた。
金利上昇による景気への影響が懸念されていた側面もあるが、市場で形成される長期金利はいろいろと思惑も重なり、大きく動けなかった側面もあろう。
これによって困ったことになったのが銀行となる。シリコンバレー銀行の破綻も預金流出による米国債の売却に迫られ、大きな損失を発生させたこともひとつの引き金となっていた。
逆イールドとなっていることで、銀行では預金金利を大きく引き上げることができない。それにより、資金がより高い利回りのMMFに向かうこととなる。
米アップルは17日、同社のクレジットカード利用者向けに、年4.15%の利率で預金サービスの提供を始めたと発表した。米ゴールドマン・サックスが貯蓄口座の提供と管理を担うことで、預け入れの上限は預金保険の保護対象と同じ25万ドルまでとなる。
こちらも運用先は貸し出しとかではなく、比較的短期の公社債やコマーシャル・ペーパーへの投資によって運用益を得た上で、高い利子を捻出している可能性がある。それによりある程度の利ざやが稼げる。
アップルがこの機会に銀行業務に乗り出すことは銀行業界にとっても脅威となる可能性はある。ただし、いつまでも逆イールドが続くことも考えづらいことも確か。銀行からの資金流出は結局、一時的なものであったということになる可能性もありうるか。