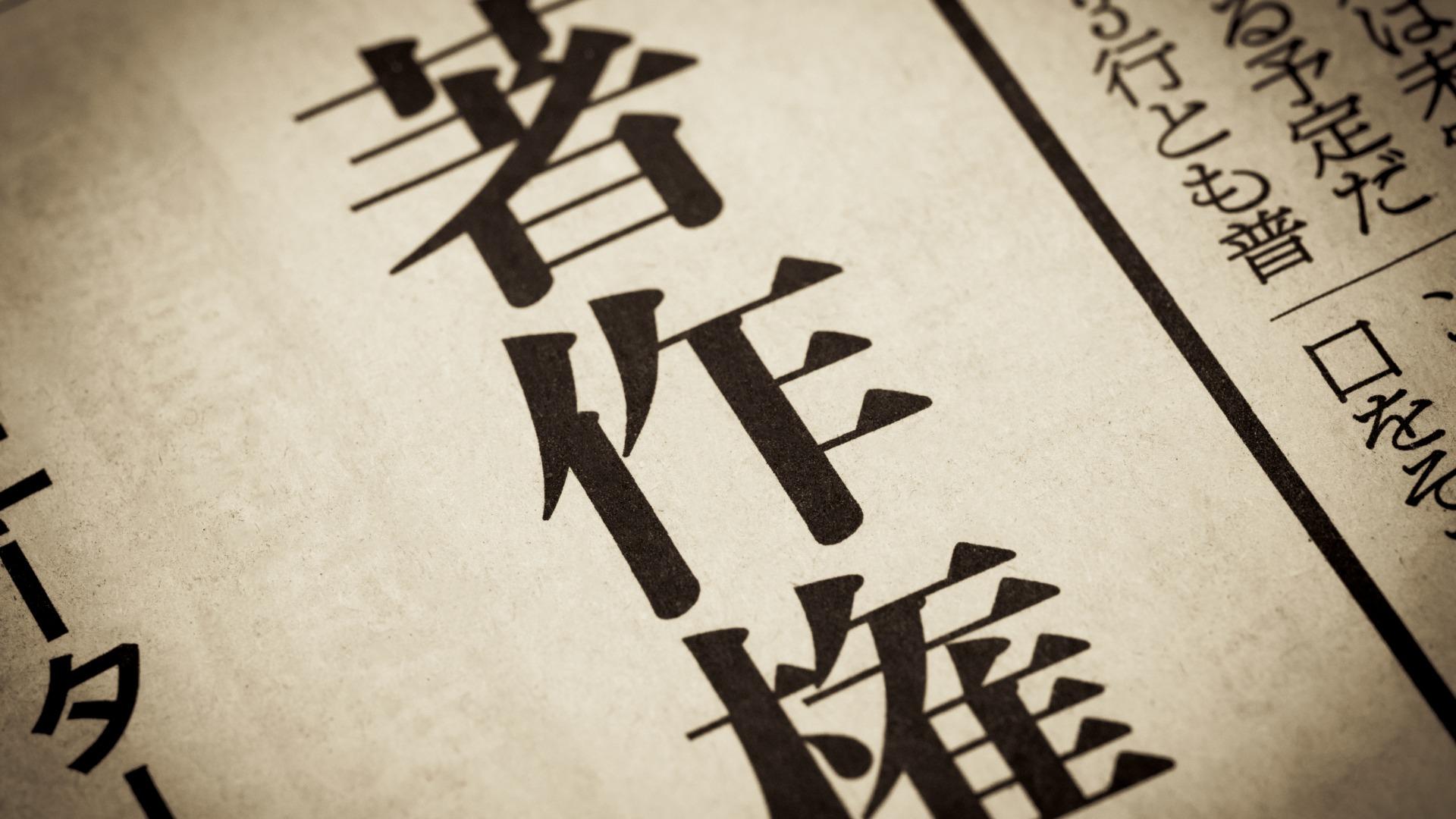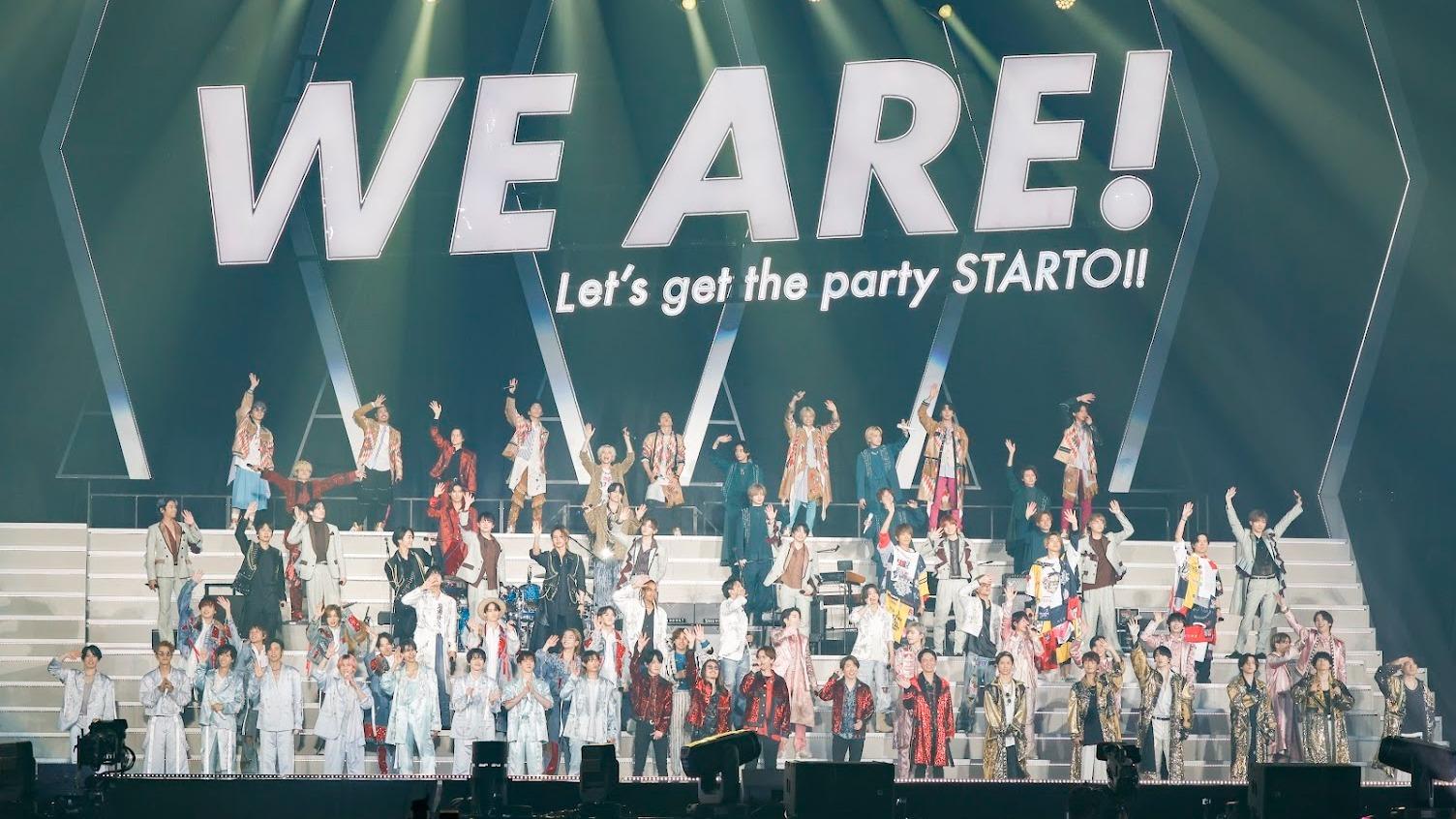米長期金利は3.5%の壁を突破、どこまで上昇するのか

19日の米国債券市場では、米10年債利回りが3.5%台を付けてきた。
6月14日に翌日のFOMCでの大幅利上げ観測から、米10年債利回りは3.498%と3.5%に急接近した。15日のFOMCでは市場の想定通り、0.75%の利上げを決めた。
しかし、この大幅な利上げがリセッションを招くとの見方が強まり、米10年債利回りはここから低下トレンドに移行した。
8月1日には米10年債利回りは2.6%割れとなったが、ここがボトムとなった。
市場では大幅な利上げによって景気が後退し、その結果、来年にはFRBは利下げを行うといった先読みの動きも強まった。その結果による長期金利の低下であった。
しかし、米国の物価指数は高止まりし、FRBは大幅な利上げを継続する姿勢を示した。
8月26日にワイオミング州ジャクソンホールで開催されているカンザスシティ連銀主催のシンポジウムで、パウエルFRB議長は、インフレの抑制について「やり遂げるまでやり続けなければならない」と利上げ継続を明らかにした。
FRBが完全にインフレファイターと化したことが確認されたことで、再び米国金利には上昇圧力が加わった。
その結果、20日に米2年債利回りは一時、4%に迫り15年ぶりの水準に上昇した。米10年債利回りは一時3.60%と2011年4月以来、11年ぶりの水準に上昇した。
21日のFOMCでは0.75%以上の利上げが予想されている。ドットチャートでは今後の政策金利の予測も示されよう。パウエル議長が会見でどのような発言をするのかも注目されている。
しかし、FRBとしてもある程度の絵は描いているとしても、現実には不確定要素も多く、具体的にどの程度までの利上げを行うのかは示すことが難しくなっているのではなかろうか。米消費者物価指数が約40年ぶりの水準となっていることからみても、ここ30年や40年の金融政策の尺度や常識が使えなくなってきている。
このため、米10年債利回りの3.5%はあくまで通過点となる可能性が高い。そしてどこまで上昇するのかという予想も現状はあまり意味をなさないと考える。