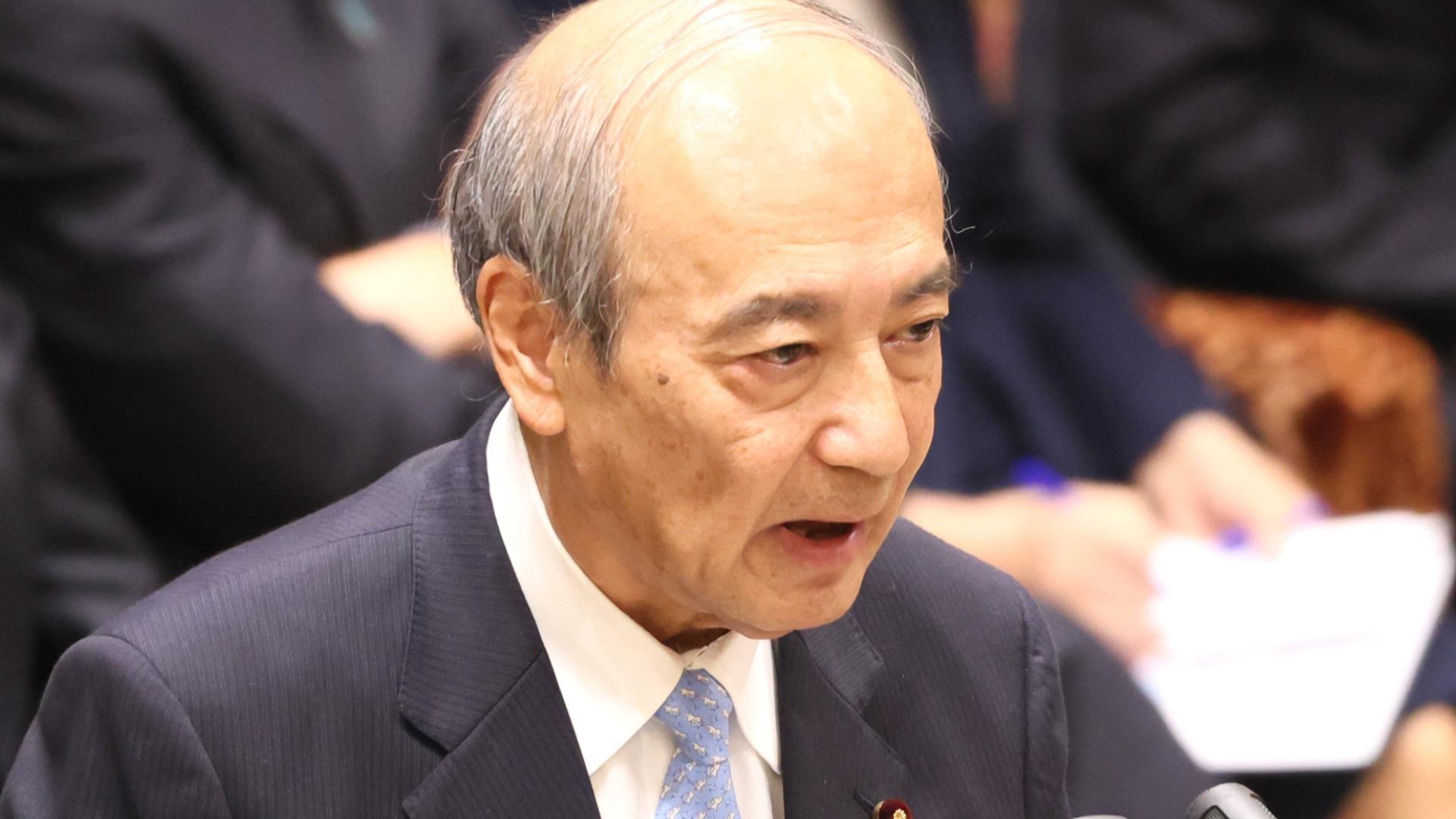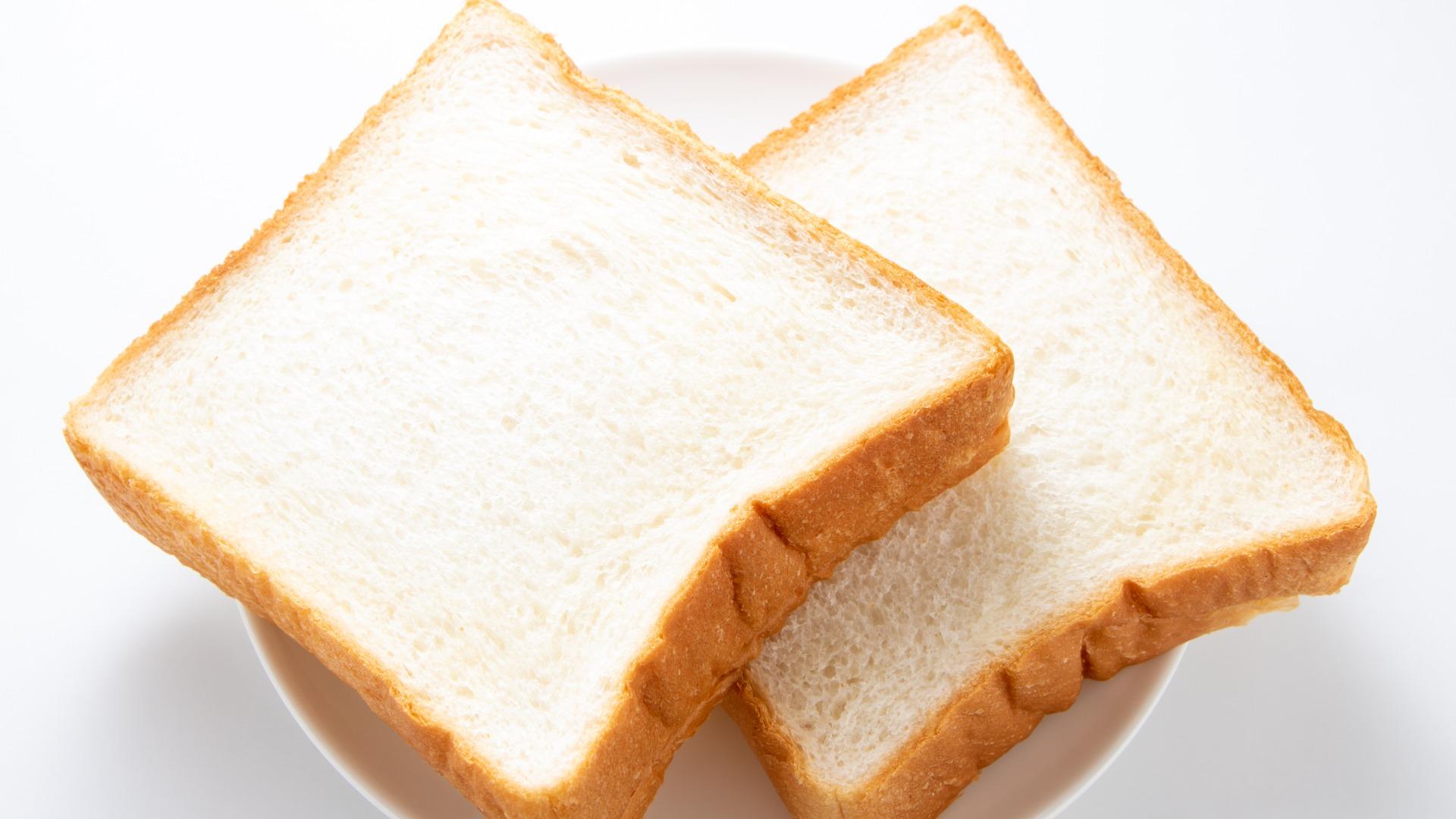アベノミクスがスタートして1年
アベノミクスがスタートしたのは、衆院解散が正式に表明された2012年11月14日とされている。当時の野田首相は11月14日に国会で行われた党首討論で安倍晋三自民党総裁に対し、当国会中の議員定数削減法案可決に協力することを確約し、16日に衆議院解散を行うと明言した。解散が正式に表明されたことで、安倍首相誕生への期待から円安・株高の動きが強まる。この急激な円高調整とそれによる株式市場の上昇は、新たな政権による金融経済対策への期待が背景にあり、その新たな金融経済政策がいつしかアベノミクスと呼ばれるようになった。(拙著「聞け! 是清の警告 アベノミクスが学ぶべき「出口」の教訓」より)
アベノミクスはどのようにして生まれたのかを覚えているであろうか。11月16日の衆院解散の翌17日、熊本での街頭演説において安倍自民党総裁は、衆院選後に政権を獲得した場合、金融緩和を強化するための日銀法改正を検討する考えを重ねて表明した上に、建設国債をできれば日銀に全部買ってもらう、新しいマネーが強制的に市場に出ていくと述べた。さらに同日の山口市での講演では、安倍総裁は、輪転機をぐるぐる回して、日本銀行に無制限にお札を刷ってもらう、と発言したのである。
政府と日本銀行が政策協調してデフレ脱却をして円高を是正し、経済を成長させていく新しい成長戦略を前に推し進めて行かなければいけません、との発言もあったが、要するにデフレの原因は金融政策にあるとして、その対策をまず日銀に押しつけたのである。衆院が解散されたとなれば、民主党への支持率の低下により、安倍自民党総裁が次期首相となる可能性が極めて高くなる。そのタイミングで安倍氏から、財政ファイナンスを意識させるような発言が飛びだした。
これを受けて急速な円高調整が始まり、その円安が株高を招き、スパイラル的な円安株高を演出した。そこにはジョージ・ソロスなど有力ヘッジファンドがかなりの金額による円売り日本株買いを仕掛けたことも影響した。この円安株高がいわゆるアベノミクスという言葉を生み出した。のちに安倍首相はあらたな金融経済政策について「三本の矢」という表現を使った。一本目の矢は日銀が大胆な金融緩和をする。二本目は、政府が財政政策で実需を生み出す。三本目は、TPPや大胆な規制改革などを含む成長戦略で、成長を持続的な軌道に乗せることである。しかし、財政政策も補正予算を主体とした公共投資の一時的な拡大に過ぎず、成長戦略もTPPはさておき、特に目新しいものではない。アベノミクスとは、結局、第一の柱である金融政策に負うところが大きい。
日銀法は結局、改正されなかったが、これは日銀総裁・副総裁人事でアベノミクスを実現してくれるであろう自分を選んだことによる。黒田総裁は安倍首相の意思をほぼ100%反映した異次元緩和策を就任からさほど時をおかず、4月4日の最初の金融政策決定会合で決定したのである。
問題はこの異次元緩和策がどのような効果があり、どのような副作用をもたらすのかという点にある。効果といっても、円安の動きはそれまでにいったんピークアウトし、日銀の大胆な緩和があらためて円安を演出したようには見えない。株式市場も同様ではあったが、米国の株式市場が過去最高値を更新するなどしたことで、底堅い動きとなった。しかし、実は円安も日本の株高もアベノミクスや日銀の異次元緩和が要因かといえばそうではない。ヘッジファンドの仕掛けのきっかけ等にはなったが、その背景には円が売られやすく、株が買われやすい環境にあったためである。それは言うまでもなく欧州の信用リスクの後退があった。
日銀の異次元緩和はリフレ政策ともいえる。2年間で物価目標2%を達成するとしたが、そのために行ったのは年間発行額の7割も国債を買い入れるという手段である。果たしてゼロ金利という状況のなかで、大胆に国債を買い入れてどのようにして物価に働きかけるのか。その説明が皆目ほからない。期待や気合いでなんとかしようとしているらしいが、そんなもので物価が上がるとは到底思えない。しかし、日銀が異常に国債を買い入れていると言う事実は残る。これが財政ファイナンスではないと言っても、状況が変わればそのように写る懸念もある。だから黒田総裁は消費増税を予定通り行うことを要求していた。しかし、消費増税だけではなく、このままリフレ的な政策が続けばいずれ財政規律に対して懸念が強まることも予想される。それを見越してか、長期国債先物の海外投資家の売買シェアが5割を超えてきている。
アベノミクスが1年経過した。国債への信用は何とか維持され、長期金利は0.6%近辺と低位で維持されている。この金利が低位で維持されていることこそ、物価は上がらないと市場参加者が予想していることを示している。しかし、物価が上がらずとも日本国の信用低下でも、長期金利は上昇する。また、リフレ派の言うとおりに仮に物価が本当に2%に向けて上昇してくれば、長期金利も上昇する。現在の長期金利の低位安定は結果としてそうなってはいるが、そうしようとしているわけではない。この妙な均衡が崩れるとアベノミクスのリスクが一気に顕在化しうる。