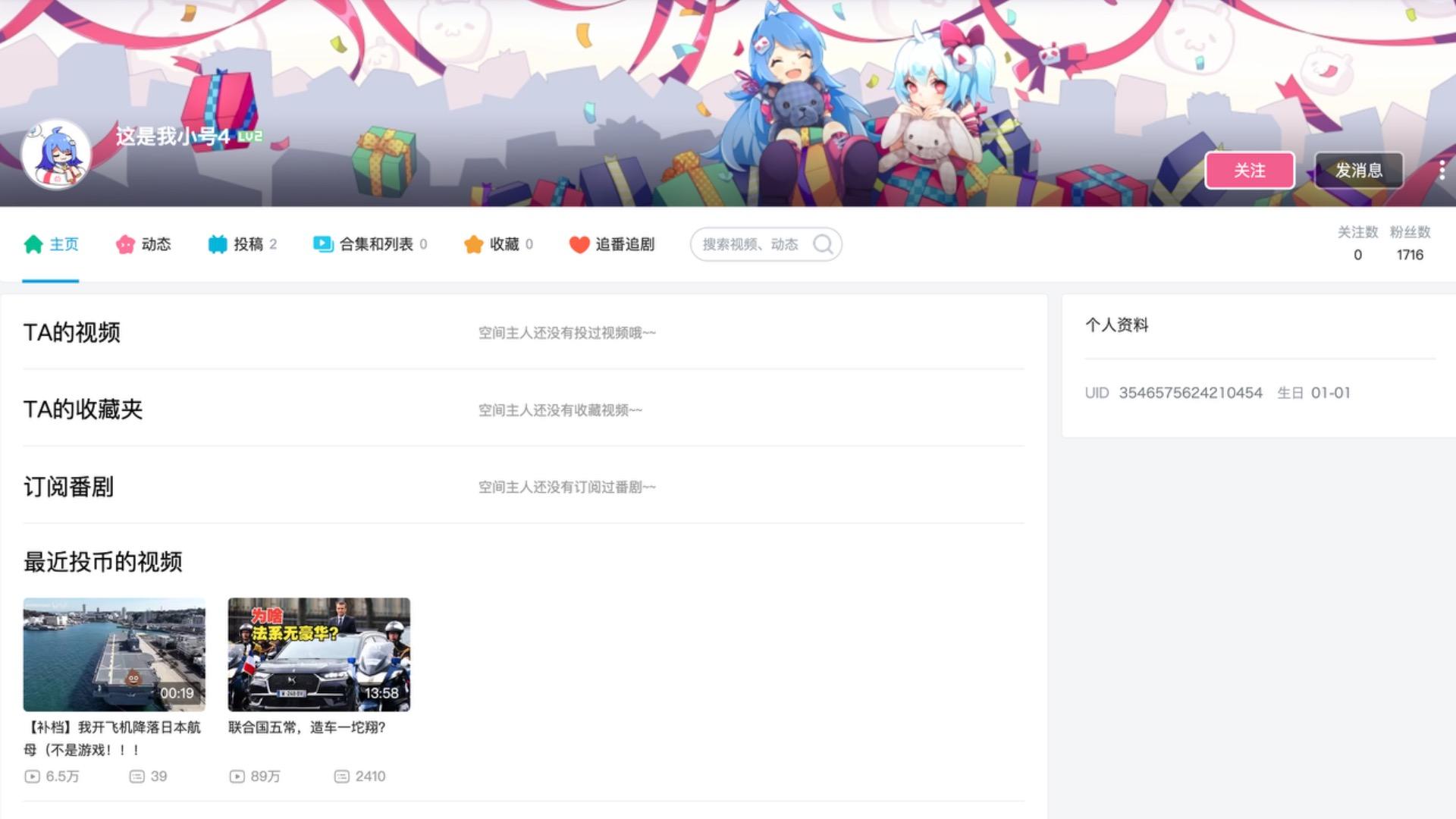C・ロナウドはどのように育ったか?一流サッカー選手育成のカギ

4月3日、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝。ユベントス戦、レアル・マドリーのクリスティアーノ・ロナウドが放ったシュートは伝説的だった。
ジャン・ルイジ・ブッフォンの度重なるセービングで攻撃を跳ね返されたと思った瞬間。右サイドからのダニエル・カルバハルのクロスに、ロナウドはゴールに後ろ向きで体を浮かせると空中で足を交差させ、球体を芯にとらえて右隅に放り込んだ。名手ブッフォンが一歩も動けなかった。敵も味方も信じられないように立ち尽くし、つかの間、沈黙が下り、その後はアウエーにもかかわらず、万雷の拍手が降り注いだ。
世界最高のゴールゲッターの称号がふさわしいだろう。
では、ロナウドはどのようにして生まれ、育ったのだろうか? 一流と言われる選手には育成時代の共通点がいくつかある。あえて一つ挙げれば、「逆境」にあるかも知れない。
ロナウドの原点
ロナウドの幼少期は、決して恵まれていたとは言えない。筆者は大西洋に浮かぶマデイラ島を訪ね、その生家を目にしたが、坂道の途中に建てた掘っ立て小屋だった。ロナウド少年は一人、坂の上に向かってボールを蹴り、戻ってくるボールをまた蹴り返していたという。日が暮れるまで友達とボールを蹴っていたが、彼以外は家族の団らんの中で夕食の時間を迎えていたからだ。
「不憫に思い、家に招き入れ、夕食をともにしたこともあったよ」
近所のおじさんはそう話していた。
当時、ロナウドの父親は定職に就かず、酔っ払ったまま町を徘徊していたという。母が客船の厨房で働き、どうにか生計を立てていた。そんな家庭では、兄がぐれてしまい、薬物に手を出している。
末っ子のロナウドは、そんな一家をどうにかしようと、プロサッカー選手として成功するために全力で打ち込んだという。誰に負けるのも、どんな劣勢でも負けるのを許さなかった。負けることは、すべてを失う、という恐怖があったのだろうか。ロナウドはその苦難に打ち克つたび、逞しく強くなっていった。たまに負けると、怒ったように泣きじゃくり、その悔しさを体に染みこませていた。
逆境が、ロナウドを強くしたと言えるだろう。
もっとも、逆境を跳ね返す力の原点は、単なるハングリー精神や負けじ魂ではなかった。
「父さんがサッカーを教えてくれた。だから、サッカーが好きなんだ」
ロナウドは親しい友人には洩らしていたという。父のことを、父が伝えてくれたサッカーを、彼は誰よりも愛していた。幼い頃の淡い記憶を忘れていない。父に感謝し、父が教えてくれたサッカーに人生を懸け、大好きだった父を取り戻し、好きなサッカーで頂点に立とうとした。それは歪んでいるように見えても、とても真っ直ぐな思いだった。
マデイラでルーツの取材をしたとき、ロナウドの熱量に圧倒されたのを覚えている。
逆境を乗り越えて強くなる
しかしロナウドだけでなく、一流選手というのはほとんど例外なく、逆境を乗り越えている。
例えば、歴代最高のストライカーの一人で、オランダリーグ、プレミアリーグ、ラ・リーガ、そしてチャンピオンズリーグでは3度も得点王に輝いているオランダ人ルート・ファンニステルローイは、幼少期にターニングポイントがあった。端的に言えば、両親の離婚。その経験は少年を大人にしたという。
「ルートは純粋にフットボールを楽しんでいました。でも、他の子どもたちと比べれば老成していたというか。両親の離婚を契機に、プロになりたい、という気持ちを強く、本当に強く出すようになりました」
当時のコーチは語っていたものだ。
ラ・リーガ史上、現役ではメッシ、ロナウドに次いで得点数が多く、ワールドカップ得点王、優勝にも輝いているスペイン人FWダビド・ビジャの場合は、幼少期の大腿骨骨折という苦難があった。「歩行も困難になるかも。選手は諦めた方がいいかもしれない」。医者にそうまで言われたが、入院中も利き足ではない左足を父に鍛えられ、諦めることなくサッカーを続けた。そしてトップレベルのクラブからは見向きもされず、炭鉱の町のクラブでユニフォームもスパイクも真っ黒に染めながら、周囲を納得させる力を身につけたのだった。
フィーゴは失敗しても弱気にならなかった
また、ポルトガルの英雄であるルイス・フィーゴは首都リスボンの対岸にあるアルマダという町で生まれ育った。集合住宅の一角。たまに奇声が聞こえ、落書きがあって、ベランダでは上半身裸の男が物干し竿に洗濯物を干していた。早い話、貧しい地区だ。
フィーゴはサッカー選手を夢見ていたが、強豪ベンフィカからは「チビ」という理由で門前払いされている。そして毎日15分のフェリーに乗って、スポルティング・リスボンというクラブの練習に通うようになった。同じチームに、天才ともてはやされた選手は他にいた。
「でも、ルイスほどの負けず嫌いはいなかったです。試合で失敗を恐れないんですよ。簡単に聞こえるでしょうが、すごいこと。彼は失敗しても怯まず、少しも弱気にならなかったですから」
フィーゴを発掘した育成部長はそう語っていた。そして、立ち塞がる天才たちを軽々と越えていった。
フィーゴのサッカーへの熱量は凄まじかったという。ユースからトップに昇格したばかりで車がないとき、先輩選手が送ってくれていたが、平気で居残り練習をして1時間以上待たせた。
「おれは体が小さいんだから、人一倍体を鍛えないとダメなんす。だから、我慢して下さいよ」
そう言えるふてぶてしさが、フィーゴを一流にしたのだろう。植え付けられたコンプレックスに負けなかった。むしろ逆手にとっている。
筆者は小説「ラストシュート 絆を忘れない」(角川文庫)を書き上げるため、Jリーグで主力になっている選手たちの育成年代を参考にした。言うまでもないが、どの選手も逆境を超えていた。必ず逆境はやって来るものなのだろう。そのとき、少年少女たちはどう立ち向かえるか――。まずは、その敵を恐れないことだろう。
<逆境に向き合えるサッカーへの愛情の熱量>
それは、ロナウドのような奇跡を起こすためのヒントになるかも知れない。