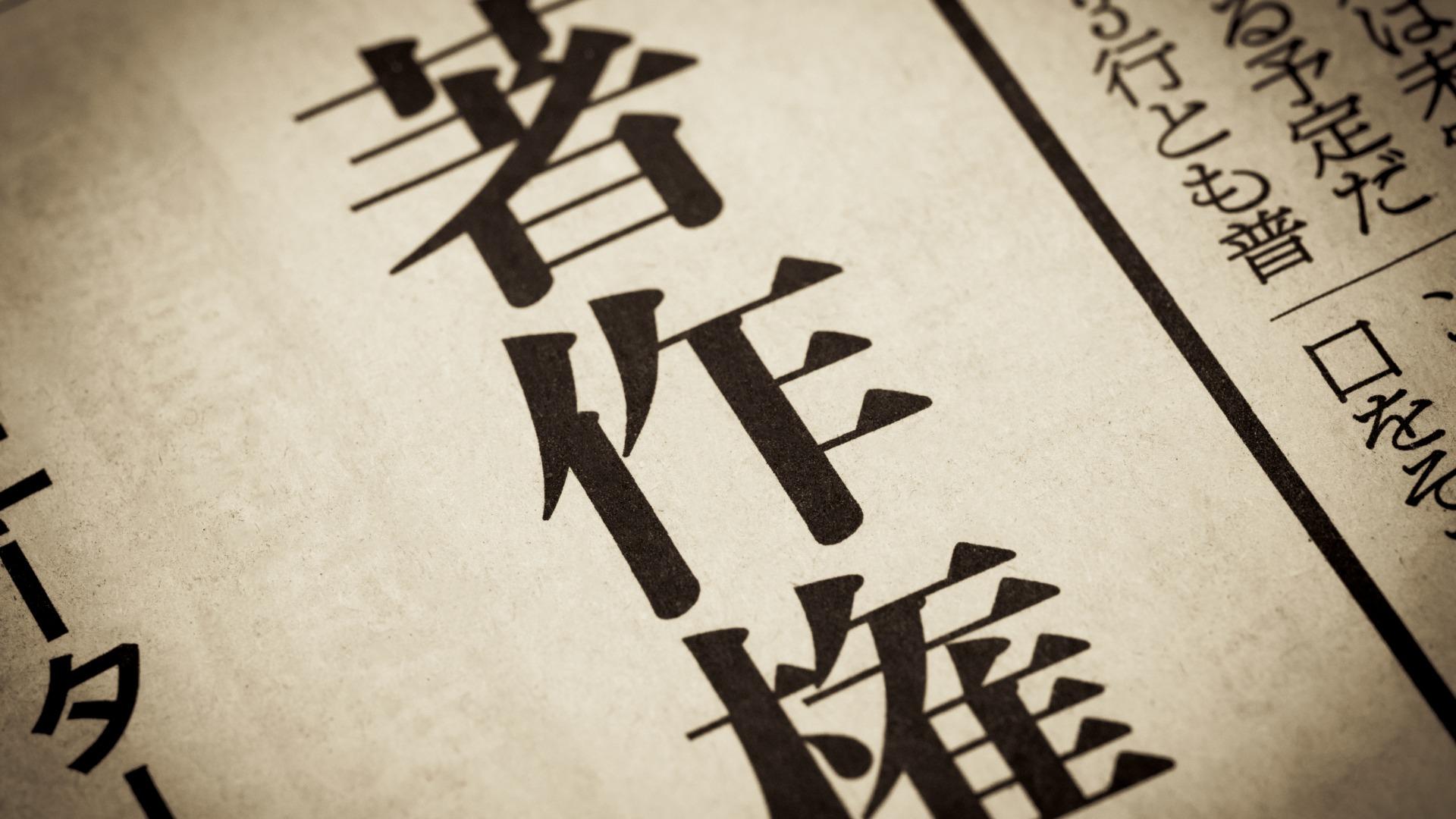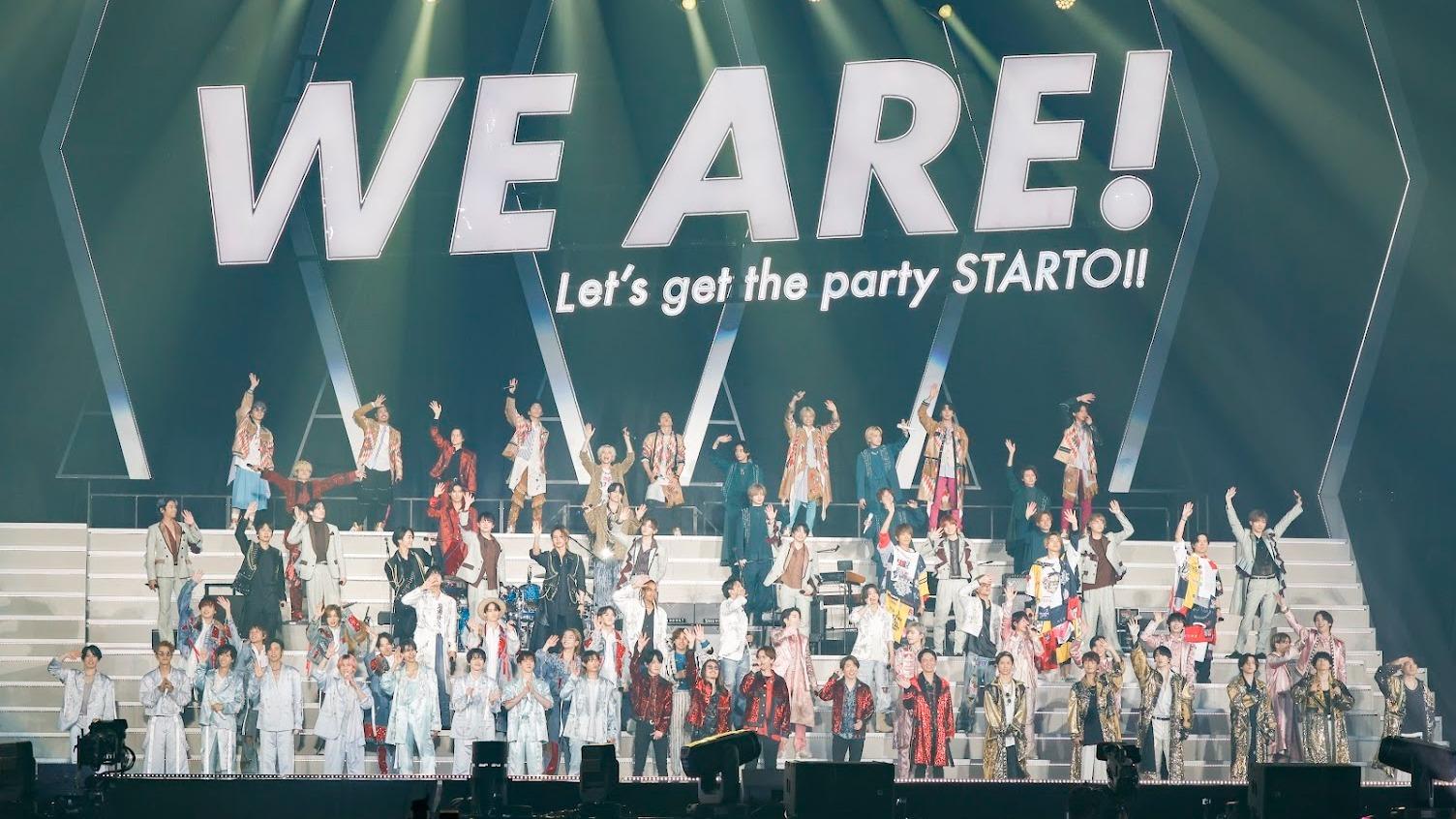小中学生がもらったお年玉の平均金額をさぐる(2020年公開版)

子供にとってはボーナス、保護者にとっては手痛い出費となるお年玉。その平均金額の実情をバンダイが2020年1月に発表した「小中学生のお年玉に関する意識調査」(※)の結果から確認する。
最初に示すのは子供が2020年の正月にもらったお年玉総額の平均金額。小中学生合わせた額では2万5594円となった。

世間一般で語られているように、子供の年齢が幼い方が平均金額は低いものとなる。中学生では3万1765円となり3万円を超える。お年玉は子供にとっては臨時収入、ボーナスのような存在であることを考えると、飛び跳ねるほどの嬉しさを覚えているに違いない。
このお年玉について、誰からもらったかを確認したところ、もっとも多かったのは祖父母からだった。90.2%が祖父母からもらったと回答している(複数の祖父母からもらった場合もありうる)。

意外なのは提示された中では保護者の割合がもっとも少なく60.8%でしかないこと。4割近くの小中学生は保護者からお年玉をもらっていない計算になる。祖父母やおじ・おばからもらうので不必要だと諭されているのだろうか。他方、この選択肢以外でも、例えば保護者の知人が正月に遊びに来た時にお年玉をもらえるなどの機会もあるだろう。
ちなみにもらったお年玉の平均封数は5封とのこと。
保護者からお年玉をもらえた60.8%の子供に、具体的な金額を聞いた結果が次のグラフ。複数からもらえた場合も合計額で記されている。

全体では5481円。ややばらつきがあるものの、保護者からのお年玉もまた、子供の年齢が幼い方が平均金額は低いものとなる。中学2年生になると大きく伸びるのは、心身ともに成長し、付き合いも広くなり、必要なお金も増えてくるからとの保護者側の配慮によるものだろうか。
2021年の正月は新型コロナウイルスの流行で帰省や正月のあいさつ回りも自粛されるだろうことから、お年玉の相場も大きな変化が生じる可能性がある。それとも今風にオンラインで挨拶した上で電子マネーか何かで振り込まれるスタイルを採るのだろうか。
■関連記事:
【子供達はどれぐらいの額のお年玉をもらっているのか(最新)】
【だれもが気になる「もらったお年玉はどうしたか」、その実情をグラフ化してみる(2016年)(最新)】
※小中学生のお年玉に関する意識調査
2020年1月6日から8日にかけて小学生か中学生の子供がいる保護者900人を対象に、インターネット経由で子供と一緒に回答する形で答えてもらったもので、有効回答者数は900人。子供の男女別・学年区分で均等割り当て。調査協力会社はクロス・マーケティング。
(注)本文中のグラフや図表は特記事項の無い限り、記述されている資料からの引用、または資料を基に筆者が作成したものです。
(注)本文中の写真は特記事項の無い限り、本文で記述されている資料を基に筆者が作成の上で撮影したもの、あるいは筆者が取材で撮影したものです。
(注)記事題名、本文、グラフ中などで使われている数字は、その場において最適と思われる表示となるよう、小数点以下任意の桁を四捨五入した上で表記している場合があります。そのため、表示上の数字の合計値が完全には一致しないことがあります。
(注)グラフの体裁を整える、数字の動きを見やすくするためにグラフの軸の端の値をゼロではないプラスの値にした場合、注意をうながすためにその値を丸などで囲む場合があります。
(注)グラフ中では体裁を整えるために項目などの表記(送り仮名など)を一部省略、変更している場合があります。また「~」を「-」と表現する場合があります。
(注)グラフ中の「ppt」とは%ポイントを意味します。
(注)「(大)震災」は特記や詳細表記の無い限り、東日本大震災を意味します。
(注)今記事は[ 【ガベージニュース】]に掲載した記事に一部加筆・変更をしたものです。