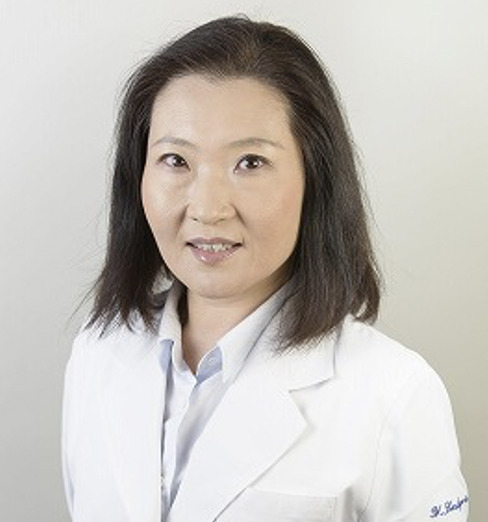希望だけをもたせる技術は提供できない──広がる卵子凍結、その可能性と課題 #卵子凍結のゆくえ
それでも、がん治療などによって妊孕性(にんようせい、妊娠するための力)を失いかねない女性へ、医学的適応の卵子凍結を行う意味は大きい。しかし、そうではない、社会的適応の場合については、現状では慎重にならざるを得ないと同病院では考えている。理事長で前院長の畑山博さん(61)は言う。 「卵子を凍結して、実際に妊娠できるかどうかがわかるのは、融解する5年後や10年後です。その間、少なくないお金も払ってもらって希望をもたせ、でも、実際に使ってみたらダメでしたとなったときに、私たちはその方の人生に責任が取れません。そうなる確率が現状ではまだ高い。そのため当院では社会的適応のケースは行っていないのです」
生命倫理政策を研究する東京大学医科学研究所の神里彩子准教授(49)も、卵子凍結の社会的適応には慎重な立場をとる。 「卵子凍結したからといって妊娠する確率が高いとは言えません。にもかかわらず、卵子を凍結したから安心だ、出産を先送りしても大丈夫だ、と考えてしまう人が増えるとすれば、それは危険だと考えています」 また、日本に現状、関連する法律や制度が一切ないことの問題も神里さんは指摘する。 「法律や制度がないゆえに、どのような施設がどのような技術で卵子凍結を行っているのか、その実態がわからないのが現状です。技術が十分でないクリニックが請け負っている可能性もあり、その点も大きな問題だと考えます」
積極的には推奨しないが認める、という学会
法律がないのは、現在の日本の不妊治療全般について同様である。一般の不妊治療は、日本産科婦人科学会が事実上のルールを作り運用されている。法的拘束力はないものの、同学会が出す見解や声明が医療機関にとっての一定の規範となっている。 社会的適応の卵子凍結について、日本産科婦人科学会の専門委員会は、2015年に「推奨しない」とする見解を発表している。しかしそれ以上の言及はなく、明確な指針が打ち出されているとは言えないのが現状だ。 一方、日本で卵子凍結が一般に知られるようになって間もない2013年に、明確な見解を表明したのが日本生殖医学会である。同年「未受精卵子および卵巣組織の凍結・保存に関するガイドライン」を発表。《(卵子の)採取時の年齢は、40歳以上は推奨できない》などの具体的な要件を記したうえで、加齢などを理由とする卵子凍結、つまり社会的適応を事実上認めた。そして2018年には、「ガイドライン」を改訂した「未受精卵子および卵巣組織の凍結・保存に関する指針」を発表。実際に行う人が増えている状況を考慮して、利用者が不利益を被らないように、より細かな要件を加えている(たとえば年齢については、2018年の「指針」では《[卵子の]採取時の年齢は、36歳未満が望ましい》としている)。 一見すると、日本産科婦人科学会は反対で日本生殖医学会は賛成、といった対立的な構図にも映る。それが卵子凍結に関する議論を複雑にしている面もありそうだ。日本生殖医学会の常任理事で不妊治療専門医の片桐由起子さんは、同学会の見解として、こう話す。 「まず前提として、当学会は、日本産科婦人科学会と基本的な立場が異なるわけではありません。卵子凍結による妊娠の先送りを積極的に勧めている、というわけでもありません。ただ、より不妊治療の現場に近い位置にある学会として、実情に沿って一歩踏み込んだ見解を出す必要があると考えました。加齢によって卵巣機能が低下して妊娠出産が難しくなるのは医学的事実であり、不妊治療を受けている患者さんの多くが高年齢であるというのも事実です。その現実を踏まえれば、若いうちに卵子を凍結保存するという技術の利用は、現状、まだ課題があることを認識しつつも、選択肢の一つとして認められていいのではないかというのが当学会としての考えなのです」