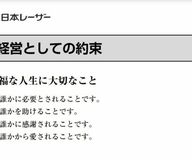マタハラで訴訟するも最高裁棄却で女性側が敗訴。判決から学ぶべき2つのこととマタハラ被害者支援のあり方

育休取得後に正社員から契約社員にされ、1年後に雇止めとされたのは「マタニティハラスメント(マタハラ)」にあたるとして、女性が勤務先の語学スクール運営会社ジャパンビジネスラボ(JBL)を提訴していた裁判は、2020年12月8日、女性側が最高裁に上告するも棄却され、高裁判決である原告女性の敗訴で確定した。
一審の地裁判決は、女性に正社員の地位は認めなかったが、雇止めは無効とし、会社の不誠実な対応などは不法行為にあたるとした。また、提訴の際に女性が開いた記者会見は名誉毀損にあたらないとした。
一方、二審の高裁判決は、一審同様に女性に正社員の地位を認めなかったうえ、雇止めも有効とした。また、記者会見は名誉毀損にあたるとし女性に55万円の支払いを命じたため、原告女性は逆転敗訴のかたちで負けることとなった。
逆転敗訴となったためか、高裁判決に対し偏った意見の記事ばかりが目立つこととなり、なぜ敗訴になったのか、そこに至る経緯や理由がまとめられた記事がなかった。
そこで、判決の経緯や理由を含めた法的解説を以下の記事にまとめた。
「マタハラで訴訟するも最高裁棄却で女性側が敗訴。高裁判決のポイントについて法律の専門家に解説いただいた」
この記事を踏まえたうえで、判決から学ぶべきことはなにか、マタハラ被害者を支援するとはどうあるべきかを以下に述べたい。
●主な経緯
2008年7月、女性は(株)ジャパンビジネスラボ(JBL)に正社員として入社。英語講師としてクラスを担当していた。クラスは、平日の夜、週末の朝・昼・夜の各時間帯に開講のため就業形態は、平日の夜及び週末が中心だった。
2013年3月長女を出産後、産休と育休を取得。しかし、1年半の育休終了後も保育園は決まらず、週5日勤務の復帰が出来なかった。そこで、契約期間を1年とする週3日勤務の契約社員として会社と再契約を交わすこととなった。
ところが、この契約から約1週間後、保育園から空きが出るとの電話連絡があったとして、女性は翌月から週5勤務の正社員として働きたいと申し出た。「契約社員は、本人が希望する場合は正社員への契約再変更が前提です」などと記載された書面を受け取っていたため、希望した時期に正社員に戻れると思ったからだ。しかし、会社は契約社員契約を締結したばかりであることを指摘した。
その後も女性はメールで正社員への契約の変更を申し出た。しかし、会社は現段階で正社員への契約変更は考えていないと回答した。
契約から18日後、女性と会社との間で面談の機会が設けられた。女性は子を預ける保育園が見付かったとして、翌月から正社員に戻すよう会社に要求した。「契約社員は、本人が希望する場合は正社員への契約再変更が前提です」などと記載された書面を受け取っていたため、希望した時期に正社員に戻れると思ったからだ。しかし、会社からは「正社員であれば他の正社員と同じ前提で働けることが条件」などと告げられたため、女性はその場で労働局に相談に行くと告げ、その後、労働紛争の解決援助を東京労働局に申し出た。
また、労働組合に加入し、加入した労働組合は会社に対して団体交渉を申し入れた。
こうした経過を受け、会社は女性に対し、退職勧奨をしていないにもかかわらず,退職勧奨をしたと他言していることを禁止するよう求める合計16通に及ぶ警告書等を交付。また、女性が録音機器を執務室に持ち込み、秘密に録音をすることは就業規則違反として録音を禁止する注意指導書なども女性に交付した。しかし女性は、「自己の行動に問題があるとは思わない」と述べ、いずれの書面にも同意しなかった。
その後、女性が加入した労働組合との団体交渉が行われた。女性と組合は正社員に戻すことを要求したが、会社は女性を信頼して正社員に変更することはできないとの姿勢を崩さなかった。
女性は録音した上司の音声データをメディアに提供した。これを受け、会社は女性が正社員としての地位を有しないことの確認を求める法的措置に及んだうえ、女性を契約終了(雇止め)とした。女性も会社を提訴し、自身は匿名としながら会社名(株)JBLを公表する記者会見を行った。
●今回の判決から学ぶべき2つのポイント
今回の判決から学ぶべきことは、大きく2つある。1つめは、育休復帰の際に契約社員として雇用契約を交わしたとしても、不利益取扱い=マタハラにならない場合があるということ。
客観的に見て正社員としてのパフォーマンスが発揮できない場合に、会社が契約社員のルートを用意することは、それ自体が直ちにマタハラになるわけではない。ただし、会社がそのルートを押し付けたり、そのルートから帰って来られないようにしたりすれば、それはマタハラになる。
今回の場合、保育園が見つからないまま正社員復帰すれば、欠勤を繰り返し業務に支障を来すなどして解雇になる可能性があった。それに比べれば、契約社員としての雇用契約を結ぶことは不利益な取扱い、いわゆるマタハラではない、と判断された。
保育園が決まってなければ、正社員のパフォーマンスを提供できないのは客観的に明白だ。難しいのは、客観的に明白ではない場合に、労働者側と会社側で問題となることがある。
育休から復帰する際、労働者が希望すれば、時短勤務や残業制限などの措置がとられることになる。こうした措置が取られながら働く場合、提供される業務の水準は元の正社員としてのものではなく時短正社員として新たなパフォーマンスレベルにならざるを得ない。会社が正社員に期待するレベルと、労働者が実際に提供できるレベルの擦り合わせは、仕事をしていく中で行わざるを得ない面もあるが、もっと責任のある仕事を任せて欲しいと主張する労働者と、パフォーマンスの低下した従業員に責任のある仕事を任せることに不安を覚える会社側 との間で、コミュニケーション・ギャップが生じることがある。(逆のパターンもあり、責任ある仕事は外して欲しいと主張する労働者と、もっと責任ある仕事を任せたいと思う会社側の場合もある。)
復帰後の場面でも、例えば、子どもを預けられる保育園が決まり正社員復帰したにもかかわらず、子どもの身体が弱く看病で、実際に有給の範囲を超える欠勤が頻発し、会社が契約社員に変更するよう促した場合、マタハラとなるかどうかの判断はとても難しくなる。
学ぶべきことの2つめは、契約社員から正社員に再契約する場合には、事前の調整や会社からの評価や判断は当然必要だとされたこと。
この裁判は「契約社員は、本人が希望する場合は正社員への契約再変更が前提です」という書面の言葉に対する認識の食い違いが、一連の紛争の発端になっている。女性は、希望した時期に正社員に戻れるものと思っていた。しかし裁判所は、希望した時期に速やかに正社員に戻れるという意味はこの言葉に含まれてはいない、とした。
正社員に戻ることを要求すること自体は責められることではない。誤解を与えるような書面を作ったことや、正社員に戻す時期や条件を明確にしなかったこと、女性に対しやや過剰な反応を示したことなど、会社側の対応に一定の問題があることは否定できない。
しかし、女性の側も、会社の実情を理解したうえ、もう少し慎重かつ柔軟な対応をとる余地はあったのではないだろうか。いじめられていると被害的になったり、他の女性従業員らに対して妊娠を考えているなら気を付けた方がいいなどと会社の悪口を言ったりせず、ブランクに対する会社の不安を解消するために一定の配慮を示していれば、ここまで対立が先鋭的になることはなく、正社員に戻ることができていたかもしれない。
●「録音は労働者にとって重要な証拠」は変わらない
高裁判決においては、会社が女性との契約を終了したこと(雇止め)を有効とした。その理由の一つとして、会社の代表者の命令や、自分自身がした誓約にも反して執務内における録音を繰り返したことが指摘されている。
これに対し、原告女性の代理人弁護士が「録音がなければ、労働者は立証できません。会社が録音に関して規律を設け、注意をすれば、雇止めとなってしまうことになります。また、記者会見は労働者が対抗でき、声を上げることができる場面」と判決を疑問視した、という記事が出た
(参照記事:女性元社員「マタハラ」主張も認められず、雇止め有効に 一審と逆転…東京高裁)
このことにより、録音すると雇止めになってしまうのではないかという不安の声が上がった。
しかし、女性が雇止めにされた理由は、録音というよりも、むしろマスコミとの尖鋭的な関わり方にあったのではないか。
高裁判決は雇止めの理由として、録音を繰り返したことだけではなく、多数回にわたり業務用のメールアドレスを使用して私的なやりとりをしたことや、会社がマタハラ企業であるとの印象を与えようとして、マスコミ等の外部の関係者らに対し、あえて事実と異なる情報を提供したことを掲げている。
育休復帰の際に正社員から契約社員になったこと、本人の希望する時期に速やかに正社員に戻れなかったことは上述のとおりマタハラではなかった。
会社へのダメージという点では、録音よりもマスコミへの情報提供の方が遥かに大きく、雇止めが有効とされたのは、こちらに力点があるように思われる。少なくとも、録音したら直ちに雇止めになるといったわけではない。
また、この判決を録音そのものにネガティブな評価をしたものとする見方もあるが、判決は、会社側の一方的な都合だけで一律に録音を禁止したわけではない。労働者がハラスメントの立証のために秘密録音することまで禁止したわけでもない。ハラスメントを立証する上で録音や書面等の証拠は労働者にとって重要なことに変わりはなく、マスコミに提供することの当否はさておき、裁判所で録音を使った立証を行うことまで不安に思う必要はないと思われる。
●マタハラの被害者支援は、判決を冷静に分析し学んだものを伝えること
高裁判決には抗議の声が上がった。
(参照記事:「裁判所はマタハラを許す気か!」東京高裁の逆転判決に抗議の声)
本人が希望する場合には正社員への契約再変更が可能といいながら、育休後に正社員復帰させてもらえず、そのまま雇止めにあったという結論だけを見ると、高裁はマタハラを認めたかのように思えるかもしれない。しかし、高裁で認定された事実と照らし合わせてみると、高裁の判断に違和感を持たない人の方が多いように思う。
裁判官を大勢で非難すればマタハラがなくなるわけではない。また、経緯や理由を問わずに妊娠中・育児中の女性を擁護する結論ばかり裁判所が出すようになれば、事業者は労働者の妊娠と向きあうこと自体を放棄して、事態はより悪い方に向かってしまうかもしれない。
マタハラ被害者を支援する者として取り組まなければならないのは、妊娠・育児を行う女性に不利な判決が出たとしても、結論だけを取り上げて非難するのではなく、なぜ裁判所がそのような判断をしたのか、まずは判決を客観的な視点で読み、冷静に分析し、そこから学んだものを伝えていくことだと思う。
今回の高裁の判断は、かなり特殊な事実関係を前提にするものであり、裁判所は私たちが「マタハラ」という言葉から普通にイメージするハラスメントを許しているわけではない。
育児中の女性が敗訴したからといって、働くことと真摯に向き合っている妊娠・育児を行う女性に対し、苦しい時に声を上げることをためらう必要はないと、この記事で改めて伝えたい。
【経緯の略年表】
●2008年7月9日 (株)ジャパンビジネスラボ(JBL)に正社員として入社。英語講師としてクラスを担当。クラスは、平日の夜、週末(土曜日及び日曜日)の朝、昼、夜の各時間帯に開講。そのため就業形態は、平日の夜及び週末が中心
●2013年1月 産前休業を取得
●2013年3月 長女を出産後、産後休業と育児休業を取得
●2014年2月26日 保育園が決まらなかったことを理由に育児休業を6か月延長
~1年半の育休終了後も保育園は決まらず、週5日勤務の復帰が出来なかった(※当時は育休最大1年半、なお現在は最大2年)~
●2014年9月1日 契約期間を1年とする週3日勤務の契約社員として再契約
●2014年9月8日 保育園から空きが出るとの電話連絡があったことを伝える
●2014年9月9日 翌月から正社員として就労したいと申し出る。会社は契約社員契約を締結したばかりであることを指摘
~その後も女性はメールで正社員への契約の変更を申し出るも、会社は現段階で正社員への契約変更は考えていないと回答~
●2014年9月19日 子を預ける保育園が見付かったとして、10月から正社員に戻すよう要求。会社から、正社員であれば他の正社員と同じ前提で働けることが条件である、契約社員として働くことを拒否したら自己都合による退職になる、正社員に戻れる時期は確定できないなどと告げられたため、女性は労働局に相談に行くと告げる。同日、会社はメールにて受け持ちクラスの担当をさせない旨を伝える
●2014年9月22日 女性は東京労働局長に対し、速やかに正社員に戻して欲しいとして労働関係紛争の解決援助の申し出をする
●2014年10月6日 女性は労働組合に加入。正社員復帰を求め団体交渉を申し入れる
●2014年10月25日 会社は女性に退職勧奨をしていないにもかかわらず、女性が外部に対し、退職勧奨をしたと他言していることを禁止するよう求める警告書等(合計16通)を交付。また、女性が録音機器を執務室に持ち込み、秘密に録音をすることは就業規則違反として録音を禁止する注意指導書等を女性に交付した
●2014年10月29日 女性は「自己の行動に問題があるとは思わない」と述べ、いずれの書面にも同意しなかった
●2014年11月19日 会社は女性との信頼関係が破綻している状況で、雇用契約を正社員に変更することは不可能という回答書を交付
●2015年5月 会社名匿名のもとメディアに録音した上司の音声データを提供
●2015年5月29日 会社は女性に正社員の地位がないことの確認を求め労働審判を申し立てる
●2015年8月1日 会社は労働審判の申立てを取り下げ
●2015年8月3日 会社は女性が雇用契約上の地位を有しないことの確認を求め提訴
●2015年9月1日 契約終了(雇止め)
●2015年10月22日 原告女性が会社を提訴し、記者会見を開く。原告氏名は匿名としながら会社名(株)JBLを公表