製作委員会「悪玉論」ではアニメの未来は拓けない

先日のNHKクローズアップ現代の放送以来、アニメの制作現場が逼迫している原因を製作委員会方式に求める意見をネット上でよく目にするようになった。しかし、これは批判の方向性としては間違っている。
たとえば、こちらの記事のような主張がそれにあたる。
「アニメの制作会社だけでは、制作費用を出せません。そのため出版社、ビデオメーカー、玩具メーカーなどの企業が『製作委員会』に入り、出資します。『委員会』に入っている企業がそのアニメから莫大な収入を得たとしても、利益は『委員会』内の企業で分配されます。制作会社に支払われる制作費用は予め決まっており、アニメがヒットしても後から追加で還元されることはありません」
コメントを寄せている河嶌氏はアニメと地域の関係などに詳しく、筆者もその論考を拝見させて頂いている。しかし、氏の意図と異なり要約・改変されてしまっている可能性もあるが、この記事で紹介された主張には首を捻らざるを得なかった。
これはいわゆる代理店中抜き論と同じく、筋の良い主張とは言えないと筆者は考えている。製作委員会方式が万能ではない(たとえば権利が分散しているため、その活用が合理的に図られない、というケースは実際目にする)こと、またテレビやネットといったメディアを巡る状態が変化していることから、そのあり方が変わらなければならないのは間違いない。しかし、制作会社が困窮するのは、製作委員会のせいだというのはおかしい。
クラウドファンディングでTVアニメは作れない
よく知られるようになってきたが、アニメ制作には大きな予算が必要だ。TVアニメであれば1話当たり約1500万円~2000万円以上、それを1クール12話制作すれば約2億円は必要となる。劇場アニメであればその予算は約5億円が相場となってくる。まず、その予算をどこから集めてくるのか? という話になる。
制作会社が1社でこの費用を負担できることはまずほとんどない、というのは各社の資本金をみればよく分かる。かつては、ファンドで複数作品の制作費を金融市場から募るという取り組みも行われたが、当たり外れのリスク・ボラティリティがあまりにも読めず、実際、投資回収に至るケースは皆無だったため、そういった取り組みは下火になっている。
「クラウドファンディングがあるじゃないか」という声も聞こえてきそうだが、興行成績も含めて大成功を収めた「この世界の片隅に」でも、映画化支援の取り組みで集まった金額は約3,900万円。TVアニメに換算すると2話分くらいの費用でしかなく、実際、このプロジェクトの目的は、「制作スタッフの確保とパイロットフィルムの制作」のため、となっている。
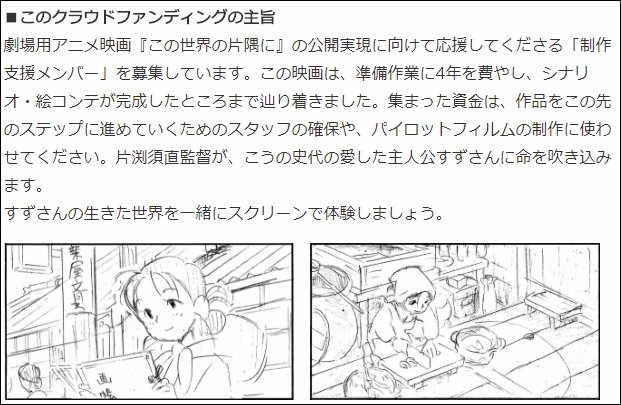
上記記事でも紹介されている事例は、短尺のネットアニメやそのキャラクター開発に目的を絞り込んだもので、TVアニメ・劇場アニメとはその規模感が全く異なっている。また「けものフレンズ」が低予算で制作され、あたかも製作委員会方式を用いなくても資金調達が可能であるように紹介されているが、筆者が確認したところでの予算規模はクラウドファンディングで到底賄えるものではない。(逆に言えば、TVや劇場をウィンドウとせず、特定地域やネットなど範囲や商流を限定した展開であれば可能で、それを否定するものではない。要は混同した議論はよくないという話だ)
「けものフレンズ」のソーシャルゲーム終了後でのあれほどのブレイクは、もちろんネットのバズ(口コミ)の力が大きかったのは確かだが、テレビで放送され、書店でパッケージが手に入る(それがまた品切れとなることで更なる話題を生む)といったメディアミックスがあってこそだ。そこで製作委員会方式が果たした役割は厳然として大きかったと評価するのが妥当だと思う。
Netflixや中国資本も製作委員会方式に取ってかわらない
では、「昨今話題のNetflixのような海外配信事業者や、中国資本からの資金調達であればTV・劇場規模の作品だって作れるじゃないか?」という見立てはどうだろうか。だが、これらも現実には製作委員会方式を置き換えるものではない。
まず、Netflixを始めとする海外配信事業者からの資金は、ハリウッド方式つまり「完成保証」を原則前提とする。簡単に言ってしまえば、映像を完パケ納品してはじめておカネが振り込まれる、ということだ。それまで必要となる費用は、何らかの方法で確保しなければならない。また、彼らは配信権以外の権利を求めないことが多いが、逆に言えばそれ以外のビジネス展開はやはりこちらでコストを掛けて行わなければ展開されない。外資からの資金調達は非常に魅力的であるものの、相対的に規模は小さくなることはあってもやはり製作委員会は必要となるケースが多い。
中国資本によるアニメ制作は別の意味で今課題にぶつかっている。たしかに制作予算を上回る資金を制作に入る段階で調達できれば、アニメそのものはできる。しかし、それが売れるかどうか、というのはまた別問題だ。日本のアニメは、ネット小説・マンガ・ラノベといったバリューチェーンによる洗練と淘汰を経て成立している。製作委員会に参加する事業者はこのバリューチェーンに何らかの形で参加しているものがほとんどだ。中国発の(日本からみれば)オリジナルの企画はもちろんのこと、日本発の作品であっても、それらの作品と競わせ商業的に成功させるのは、これほどまでに難しいのだということを、いま関係者は痛感しているところではないだろうか。
ここまで見てきたように、アニメビジネスは極めて高リスク(※リスクとは本来下振れだけでなく、上振れも意味する)なものだ。上記記事では、「制作会社に支払われる制作費用は予め決まっており」と指摘するが、制作した映像を納品した段階で、原価を上回る費用を得ることが出来るというのは、このリスクを回避する/できるということと同義である、というのは繰り返し強調したいところだ。適切な工程管理を行い、合理的な利益を乗せて予算請求できていれば、制作会社のリスクは極めて低く、実際、一般企業と同じく受注が好調で成長している会社も存在する。そうやって評価を確立し、資本を充実させることに成功した会社の中には、製作委員会に参加して自らリスクを取るものも現れるし、契約に際し制作力の高さを武器に「成功報酬」を委員会に求めるところもある。(従って、「アニメがヒットしても後から追加で還元されることはありません」というのも誤りということになる)
制作会社自らが変わる必要がある
では問題の本質はどこにあるのだろうか? いま述べたように、「適切な工程管理」と「合理的な利潤要求」という制作会社側の課題に尽きる。前の記事でも書いたが、受注競争のなか、赤字覚悟での受注というケースも散見され、その結果「適切な工程管理」(これは外資事業者との向き合いでも欠かせない)が難しくなり、「自転車操業」に陥る――この状況は記事でも記された通りで現状認識は一致している。しかし、その原因をリスクをある種吸収し、収益機会を拡大する役割を担ってきた製作委員会方式に求めるのは間違っていると言わざるを得ない。
国が働き方改革を推進するなか、アニメ制作会社での労働環境を巡る問題にも厳しい目が向けられている。ascii.jpで数土直志氏に行ったインタビューで述べられたように、これらの状況を改善すべく業界再編の取り組みが求められているし、水面下では各所で進んでいる。これらの取り組みと改善が進めば、氏がいうように「日本のアニメの未来は明るい」と筆者も考えているが、アニメビジネスの重要な立役者の1つである製作委員会方式を悪玉にしてしまっては、本質から目を逸らし、逆効果しかもたらさないというのが正直な印象だ。










