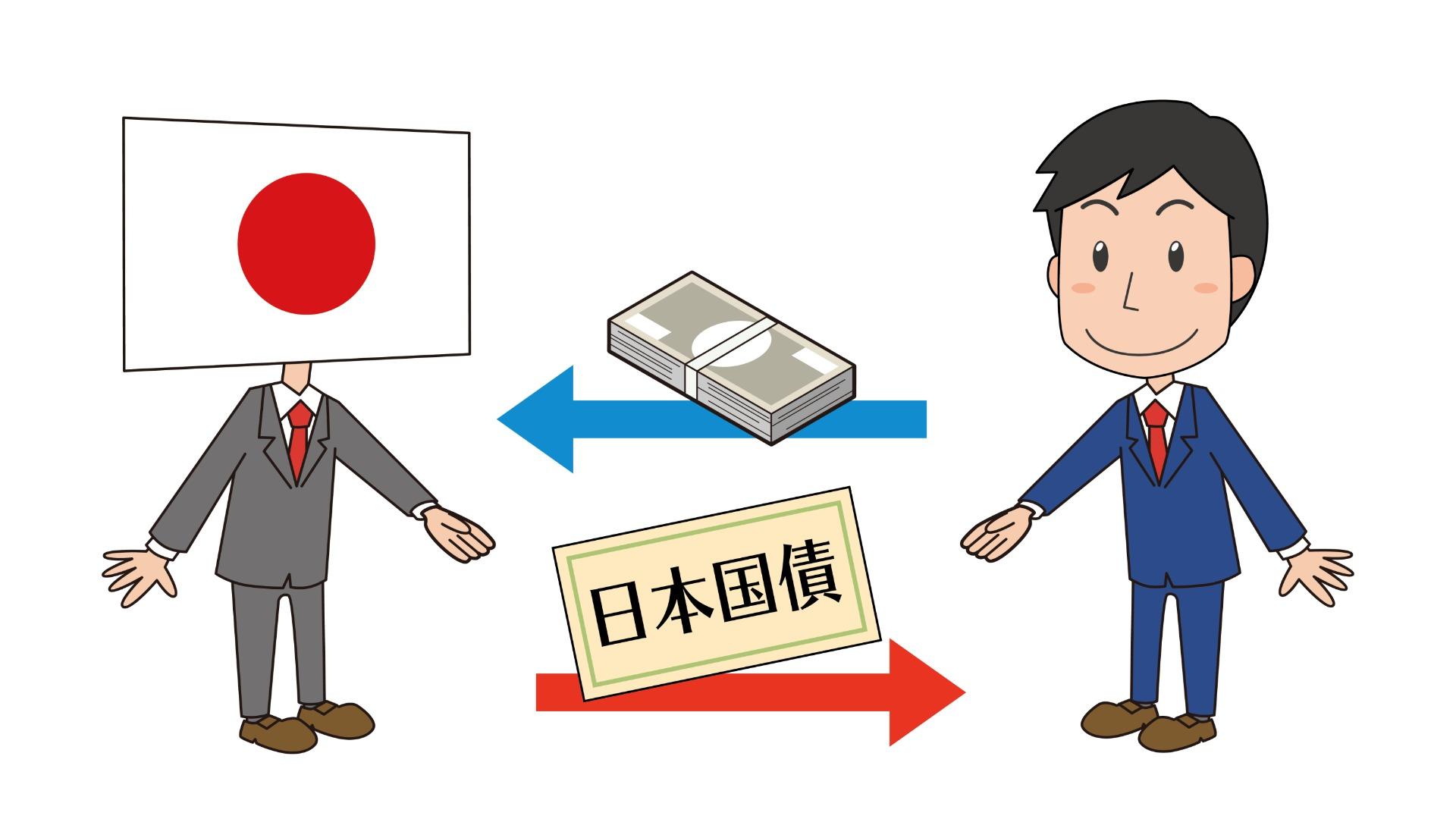行き過ぎた“小保方さんバッシング”が始まりである。
「理化学研究所の笹井芳樹・発生再生科学総合研究所副センター長が、神戸市内で自殺を図った」
との速報が流れた。
1月末に「世紀の発見」と報道されて以来、さまざまな報道がされてきた。
以下の記事は、3月に私が、それらの報道に対して抱いた感想を記事にしたものである。行き過ぎた“小保方さんバッシング”と女性活用の“闇”
この頃は、もっぱら小保方さんバッシングが過激になっていた時期。
どうかお読みいただきたい。これが今の日本=私たち の姿であり、今回の出来事のスタート地点でもあったということを。
これらのバッシングは、論文が投稿された経緯とは、切り離して考えなくてはならないと思っている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
なんとも言葉にしがたい、憤りを感じている。完全に超えてはいけない“一線”を越えている。露骨すぎる。
マスコミも世間も、怖い。本当に怖い。結局、行きつくところはここなのか? そんな思いでいっぱいである。先週、発売された週刊誌の内容は、とにもかくにもひどかった。
小保方さんに関する、バッシング報道である。
いったいこの報道にどんな意味があるのか?
持ち上げられた人が落ちていく様は、そんなに面白いですか?
安全地帯から石を投げるようなことをして、満足ですか?
ときにマスコミは、人間の中に潜む闇の感情を引き出す“悪の装置”と化す。と同時に、世間の人たちの“闇”を匿名化し、消費させる都合のいい装置でもある。
要するに、下劣なのはマスコミだけじゃない。
フェイスブックやツイッターなどでも、悪趣味なジョークが飛び交っていた。本人たちは、ブラックジョークのつもりなのだろうけど、完全にアウトだ。
と書きながらも、おそらく私の中にも“闇”は存在しているのだと思う。だから余計に怖いのである。
いずれにして、不適切と不正は分けて考えなきゃいけない。現段階では、論文内容に不適切な部分は確認されているが、不正かどうかは調査継続中と、理化学研究所は発表している。
もし、仮に、だ。仮に不正があったとしても、あそこまで小保方さんを追い詰められるほど、世の中の人は清廉潔白なのか。
少なくとも私には、「私は潔白です!」と言い切る自信はない。「いつ、どこで」と明確に答えられるような不正をしたわけじゃないけど、小さなインチキはあったと思う。
おそらく、今、この状況で、この問題に触れることはあまり賢明ではないだろう。でも、書きます。
取り上げる理由は、あの1月29日の発表から今日に至るまで、今回の問題の背後には、「トークン」としての「女性」のプラスとマイナスの両方が顕著に含まれていて、それが今回の行きすぎたバッシングにまでつながった、そう思えてならないからだ。
トークンとは、「目につきやすいもの、目立つもの」を意味し、少数派やマイノリティはトークンになりやすい。トークンは、社会や組織の中では、「珍しい存在」であるがゆえに、見せもの的な立場に置かれ、ときにさまざまなプレッシャーを経験する。その状態から引き起こされるさまざまな現象を、トークニズムという。
もし、小保方さんが女性じゃなかったら……。
おそらくここまで、卑劣な報道にはならなかった。
いや、それ以前に、小保方さんが30歳という若さで、ユニットリーダーになることもなかったかもしれない。
1月29日のマスコミ向けの、ちょっとだけ華やかな記者発表もなかったかもしれないし、マスコミ報道がここまで加熱することにもならなかっただろうし、世界中の研究者たちが、ネイチャーに掲載された論文を、ここまであら探しすることもなかったに違いない。
そもそも、アカデミックの世界、メディアの世界、おカネの世界は、融合しづらいものだ。学問という単純には白黒つけられないものと、白か黒かでニュースにしたがるマスコミ。自己の内発的動機主体で行われる研究と、利益を上げざるをえない医療産業。
その相容れないもの同士が結びついた現代の社会構造に、トークンとしての「女性」が加わったことで、問題はより複雑に、そして、陰湿になった。
そこで、今回の一連の問題を反面教師に、「トークンとしての女性」について、考えてみようと思います。
共著者の若山照彦山梨大教授が、論文の撤回を打診したとのニュースが駆け巡るまでに感じていた問題点については、既に以下のコラムでも書いているので、興味のある方はそちらをご覧ください(「小保方博士に“熱狂”したニッポン人が露呈した、“品格”のなさ?」、「STAP細胞は“黒”か“白”か?」)
未だに進まぬ、科学研究分野の女性進出
どこの企業でもそうであるように、研究者の世界でも女性の積極的活用が勧められている。「女性研究者 助成金」くらいのキーワードでググってみれば、さまざまな大学、財団、一般企業が、いかに女性研究者の育成に積極的であるかが、お分かりになると思う。
理化学研究所もかなり積極的で、「科学だけでなく、男女共同参画の問題でも最先端の施策を実現し、女性研究者がやる気を出せる、日本のモデル研究所となるよう努力している」のだという(こちらを参照)。
ちなみに、平成15年に男女共同参画推進本部が、「2020年までに指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度になるよう期待する」という目標を設定した当時、科学技術の分野における女性研究者の比率は11.2%だった。その後はさまざまな取り組みの結果、平成24年には14.0%まで連続して上昇している。
が、その割合は分野によって大きく異なる。最も多いのが人文・社会科学で28%。もっとも低いのは工学で、わずか5%。今回スポットがあたった理学は、工学に告ぐワースト2位で、12.6%となっている(総務省「平成24年科学技術研究調査」)。
1990年代には、女性研究者の“ガラスの天井”なるものを、統計的な分析から明らかにした論文が、欧米にセンセーションを巻き起こしたこともあった。
論文は、1997年にスウェーデンの医学者、WennerasとWoldによって書かれたもので、掲載されたジャーナルは、皮肉にも今回も話題になった『ネイチャー』だった(C.Wenneras & A.Wold; "Nepotismand Sexism in Peer-Review", Nature, 1997.)。
WennerasとWoldは、「スウェーデン医学研究評議会(Swedish Medical Research Council)による研究費補助金の審査過程で、男性は「男」というだけで高く評価され、女性は「女」というだけで低く評価されていた」ことを、統計的な分析から明らかにしたのである。
さらに、審査員となんらかのコネがあることも、審査の評価に影響していた。
性差別と縁故主義……。学問に、“王道”が存在していたのだ。
性差別も縁故も理屈じゃないから、余計にたちが悪い
Wennerasらは、コネを持たない女性が科学業績だけで “ガラスの天井”を破るには、最高ランクの雑誌に男性より20本ほど多くの論文を発表する必要があるとした。それは不可能に近いことを、意味している。
なんせ、程度の差はあれ、査読付きのジャーナルに投稿して掲載されるまでには、最低でも3カ月、1年近くかかることもある。男性より20本も多くの論文を発表するなんて、気が遠くなる。よほどの体力と頭脳と根性の持ち主じゃない限り、……いや、それでも無理。うん、やはり不可能だ。
ネイチャーという世界的なジャーナルで、研究費補助金獲得の機会の不公平さが暴かれた結果、スウェーデン医学研究評議会はその翌年から、女性の審査員を増やし、審査過程の透明性を高めた。特に、審査過程の透明性には明確な基準を示し、力を入れたそうだ。
男であれ女であれ、しっかりと仕事をすればちゃんと評価される――。この論文は、女性というだけで「機会」が失われないための取り組みが広がるきっかけの1つになったのである。
とはいえ、縁故主義などの感情は理屈じゃないうえに、性差別は大抵の場合、無自覚の価値観から派生しているので、そうそう簡単に解決されるもんじゃない。
無自覚の価値観とは、親の考え、子供の時によく見たテレビや雑誌に描かれていたこと、周りの人がよく言っていたことなど、社会に既存の価値観が、自分でも気がつかないうちに、あたかも自分の考えのように刻まれていく価値観である。
無自覚なので、悪気もない。自覚なきものは、そのまま次の世代に引き継がれ、地面の奥深くまで、どんどんと根っこを張り巡らせていく。
しかも、人間にはもともと自分と似た存在と馴染み、安心する傾向があるので、性差別は根深さを増す。同じ性、同じ大学、同じ職場、共通の知人、など、そんなたわいもないことで距離が近くなることは多い。
しかも集団の中で、親和性のある人たちが多数派になると、その人たちだけの「楽園」ができあがる。多数派の楽園がその集団の規範となり、ますます結束力は強められる。
その結果、少数派の人たちは差別されるようになる。規範となっている自分たちの楽園を守るために、区別ではなく、差別するのだ。
この少数派を、「トークン=目立つ存在」と位置付け、プラス面とマイナス面を明らかにしたのが、米ハーバード大学経営大学院教授のロザベス・モス・カンターである。
カンターは1970年代、5年間ほど、外部コンサルタントとして働いていたインダスコ社という企業で、トークンとしての「女性」の存在に着目し、記録したエスノグラフィーを、「Men and Women of the Corporation(邦題:企業のなかの男と女)」として出版した。このエスノグラフィーほど、私が職場環境の重要性を考える上で、多くのことを学ばせていただいた一冊はない。実に明快で、リアルで、示唆に富んでいる名著である。
カンターによれば、インダスコ社の上級職、特にセールス部門の女性は、非常に目立つ存在で男性の誰よりも注目を集めていたそうだ。自分はあまり目立たないと感じている女性でも注目されていて、彼女たちは常にゴシップの的だった。彼女たちの一挙手一投足が、監視され報告される。社内中の誰もが彼女たちのネタを歓迎し、彼女たちのゴシップを報告しあうのが日常だった。そして、大抵の場合、それらは“悪意”をもって伝えられていたのだ。
女性は一度の失敗でゴシップ対象に
例えば、ある上級職の女性が、同僚とホテルのエレベーターで少しばかりはしゃいでいたら、その数日後、「職場以外の場所でも、派手な振る舞いをする女だ」と噂になった。ただ楽しそうに話しているだけで、「派手な振る舞いをする女」などと揶揄される。しかもゴシップの9割以上は、仕事以外のこと。つまり、トークンとしての女性にプライバシーはなかったのである。
しかしながら、トークンが有利になることもあった。多くの男性は、上司やお客さんに覚えてもらうために、ネクタイの色を派手めにするなど、ありとあらゆる「覚えてもらう」努力をしていたが、女性たちは「女」というだけで覚えてもらえた。
営業の上級職の女性が売り上げトップになると社内中に知れ渡ったが、男性がトップになっても話題にならない。
トークンとしての女性は、その存在を認めさせるという意味では、実に有利な立場にいたのだった。
が、それは「最初の失敗をするまで」の間だけ。たった一回でも失敗をすると、男性との関係、服装、髪型、言葉遣い、など、仕事とは全く関係ないゴシップばかりが広がっていき、「そんなことやってるから、失敗するんだ」といわんばかりの厳しい視線を浴びせられたのである。
さらに、トークンは会社の経営陣の男性たちから、利用されることもあった。その一説を以下に抜粋する。
ある上級職の女性は、取締役会の会長上層部から、ある昼食会に出席するように要請された(このとき会の趣旨は教えてもらえなかった)。会食の当日、副社長が彼女のエスコート役として、彼女を迎えにきた。彼女は会場に着いて初めて、会食が各社の役員の集まりであることを知った。しかしながら、彼女の名前は参加者リストにはなく、代わりに男性役員の名前が登録されていたのだ。
インダスコ社の会長は、「わが社には、男性エスコートを付けるほどの、優秀な『女性』がいる。そういった女性をわが社では登用している」ということを社内外に、アピールするために彼女を呼んだのだった。
彼女のプライドを全く無視し、彼女をまるでショーケースの展示品のように扱ったのである。
その上級職の女性は、「まるでデートに連れ出されたようだった。私は何かの功績ある女性としてではなく、ただの女性として招かれた。屈辱だった」と語った。
理化学研究所の会見は「女性らしさ」を出しすぎでは
このカンターの一説ほど、トークンに向けられる性差別の、卑劣さをリアルに伝えているものはない。
1月29日に多くのマスコミを集め、理化学研究所が行った会見と、ちょっとばかりダブル。
もちろんインダスコの場合とは違い、「研究者」として小保方さんを全面に出したのだろうけど、「女性らしさ」をアピールした点には、同じ匂いを感じざるをえなかった。
念のため繰り返すが、このエスノグラフィーは1970年のものだ。今から40年以上前の状況と同じことが、日本社会で起きてはいやしないか? そう思えてならないのである。
ノーベル賞級の大発見だ! 割烹着だの、どこそこの指輪だの、と大騒ぎしたマスコミ。論文発表から相次いだ、論文に関するさまざまな指摘。挙句の果てに行きついた、下劣なバッシングの数々。
その背後には、
「なんで、あの人だけ評価されるわけ?」
「なんで、自分が選ばれないで、彼女になったわけ?」
「所詮、女っていうだけで、選ばれたんだろう?」
そんな嫉妬が、どこかにあったんじゃないだろうか。
不思議なもんで、人間というのは嫉妬する自分を恥ずかしいと思うらしい。だから、必死にその嫉妬心を隠すために、一瞬でも“あら”を見つけると、正義を振りかざす。
これって、倫理的にどうなのよ? 上司としてどうなのよ? 職業人としてどうなのよ? 責任とってないでしょ? といった具合に、だ。
そんないくつもの理性を凌駕した感情の波が、今回の問題を膨張させた。そう考えると、なんだかとんでもなく複雑な思いになってしまうのである。
周りも本人も、念入りに脇を締めなきゃいけなかった
少々言い過ぎかもしれないけれども、女性の積極活用は、両刃の剣なんだと思う。
トークンとなるチャンスを与えた人(=上司)も、目立つ存在となるチャンスを得た本人も、締めすぎるほど、脇を締めなきゃならなかった。
だって、「女性」というだけで注目されるのだ。
「ホラ、やっぱり女だからね」と言われないように、共同研究者の先生方も、どこから突かれても、正々堂々と主張できるものに論文を仕上げなければならなかった。もし、本当に小保方さんの発見に研究者として価値を見出し、若き研究者の芽を活かしたいと思っていたならば、だ。
そして、小保方さんは……、私は彼女が若かったことが、結果的に不幸な方向につながってしまったと考えている。
彼女は、トークンとしての女性を経験していなかった。いや、経験したとしても、若さゆえの大胆さが、裏目に出てしまったのかもしれない。
「周りに何を言われても関係ない!」――。若いとき、私はよくこんな風に思っていた。
男性ばかりの天気予報の現場で、男性の出演者の多いテレビの報道番組で、男性ばかりが講師を務める講演会で、男性の年配の偉い先生ばかりが集うシンポジウムで、私は恥ずかしげもなくノースリーブや、背中の大きく開いた派手な服装で出向いた。服装を注意されたりすることがあっても、「中身がしっかりしてれば、それでいいじゃん」――。そんな風に、いつも思っていたのだ。
だが、年齢を重ねて、自分が見えてくると、自分がいかに未熟で中身もしっかりしていなくて、いかに大胆だったかを知り、恥ずかしくなった。
「くだらないことでケチをつけられることほど、くだらないことはないので、そんなくだらないことでケチ付けられないようにしよう」――。そんな風に考えるようになった。
「どこから突っ込まれても、完璧にしなきゃ」と必死になった。「100点じゃなく、180点目指そう」。そう思うようになった。
ただ、これまた不思議なもんで、最近はまた、ちょっとだけ大胆さを取り戻している。開き直り? いや、違う。図々しくなった? そうかもしれない。いずれにしても、“今”に至るには、20年もの歳月がかかっている。
そして、今。失敗を失敗にさせなかった周りの“オトナ”たちに深く感謝している。失敗しても、追い詰められることがなかったのは、周りの人たちの力なくしてありえなかった。
未熟だからこそおもしろくもあり、若さゆえの大胆さが、世の中を変えることもある。それをプラスに導くもの……。それを今一度、誰もが考えなきゃいけないんだと思う。