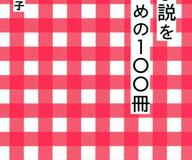『私、能力は平均値でって言ったよね!』――ハイスペ人材は目立つと叩かれるのでひっそりしたいと願う

FUNAが「小説家になろう」に連載する『私、能力は平均値でって言ったよね!』が19年10月からTVアニメ化された。
導入部のあらすじはこんな感じだ。
ちょっと抜けてる秀才タイプの女の子が車に轢かれるも、生前、歴史的に重要な人物が死ぬことを防いでいたという働きを買われて自分の望む状態で次の世界に転生できることになる。
平凡な生活を望む彼女は「平均値で!」と望むが生まれは子爵。
その世界の階級ランク的に十段階の五番目だから。「平民じゃない!」と嘆く主人公。
だがほかにもさらには魔力から何から、その世界の頂点である存在と最底辺の存在の真ん中の能力を付与されており、凡俗に比べると全スペックが圧倒的。
ただし家族は主人公の存在を疎ましく思っており、追い出されるようにして無一文で学校に入り、自立をめざす。
前世の知識はあるがその世界の常識はない彼女はことあるごとにズレた振る舞いをするが、本人の悪意のなさと周囲の性格のいい人間に恵まれることでなんとかやっていく。
しかしどこに行っても能力の高さがバレてしまい、次のステージに向かうことになる……。
「本当はすごいけど、表向き違います」パターンの作品だが、トーンはコミカル。
本気で普通に生きたいと思っている……が、そうはならずに転がっていく。
もちろん、主人公が望むような本当に平凡な一般人の話だとしたらさほどおもしろくならないわけで、読む(観る)側からすれば、活躍してもらったほうがいいに決まっている。
こういう「普通」「平均」「目立たない」を望むと口では言いつつ、作中の主人公のように特殊能力があって特別扱いされる、という設定は日本のエンタメでよく見られるものである。
たとえば時代小説でも「ふだんは長屋住まいの料理人だが、実は陰謀で藩を追われた剣豪」みたいな、本当はすごいのにひっそり生きてますパターンがよくある。
ほかにも、芥川賞を獲った村田沙耶香の『コンビニ人間』ともある意味似ている。
あの作品は、世間の常識が全然わからない女性が、やはり頭のおかしい同僚の男を家に置いておけば周囲の人間から
「恋人いないの?」
「結婚しないの?」
とうるさく言われなくなることに気づき、男を風呂場の浴槽に放置していたら妹(こっちはまとも)に発見されて
「『家に男がいる』ってこういう意味かよ!」
とビックリされてしまったりする。
「普通」「常識」を過剰に求められる(あるいは、それに過剰に適応しようとしてしまう)日本社会の窮屈さと、そこからナチュラルにはみ出てしまう人間のおかしみを描いていた。
『コンビニ人間』にも『私、能力は~』にも「はみ出ていていい」「他の人とは違っていて当たり前」という価値観がない。
ヒーロー稼業以外の表の顔も裕福だったり、成果をあげようと奮闘していたり、「昼は大企業のCEO、夜は必殺仕事人ばりに法で裁けない悪を討つ。しかもイケメンでモテまくる」という設定のキャラよりも、顔もスタイルもよく最強であっても「まぬけな性格」「偏った趣味」「異常な謙虚さ・卑屈さ・無欲」といった属性がくっつけられたほうが日本では人気が出やすいように思う。
こういう傾向は小説から映像、ビジネス書まであらゆる面で見られる。
少し古い話になるが、たとえば「仕事も育児も全部こなす」みたいなマリッサ・メイヤーの本は日本では本国と比べるとそれほどは売れず、しかしDeNAの創業者・南場智子の本はベストセラーになった。
南場さんはハーバードMBA→マッキンゼーを経てベンチャーを立ち上げたスーパーエリートなのに、愛嬌があって「自分は失敗ばかりだ」などとあけすけに語るからだ。
ハイスペ人材も弱さを見せて「自分も普通の人間です」アピールをしたり、天然だとかといったそぶりを見せないと日本では受けいれられにくいのだ(ホリエモンもライブドア時代より逮捕後の方が好感を持たれているのは「弱い部分も時々見せる」に切り替えたからだろう)。
『私、能力は~』にもそういういじましさを感じる。
よく知らない異世界でヘタに目立ったら命が危険にさらされるかもしれないから回避する、というのはわかる。
しかし主人公のふるまいはどう見てもそれ以上に「普通」「平均」「平穏」を望み、つまり身の危険を案ずるよりもむしろ「叩かれる」とか白い目で見られるといった社会的な摩擦が生じない人生を求める度合いの方が強く見える。
だが、普通以上の能力を発揮しまくる快楽もそこにはある。
笑えて楽しい作品だが、ねじれを感じる一作でもある。