小山評定は、なぜ開催をめぐって大論争になっているのか
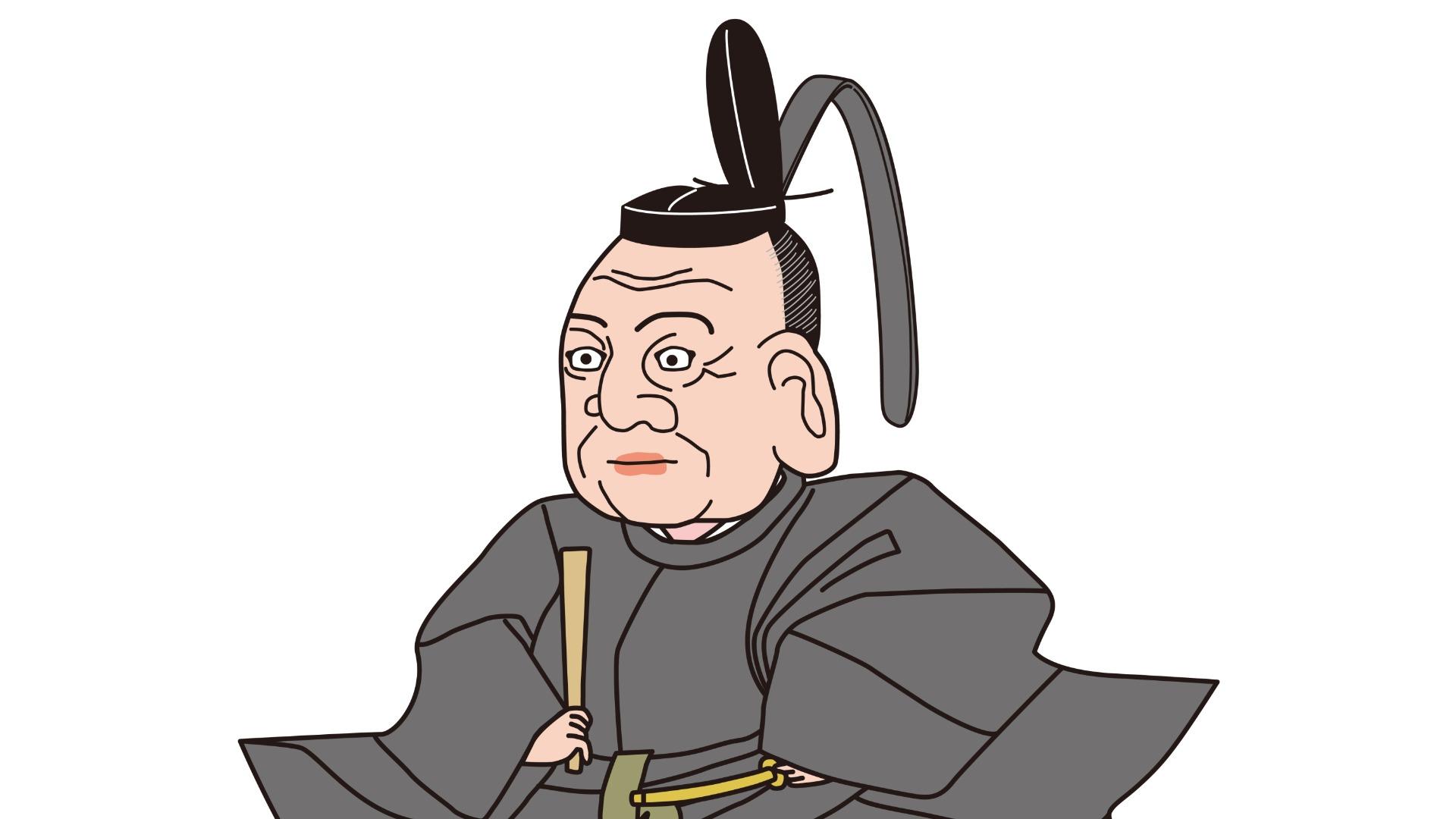
小山市立博物館(栃木県小山市)では、企画展「小山評定とその時代の軍装」が開催されている。ところで、小山評定は近年になって大論争になっているが、その理由について考えてみよう。
慶長5年(1600)6月、徳川家康は上洛を拒否した上杉景勝を討伐すべく、会津へと出陣した。翌月、増田長盛ら3人の奉行が「内府ちかひの条々」を諸国の大名に発し、家康を討伐すべく檄を飛ばした。西軍の決起である。
西軍の決起を知った家康は、いったん会津征討を中止し、西軍への対処を考える必要が生じた。そこで、7月25日、家康は小山(栃木県小山市)に諸将を召喚し、会議を催した。この会議こそが小山評定であり、家康の運命を大きく変えた。
通説によると、小山評定ではまず石田三成らの挙兵が知らされた。諸将の中には、大坂で妻子が人質になっている者もいたので、家康は「どちらに味方するかは、各自の判断に任せる」と述べた。
すると、福島正則が率先して、妻子の命を擲ってでも、家康に与することを宣言した。諸将は正則の言葉に次々と賛意を示した。流れは大きく家康支持に傾いたのである。正則に率先して家康に与する発言をするように仕組んだのは、黒田長政だったといわれている。
結果、まず三成らを討つことになり、先鋒として福島正則と池田輝政を清洲城(愛知県清須市)に遣わすことになった。加えて、遠江国掛川城(静岡県掛川市)主の山内一豊は、家康に城を提供すると申し出た。すると、東海道沿いに居城を持つ武将たちは、皆同じ申し出をした。
こうして家康は宇都宮に結城秀康(家康の次男)を上杉氏の備えに置くと、7月26日以降、次々と諸大名が西上していったのである。しかし、以上の話は二次史料に書かれたことで、小説や時代劇のネタにもなった。
小山評定を探るうえでの最大の問題点は、根拠となる一次史料(同時代史料)がなく、二次史料にしか経緯を示す記述がないことである。その結果、信頼度が高いとされる二次史料を分析し、関連する一次史料をもとにして、家康がいつの時点でどこにいたのかが焦点となった。
当初、「小山評定はなかった」という説はセンセーショナルに伝わったが、現在は「あった」と考える説が優勢だろうか。論争は今も続いているので、今後の研究に注目したい。










