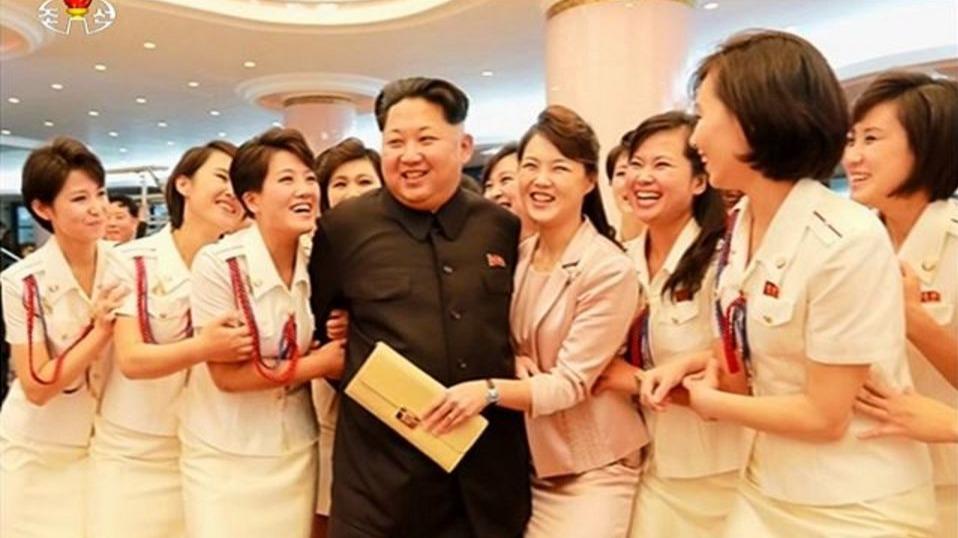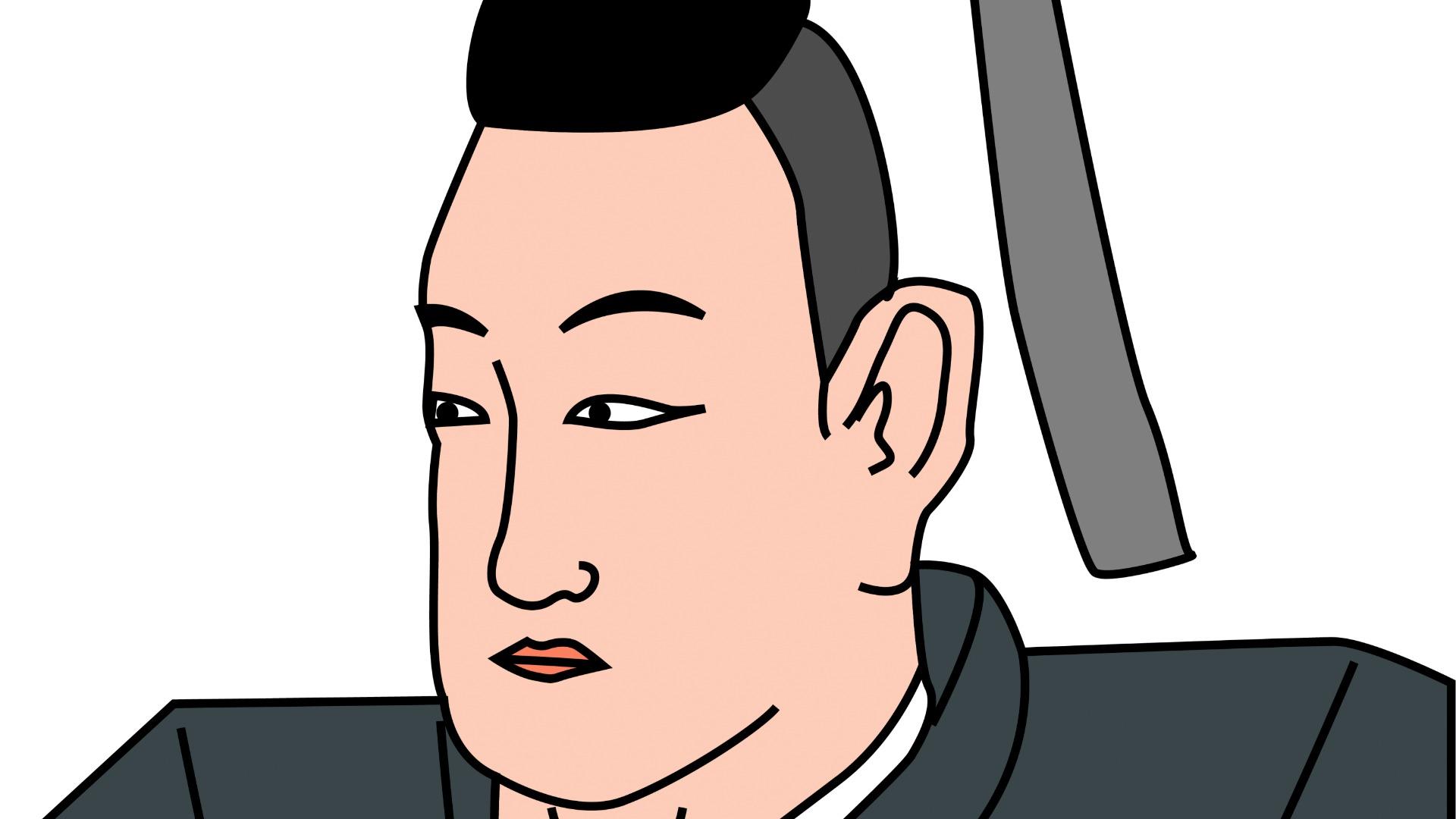コロナ対策用のマスクやアルコール、医療費控除の対象になる? FPが解説
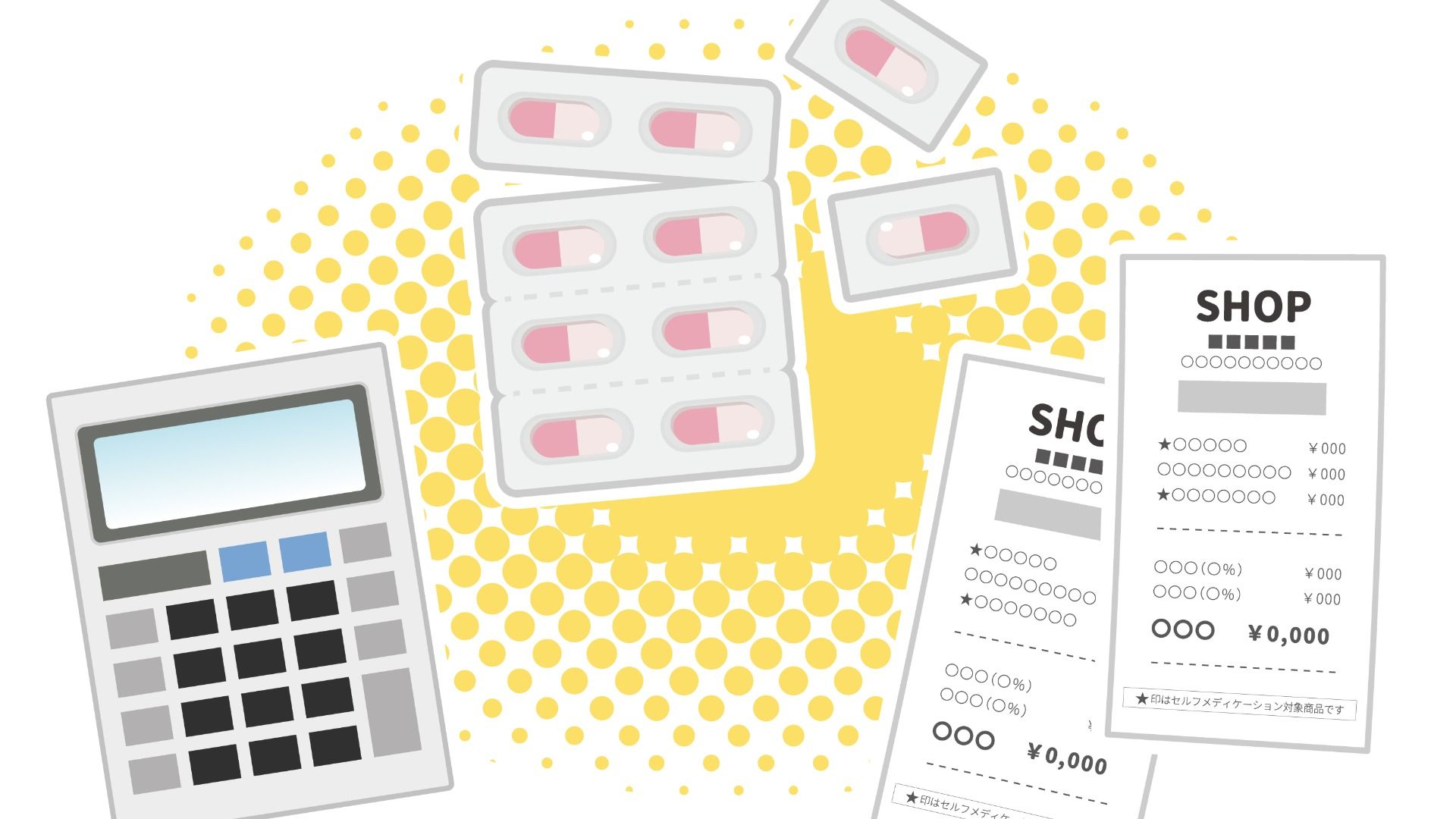
2020年は新型コロナウイルスに振り回された一年となりました。各家庭でもマスクや消毒用アルコールを頻繁に購入したほか、人によっては自費でPCR検査を受けたり、導入が進んだオンライン診療を受けて処方薬を配送してもらったりということもあったと思います。こうした感染対策のための家計支出は、確定申告によって税金が戻る「医療費控除」の対象になるのか、見ていきましょう。
◆年末調整では戻らない納め過ぎの所得税、「還付申告」が必要
2月16日から2020年分所得税の確定申告が始まりました。緊急事態宣言の延長に伴い、期限は4月15日と、通常より1か月長くなっています。ただし「医療費控除」など納め過ぎた税金を返してもらうための「還付申告」は1月1日から受け付けが始まっており、2020年分は5年間(2025年末まで)申告することができます。
※「医療費控除」と「還付申告」について
会社員・公務員など給与所得者(仕事の対価として給料を貰っている人)の所得税は、年末調整によって1年間の税額を精算します。給与から多めに天引きされていた分が戻るケースが多いようです。けれども、年末調整では戻らない納め過ぎの税金もあります。その代表例が「医療費控除」が使えるケース。「医療費控除」とは、本人や生計を同じにする家族が入院した、多額の薬代がかかったなどで医療費負担が大きかった場合、税負担を軽減する制度です。
所得税額は、収入から経費と各種控除を差し引いた金額をもとに計算されます。控除対象が多ければ、納めるべき所得税額も少なくなるわけです。勤め先が所得税額を計算する際、「医療費控除」の対象になるかどうかまでは把握していません。また、税務署から「あなたは税金を納め過ぎですよ」とは連絡してくれません。納め過ぎの税金を戻してもらうためには、それぞれが「還付申告」する必要があるわけです。
◆コロナ対策の出費で「医療費控除」は使える?
「医療費控除」の対象となる医療費は、「医師等による診療や治療のため実際に支払った費用(生命保険などの入院給付金、健康保険の高額療養費などを差し引いた金額)」と「治療や療養に必要な医薬品の購入費用」が原則となっており、「医療費控除」の受け方には次の2通りあります。両方は使えず、どちらかの選択になります。
【1】実際に支払った医療費のうち10万円を超えた金額を所得控除する方法
よく「医療費が10万円を超えたら確定申告を」と言われる方法です。たとえば、実際に支払った医療費の総額が25万円だったとすると、25万円-10万円=15万円が「医療費控除」の金額となります。
必ずしも「医療費10万円超の部分」ではなく、総所得金額が200万円未満の人は「総所得金額の5%の金額」を超えた分が「医療費控除」として認められます。収入が給与だけの人は、目安として年収が297万円以下(総所得金額199万7600円と計算される)であれば該当します。
たとえば、年収250万円の人だと総所得金額は167万円となるので、その5%の8万3500円を超えた金額を所得控除できます。実際に支払った医療費の総額が9万5000円で「10万円に足りない!」といった場合も、還付申告できますからあきらめないようにしましょう。また、実際に支払った医療費の総額が25万円だった場合、25万円-8万3500円=16万6500円が「医療費控除」の金額となります。
医療機関に支払った医療費の実費以外にも、
・市販薬の購入代(治療目的でないビタミン剤などはNG)
・治療のためのマッサージなどの施術代(体調を整えるための施術代はNG)
・通院のための交通費(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代はNG)
などを「医療費控除」の対象として合算できます。
対象となるかどうかは、国税庁のHP医療費控除の対象となる医療費で確認しましょう。
2020年は新型コロナの感染予防のため、マスクや消毒用アルコールにかなりの支出があったというご家庭が多いと思います。これらは「治療」のためではなく、「予防」のための支出ですから、残念ながら「医療費控除」の対象にはなりません。健康維持のために購入したビタミン剤などと同様の理由です。
諸事情で新型コロナに感染していないことを証明する必要があり、自費でPCR検査を受けた人もいると思います。この場合の検査費用も、残念ながら「医療費控除」の対象にはなりません。陽性の疑いがあって治療につなげるため、医師が検査の必要ありと判断して受けたわけではないからです。
ただし、自費でのPCR検査の結果、陽性だったため医療機関で治療を受けることになった場合、治療にかかった自己負担分は「医療費控除」の対象となります。医師の判断で受けた公費負担のPCR検査の結果、陽性で治療を受けることになった場合も同様です。
また感染対策として導入が進んだオンライン診療でかかった費用については、概ね「医療費控除」の対象となりますが、「医薬品の配送料」は対象外とされています。
新型コロナに関する医療費控除の取扱いについては、国税庁のHP新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係が参考になります。
【2】対象の医薬品購入が1万2000円を超えたらできる「セルフメディケーション税制」
もう一つの受け方が「セルフメディケーション税制」です。こちらは、勤務先や自治体の健康診断を受けているなど「健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取組み」を行っている人が、制度の対象となる「スイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用から転用された医薬品)」を薬局やドラッグストアで年合計1万2000円以上購入した場合、超えた部分を所得控除できるという内容になっています(最高8万8000円)。
「スイッチOTC医薬品」であるかどうかは商品パッケージに記載されているほか、購入時のレシートにも記載されているので確認しましょう。「すでに捨ててしまった!」という方は、今年から要注意です。
支払額が10万円を超えるほど医療機関にはかからず【1】に該当しないけれども、購入した市販薬が結構あるというご家庭の場合は、こちら【2】での申告を検討するとよいでしょう。
◆申告手続き、パソコンやスマホを使って自宅でも
「還付申告」の手続きは、確定申告書に必要書類を添付して税務署に提出すればOKですが、コロナ禍でもあり、パソコンかスマホによる「e-Tax」を利用しての申告をお勧めします。マイナンバーカードと、マイナンバーカード読取対応のスマホ(あるいはICカードリーダライタ)が必要ですが、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成した申告書を提出できます。
スマホで「医療費控除」の入力を行う方法は、国税庁のYouTubeチャンネルでも案内しているので参考にしましょう。たとえば、スマホ申告(医療費控除の入力方法)などがアップされており、「確定申告書等作成コーナー」にリンクするQRコードも出ています。
従来どおり紙で作成した申告書も郵送での提出ができるので、コロナ禍のなか税務署に出向いて密になることは避けられます。(なお、マイナンバーカードを持っていない人は、税務署で発行されたID・パスワードで「e-Tax」を利用する方法もあります。発行してもらうために税務署に行く必要がありますが、専用端末により10分程度で発行手続きできます)。
いずれの方法も申告に必要な書類は共通します。
上記【1】の「医療費控除」を選択した場合、手続きに必要な書類は、(1)確定申告書A(「e-Tax」を利用する場合は入力画面で作成)、(2)2020年分の給与所得の源泉徴収票、(3)医療費控除の明細書、です。(2)はすでに勤め先からもらっているはずです。
「e-Tax」を利用する場合、かかった医療費のデータ(医療を受けた人の氏名、病院・薬局など支払先の名称、支払った医療費の額など)を入力することにより、(3)の医療費控除の明細書が自動的に作成されます。件数が多くて一件一件入力していたのでは間違えそうなら、Excelの医療費集計フォームを使用した入力が便利です。あとで読み込むことができ、医療費控除の明細書が作成されます。
医療費控除の明細書を記入する際、「生命保険や健康保険の高額療養費などで補てんされる金額」がある場合は、何に対して補てんされたのかに注意しましょう。うっかりすると、支払った医療費のトータルから補てんされた金額を差し引いてしまいますが、「給付の目的となった医療費」の金額を限度として差し引けばいいことになっています。たとえば入院した場合、入院のためかかった医療費の額より生命保険の入院給付金額が多かったとしても、多かった金額分を他にかかった医療費からは差し引く必要はありません。
(「知らないと不利な申告をしてしまうかも、「医療費控除の明細書」の書き方の注意点」参照)。
次に、「セルフメディケーション税制」を選択する場合ですが、先の(1)確定申告書A、(2)2020年分の給与所得の源泉徴収票、(3)セルフメディケーション税制の明細書、(4)健康の保持増進および疾病の予防に関する取組を行ったことを明らかにする書類(健康診断の結果通知表、インフルエンザの予防接種の領収書など)が必要になります。
以前は「医療費控除」の還付申告に医療費の領収書の添付が求められていましたが、現在は医療費控除の明細書、あるいはセルフメディケーション税制の明細書だけで良くなりました。ただし、税務署から確認のため領収書の提示を求められる可能性はあるので、5年間は捨てないようにしましょう。
【この記事は、Yahoo!ニュース個人編集部とオーサーが内容に関して共同で企画し、オーサーが執筆したものです】