反骨のスポーツジャーナリスト、大野晃さん逝く
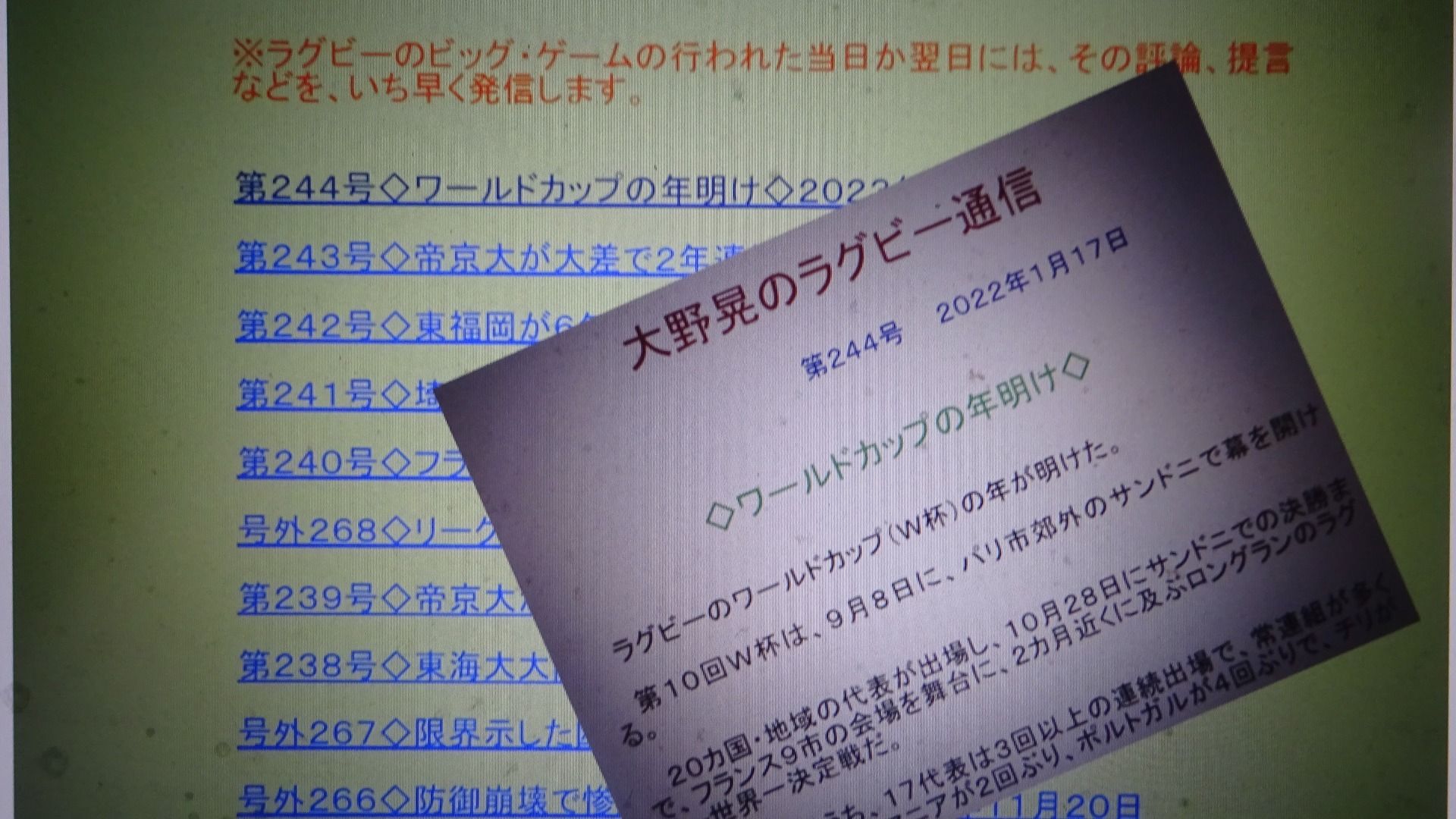
ラグビーとお酒を愛した反骨のスポーツジャーナリスト、大野晃(あきら)さんがこのほど、天国に旅立った。享年75。反権力、反権威、反迎合…。酒を飲んではメディアの軟弱な姿勢を批判し、こう口にしていた。「選手たちのことを本気で考えているのか」と。
2月27日、病気で死去。新潟県出身。葬儀は家族で営んだ。大野さんはいつも、怒っていた。そう、見えた。ジャーナリズムとは、メディアが時事的な事実や問題に関する報道・論評を伝達する活動を指す。だから、批判的な問題意識を尊ぶ。大野さんは生前、日本のスポーツメディアには本物のジャーナリストはいるのかと不安を漏らしていた。
大野さんのジャーナリストとしての転機は、毎日新聞運動部記者時代の1980年の日本のモスクワ五輪ボイコットの取材経験だった。日本スポーツ界が政府の圧力に屈する形で五輪不参加が決まった出来事である。
筆者は、東京は亀有の大野さんの自宅の三階仕事場で、その時のことをじっくり聞いたことがある。大野さんは、オリンピックを政治の道具とすることに反対し、「モスクワ五輪ボイコットとは日本スポーツ界の“敗戦”だった」と言った。
たしか、筆者がモスクワ五輪を漢字一文字で表現すると?と聞けば、大野さんは「怒りだね、怒(ど)だ」と即答した。
「スポーツ界、メディア、ぜんぶに対する怒りだね。自分たちメディアが問題意識を広げることができなかったことに対する怒りだよ」
その怒りが、大野さんのジャーナリスト魂に火を付けたのだろう。選手ストーリーや競技中心の報道スタイルから、検証記事、スポーツ界のあり様を問う新聞連載を手がけるようになった。1981年、名古屋が1988年五輪招致に失敗すると、モスクワ五輪ボイコットの影響を問い、アジア軽視のツケだと指摘した。<五輪精神を忘れていた日本><政治の介入を排除し、スポーツ界自立の機に>
大野さんは日本スポーツ界の危機を感じ、読み応えある連載記事を新聞、雑誌で次々と打ち出していった。
「アジアスポーツの新しい風」(1990年)
「ステートアマの消滅」(1992年)
「世紀末スポーツを切り結ぶ~報道者の自己批判」(1994~95年)
大野さんはラグビー記者としても健筆をふるった。ラグビー専門誌のラグビーマガジンで長くコラムを連載し、多くのラガーに文章を通し檄を飛ばしてきた。筆者も随分、世話になった。勝負の肝を見ろ、チームの戦術、長所・短所を指摘せよ、とよく言われた。歴史に学び、未来を予見せよ。ラグビーとは、15人の結集された力、全人格の優劣を競うスポーツだとも。
大野さんは2000年、52歳で毎日新聞社を退社し、若手記者を育てるため、日本スポーツ・ジャーナリズム研究会(FSJ)を設立した。筆者もメンバーだった。酒を飲みながら、スポーツマターの議論を深めた。取材の視点や問題意識の甘さを、よく指摘された。時には怒鳴られた。
大野さんはネットで連載コラムをアップし続けてきた。
『FSJ通信』として2000年5月24日号「モスクワ五輪ボイコット20周年」から絶筆となった今年1月25日号「憂慮すべきは子どものスポーツ離れ」まで542本、『大野晃のラグビー通信』としては2000年12月7日号「日本協会の視野狭窄を恐れる」から今年1月17日号「ワールドカップの年明け」まで512本、すなわち両方合わせて実に1000本を超える記事を書いてきたことになる。その熱量たるや。
筆者が、大野さんとラグビーの取材現場で一緒になったのは2019年のラグビーワールドカップ(W杯)が最後だった。
日本代表がアイルランド代表に番狂わせを演じた9月28日・静岡での大一番(〇19-12)、ラグマガ誌の田村一博編集長は記者席で初めて大野さんの隣になったそうだ。
同編集長の述懐。
「日本が逆転した時、みんな興奮していたけれど、大野さんだけは冷静に落ち着いているだろうと思ったら、“イケーっ”って大声出して、テーブルをたたいていたんです。驚きました。でも、これがスポーツジャーナリストの基本で、興奮する時は率直に興奮し、しかし、文章は冷静なペンで書くということなんでしょう」
その時、大野さんが書いた『ラグビー通信』の原稿「再び日本代表に奇跡が起こった」を見る。日本の勝因を的確に分析した上で、こんなフレーズもあった。
<筆者は予想が外れたことに、恥ずかしながら、心躍っているのだ>
大野さんは、誠実、実直、ピュアな人だった。ありがとうございました。合掌。










