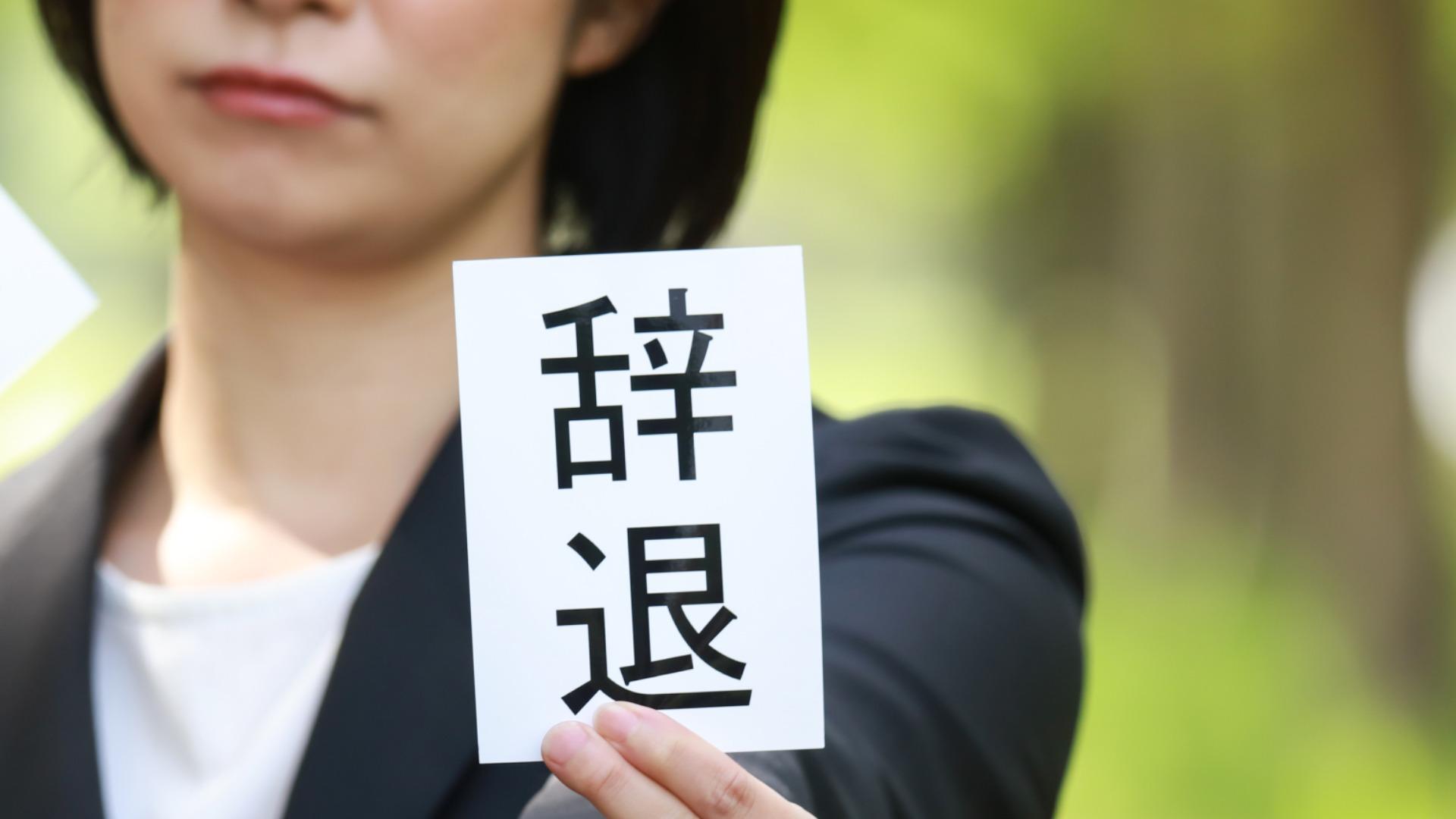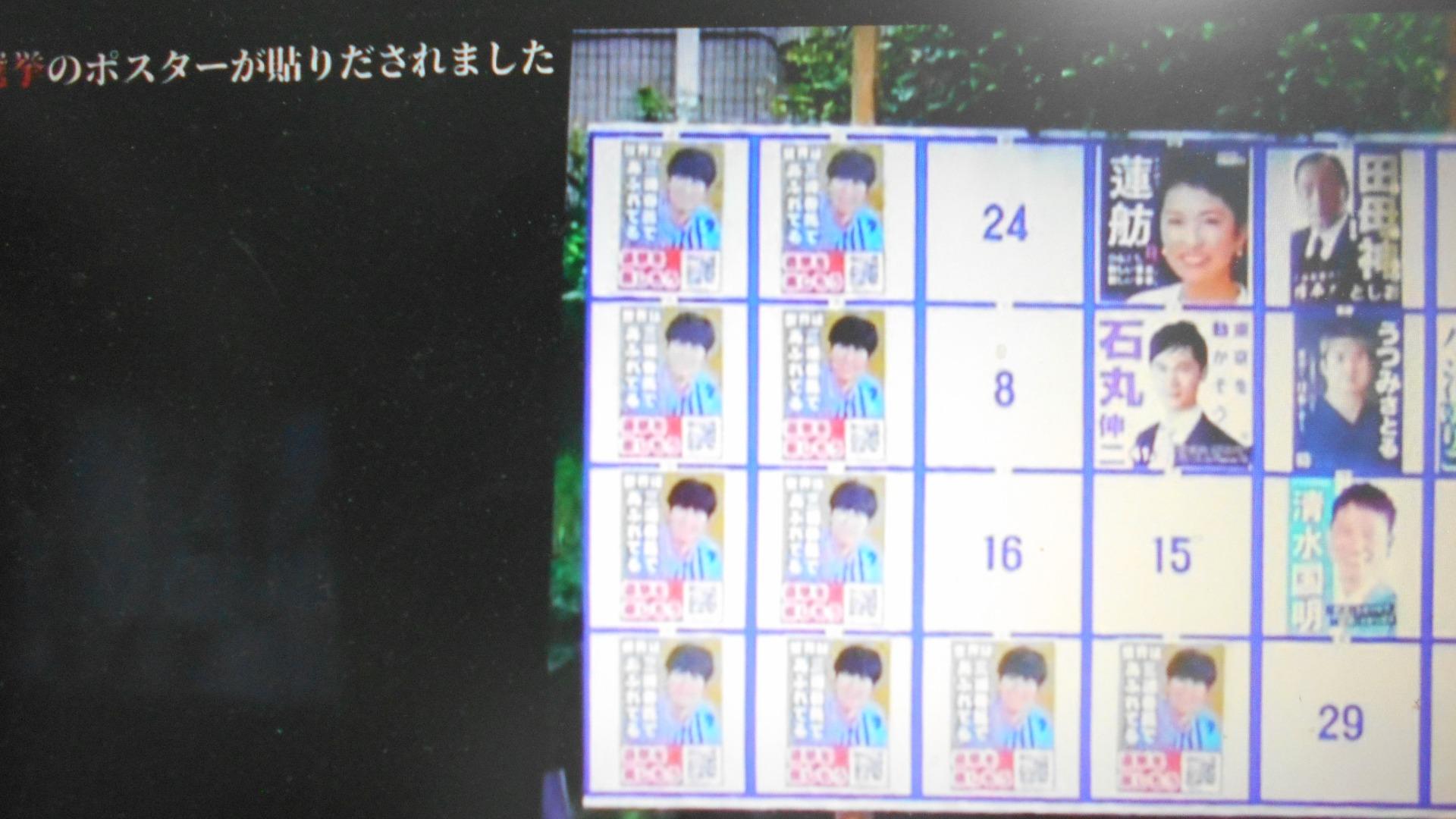米国で介護ロボットを自分や家族に使いたい人は41%

高齢化の進行に伴い注目を集めている新技術の代表格が介護ロボット。米国では介護ロボットはどのような印象を持たれているのだろうか。同国の民間調査会社Pew Research Centerが2017年10月に発表した、技術と人々の暮らしに関わる調査結果「Automation in Everyday Life」(※)を基に確認していく。
まず最初に示すのは、介護ロボットを回答者自身やその家族に使うことに対し、興味があるか否か。原文では単純に「介護ロボット」とのみ表記されているため、自律型の完全介護ロボットとは限らないが、報告書内では「ロボット」の表記は工場内の流れ作業で使われるロボットなどを指しているため、介護者する側が人間でその能力を補助するようなサポーター的な役割の道具ではなく、そのロボットのみで介護するような存在を指していると解釈できる。

回答者自身がすでに介護を受けるような立場にある、あるいは家族に介護をしている人もいるケースもあれば、現在は若年層の年齢で介護の話などまだ先の人もいる。そのような調査対象母集団全体としては41%が、介護ロボットを自分自身や家族に使ってみたいと考えている。
それではいかなる理由で介護ロボットを使いたいのか、あるいは使いたくないのか。それぞれの立場の人に主な理由を尋ねた結果が次のグラフ。

使いたい人の理由のトップは「家族への負担を減らせる」「よい介護の質が望める」で21%。介護ロボットが高品質の介護機能を持ち、介護を任せることができるため、その分家族のリソースを介護以外に使えるとの期待がある。次いで「高齢者の自立に役立つ」が15%。人による介護はどうしても限界が生じてしまうが、ロボットならばその心配もいらない。「いつでも介護できる」も本質的には同じようなものだろう。
他方使いたくない人の理由のトップは「人との接触が無い」で54%。要は「機械任せ」となり、介護される側が孤独感や不快感(モノ扱いされているのではとの認識)を覚えるのではないかとの不安・不満。「単に発想がイヤ」「介護は家族がするもの」も内情はあまり変わらない。次いで完全自動運転車でも指摘されている「ミスのリスク」が12%で続く。
大勢としては、使いたい人はそのメリットに注目し、使いたくない人は「介護を機械任せにするのはよくない」とする固定観念によるところが大きい。介護そのものは一過性のものではなく、継続的に行われるものだから、より「機械任せにされる」との認識が強くなってしまうのだろう。
その「機械任せにされる」の思いは、介護ロボットそのものへのあらゆる方面への不信感にもつながっている。

介護ロボットを使いたい人は介護ロボットへの肯定的意見には多数の人が同意を示し、否定的な意見には少数しか同意しない。使いたくない人は肯定的意見には少数しか同意せず、否定的意見には多数が同意を示す。あるいは逆で、色々な面で不安や否定的見解を持つからこそ、介護ロボットを使いたくはないと考えているのかもしれない。
もっとも「若年層の高齢層への介護負担の心配を減らせる」との意見は、介護ロボットを使いたくない人でも57%が同意を示している。若年層の負担への懸念は非常に大きいようだ。
■関連記事:
※Automation in Everyday Life
調査専用の調査対象母集団(RDD方式で選択された固定電話・携帯電話を有するアメリカ合衆国の18歳以上を対象に選択)を対象に2017年5月1日から15日にかけて実施されたもので、有効回答数は4135人、うち就業者は2510人。国勢調査の結果を基に性別、年齢、学歴、人種、支持政党、地域、就業中か否かなどの属性でウェイトバックが実施されている。
(注)本文中の各グラフは特記事項の無い限り、記述されている資料を基に筆者が作成したものです。