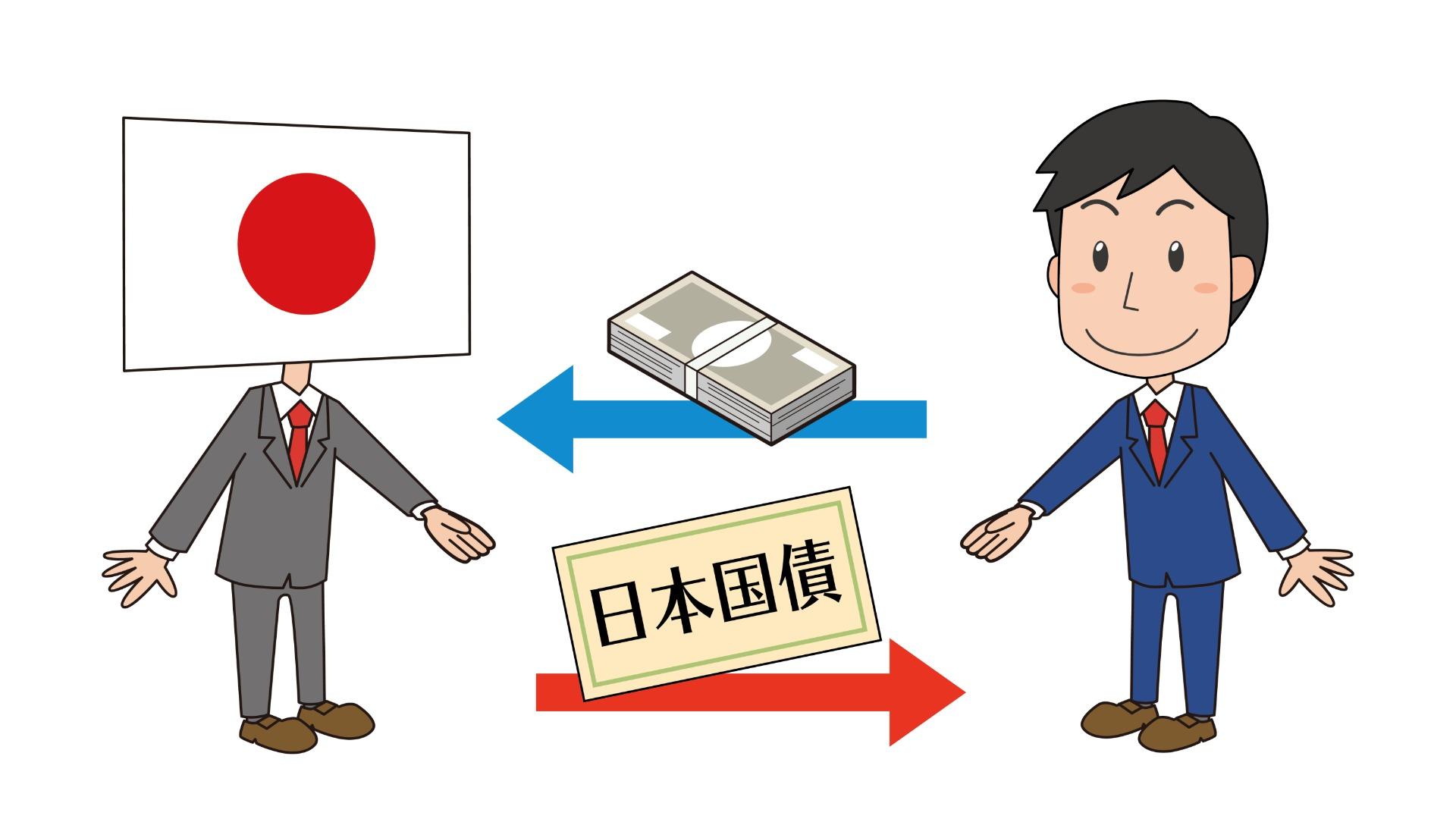樋口尚文の千夜千本 第113夜「蚤とり侍」(鶴橋康夫監督)

風柳をもって反骨となす痛快艶笑時代劇
鶴橋康夫監督といえば『魔性』『雀色時』などのテレビドラマの傑作群で、妖しい琥珀の怪光線のなか人物たちがおもむろに社会の規範を逸脱してエロスや犯罪の深淵に堕ちてゆくさまを衝撃的に描いてきたが、映画では案外『愛の流刑地』のようにごくシリアスなものよりも、『後妻業の女』のような艶笑コメディのほうが面白さが際立っているかもしれない。『後妻業の女』はシニアの観客を多く集めたに違いないが、同じシニアが観られる映画でも山田洋次監督のヒットシリーズ『家族はつらいよ』であいかわらずセックスが捨象されて健全な笑わせ芸が追求されているのに対し、当年とって78歳の鶴橋映画にあっては性愛や犯罪のモチーフと、そこから来るいささか不謹慎な笑いが暖簾の色である。
しかし『蚤とり侍』とはケッサクな題材で、時はいわゆる田沼時代、お客の猫の蚤をとるという口実でやってきて、実は女性たちにご奉仕する添い寝業のことを指すという。要は出張ホストみたいなことで、この「蚤とりさん」たちが「猫の蚤、取りましょう~」と客寄せの声をあげながら市中をそぞろ歩くと、あちこちからその気満々の女子たちの声がかかる。藩のエリートだった主人公の寛之進(阿部寛)はバカ殿に恥をかかせたかどで城を追われ、貧乏長屋でこの「蚤とり」をやるはめになる。阿部寛は『テルマエ・ロマエ』やドラマ『結婚できない男』などで、あの彫刻のような顔立ちと堂々たる体躯を持て余すように右往左往するたび爆笑を誘ったが、今回もその喜劇的資質を全開にしてしたたかに笑わせてくれる。
謹厳実直な城内でのスタイルとは真逆の、なんともチャラくお水っぽい着物をあてがわれた寛之進は、初めての客のおみね(寺島しのぶ)にも生真面目なご奉仕を試みるが、エリート侍の矜持も「この下手くそが」のひとことで一刀両断にされ、ここで彼のパラダイム・シフトが始まる。職場でのポストも女たちには何の価値もなく、この巷では優しく愛して喜ばせてくれる男がよほど尊敬されるのである。その方面の達人である伊達男の清兵衛(豊川悦司)との出会いでショックを受けた寛之進は(根が実直なもので)この性豪の手管を盗むべく房事の観察に余念がない。豊川悦司も寺島しのぶも、『愛の流刑地』の深刻な演技とはうってかわって、このへんてこな艶笑譚を実に機嫌よく演っていて好感が持てる。
この遊びなれて余裕ある清兵衛が、小間物問屋の婿という立場ゆえに実は肩身が狭く、とんでもない恐妻家だというのがおかしい。旦那のご乱行に手を焼いて、とんでもない浮気防止策(これは観てのお楽しみ?であるが)に打ってでる妻のおちえに扮した前田敦子のコメディエンヌぶりがとてもいい。よりによってこの役に前田敦子をというのは案外思いつかないことだと思うので、ここは鶴橋監督の慧眼に恐れ入る。この夫婦のくだりを筆頭に、今回の鶴橋監督は『後妻業の女』以上にどこか飄々と洒落てみせて、実に肩がこらない。それが後半、お上の「蚤とり」禁止令のくだりからは反骨の気風も描いて、爽快な時代劇的ファンタジーに転ずる。
ということで、笑いありお色気ありあり爽快さもあるという、けっこう今どきのシニア層にはウケそうな異色時代劇なのだが、かつてあれほど異様な描写の迫力と深甚な主題の問いかけをもって鬼気迫るドラマを送り出し続けていた鶴橋監督が、こうして80代も目前という時にいよいよ軽みと毒気と諧謔を作風に張り出させているさまは大いに歓迎すべしである。しかし、天災で田畑を追われた農民も多かったのに、商人との癒着による拝金主義で政治が腐敗した田沼時代というのは、3・11の復旧も遠いそばからモリカケ問題で大騒ぎの当節にも大いにリンクして、時々チクッとアクチュアルな風刺を感じる作品であった。