【熊本地震から6年】コロナ禍で現地へ行けない……学生ボランティア団体が直面した遠隔支援の難しさ

熊本地震をきっかけに発足した学生ボランティア団体が、3月末をもって活動を終了した。2020〜21年度はコロナ禍で現地に行けず、「思うようにいかない部分もあった」(同団体)というが、手紙やオンラインビデオ会議システムを活用して被災者らとの交流を続けた。遠隔支援の難しさなどについて、元代表らに聞いた。
「被災者の孤立を防がねば」
団体の正式名称は、中央大ボランティアセンター公認学生団体「チームくまもと」。熊本地震の発災後、有志の学生らが被災した西原村でボランティア活動にあたってきた。その後、より主体的に行動できるよう、学生らが中心となって正式に団体を立ち上げた。
当時の中心メンバーの一人が、熊本市出身で16〜17年度に代表を務めた木村亘佑さん(25)だ。現在は、都内の福祉・介護分野のコンサルティング会社に勤務する。木村さんは、東日本大震災の被災地に通い、ボランティア活動にあたっていた。ニュースで熊本地震の発生を知った木村さんは、「これまでの経験が生かせるのではないか」と考え、翌月に西原村を訪問した。そこから月に1回程度のペースで被災地に通い、足湯活動や農業ボランティア、訪問(見守り)活動など様々な形で被災者らと関わってきた。

東北でのボランティア経験から、地震によって地域コミュニティーが崩壊することを理解していた。「被災した方々の孤立を防がねば」との一心で、木村さんと団体メンバーらは西原村での訪問活動などを続けてきた。
木村さんが卒業した後も、団体は年に4回程度のペースで西原村を訪れていた。状況が一変したのは、20年。新型コロナウイルスの感染拡大により、被災地を訪問することが困難となった。実は、コロナ禍に入る前から、団体としての活動収束についての議論が交わされていた。仮設住宅の集約などに伴い、団体として活動できる場面が減少したことなどが背景にある。最終的に、現地を訪問しながら活動を収束させていくという道筋を立て、被災地の関係者らにも説明した。その矢先に起きたパンデミックであった。
遠隔では「被災者の思い」まで分からない
団体は当初の計画を大幅に変更。現地に手紙を送ったりビデオ会議システムを用いたりして、コミュニケーションを続けた。
20〜21年度に代表を務めた中央大経済学部4年の保崎翔太さん(21)は、「手紙では反応が分からないし、ビデオ会議システムでは深い話ができない。被災した方々の本音に触れられず、もどかしさが募った」と振り返る。

仮設住宅の入居者全員と連絡がつくわけではなく、また訪問活動もできない以上、東京からは様子が全く分からないというケースも出てきた。現地の支援者らを通して集まる情報はあるが、「被災者の思い」までは分からない。保崎さんは「現地に行ってこそ感じられる部分は大きい。直接会うことの大切さを痛感した」と胸の内を明かす。木村さんも「学生たちはそれぞれの思いを胸に活動にあたっていた。それだけに、訪問できない状況は残念だったであろう」とメンバーらの思いを汲み取る。
現地に行くことが叶わないまま、今年3月末で団体の活動は終了した。しかしながら、保崎さんは「つながりが途切れたわけではない」と説明する。「何度も通わせてもらううちに、現地のたくさんの人たちと関わりができた。僕個人としてはこのつながりを大切にしていきたい」とし、コロナ禍が収束した後、状況が許せば現地を再訪したいと考えているという。「自分達だけでは何もできなかった」とも語り、活動に関わった全員に対し感謝の思いを口にした。
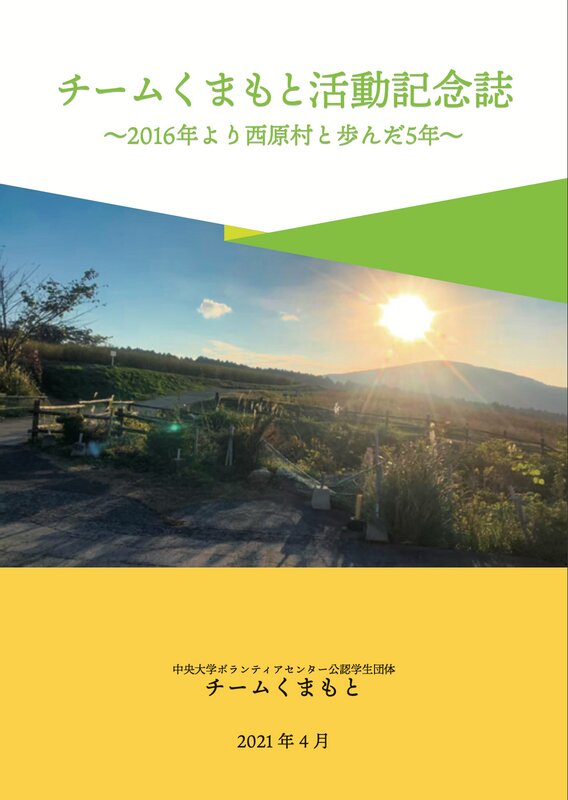
チームくまもとは、活動が終了するのを前に、活動記念誌を制作した。震災発生から現在に至るまでの西原村の記録や、団体の活動記録、学生らによる活動の振り返りなどで構成されており、活動収束の経緯、学生の心の葛藤も綴られている。37ページで、PDFデータはオンラインでダウンロードできる。










