「減産」を主張し始めた産油国、原油高が続いているのになぜ?
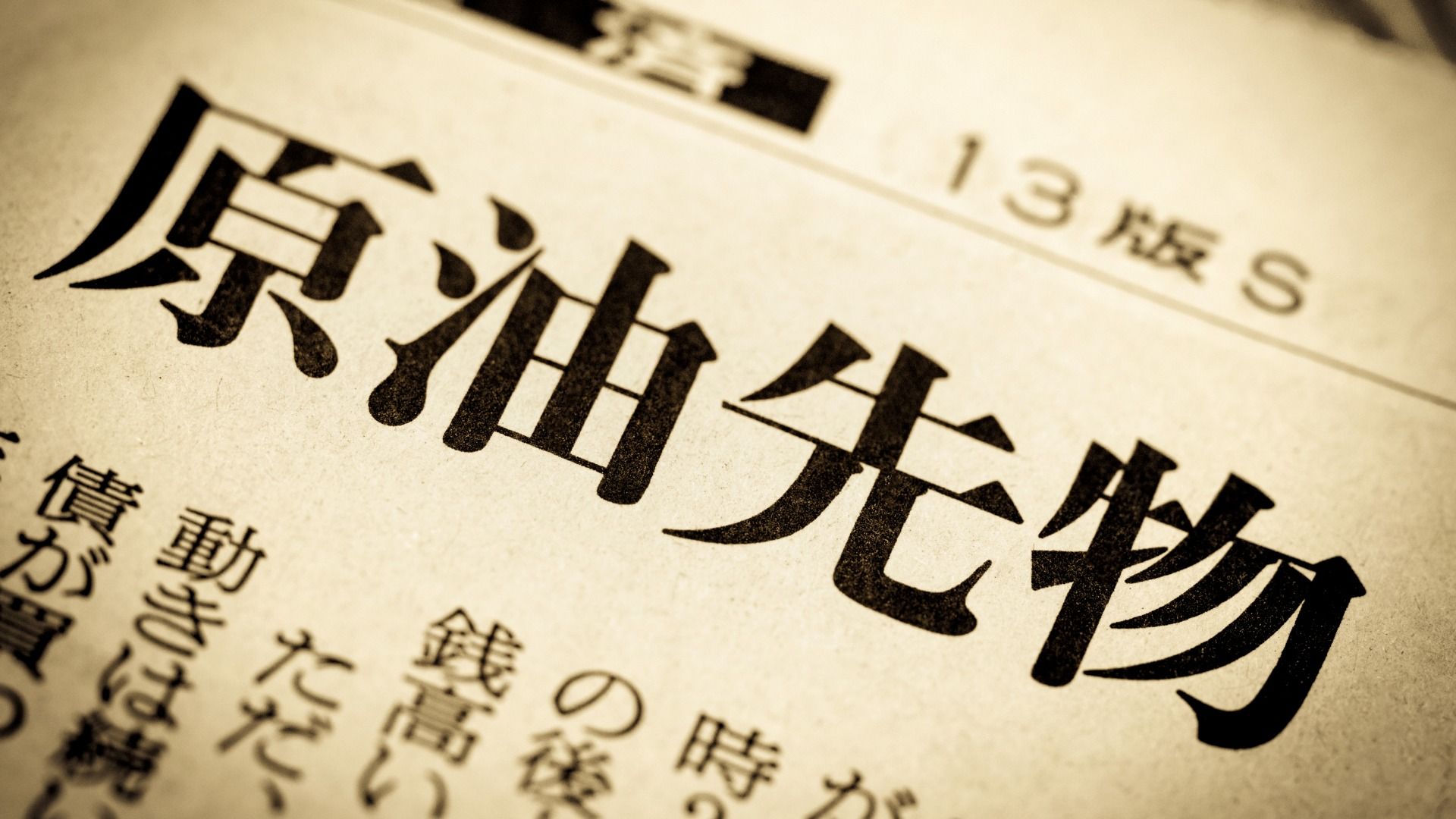
産油国が、原油の「減産」を巡る議論を活発化させている。きっかけになったのはサウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相がBloombergの取材に対して、石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」が生産を引き締めることが必要になるかもしれないと語ったことだ。この発言に対しては、イラク、アルジェリア、UAE、スーダンなどが相次いで支持を表明しており、最短で9月5日に開催されるOPEC+閣僚会合において、この問題が協議される可能性もある。
資源エネルギー庁の「石油製品価格調査」によると、レギュラーガソリンの全国平均価格は3月14日の1リットル=175.2円をピークに直近の8月22日時点では169.0円まで値下がりしている。政府の補助金効果に加えて、原料である国際原油価格が高値から下押しされている影響だ。それでも前年同期の158.2円と比較すると10.8円(6.8%)の値上がりであり、ガソリン負担はもちろん、物流コストの増大を通じて、家計や企業活動に大きな影響を与え続けている。
こうした状態は世界各国に共通しており、特に約40年ぶりの高インフレに苦しむ米国は、7月にバイデン大統領が中東を訪問した際に、サウジアラビアなど産油国に対してトップ外交で「増産」対応を要請していた。それにもかかわらず、OPECプラスが「減産」を検討し始めたのはなぜだろうか。
サウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相は、先物市場で決まる国際原油価格が、需給などのファンダメンタルズ(基礎的条件)を反映していないことを理由にあげている。「先物市場と現物市場のかい離がますます広がっている」としている。
国際原油価格は2020年4月のマイナス価格から今年3月の1バレル=130.50ドルまで急伸していた。一般的には投機マネーの流入がイメージされ易い環境だが、実際には急激な価格変動が嫌われて資金を引き揚げる動きが強くなっている。いわゆる市場の流動性が失われている状態にあり、それが更に価格変動を激しくさせる悪循環に陥っている。特に6月以降は、世界経済の減速懸念を手掛りに現物市場を無視した投機的な安値が形成されているとの不満が、産油国の間に広がっている模様だ。
8月3日のOPECプラス会合後に発表されたプレスリリースでも、慢性的な投資不足で余剰生産能力(=増産余力)が低下しており、深刻な供給障害や今後の需要拡大への対応力が損なわれていることに懸念が表明されていた。また経済協力開発機構(OECD)の商業在庫が、パンデミック前の2015~19年平均を2.36億バレル下回る27.12億バレルに留まっていること、戦略石油備蓄が過去30年で最低レベルに落ち込んでいることにも懸念が表明されていた。
石油産業の慢性的な投資不足を解消するには、原油価格の高騰で投資継続・拡大の魅力を高めていく必要性がある。そして先物市場がこうした現物市場の警告を無視して安値を形成すると、投資不足の問題が更に深刻化することで、将来的に現在よりも一段と深刻な供給不足が発生しかねないとの警戒感がある。現在の原油価格水準で増産ではなく減産を協議することに消費国が反発するのは必至だが、それだけ産油国が石油産業の投資不足に強い懸念を抱いていることを象徴する動きとして、世界が懸念を共有すべき時かもしれない。










