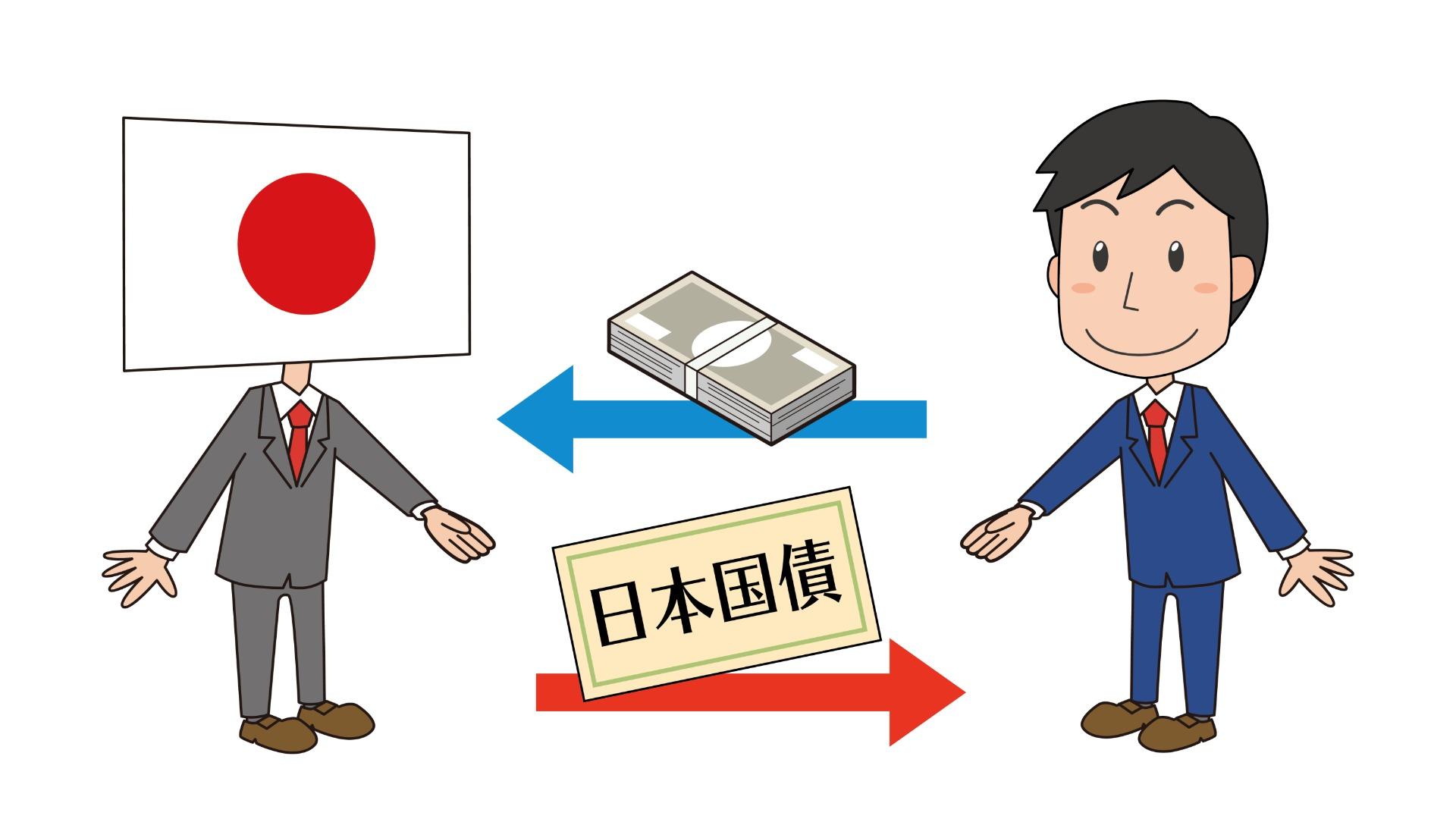WBCで侍ジャパンの前に立ちはだかったメキシコ野球に14年前に挑戦した男、吉岡雄二

吉岡雄二の名は、多くの野球ファンの間でおなじみのものだろう。ただし、今、その名を知っている者の多くは、かつての巨人の「未完の大砲」でも、今はなき大阪近鉄バファローズの「いてまえ打線」の中軸打者でもなく、オフ恒例の人気テレビコンテンツ、「リアル野球BAN」に登場する「元プロ野球選手」として彼を認識している。高校野球部の先輩であるタレントの石橋貴明率いる「石橋ジャパン」に欠かせないメンバーとしておなじみの彼だが、その本業は、独立リーグ球団、富山GRNサンダーバーズの指揮官、つまりプロ野球監督である。東京で生まれ育った吉岡だが、引退後、四国アイランドリーグplusの愛媛マンダリンパイレーツの打撃コーチを皮切りに、サンダーバーズ監督を経て北海道日本ハムファイターズ二軍打撃コーチ、そして2021年シーズンからは再び富山で監督に復帰するという流浪の指導者人生を送っている。東京から離れた地方の球団を渡り歩いているが、そんなことは気にはならないと笑う。なにしろ彼は、現役の最後を「野球の果て」メキシコで終えているのだから。
名門・巨人から近鉄、楽天。流浪の現役時代
吉岡に話を聞いたのは、昨年夏、彼が指揮を執るサンダーバーズの本拠、富山の県営球場でのことだった。建造から70年以上経っているというこの古い球場では、あの王貞治もプレーしている。読売巨人軍の父、正力松太郎の出身地でもある富山では、かつて隔年で公式戦が行われていた。現在でも数年おきに試合が行われるが、この遺跡のような球場ではなく、平成になってから建てられた市営のアルペンスタジアムにその舞台を移している。プロキャリアを巨人で始めた吉岡も当然現役時代、富山でプレーしていたはずだが、その記憶はないと言う。

「試合はあったはずですけど、覚えていないんですよ。昔はジャイアンツの二軍は週末といえば地方遠征だったので、アルペンスタジアムのこけら落としとかで富山に来ててもおかしくはないんですけど」
平成最初の夏の甲子園の優勝投手として入団した巨人では、肩の故障のため早々に打者に転向した。長打力を見込まれ、4年目に一軍デビューを果たしたが、その後4シーズンで残した本塁打は5本のみ。結局巨人では「未完の大砲」に終わった。
その才能が開花したのは、近鉄へ移籍した後のことである。移籍2年目の1998年シーズンの途中からファーストのレギュラーポジションを確保すると、222打席で13本塁打とそのスラッガーとしての才能の片鱗を見せた。以後、6シーズンに渡って「いてまえ打線」の中軸打者として活躍。2001年の近鉄球団最後のリーグ優勝にも貢献した。
しかしその優勝からわずか3年後、「球界再編騒動」が起きる。2004年シーズンを最後に大阪近鉄バファローズはオリックス・ブルーウェーブに吸収され、その歴史に幕を閉じることになった。近鉄の選手は、オリックスに「残留」か、新たに創設された楽天イーグルスに「移籍」することになったが、吉岡は新球団を選んだ。本来ならば、オリックスが戦力になりそうな選手を先にピックアップすることになっていたのだが、前年シーズンをアキレス腱断裂で棒に振っていたこともあってか、吉岡の場合、自身の意思が優先された。
「近鉄最後の年は、オープン戦で怪我して、結局、最後の試合に記念出場しただけだったんです。だからなんというか、一からやり直したいという思いが強かったんですね。新球団の方に行きたいと伝えました」
オリックスが若いプロスペクトを引き抜いていったせいか、新球団は、ベテランの多い所帯となった。要するに、半ばお払い箱になった選手の寄せ集め集団としてスタートを切ったのだ。
「近鉄最後のシーズンは、僕、野手で上から3番目ぐらいだったんです。ところが、楽天に行ったらいきなり上に20人ぐらいいるような感じでしたね。30代が一気に増えた状況でした。だから自分が若手になったような感じがしましたね。でも、首脳陣はチームをまとめるのが大変だったと思いますよ。それに裏方さん。近鉄からの方が多かったんですけど、人数が減って仕事が増えた上、大阪に家族を残しての二重生活でしたから」
「野球の面白さ」を求めて海外へ
球団創設の2005年シーズン、吉岡は主軸バッターとしてケガから復活。レギュラーとして.282という数字を残したが、チームは断トツの最下位に終わり、新生チームをなんとかやりくりした監督の田尾安志は解任に追い込まれた。翌シーズンからは、知将・野村克也がチームの指揮を執ったが、彼は30代後半に差し掛かった吉岡ではなく、若手を起用することを選んだ。2006年以降、出場機会は目に見えて減っていったが、それでも吉岡の脳裏に引退の二文字がちらつくことはなかった。
「もちろん、年齢的には、戦力外もあるなというのは頭にありましたけど、他の球団だったら試合に出ているような年齢じゃないのに、二軍では結構試合に出させてもらっていたので、戦力とは考えてもらっているのかなと。上の人の本音は分かんないですけど、プレーさせてもらえている状況だったので引退とかは考えませんでしたね。それに自分自身、バッティングの感じは良くなってきた部分もすごくあったんで」
しかし、2008年シーズンに12試合の出場に終わると、そのオフに自由契約を言い渡された。それでも吉岡は引退する気にはならなかった。
「一軍でバリバリできるという自信はもうなかったですけど、もう少し続けたい気持ちの方が強かったですね。最後の年はずっとファームでしたけど、若い選手たちとやる中で野球が面白くなってきたんですよ。二軍ですからバッティング練習でも自分の番が終わればボール拾いするんですけど、その時、若手のバッティング見ながら、俺もこうやったらいいのかなって、何かこう、ヒントになるようなことがあって、それまでできなかったことに対してやり方が見えてきたんです。若い子たちの練習を見て、勉強になりましたね。そうしているうちに、もともと自分からアドバイスするようなタイプではないですが、彼らから何か聞かれた時に答えられるようにって考えるようになったんです」
しかし、現役続行と言っても、「再生工場」とも言われる野村から戦力外通告されたベテランを採ろうというチームは日本にはなかった。
吉岡は最後のプレーの地としてアメリカを選んだ。近鉄時代の関係者を通じてアメリカ人エージェントを紹介してもらい、国外での現役続行を模索すべくトレーニングを続けていたが、エージェントは、それでは話も進まない、アメリカでプレーしたいならアメリカに行くべきだ、と指針を示してくれた。経費を自前で賄うなら、アレンジはしてやる、というエージェントの言葉に誘われ、吉岡は、2009年2月下旬、ロサンゼルスへ旅立った。エージェントが用意してくれた施設で体を作りながら、いくつかの球団のトライアウトを受けた。
「向こうではエージェントが何人かの選手を集めて、メジャー球団のスカウトを呼んでトライアウトを開くんです。それで契約できた選手がメジャー契約までこぎつけたら、そこから代理人料が発生するというわけです。まあ、蓄えはあったし、女房も『好きにすれば』って言ってくれていたので、焦りというほどのことはなかったですけど。でも、いつまでもこんな生活を続けるわけにはいきませんよね。メジャーはさすがにきついだろうけど、マイナーだったらなんとか契約を取れるかもと思っていたんですが、現実は厳しかったですね。あとはもう辞めるか辞めないかという判断だけでした」
吉岡と契約を結ぼうという球団は現れなかった。37歳という年齢は、マイナーから鍛え上げるにはとうがたちすぎていた。先が見えないまま、吉岡はロサンゼルスで練習を続けた。
そのうち開幕も過ぎた。渡米後2カ月以上経ち、しびれを切らした吉岡の、どこでもいいからどこか受け入れ先を見つけてくれという言葉にエージェントが応えてくれた。
「メキシコはどうだ?」
メキシコにプロ野球リーグがあることすら知らなかった吉岡だが、1週間後にはもうメキシコに降り立っていた。
メキシコをさまよい3 チーム目でついに契約
吉岡が最初に向かったのは、メキシカンリーグきっての名門チーム、スルタネスの本拠、モンテレイという町だった。すでにシーズンは始まっており、吉岡は4つある外国人枠が空くのを待つという立場だった。
「ソフトバンクにいた山村(路直)というピッチャーと一緒だったんですよ。もう外国人は4人メンバーに入っていて、僕らは練習しながら空きが出るのを待っている状態でした。ところが、試合見ていても、4人ともいいんですよ。そうやって2週間ぐらい過ごしていたんですけど、ここじゃ無理じゃないかってことになったんです。エージェントはなるべくふたり一緒がいいだろうって考えていたみたいですけど、もう僕の方から『別にバラバラでいいよ』って。山村はモンテレイに残って結局、契約できたんですけど、僕は次、カンクンに行ったんですよ」
吉岡は北部の工業都市・モンテレイから南部ユカタン半島のリゾート都市・カンクンへ飛んだ。この町には、かつてメキシコシティに本拠を置いていた名門チーム・ティグレス(タイガース)が本拠を置いていた。ここでも契約に至ることはなかったが、チーム関係者から別のチームのロースターに空きがあることを知らされた。
広いメキシコの南の端から再び北へ飛んだ。今度の行き先は、アメリカとの国境の町、ヌエボラレドという町だった。麻薬を扱うマフィアが跋扈するこの町は、メキシコでも一、二を争うほど治安が悪いとの悪評を轟かせていた。
「まあ、もともとメキシコじたい、治安が悪いって聞いていましたから。メキシコシティだって危ないですよね。空港が、もう、すごく危ないイメージでした。警察もマフィアも一緒だって聞いていたんで、全然信用できないって(笑)。向こうに住んでいる日本人も、拳銃突き出されて、全部出せみたいなのが普通だって言っていました」
ようやく3チーム目で入団が決まった。この町のテコロテスというチームには、すでに外国人選手が3人在籍していたが、その内の2人には、日本でのプレー経験があった。
「オリックスにいたロベルト・ペレス(1999年)と巨人にいたペドロ・カステヤーノ(1997年)。両方ベネズエラ人だったんですけど、カステヤーノは、ベネズエラは危ないからオフも帰らないってカンクンに住んでいるって言っていました。もうひとりのピッチャーもベネズエラ人でみんな同じホテルに住んでいましたね。日本人はひとりだったんですが、日本に行ったことある選手たちが困ったことがあったらなんでも言えよみたいな感じで、よく声かけてもらったんで助かりましたね。年齢も近かったし」

「助っ人」としてのプレー
「4人目の助っ人」としてテコロテスに入団した吉岡。はじめは、「いったん入団できれば、同じ野球、なんとかなる」とある意味高をくくっていた部分があった。なにしろピークを過ぎたとは言え、こっちは世界第2のパワーハウス、日本でレギュラーを張っていた身だ。おまけにこの年のシーズン前に行われたWBCで日本は連覇を果たしている。ある意味、吉岡の立場は、昭和の時代のアメリカ人助っ人のようなものだった。あの頃、メジャーではもう使い物にならなくなった選手でも日本では十分通用したし、またそれゆえ、少なからぬ選手が日本野球を見下していた。吉岡は決してメキシコの野球を見下してはいなかったが、この未知の国でのプレーを楽観視していた。しかし、いざチームに合流すると、かつての昭和の助っ人外国人たちがぶつかったのと同じ壁に当たることになった。
「当然だけど、日本語が通じない。話す機会が少ないことがこれだけストレスになるんだって初めてわかりました。言いたいことをうまく伝えられない、向こうの言うことをしっかり聞けないのが、これだけ野球に影響出るんだってことにも初めて気付かされました。そうなると、なにかこう、声がけ1つにしても、気になることが多くなっちゃうんですよね。そういう部分のしんどさ、日本に来た外国人選手もこういう思いしていたんだろうなってメキシコで分かりました」
吉岡は、その問題を自らメキシコ人たちのもとへ飛び込んでいくことで解決した。フィールドを出た後も極力同僚と行動を共にするように心がけたのだ。
「とにかく、チームメイトからの誘いは一切断らないようにしてました。全部イエス、行くよって。実際行っても、言葉もあんまりわからないから話とかそんなにできないですけど、でも、同じ空間にいるだけでも、なにかこう、チームメイトとの距離感が変わってくるじゃないですか。そうすると、一緒に出かけた選手が、あとで監督とかに僕の話をしてくれたり、助けてくれたりするようになってきました」
言葉の問題は、のちにカンクンで世話を焼いてくれた日本人が売り込みをかけ、通訳としてつくようになったため解決したが、その頃には、吉岡自身もある程度のコミュニケーションを取れるようになっていた。
「向こうも何か優しい感じでしゃべってくるので。だんだんわかるようになってきましたね。テレビとかも、最初めっちゃ早口に感じたんですけど、だんだん単語を拾えるようになってきました。まあもっとも今はもう忘れちゃいましたけどね、スペイン語」
「助っ人」としてやってきた吉岡は、チームの浮沈を左右する存在としてすぐにポジションが与えられた。そのポジションは、慣れ親しんだファーストではなく、若手時代に守っていたサードだった。
「カステヤーノがファーストだったんで、メキシコではほとんどサードでしたね(サード72試合、ファースト14試合)。日本ではもっぱらファーストだったんですけど。最初どうなるのかなと思いましたが、やってみると、きつくはなかったですね。何かまた、久しぶりのいい緊張感みたいなのはありましたね」
チームのホーム球場は、メキシカンリーグでも最古参の部類に入る1940年代建造の古い球場だった。最初に見たモンテレイの球場とは雲泥の差があったが、野球をやるのは一緒と吉岡は割り切った。
(続く)