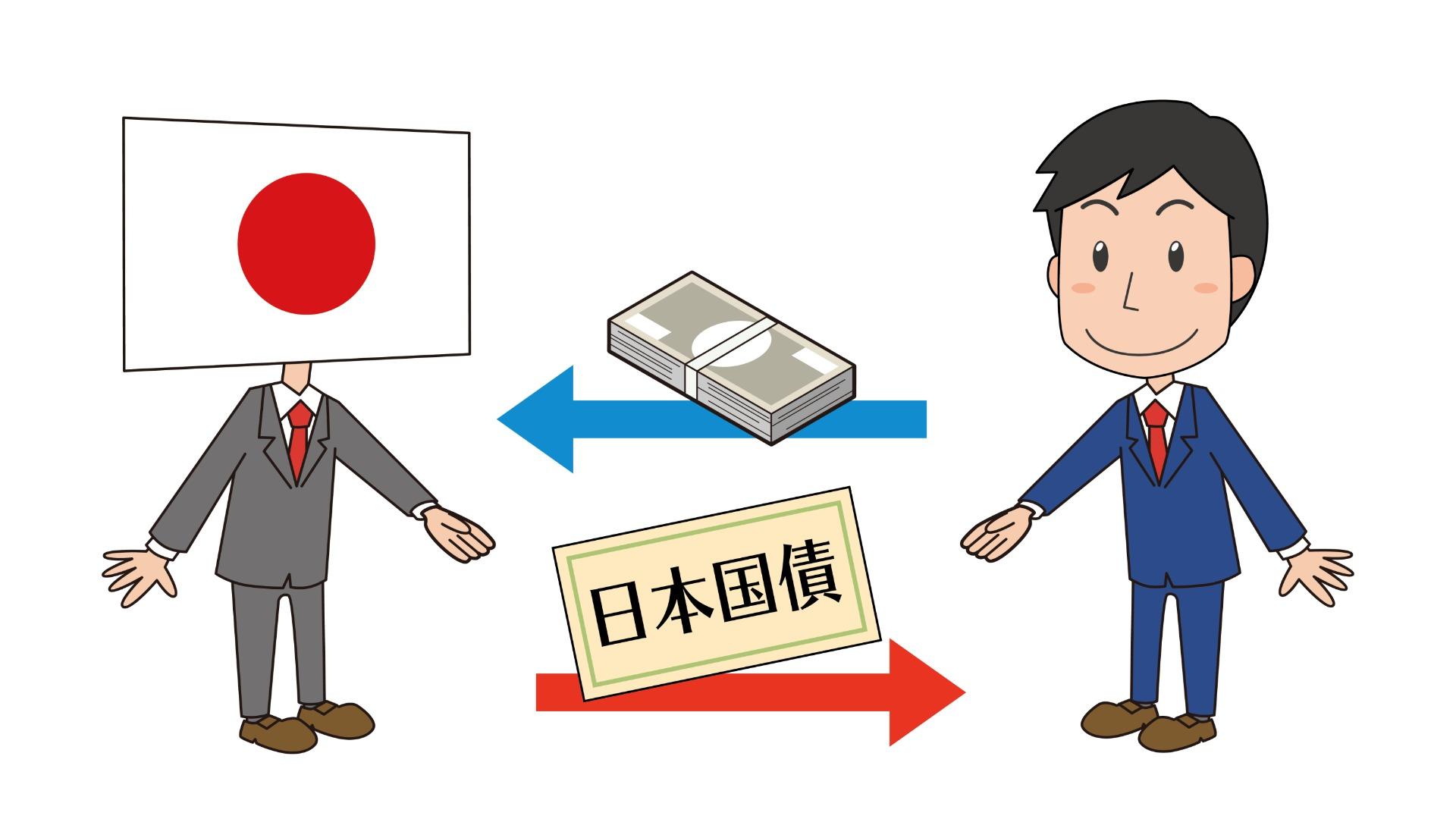アラフィフで「現役復帰」した元甲子園球児がメジャーに挑戦した日を振り返る

野球というのは、比較的「引退」の線引きがはっきりしている競技だ。とくにプロともなると球団との契約が切れ、次の契約先が見つからないと、そこで引退となる。まあ、その後、草野球を続ける者もいるにはいるが、そこで「まだまだ現役」と言い張る者はほとんどいないだろう。
しかし、トップレベルにプロのないスポーツの場合、この線引きは非常にあいまいになる。武道の世界などはその典型で、指導者になった後も当たり前のように選手として大会に出るし、「生涯現役」とご高齢になっても「現役」の看板を下ろさない「師匠」の存在は珍しいことではない。
昨年49歳になった島内博史さんは、「現役復帰」のシーズンを関西独立リーグ・淡路島ウォリアーズで過ごした。
「まあ、地元にできた球団ってことでお世話になることにしたんですけど」
とはいえ、このリーグは、基本選手報酬はなし。それぞれの夢に向かう場所だけを提供するというスタンスだ。だから島内さんも某スポーツメーカーの社員として勤務しながら主に週末だけ独立リーガーとして活動した。そんな条件ながら球団が入団を認めたのは、彼の「プロ経験」を買ってのことだろう。島内さんは、20年ほど前、たった1シーズンだけ存在したカナダのプロ野球リーグでプレーした選手のひとりなのだ。
大阪市内の喫茶店。その姿はどこにでもいそうな優しいお父さんといったものだった。島内さんは現在淡路島から毎日大阪まで通勤している。
「皆さん驚かれますけど、そんなに遠くないですよ。乗り換えも1度だけですし。子供を育てることを考えるとやっぱり大都会よりあっちのほうがいいですから」
彫りの深い顔立ちは九州生まれと聞いて納得した。1歳のときに父親の仕事の都合で大阪に引っ越してきたという。
野球に出会ったのは小学4年生の時、本格的に取り組んだというより、地元の軟式チームにちょっとした遊び感覚で入ったのがきっかけだった。それでも素質があったのか、すぐにキャッチャーのポジションが与えられた。
「ほんとはキャッチャーなんて嫌でね。だって球拾いばかりじゃないですか。中学でも野球は続けたんですけど、うちの中学は準硬式でね。もうなくなってしまいましたけど、僕の住んでいた町ではトップボールっていう硬い軟球を使う準硬式野球が盛んだったんですよ」
それまであまり欲のなかった島内少年が「より上」のレベルでプレーしたいと思うようになったのは、この頃からだった。
「1つ上に中日から阪神に行った筒井(壮,現阪神コーチ)さんがいて、そういう方のプレーを見てからですね。あと、準硬式だと大阪までしか大会がないんですよ。それもありました」
その先輩の背中を追いかけて島内少年は高校野球の名門、上宮高校に進学した。
島内さんが最上級生となった1993年、上宮は春のセンバツで岡島秀樹(元レッドソックスなど)の東山(京都)、赤星憲広(元阪神)の大府(愛知)、平井正史(元オリックス)の宇和島東(愛媛)など、のちにプロの第一線で活躍する選手を擁した強豪を抑え悲願の初優勝を果たした。登板機会こそなかったが、島内さんは3番手投手として背番号11をつけてベンチ入りを果たしている。
「でも、この時はもうギリギリ(ベンチに)入れただけで、実際、大会が始まったらもうマウンドには上がりたくなかったですね。ホント、ビビりでしたから(笑)」
それでも、この頃から自分の中で「プロ」という目標がぼんやりと浮かんできたと島内さんは言う。
「ひとつ上に、さっき言った筒井さんのほか、黒田(博樹,元ヤンキース、広島)さんや西浦(克拓,元日本ハム)さんがいたんです。西浦さんはエースで高校からドラフトされたんですが、黒田さんは控えでしたし、自分でもなんとかなるのかなって、漠然とですが思うようになりました。僕も黒田さんと同じように大学に進んだんですが、高校時代控えだった先輩がプロに進んで活躍されるようになっていくのを見て、(背番号)11番でもなんとかなるんだってだんだん思うようになりましたね」
最後の夏が終わり、島内さんが進学先として選んだのは、天理大学だった。しかし、プロ野球にも何人か輩出している名門野球部に進んだものの、プロになる夢と現実との狭間で心は揺れ動いた。プロ入りしていく高校の先輩たちの姿に「よし、俺も」と思う一方で、島内さんは次第にボールを投げれなくなっていった。高校時代から感じていた違和感が大学に進んでからも取れることはなかった。いわゆるイップスという奴である。
「大学の時もベンチ入りはしましたが、まあ敗戦処理ですね。全国大会にも出たんですけどね。4年のとき。高橋由伸(元巨人)の慶応に完封負けしました」
島内さんは人生の目標を教職へとチェンジした。天理大学はプロ野球選手以上に多くの人材を教育界に輩出している。しかし、これも実際に教育現場を見て挫折することになる。
「僕には無理でした。派遣された実習先がけっこう荒れていた中学で、実習生にも容赦なかったんです(笑)。校舎から夜中に飛び降り自殺する生徒の話なんか聞かされると、僕には無理かなって」
結局、島内さんは野球を続けることにした。社会人実業団のミキハウスから声がかかったのだ。
「ミキハウスが創部3年目くらいで、本格的に強化していこうってなったんです。まあ、イップスって言っても、マウンドから全力投球っていうのはあんまり問題なかったんで、なんとかなるんじゃないかと。フィールディングの時の送球がアレだっただけで。だから投内連携の練習なんかは嫌でしたね」
社会人野球への就職の一方、「ほんとはアメリカでやりたかった」と島内さんは振り返る。島内さんが大学に進学したのは1994年のこと。その5年前に空前のヒットを記録した野球映画「メジャーリーグ」の続編がこの年に公開されている。
「高校の時に先輩にメジャーリーグ大好きな人がいて、そのころから、結構影響を受けていたんですよ。それで、大学2年のときに2週間短期留学したんです。まあ、留学っていうほどのことでもなく、アメリカの大学にいた友達に誘われてちょっと遊びに行ったくらいの感じなんですけど。向こうの野球は実際どうなんだろって行ってみたんですが、ちょうどオフ期間で(笑)。なんだ野球できねえじゃないかと思ってたら、大学の関係者が『ちょっと投げてみろ』って。それで投げてみたら、85マイル(136キロ)ぐらいだったんですけど、うちで来るならプレーさせてやるよって。ちょうどその年は野茂(英雄,当時ドジャース)さんがアメリカに行った年で、『俺も』と思ったんですけど、英語のテストはあるんだよねって言われて断念しました(笑)」
この時は実現しなかった「本場」でのプレーだが、この時の体験が島内青年のその後の人生に大きく影響を及ぼすことになる。この体験もあって、社会人で活躍してからでも海外に行けるんじゃないかという思いを抱きながら、島内さんは実業団の世界に飛び込んだ。
しかし、現実は甘くなかった。チーム強化に邁進する会社はイップス持ちのピッチャーを長い目で見守ることはなかった。わずか2年で島内さんはクビを言い渡された。
「まあ、会社の言うことは理解できました。自分でもわかっていましたから。最初からもう肩が痛くて言うこときかなかったし、イップスも抱えながらで、試合でも出ては打たれるの繰り返しでしたから。『社会人の壁』を痛感しました。当時、金属バットから木製へ変わりかけたぐらいの時期だったんですけど、それでももう全然通用しなくて」
ただし、会社は前途ある若者の将来を考えて、会社には残る選択肢を用意してくれた。日本経済が「失われた30年」に突入していた当時にあって、温情ある提示ではあったが、やりがいを奪われた若者はそれを受け付けることはなかった。
「僕は契約社員だったんで、辞めるにもそんなにためらいはなかったですね。最初からずっと会社にいるつもりもなかったですし」
その後の数年間を「空白の時間」と島内さんは表現する。
「長野へ行ってスキー場で働いたり、北海道のリゾートに行って住み込みで働いたり。現実逃避ですね。大阪に戻ってインストラクターしていた時期もありました。体を動かすのは今でも好きですからマラソンに挑戦したり、ずっと運動はしてたんですが。アメリカにも行きましたよ。ヤンキースタジアムで伊良部(秀輝)さんが投げてました」
そんな島内さんに大きな転機が訪れたのは2003年のことだった。
「大学の先輩に脇田善旨さんって方がいるんです。3つ上だったんですけど、結構ウマが合うっていうか、卒業後もちょくちょく連絡を取り合ってたんです。脇田さん、大学では1勝もしていないんだけど、卒業後社会人野球で大活躍されたんです。その後チームが廃部になって、アメリカに行ったんですけど、独立リーグでローテーションに入って6勝もして、その後マリナーズの招待選手にもなったんです」
その先輩に飯でも食おうと呼び出されたのは、2002年のシーズン後のことだった。このシーズン独立リーグのひとつであるザイオン・パイオニアーズで24試合に登板した脇田投手は、翌年のシアトル・マリナーズのスプリングトレーニング参加の切符を手にしていた。その先輩は、久しぶりにあった後輩が人生に煩悶する様子を見て一喝した。
「お前、以前はアメリカでやりたいなんて言ってがんばってたよな。でも、今のざまはなんなんだ!」
年が明けると、島内さんはその先輩とアメリカ行きの飛行機に乗っていた。
スプリングトレーニングには脇田先輩のほか、数人の日本人が参加していた。この頃、メジャー球団のいくつかが、日本で埋もれている才能を発掘しようと様々なルートから無名の選手をアリゾナにかき集めていたのだ。
ここで島内さんに大きなチャンスが訪れる。招待選手だった先輩が、肘の故障を起こしたのだ。
「おい島内、お前代わりに投げろ」
余っていたユニフォームを着て、島内さんはブルペンのマウンドに立った。
しかし、2年もブランクがあった上、ろくに準備もしていない中、マイナー契約とはいえプロ球団の入団テストに合格するはずもない。結果は言うまでもなかったが、ここでテストを一緒に受けていたひとりの日本人選手から声をかけられた。
「カナダにプロリーグができるんです。一緒に行きませんか?」
(つづく)