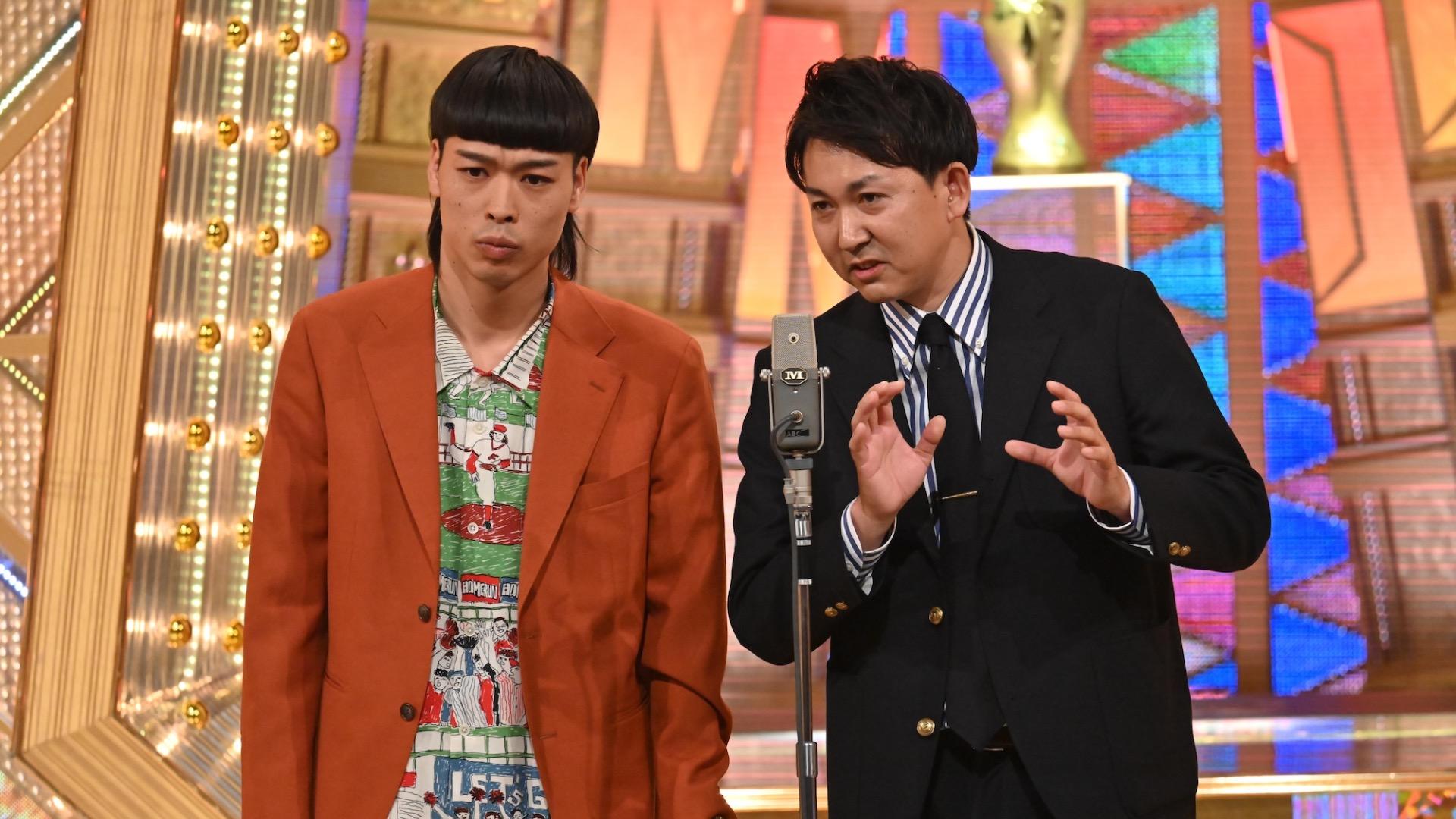民主派勢力が軍事政府に大規模反撃を開始。国民統一政府(NUG)と少数民族との連携は? ビデオリポート

軍事クーデターから3年、2024年2月1日。在日ミャンマー人たちは「ミャンマーを忘れないで」というプラカードを手に道往く人にアピールし、「軍政に圧力を、避難してくるミャンマー人に在留許可を」といった嘆願書を外務省職員に手渡した。
彼らの祖国では、自国民を虐殺する軍事政府に対して、民主派勢力が昨年10月末から大規模な反撃に出ている。その結果、民主派が治める地域が国土の大半となっているようだが、国軍側は死傷したり、投降したりする兵士が増え、劣勢を挽回しようと今年2月、国民皆兵と徴兵を始めた。自国民同士の殺し合いを強いる軍政から日本を含む外国へ逃れる若者も急増し、在日ミャンマー人は9万人に届こうとしている。
ここまでは日本に居てもインターネット等を通じて知ることができる状況だ。しかし、これだけでは内戦の行方も、必要な支援も見えない。武力によって政権を奪われた国会議員らが中心になっている国民統一政府(NUG)と防衛を含む行政を担っている少数民族勢力の連帯は?戦況は?避難民や国軍から奪還した地域の状況は?国軍を文民統制できたあかつきの体制は?様々な疑問を携えて、今年4月タイ北部からミャンマー状勢を探った。

かつてビルマと呼ばれたミャンマーには135の少数民族がいると言われている。ビルマ族と少数民族の比は7:3で、少数民族のなかにはビルマ語を話し都市部に住んでいる人も多い。しかし、武力を使って国を治めようとする軍事政府は、国土の東西と北でそれぞれ国境に接する山岳部に住み、独自の言語を使う少数民族を差別し、天然資源や貿易の利権を持っている彼らを搾取してきた。
1948年の独立以来、少数民族は時代の波と部族ごとの差はあれど、自治を求めて中央政府の軍=国軍と戦ってきた。1988年の民主化運動の際も、民主派のビルマ族は武装組織を持つ少数民族と合流し、一度は民主連盟ビルマ(DAB)という反軍政の連帯が全国規模で形成された。だが、その中心的存在だったカレン民族同盟(KNU)に対して、軍事政府はカレン族の仏教徒とキリスト教徒の軋轢を煽ることで分裂させ、仏教系の武装勢力を国軍に編入させた。今日ではイスラム教を信仰するロヒンギャ族が弾圧され、数十万人が難民となっているように、要は軍事独裁政権への対抗勢力が団結しないよう、民族間の差別を煽り続けてきたと言える。

だが、今回の国軍に対する反撃には、ミャンマー東部を本拠地とし、ロヒンギャ族との関係が深いアラカン軍(AA)も連帯している。3年前のクーデター以降、国軍を批判する者は少数民族に限らず、ビルマ族であっても殺されることが明らかになったことで、対抗勢力の間での差別を煽って団結を阻むという軍事独裁者の策略は、もはや見透かされたようだ。
今回の現地取材では、閣僚経験がある元国会議員からNUGの内情を含めた全体像を聞け、NUGを支持して連携する少数民族の防衛軍幹部からは「国土の9割を押さえた」との発言があった。しかし一方で、国軍の徴兵については、タイ国境へ逃れてきた農民たちが「女だけでなく、8歳の子どもも連れて行かれるから」と避難の理由を訴えた。

内外には様々な社会経済問題が山積しているが、人にとって最も大切な命や人権が奪われ続けているミャンマーという国が、未だこのアジアにある。在日ミャンマー人たちが掲げたプラカードの「忘れないで」は、このことである。