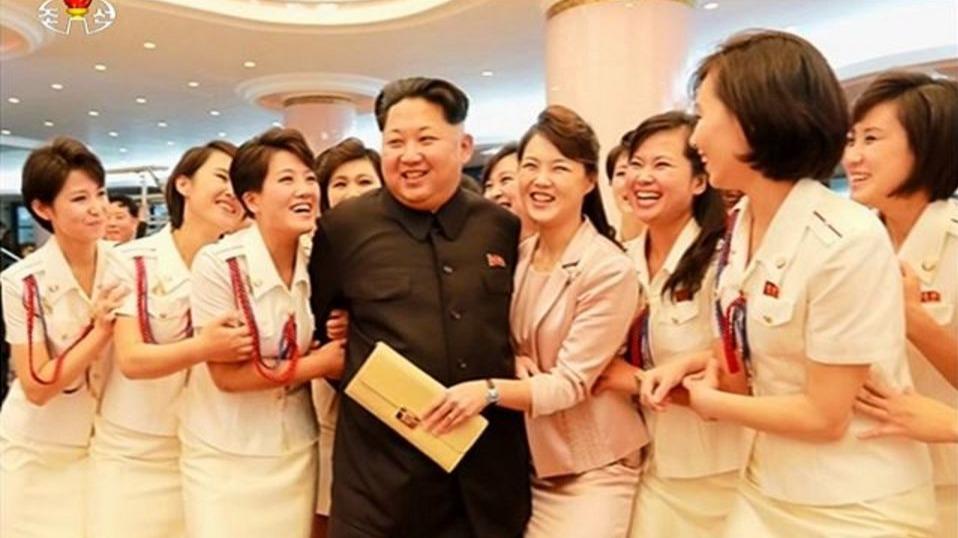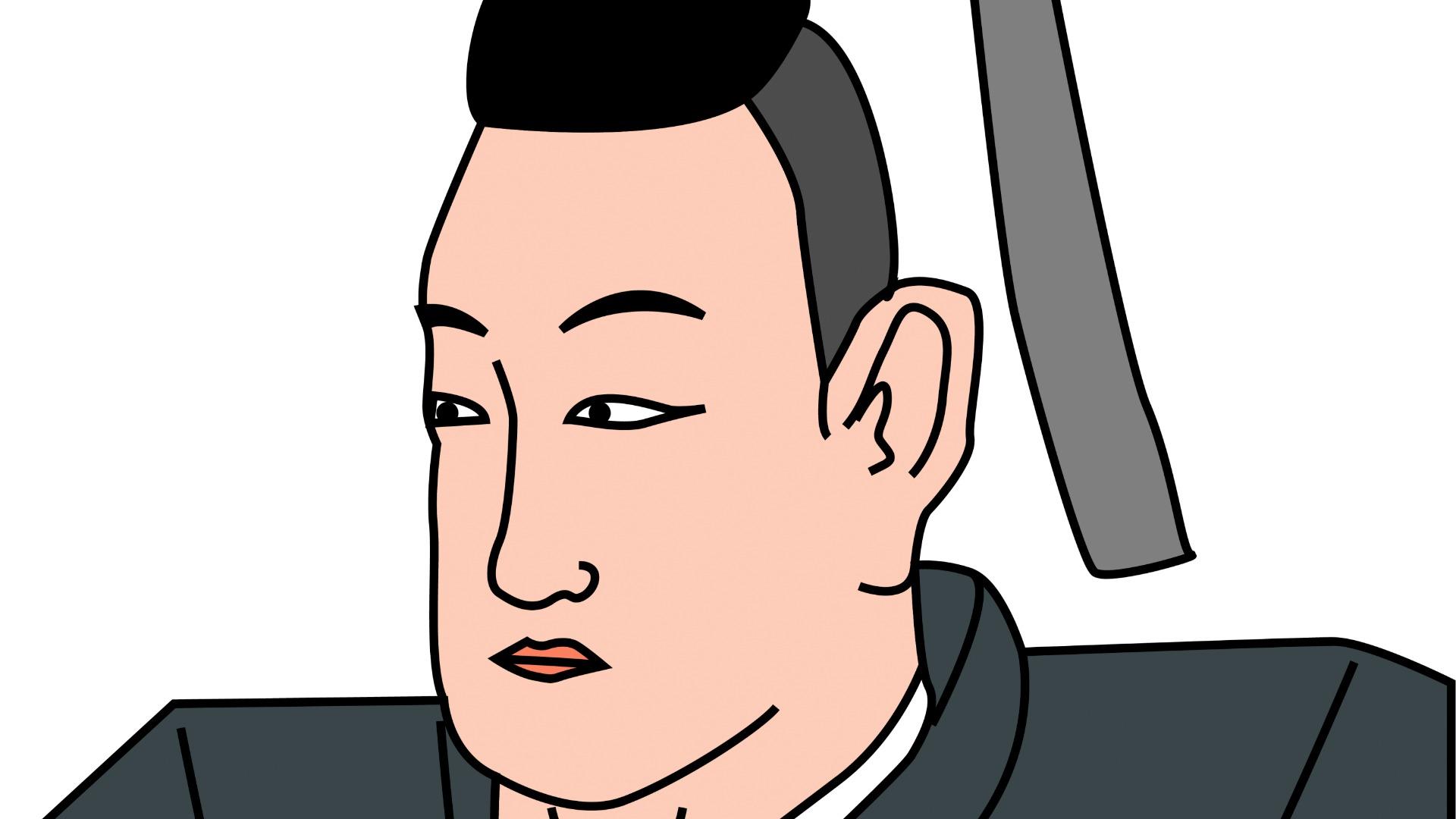広がりを見せる"本質の認知"。スケートボードと都市の共存への糸口「プラザ」とは!?

「カルチャー」を応援するイベント

「やっぱりこうなっていくよね」
先日開催された「Tokyo Skate Plaza by Jameson & Dickies」のイベントを撮影してみて、そんなことが真っ先に頭に浮かんだ。
これはアイリッシュウイスキーの「JAMESON(ジェムソン)」と、アメリカ発のワークウェアブランド、「Dickies (ディッキーズ)」とのグローバルコラボレーションによる限定デザインボトル『ジェムソン Dickies リミテッド』の発売を記念して行われたスケートボードイベントになるのだが、最近のスケートボードを取り巻く社会事情を考えると、自分には行われるべくして行われたようなイベントである気がしてならないのだ。
陽の当たるようになったコンテストと、影になったストリート

陽の当たる場所には必ず影がある。
強い陽が当たれば影は濃くなるが、太陽が真上にある時は短いので目立ちにくい。
でも時間が過ぎれば、影は大きくなり、否が応でも目につく。
これが最近のスケートボードを取り巻く社会事情であり、社会から見た今のスケートボードを端的に表現した言葉だと思っている。
スケートボードは東京オリンピックで眩いばかりの光が当たった。社会は初めて見る陽の当たった場所に色めき立ったが、最も高い位置、真上にある太陽に照らされたわずかな影に、当時は気づいていなかった。
だがそこから2年以上経った今は、社会的な話題の移り変わりと共に太陽も傾き、影がどんどん伸びている状態ではないかと思う。

ここでいう影とは、もちろんストリートスケートのことだ。
現在の日本社会において、基本的にストリートスケートは悪とされる傾向にあると思う。
スケボー、暴行、街中、事件……、これらのワードが入った記事は炎上しやすい傾向にあるし、世間の話題にもあがりやすい。マスメディアからすればニュースとして取り上げる格好の素材になるし、その部分を強調するタイトルや見出しをつければ、PVが稼げると考えているところも多いだろう。
さらに最近では度が過ぎた報道も増えているように感じる。
8月末には札幌で「大通公園でスケボーをしていた女(40)が、観光客に暴行」というニュースがあったのだが、実は誤報で、「女はスケートボードをしておらず、酔っ払ってスケートボーダーに絡んできた」というのが事実。しかも当事者の方は、ニュースを発見した際マスコミに事実誤認の話をしたにもかかわらず、当初は取り合ってくれなかったそう。
それでも数日後に記事は削除、変更されたので結果的には良かったものの、現在のスケートボードはそれほどまでマイナスイメージが先行してしまっているのかと思わざるを得ない。
そしてそういった傾向が強まれば強まるほど、どの世界でも出てくるのが、世の中の不条理に対するアンチテーゼではないだろうか。
スケートボードでは、それが俗にいう「カルチャー」の部分になる。
「Tokyo Skate Plaza by Jameson & Dickies」は、そういったシーンの「本質」や「核」となるところを適切に捉え、より良い社会を築くきっかけを与えてくれるようなイベントになったのではないかと思う。

なぜなら、当日はプロスケーター達によるセッションのみならず、「街とスケートボードは共存できるのか!?」をテーマにした熱いトークセッションが繰り広げられ、そこには今後の日本のスケートボードの在り方に対するヒントが多く詰まっていたからだ。

「スケートプラザ」とは!?

そのヒントこそが、イベント名にも流用されている「スケートプラザ」だ。海外ではよく街の広場のようなところでスケートボードをしている光景を見かけるのだが、そういった場所を総称してスケートプラザと呼ぶ。
そもそも「プラザ」とは、スペイン語を語源に持つ、人の手によって作られた、都市にある公共の広場や市場のことをいい、広い意味を持つ。しかしそれが「スケートパーク」となると、スケートボーダーのために造られた、柵や建物で囲った場所になってしまうので、見方を変えれば狭い空間ともいえる。
というのも、スケートボードはもともとストリート(道路)で生まれた、自由で振り幅の広いアクティビティなので、時代の流れで後から生まれてきたスケートパークに収まりきるものではないという人も多いのだ。
そこで生まれたのが「スケートプラザ」という考え方で、街の景観と同化したスケートボードができる公共の空間を指すのだが、そこには他にダンサーもいれば、音楽をやっている人もいるし、もちろん散歩をしている人もいる、多種多様なコミュニティの人たちが同じ場を共有することでいろんなコミュニティが繋がり、地域が活性化していくというシステムだ。
自分も、「スケートプラザ」という言葉を20年近く前に初めて耳にした時は思わず興奮した。2005年にオープンした「The Rob Dyrdek/DC Shoes Foundation Skate Plaza」が最初だったと思うが、今までにないデザインがものすごく斬新に映ったのだ。
この空間はスケートボードをすることを前提にしたスケートパークの要素も持ちながらも、ベンチや手すりといった公共広場のエッセンスを再現し、市街地の雰囲気を提供した初めての場所だった。
アートや造園もデザインに取り入れているので、プラザという言葉は文化的な雰囲気を与える多目的な場所という認知が広まっていったのだろう。

日本にプラザはある!?

では今の日本で「スケートプラザ」があるのかというと、トークショウで挙がったのが大阪の三角公園(御津公園)だった。
アメリカ村のランドマークでもあるこの場所は、いろんなジャンルの人が集まる大阪ストリートカルチャーの中心的存在で、スケートボードも比較的許容されている空気感がある。さらにヒップホップやパンクの人もいるので、関西の若者文化を育てたエリアともいえるだろう。
中には変な人もいるといってはいたのだが、それも裏を返せばあらゆるものを受け入れてくれる懐の広さがある空間だからこそ。世界を見てもあれだけコンパクトな場所に、いろんなジャンルの人が集中しているところはないとのことなので、稀有な場所といえるだろう。

他にも2001年に地域の再開発により閉鎖されてしまったが、秋葉原にあった駅前広場もトークショウで名前が挙がった場所だ。
ここは普段はスケートボードはもちろんのこと、バスケを楽しむ人などで賑わいをもたらしていたところで、週末ともなると貴重な屋外イベント会場として使われる多目的なスペースでもあり、人が集まるアキバを象徴するシンボルのひとつだった。
当時ここで滑っていた江川“YOPPI”芳文氏も、「秋葉原だから電車の騒音もあるし、スケートボードで音が響いても、怒られることもなく自由にできたのが皆にとって良かった」と話している。
東京にも、以前は多様性を受け入れる文化を持った場所があったのだ。
世界一有名なスケートプラザ

日本のプラザの話をしたら、海外の事例にも触れた方が対比ができてわかりやすい。トークショウで挙がったのは「マクバ」と呼ばれるスペイン・バルセロナにある現代美術館だ。
ここは端的にいうと美術館の前にある広場に過ぎないのだが、すぐ隣にはカフェやレストランが立ち並び、外にある縁石でご飯を食べている人もいれば、散歩してる人もいっぱいいる。そんな風景にスケートボードが何の違和感もなく調和している場所なのだ。そして20年以上に渡り、世界中からスケーターが訪れるという流れも続いている超がつくほどの有名スポットでもある。
だが以前のこのエリアは、バルセロナのダウンタウンの一角に追いやられていたそう。でもそこから見事に文化復興を遂げ、今やナイトライフと国際色あふれるバルセロナ随一のスポットへ変化。自由奔放な若者たちが集うエネルギーに満ちた場所として認知されるようになっている。
海外ではスケートプラザがあると街が盛り上がる、街おこしに繋がるという説があり、実際に都市計画に盛り込まれているところもあるのだが、それを立証している場所がマクバといえるのかもしれない。
街とスケートボードが共存するために

ただ日本で「スケートプラザ」を作るのは容易ではないだろう。街中でスケートボードをする人は、異端児として見なされてしまうのが今の日本社会の見解だからだ。
だからこそ必要なのが「土台作り」ではないかと思う。
というのも、海外では「アメリカって皆がスケーターなんですよ」とか、「自転車に乗ってたというのと同じような感覚で、スケボーやってたんだよっていう人が多いんです」とか、「スケボーに乗っちゃう警察官や警備員もいました」なんて言葉が出るほど生活に馴染んでおり、多くの日本人が捉えているオリンピック後のスケートボードとは、根本的なところから全く違う認識になっているからだ。
だからこそ、今後の日本はそういった形で”認められる”ことが重要であり、それが街との共存の第一歩になるのではないか、だから皆で頑張ってこれからも広めていきましょう。というところがこのトークショウの結びとなった。
もちろん自分もそこは至極納得しているし、だからこそ今回のようなイベントが開催されたのだと思う。

それに今の日本には堀米雄斗という一般国民に広く知られるスターも存在する。彼のような存在がいれば変わってくるだろうと言う話はイベントでもされていたが、アメリカではトニー・ホークがその役目を担ったように、彼も東京のストリートで撮影した映像作品『Nike SB | Yuto Horigome in Tokyo』をリリースしたり、アンバサダーを務める講談社と共にInspire Impossible Storiesというメディアを立ち上げたりと、「カルチャー」を広げる活動も精力的に行なっている。
まだまだ時間はかかるだろうが、今後そういった動きがさらに活発になっていくことで徐々に認められるようになり、現在の「禁止」や「排除」ではなく、「共存」の道に進んでくれたら、日本はもっと心の豊かな国になるのではないか!? と思うのだが、どうだろうか。
撮影:吉田佳央(@yoshio_y_)