徳川家康はあんなに織田信長にペコペコする必要があったのか。そのターニングポイントとは
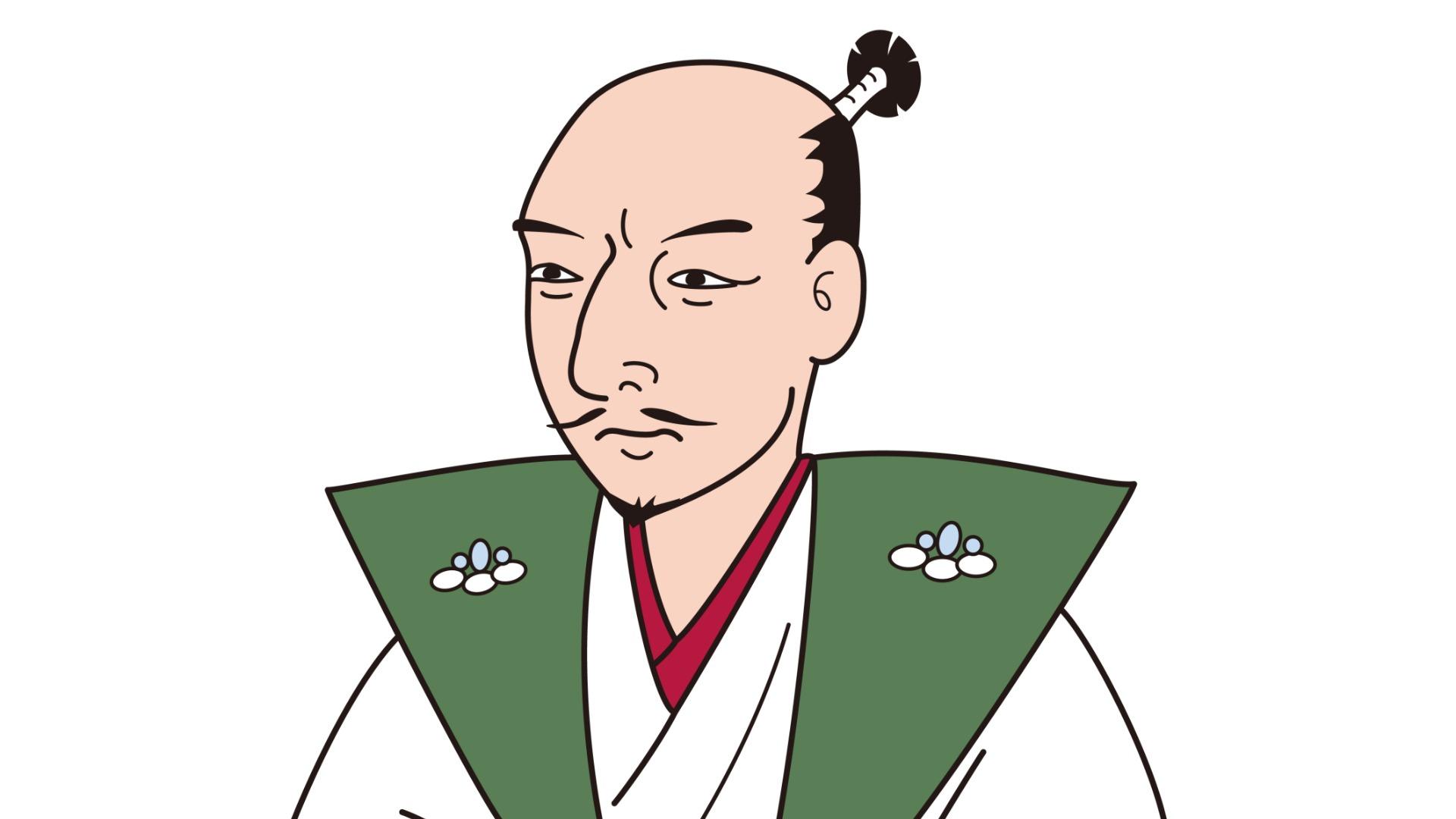
今回の大河ドラマ「どうする家康」では、ずっと織田信長が上で、徳川家康が下という関係になっている。今回は、両者の関係が上下だったのか、対等だったのかについて考えることにしよう。
永禄3年(1560)の桶狭間合戦後、元康は自立化を目論んで今川方から離反し、西三河の平定に着手した。同時に信長とも抗争を繰り広げ、刈谷(愛知県刈谷市)など、三河と尾張の国境付近に軍を進めていた。
しかし、家康と信長は、永禄4年(1561)頃に和睦を結んだ。同じ頃、信長は美濃の斎藤氏と戦争をしていたので、同時に家康と戦うことは得策でなかった。家康も戦争を避けて、信長と同盟を結んだほうが良かったのは同じである。
こうして家康と信長は同盟を締結したが、あくまで対等な関係だったことに注意をしておきたい。つまり、大河ドラマのように、家康が信長から恫喝され、ペコペコする必要はなかったのである。なお、信長と家康の同盟は、領土協定に限定されていた。
平野明夫氏によると、両者の関係は、元亀元年(1570)以前と天正3年(1575)以降とで質的な変化が生じたという。元亀元年以前、家康は信長への軍事的支援を行ったとき、将軍足利義昭の要請に基づいていたという。
つまり、信長は将軍足利義昭の仲介がなければ、家康に軍事的支援を要請できなかったのだ。将軍足利義昭のもとにおいて、信長と家康は対等な立場にあったのである。しかし、天正元年(1573)に足利義昭が京都から追放され、2人の関係は変化した。
天正3年(1575)5月に長篠の戦いが勃発すると、家康は信長の「国衆」と位置付けられ、軍事動員される存在となった。この段階において、家康は信長に臣従したといえよう。もはや、信長は足利義昭を介する必要がなくなったのだ。
天正10年(1582)3月の武田氏滅亡後、家康は信長から駿河国を与えられた。家康は信長から知行宛行を受けているので、2人が主従関係にあったことが明らかである。家康にとって信長は、「上様」つまり主人だったのである。
主要参考文献
平野明夫「織田・徳川同盟は強固だったのか」(『信長研究の最前線』洋泉社歴史新書y、2014年)










