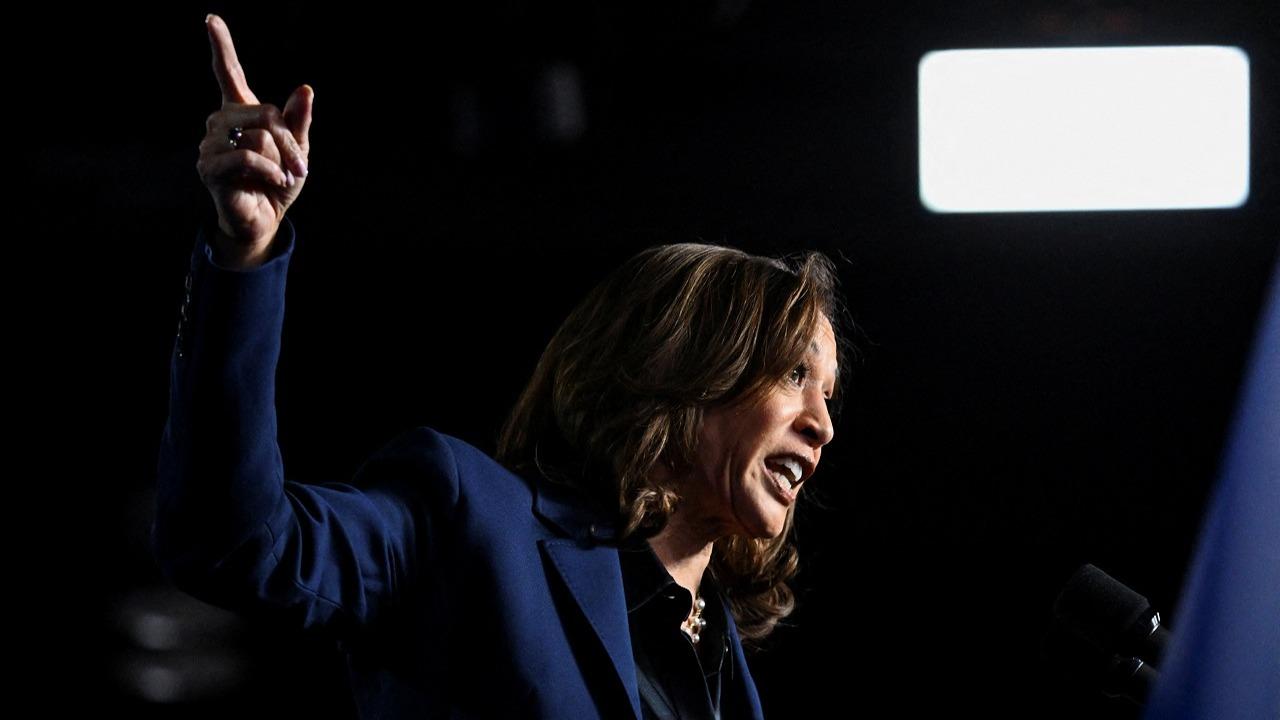【宮城県 松島町】深すぎる沈黙の土木遺産!芸術から歴史まで様々な物語がここに有り [幡谷地区]


今回は、皆さんに「明治潜穴公園(めいじ せんけつ こうえん)」という、2007年から土木遺産として登録されている場所をご紹介していこう。

この公園は松島町の幡谷地区にあり、一見すると遊具などの遊べる場所も特になく『一体何があるのだろうか?』と、やや不思議な印象と雰囲気が漂う場所。しかし、筆者はこれまで様々な「公園」を巡ってきたが、こんなにも奥深く様々な要素が散りばめられている場所は初めてであった。それもあり、ぜひ皆さんにご紹介をしていこうと腕まくりをしている訳だ。
この場所には、とてもこの記事内ではご紹介しきれないほどの「壮大なストーリー」が含まれているため、できるだけ簡潔に「魅力ポイント」を項目別にして書き綴っていくことにする。読み進めていく内に、少しでも皆さんの興味に『ピンッ!』とくるものが提供できたら幸いだ。
魅力ポイント その1:明治時代の建築物が存在する

「明治潜穴公園」という名前から、なんとなく『穴(トンネル)がある場所なのか?』と想像した方は大正解。そして公園名の「明治」とは明治時代の意味が含まれる。
江戸から明治時代にかけて、当時存在した巨大な沼「品井沼(しないぬま)」を陸にして、米を作ろうという壮大な計画が立ち上がった。そこで、沼の水を松島湾へと放出しようと、全長約7キロメートルの排水路(トンネル)が建設された訳だ。その中の1つが「明治潜穴(別名:高城川トンネル)」であり、1910年(明治43年)に完成し当時の建築物が今もなお、同公園に生き続いているのだ。

公園の敷地内には、明治潜穴を見学するための「ビューポイント」がいくつかあるのだが、その中の1箇所をご紹介しよう。まずは公園駐車場から奥へと進み、右方向へと進んでいこう。

すると奥に西洋式の街灯が見えてくる。そこがビュースポットとなのだが、明治潜穴を見ようと近づいていくと・・

なんと現在(2023年7月6日時点)は、周囲の雑草にすっぽりと覆われしまっていて、わずかにだが下へとおりる階段が見えるだけという状況だった。

これでは皆さんに申し訳ないので、公園内の解説看板にある本来の明治潜穴の姿と、現在を比較する形式で見てみよう。明治潜穴は煉瓦造りのしっかりとしたトンネルで、雑草がなければかなり間近でその見事な建築を見学することができる。とても数少ない土木遺産を直で体感できる貴重なスポットなので、また近くで見学できる日が来ることを期待したい!
魅力ポイント その2:明治時代を感じる赤レンガの建造物

明治時代といえば西洋式の文化などが徐々に日本へと広がり始めた頃。日本古来の伝統模様などを活かしながらも洋風なモチーフも採用されていたり、ファッションそして建築デザインなども変化を遂げていた。そんな明治時代の雰囲気が漂う公園内の建造物(上記写真参照)は、明治潜穴のトンネル部分を彷彿とさせるユニークな形状で、見事な立体芸術作品。実はここ、中に入っていくと・・そこは休憩所になっているのだ!中にはベンチや喫煙場所なども完備されている。

しっかりと計算され組まれている西洋風の赤れんがの壁と、各柱のてっぺんにはよく見ると可愛らしい鱗(うろこ)模様の屋根が付いているのだ。太陽の光とこの建物が作り出す影が、芸術好きにはたまらないかもしれない。

横側からの眺めもまた非常に味わい深く、まるで美術誌の表紙モデルにもなりそうな素敵な空間なのだ。建築デザインなどお好きな方には、実際に見てほしいおすすめの場所だ!写真と現物はやはり迫力が違うぞ。
魅力ポイント その3:品井沼干拓のキーパーソン「わらじ村長」を知る

わらじ村長こと「鎌田 三之助(かまた さんのすけ)」は、現在の宮城県大崎市鹿島台の村長(※当時は鹿島台村)を務めた方であり、品井沼の干拓事業を行なった人物だ。同事業には3名の主要なリーダーが存在し、そのうちの1人が鎌田氏だった。沼の調査から干拓の計画書の作成など、宮城県と国を相手に壮大な時間をかけて完成させた同氏たちの記録は、現在大崎市鹿島台の「鎌田記念ホール」で映像と共に事業の内容などを学べるようになっている。ちなみに「わらじ村長」とは同氏のあだ名であり、その理由も鎌田記念ホールで知ることができるぞ。

公園内には「明治潜穴」以外の排水路(トンネル)についても解説している看板があり、そこには時系列順に詳しい仕組みなども記載されている。例えば「鎌田記念ホール」を見学してから各現場のトンネルを見にいく、またはその逆にしても、同氏たちの歴史と共に現地を見学するとより面白く、そして感慨深い気持ちとなるだろう。現代のこの地域で稲作が行えているのは彼らたちのおかげであり、そこに感謝を忘れることはできない。
魅力ポイント その4:春には京都「祇園しだれざくら」が舞う

敷地内の一角には大きな「祇園しだれざくら」が生育していて、春には美しい雅な桜を楽しむことができる。この桜は、天保3年創業の京都「植藤造園」の16代目「佐野 藤右衛門(さの とうえもん)」氏から寄贈を受けたもの。佐野氏は世界でも名高い庭師であり、桜を愛してやまない人物。日本だけにとどまらず世界中へ飛び回り、桜を守るため調査などを行なっている。

同氏が、この公園に大切な桜を寄贈した理由としては、明治潜穴を含め品井沼干拓までの諸々の歴史を永く後世へとつなぐことを願い、桜をこの地に贈ってくれたという訳だ。
江戸から明治時代、そして現代へと時間は止まることなく流れていく。その中で、この記事が皆さんにとって明治潜穴の存在を含め、関連する歴史を知るきっかけとなれば、筆者はとても嬉しい限りだ。今回はとても長く深い内容だったが、最後まで読み進めてくれた皆さんには、感謝の気持ちでいっぱいだ。(いつも本当にありがとうございます!)
さあ、みんなで「わらじ村長」たちのストーリーを探りにいこう!
名称:明治潜穴公園(めいじ せんけつ こうえん)
住所:宮城県宮城郡松島町幡谷泉ケ原