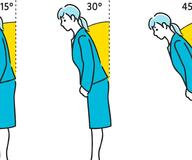「ネトウヨ」より「ジジウヨ」がこわい
昨日は69回目の終戦の日だった。政府主催の全国戦没者追悼式のほか、各地でいろいろなイベントが開かれただろう。この暑さは式典の類に好適とはいいがたいが、この夏の真っ盛り、盆休みに合わせたかのようなこのタイミングは、日本人の季節感に妙にマッチしているようにも思う。というわけで、最近思うことをつらつらと書いてみる。
以下はきちんとしたデータや理論で裏付けた話ではない。この種のテーマはタッチーなのでことばの定義とかめんどくさいが、そのあたりも割とふわっとしたままでいく。高齢者層、もう少し広げて中高年層の間に勇ましげな論調がめだつなあ、みたいな印象論、という前提でご理解願いたい。
記事タイトルの「ネトウヨ」「ジジウヨ」は釣りっぽいが、主に語呂のよさで選んだ。世間でどういうニュアンスで受け取られているかは一応承知しているが、個人的に特段貶める意図はない。「ジジ」ということばは高齢の男性を意味するわけだが、そうした人々に限ったものとは考えていない。だから「オジウヨ」でも「オバウヨ」でも「ババウヨ」でもいいかもしれないし、それらを総称することばがあればもっといいのだが、とりあえず「ジジウヨ」で代表させておくことにする。
「ウヨ」は「右翼」の略語だが、そっち方向と位置づけられるものはさまざまある。愛国心を重んじ、日本の軍事的プレゼンスを拡大すべきといった考え方が中心的、なのだろうか。保守は右翼とは必ずしも結びつかないだろうが、現代日本の文脈では近いものと考えてよさそうだ。広くとらえると、いわゆる嫌韓、嫌中やその他の排外的思想や、伝統的(戦前あたりを理想とする考え方としておく)な習慣や制度をよしとする価値観もそれに近い方向性といえる。
もともと総じて中高年層、特に男性は右翼的というか保守的というかタカ派的というか排外的というか、そういった傾向が強いことは知られている。たとえばヤフーの意識調査でこんなのがある。
「安倍首相の靖国神社参拝は妥当?」(2013年12月26日~2014年1月5日)
これでみると総投票数49万弱のうち「妥当」が76%を占める。投票者の80%が男性、50%以上が50代以上だ(40代以上なら8割だ)。思い切り偏っていて、統計としての信頼性を求めるわけにはいかないが、少なくともこの種の問題に興味を持つ人のうち高齢男性がかなりの割合を占めている、ぐらいのことはいえそうだ。
威勢のいい言動ということでいえば、たとえばこの前の都知事選で「予想外」の善戦をした田母神俊雄氏を支えたのも、やはり中高年層であったらしい。以下の記事は、朝日新聞の出口調査による世代別の投票動向に各世代の投票率を加味して推計したものだが、これだと20~30代で得票全体の4割、つまり40代以上で残りの6割を占めることになる。50代以上でも36%を得ているという。
「若者は本当に田母神氏を支持したのか?」(Yahoo!ニュース個人2014年2月11日)
もともと「ネトウヨ」自体、その平均は「38歳強」なのだそうで、一般的なイメージでいう「若者」層とはややずれがあるわけだが、ネットでのプレゼンスがそれほど高くないとされる、それより上の世代でも、こうした傾向はみられる。それが顕著にあらわれているのが、いまや50代どころか60、70代をターゲット読者層とする総合週刊誌などの雑誌の記事傾向だ。
たとえば『週刊ポスト』。2014年8月15・22日号は時期が時期だからということもあるが、こっち方向の記事が目立つ。
米軍慰安婦たちのスクープ証言「私は韓国『基地村』の売春婦だった」
櫻井よしこ「猛毒を撒き散らす中国と対峙する覚悟が必要です」
特攻隊員の手紙 妻へ、母へ、我が子へ──男たちは気丈な言葉を遺し、心で泣いた
もともと小学館は「こっち方向」が強いから(『SAPIO』などはほぼ丸ごと全部それだ)、こういう方向性になるのはある意味自然だろう。「日本人の遺骨に「1柱200万円」を要求した日朝協議の屈辱シーン」「北朝鮮と中国が結託した「パールライス12・5万t」強奪計画」(7月25・8月1日号)、「「台湾は国じゃない」と決めつける NHKほか大メディアの「媚中と無知」の大暴走」(7月11日号)、「「反日・嫌韓」解決できない、必要ない!の声が圧倒的多数」(6月20日号)といった具合で、以前からこの手の話題をちょくちょく取り上げている。
『週刊文春』だと、2014年8月9日号に「大特集「反日」の真実 中国よ、韓国よ、君たちが間違っている 第1部 習近平も中国人もどうかしている 橋爪大三郎×津上俊哉」、6月29日号には「尖閣危機をよそに「集団的自衛権NO」で共闘 中国がほくそ笑む 公明・朝日売国オウンゴール」なんていう記事が出ている。ウヨ界隈では「親中韓的」としてあまり評判がよろしくないらしい『週刊現代』でも、2014年8月9日号の石原慎太郎インタビューでは、石原が「今の野望は何か」との問いに対して「支那(中国)と戦争して勝つこと」と答えたと書いたりしている。
ふだんこの手のものをほとんど読まないので見出しを見るだけで目がクラクラするが、どちらかというと反中韓といった色彩が強いことがわかる。考えてみると、集団的自衛権のような話は少なくとも現段階では抽象的な問題だ。世界の注目が集まるガザ地区やイラクなどの情勢に関してそっち方向の人たちが一致した明確な意見をもっているというふうにもみえない。というわけで、彼らの現実の関心事項が主に中国、韓国との関係であることはまあ当然といえば当然の話でもある。
世代論に走るのは本意ではないが、「戦争を知らない子どもたち」のなれの果てであり、日本がこれらの地域に対して何をしたのかを直接見てはいないこの世代にとって、これらの国々は、かつては概ね意識の外にあったのではないかと思う。日本は欧米に追いつき追い越せとやってたし、これらの国々は政治的にも経済的にも、かつては日本とは状況が異なり、はるかに遅れていたから、比べる意味があまりなかった。もちろんそうなった原因の一端は日本にあるわけだが、いずれにせよ、この世代の日本人の中には、現在みられるような中韓の存在感の大きさを、「昔ならありえなかった、いつの間にか追いつかれた」とみる人がいるのだろう。
これらの国々のかっこ悪いところやまずいところを一生懸命探して指摘するのも(上記の週刊誌もそうだし、産経新聞などもそういう記事が大好きだ)、日本がいかに外国に評価されているかをやたらに強調するのも(外国に、がポイント)、彼らが失われつつある自信を保つために必要としているのではないか。自尊心のよりどころを国に頼らざるを得ない人がこうした考え方に惹かれるという見解もあって、実際そういう人も少なからずいるだろうとは思うが、後述のようにこの層には社会的立場のある人も少なくないから、むしろ「ジャパン・アズ・ナンバーワン」といわれなくなった喪失感のようなものがあるのかもしれない。
で、こうした「ジジウヨ」たちが、(典型的にイメージされる若年層の)「ネトウヨ」よりこわいというのは、第一義的にはこの層の人たちが、若年層の人たちと比べて明らかに現実の政治を左右する力が大きいということだ。それは端的にいえば投票率の差ということになるが、必ずしもそれだけではない。「ネトウヨ」も「30代、40代が主力であり、比較的富裕な中小の自営業者を中心」とする、との指摘がある。「ジジウヨ」たちの中にも、社会的立場があり、発言に社会的影響力のあるであろう人たちが少なからず含まれていると考えるのが自然だろう。実際、『週刊ポスト』の媒体資料には、読者層の過半数が年収900万円以上、とある。実際にどうかは知らないが。
それはともかく、彼らは、戦争を知らず、今後も知る必要はない。『戦争を知らない子どもたち』が発売されたのは1970年だが、当時戦争といえば日本が参加していないベトナム戦争だったわけで、ほとんどの人にとって戦争は既に身近なものではなかった。もっと上の世代でも、戦後生まれは既に60代のほとんどを占める。70代もほとんどが戦場を知らない。石原慎太郎だって終戦時には12歳だった。
そして彼らは、平和の配当としての高度成長やその後の繁栄を謳歌し、今に至った。年齢的にみてもう戦争に行くことはない。全面戦争が困難になった現代では、身近な場所が戦場になることもないだろう。どうせ今後の人生もそう長くはないし、何か言っても責任を問われる立場ではない。基本的に気楽なのだ。
過激な主張は、それ自体としてはもちろん自由だし、必ずしも危険とまではいえない。だが、これがマスメディアに載って繰り返し拡散され、強化されていくと、とたんに危険度が高まる。さらに異論を封じる空気が広がっていくともうレッドゾーンだ。戦前の日本から学ぶべきことはいろいろあるだろうが、よくいわれるような軍部の独走とか政府の言論統制とかよりも、対外強硬論を煽ったメディアや論者が世論と呼応して、暴走が止まらなくなっていった経過の方が重要ではないかと思う。
最近古本屋で買って面白く読んだ本がある。
武藤貞一著『日支事変と次に来るもの』(新潮社、1937年(昭和12年))
武藤貞一は記憶が正しければ当時朝日新聞の論説委員で(その後報知新聞の主筆になった由)、評論家として国民に戦争への覚悟を繰り返し説いた人だ。1892年(明治25年)生まれのこの人は、1937年時点で45歳。当然ながら自ら戦争に行くこともなく、戦後も生き残って反共の立場からの評論活動を続けた。方向性はともかく合理性を重んじた人であったと評価されているようだが、実際にこの本を読んでみると、正直そうでもないように思う。たとえば、出版の2ヶ月前に起きた盧溝橋事件(1937年7月7日)に関連して、
「・・・アメリカが絶対傍観を守っているのは、ソ連の赤化攻勢を東亜に確認するが故である。イギリスが冷静なのも、北支に日本が防共壁を築いてくれることは、それは支那の利権に関する限り、さして排撃すべきことでないとするからである」
と書いている。アメリカはソ連と対立しているから、ソ連に対抗するための日本の動きを静観するだろうという見立てだが、その後で今度はユダヤ黒幕論を持ちだして、
「世界赤化を目指して資本主義倒潰に驀進しているロシア・ユダヤ政権と、資本主義国際戦争への猛烈なる誘導を「軍備拡張、国防強化」といふ名目で進み、政府や議会に断然君臨しているアメリカ・ユダヤ政権とは、その実、仲のよい兄弟なのだ」
とも書いている。つるんでいるのか対抗しているのかどっちなのさと聞きたくなる。
対ソ連という観点で米英が日本を見逃してくれるだろうとの見方は、当然ながら当時のソ連のめざましい発展が背景にある。日本の中国進出は、ソ連に対抗するという要素が強くあった。共産主義の波及への恐れは米英も共有しているはずだというわけだが、実際のところは、その後米英ソが国民政府を支援し、1939年には日米通商航海条約が破棄されたことで、情勢を見誤ったものであったことが明らかとなる。
すると今度はこの人、この本ではほとんど触れていない対米戦の必要性を説く『日米十年戦争』(1941年(昭和16年))を出版し、「アメリカが大陸を南漸して太平洋岸に出て来たとき、延いてはペリーが浦賀湾頭に砲声を轟かしたとき、今日の成行きは約束されてい」たと書いている。じゃあなんで1937年の本では「絶対傍観を守っている」と書いたのか。そして、日米開戦で米国が南方資源を失うとの指摘も当然のようにはずれた。単にそのときそのときの時局に応じて適当に論を立て、戦争に向けて煽り立てただけではないか、というのが正直な感想だ。
とはいえ、結果としてこの人がまちがったことを批判したいのではない。この人は当時人気の評論家であり、この本以外にも『英国を撃て』『戦争』など多くの著作がある。私が入手したこの本は第5刷で、初版から合わせると15万部が刷られたことになる。すべての漢字にふりがなが振られていて、親しみやすい文体とともに、想定される読者層の広さが伺える。実際、この本が出版された翌年に国家総動員法が成立しているから、この本もそうした世論形成にそれなりの役割を果たしたのだろうが、逆に、こうした言論を歓迎する空気が、この人にこうした本を書かせたということでもある。
少なくとも日本においては、民主主義と帝国主義は表裏一体のものとして発展した。それは明治時代の自由民権運動のころから綿々と続いてきた流れであり、軍部の独走とかメディアの責任とかだけに帰すべきものではない。軍部の政治への進出も、民衆の不満を背景とした「世直し」と受け取られていたし、海外への進出に対しても、利権を通じた国民生活向上への期待が寄せられていた。そして、こうした考え方に沿わない人々は沈黙を強いられた。権力によってというより、主に相互監視によって。
いずれにせよこれらは内向きの論理であり、多くの外国から容認されるものではなかった。だからこそ日本は、不本意ながらも大きな戦争にのめり込まざるを得ず、結果として国家存亡の寸前にまで追い詰められた。他の道が現実としてとれたかどうかはわからないが、少なくとも、異なる見方、多様な考えを社会の中に確保することがいかに大事かということはいえると思う。その点は今も同じだ。警戒すべき対象は法制度よりむしろ、私たち自身の心の中にある。
武藤貞一は
「平和の欲求ほど戦争を拡大させるものはなく、挙国一致の強硬態度ほど事態の不拡大に裨益するものはない」
と主張したが、私はそうは思わない。戦前に少なくともある程度成立した「挙国一致の強硬態度」が何をもたらしたか、改めて振り返るまでもなかろう。そして、そうやって「一致」した人々の大半は戦後一転して責任を一部の指導者に押し付けた。マスメディアもだ。いわゆる「一億総懺悔」論はよく、一億総無責任化であると評される。みんなが同程度に悪いからお互いに批判しあわないという暗黙の合意だ。その意味で、戦争時のあれこれに関する責任論が現在まで尾を引いているのも、当時、意見の多様性が確保されていなかったからだと思う。
もちろん、「ネトウヨ」が若年層の一部でしかないのと同様、「ジジウヨ」が高齢者層の多数を占めることもそうそう考えにくい。だが、声の大きい人々の主張は、実際より大きくみえる。そしてネットによって大衆同士が国境を越えてつながりあう今の時代、その影響力はこれまでより大きくなってきているのではないかと思う。ウヨ的な考え自体をいちがいに否定するものではないが、そのリスクについては意識せざるを得ない。
おそらく、中国にも韓国にも、似たような層の人々がいるにちがいない。過激な言論を内向きに発したつもりでも、それが伝わってさらなる反発を招き、さらに過激になっていくさまは、呼応しあった動きのようにもみえる。よくネットを同種の意見が集まる「エコーチェンバー」になぞらえるが、真逆の意見が他のグループから入ってきた場合にはさらに加速されるということだろうか。それがメディアを通して拡散されていくことは、新聞や週刊誌、ネットメディアなどにおいて「ネットではこのような意見が」といった記述が多くみられることから明らかだ。そういった状況はやはりよろしくない。特に、社会的な立場や影響力がある人々、暇がありかつリスクやコストを追わずにすむ立場の人々がこうしたプロセスにはまっていくのは大変よろしくない。経験を積み、判断力を期待されるこの層の人たちには、煽ることばの巧みさではなく、周囲を広く見渡す冷静さを期待したい。
最後にもう1つ。「ジジウヨ」に限らず誰しも、自分と違う意見に触れることは、絶対に必要だ。そしてそのためには、考えのちがう相手に対する敬意が最低限必要になる。その意味でヘイトスピーチには反対だが、ヘイトスピーチを規制しようという動きに対しても、最大限慎重でありたい。その意味でも、過激な言論は自制することが必要だろう。たいていのことは、過激な表現でなくてもいえるはずだ。
というわけで、ふわっとした印象論はこれにて終了。