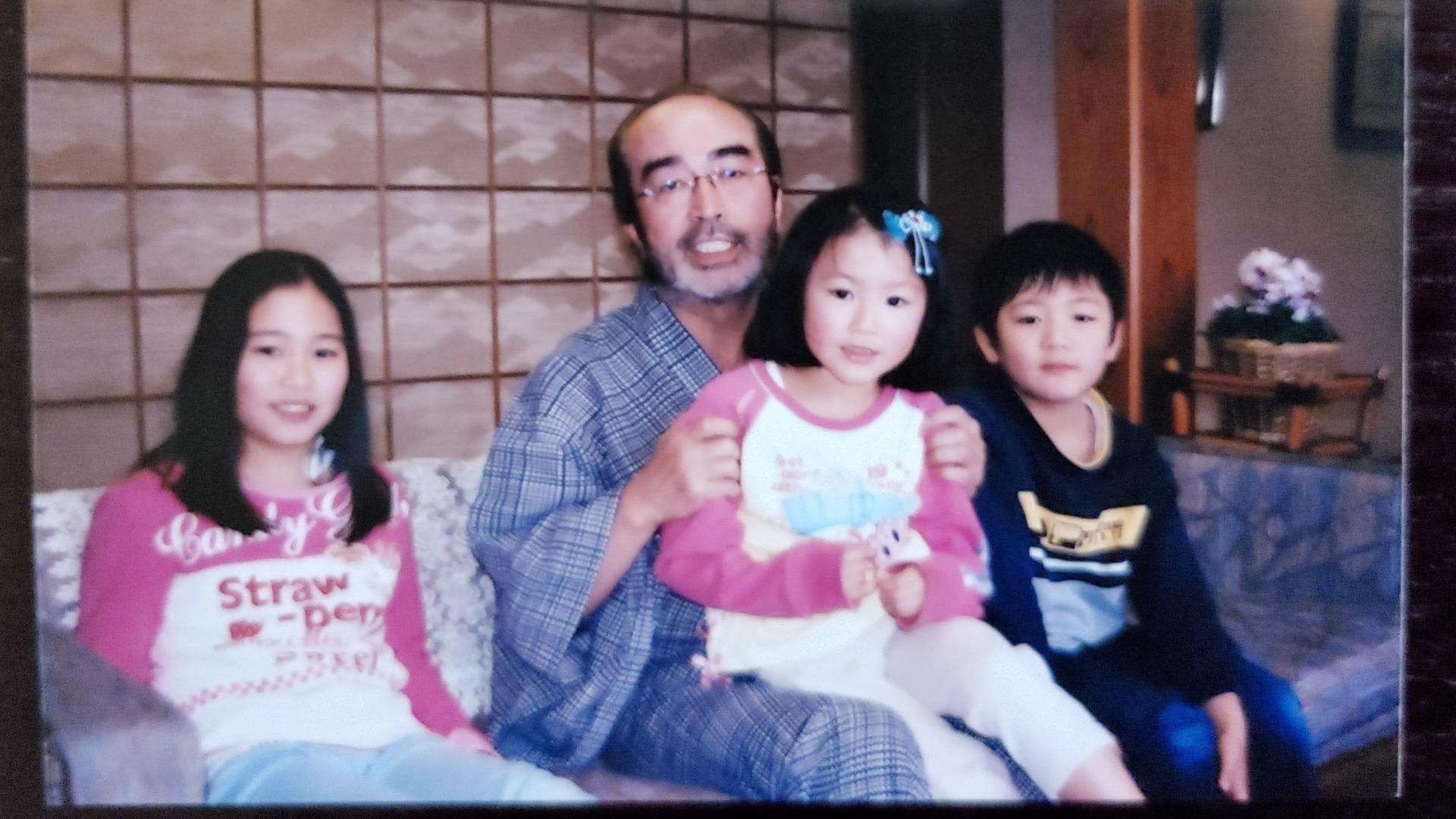「働き方改革」を仕切り直そう! なぜ「働かせ方改革」になってしまったのか

現在の労働力不足を解消するという主旨での「働き方改革」
いまではどこにいっても「働き方改革」という言葉を聞くが、その言葉の意味は、使われる文脈によってまちまちだ。あるときは過労死防止の意味であり、あるときは個別の企業の業務改善の意味であり、あるときは労働生産性向上の意味であり、あるときは多様な働き方の実現の意味で使われる。なんでもかんでも「働き方改革」と言ってしまえば聞こえがいいという感すらある。
「働き方改革」という概念がどこから発生してどう変化してきたのか、「働き方改革関連法案」が成立したこのタイミングでいま一度整理しておきたい。
議論の発端は、2015年10月から2016年6月にかけて計9回開催された「一億総活躍国民会議」を経て2016年6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」。文書には以下のような課題認識が表明されていた。
少子高齢化の進行が、労働供給の減少のみならず、将来の経済規模の縮小や生活水準の低下を招き、経済の持続可能性を危うくするという認識が、将来に対する不安・悲観へとつながっている。日本が少子高齢化に死に物狂いで取り組んで行かない限り、日本への持続的な投資は期待できない。
広い意味での経済政策として、子育て支援や社会保障の基盤を強化し、それが経済を強くするという新たな経済社会システム創りに挑戦する。
子育てや介護をしながら仕事を続けることができるようにすることで労働参加を拡大し、潜在成長率の底上げを図る。
出典:ニッポン一億総活躍プラン
要するに、(1)現在の労働力不足を補うために子育て中の世帯や介護中の世帯からも労働力を集めよう、(2)出生率を上げて将来の労働力をできるだけ減らさないようにしよう、という2つの狙いがあった。いずれにしても国の狙いは労働力の確保であり、もともと経済政策として位置づけられていたのだ。
現在の労働力不足解消のために「女性の活躍」が求められるようになった。女性が結婚・出産後退職し労働市場から姿を消すいわゆる「M字カーブ」を解消すれば、労働力が増えるという理屈である。
「企業戦士+専業主婦」という昭和的片働きモデルから、共働きを前提にしたライフスタイルへの変革である。一つの世帯から一人の男性が平均で1日9時間ほどの賃労働に従事すれば家族が養えていた社会から、夫婦がともに賃労働に従事することで社会としての総労働力を増やそうという発想だ。
ただし元来、いわゆる「家庭に入った女性」が何もしていなかったわけではない。24時間会社で働く企業戦士を支えるために、「無賃」で、家事・育児を行っていたわけだ。つまり社会として、専業主婦の活躍に依存していた。専業主婦がいないと回らない社会だった。
共働きを前提にした場合、それまで専業主婦たちが担っていた労力を誰が担うのかという問題が当然発生する。北欧スウェーデンでは、育児や介護などの「ケア労働」を国の仕事として巻き取った。国の「ケア労働」従事者の多くは女性であり、結果的に、それまで女性が家の中で「無賃」で行っていたことを、公的サービスの職員として家の外で「賃労働」として行うという構造に変革したことになる。アメリカではそこを低賃金の移民の家政婦に頼る部分が大きい。国際的な経済格差を利用した構造であり、国際的な経済格差に依存する不安定なしくみだともいえる。
日本でも21世紀に入ってからすでに、家事・育児をしながらでも仕事が続けられるような制度は拡充されてきた。それらは主にワーキングマザーを対象に用意されていた。しかし、フルタイムで働きながら、育児もし、一家の家事全般を担うのでは、負担が大きすぎる。
というわけで「男性も家事・育児を」という話になる。つまり、夫婦で平等にワークライフバランスを保てる社会を実現しようということだ。「イクメン」「カジメン」への期待である。しかし十分に期待に応えることはできなかった。現在の長時間労働社会では、仕事を終えてから育児や家事をするというのは現実的ではない。
そこで部下のワークライフバランスにも配慮したマネジメントができる「イクボス」に期待が移る。部下の残業を減らし、仕事と家庭の両立がしやすい職場をつくることが、中間管理職の大きなミッションとされるようになったのだ。ただし、業績を悪化させてはいけないというのでは無理筋だ。
ワーキングマザー→イクメン・カジメン→イクボスと、しわ寄せを押しつけ合っている構図が見える。社会全体の働き方を変えないと、しわ寄せはいつまでも解消できない。だから「働き方改革」。以上が、現在の労働力を増やすという側面から見た「働き方改革」である。
未来の労働力を確保するという主旨での「働き方改革」
一方で、未来の労働力を確保するために、子育て支援を強化しようという側面から見た「働き方改革」は以下のように説明できる。
子育てとはそもそも未来の社会の構成員を育てること。つまり未来の社会をつくる社会的事業であり、そのコストは本来社会が担うべきものである。子供を産むか否かは個人の自由であるが、だからといって子育てを“個人の営み”に矮小化してはいけない。しかし現状実際には親が、そのコストの大部分を負担している。つまり子育て中の親は、「賃労働」を通して現在の社会のために働いているだけでなく、未来の社会のためにも「無賃」で働いていることになる。
未来の社会づくり事業である子育てに時間や労力を費やす分、現在の賃労働に費やせる時間や労力に制約が生まれ、現在の労働市場においては状況的に不利な立場になりやすい。「労働者」としての価値が下がりかねない。その状況的不利をいままでは多くの場合女性が引き受けていたわけだが、それを男性も引き受けようというのが「イクメン」の流れだということができる。
さらに、子育てが未来の社会づくり事業ではなく個人の営みとしてとらえられる社会では、子育てにかかる時間的・労力的・費用的負担はほぼ自腹扱いとされ、子育て世帯の負担感は重くなる。労働市場で状況的不利を被り負担も増すというのでは、「だったら子供なんていないほうがいい」という判断が合理的に見えてしまう。少子化が進むわけだ。
負担感を少しでも軽減する施策が、教育の無償化や保育の充実などである。子育てにかかる負担を親個人に押しつけるのでなく、できるだけ社会として負担しようという発想だ。そして、労働市場において子育て中であることが状況的不利にならないように、子育て中の労働者にも無理のない働き方を、社会全体の働き方のスタンダードにしてしまおうというのが「働き方改革」の目的であるといえる。
子育て中の労働者でも無理なく働ける制度を充実させたところで、子育て中でない労働者が何の制約もなく24時間働けてしまうのであれば、子育て中の労働者の状況的不利は相対的に解消されず、「子育て」が「キャリア形成上のリスク」と認識される構図は変わらない。だから社会全体として、長時間労働文化を解消し、子育て中の労働者にも無理のない働き方を世の中のスタンダードにする必要があるのだ。
「働き方改革とかいって、もっと働きたいひとが働きづらくなるのはおかしい」という言説を巷ではよく聞くが、まだまだ働けるひとの働き方までも制約しなければいけないのは、少子化解消という目的から導かれる手段なのである。個人のパフォーマンスよりも社会全体を一つのチームとして考えた場合のパフォーマンスを向上するために、働き方のペースを揃えましょうという発想といえる。
これからは、社会の変え方を変えなければいけない
以上が、現在の労働力の増加、そして未来の労働力の確保という二つの側面から見た「働き方改革」の意義である。これらを踏まえて、1日何時間外で働いて、1日何時間家事や育児に費やして、1日何時間遊んで、1日何時間休むのかを、社会として議論し、それを実現する方法を模索するというのが「働き方改革」に求められていた段取りであったはずだ。結果的には、二つの側面からアプローチした新しい働き方は、「子育てしながら無理なく働ける」という意味で同一になるはずだ。「働き方改革」とは、ただ漠然とできるだけ残業を減らすとかできるだけ業務効率化を図るとか、そういう話ではなかったはずなのだ。
しかし現実に「働き方改革実現会議」で時間をかけて議論されたのは、労働基準法の残業規定の抜け道「36協定」をどうするかであり、過労死を防ぐという意味での残業規制をかけるかどうするかという次元の話になってしまった。「ワークライフバランス」の「ライフ」が、「生活」ではなく「命」の意味にすり替わった。子育てしながら無理なく働ける社会の実現とはほど遠い。その意味で、当初の「働き方改革」の目的からは大幅にずれた結論にたどり着いたといえる。
それでも「青天井」と呼ばれた残業規制に歯止めがかけられたのであれば、「小さな前進」ということもできた。しかし結局作成された働き方改革関連法案にはこれと矛盾する「裁量労働制の拡大」や「高度プロフェッショナル制度」も抱き合わせにされていた。これらは言ってしまえば、一定の条件を満たす労働者を残業規制対象から除外するという制度である。せっかく36協定の抜け道を塞いだのに、別の抜け道をつくってしまうことになる。「働き方改革実現会議」での議論は何だったのかという話である。
こうして「働き方改革」という言葉だけが一人歩きを始め、当初本来の目的は忘れ去られ、労働力強化や業務効率化など、企業側・雇用者側に都合の良い論理で語られるようになってしまった。いつの間にか、「働き方改革」が「働かせ方改革」になってしまったのだ。いや「改革」ですらない。「改革」や「革命」という言葉には、既得権者の力を弱めるニュアンスがある。しかし今回の「働き方改革」は、昭和型のビジネスモデルの延命措置にすら見える。
今回の法案では、おそらく「改革」と呼べるほどの変化は起こらないだろう。「働き方改革」の仕切り直しが必要だ。その際の視点として、以下の二点を挙げたい。
(1)「何を変えるか」よりも「何を目指すか」の議論を
(2)子育ては未来の社会をつくる、公共事業であるという認識を広める
(2)については前述の通りである。以下、(1)について補足する。
国連が採択した「SDGs」というものがある。日本語では「持続可能な開発のための2030アジェンダ」と表現されるもので、「貧困の解消」「ジェンダー平等の達成」「持続可能なエネルギーの確保」「平和維持」などの人類共通の「目標」が掲げられている。
国や地域や文化的背景の違いによって、人類の置かれている立場はさまざまである。そこで、画一的に「世界をこう変えていこう」というのではなく、まずは「目標」のみを共有し、それぞれの立場でそれぞれにできることをやっていこうという呼びかけの意味がある。
画一的な正解が存在しない多様性の時代において、トップダウンで一律に何かを変えるのは難しい。それならばまずはビジョンのみを共有し、具体的な解決策については各々の主体的判断に委ねようという方法論だ。
「一億総活躍社会」とそこから派生した「働き方改革」も、多様性が前提にあるのなら、一律で法律や制度を変えることにこだわるのではなく、労働者の主体性を起点として、社会としてのビジョンの共有に時間とエネルギーを割くべきだったのではないだろうか。逆に言えば、それをしなかったから、「働かせ方改革」になってしまったのではないだろうか。
多様な人々が同じビジョンに向かって少しずつ主体的な変化を始めることで、結果的に社会がじわじわと変わる。そのような変化のモデルをイメージしたほうが、実は確実に世の中は変わるような気がする。急がば回れである。これからの時代においては、社会の変え方も変えなければいけないのかもしれない。