危機を煽ることで回避される感染症の危機
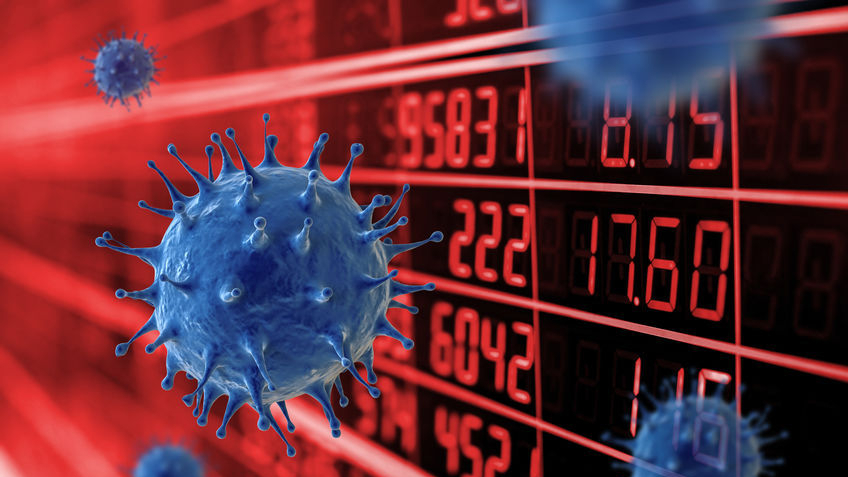
人は、多種多様なリスクに取り巻かれて生きるなかで、それらのリスクに上手に付き合うすべを心得ています。しかし、ときに、慣れすぎたリスクを過小評価し、不慣れなリスクを過大評価することは避け得ません。故に、政策的には、リスクに関する啓蒙が極めて重要で、ときには適切な危機感を醸成し、ときには逆に危機感の鎮静化を図るわけですが、そこには情報操作の側面がないこともありません。
人が生きるとは

道を歩けば、高い建物から物が落ちてくる、車が歩道に突っ込んでくる、通り魔に会う、新型コロナウイルスに感染するなどの多くのリスクに曝されますが、人は、それらのリスクを合理的に計算して、許容範囲内のものは受け入れ、許容範囲を超えるものにはリスクを制御する対策、例えば、ヘルメットを着用する、車道に近いところを歩かない、夜中に人通りの少ない暗い道を歩かない、マスクをして他人と距離をとるなどの対策を講じ、いかに対策を講じても許容範囲に収まらないリスクがあれば、そもそも道を歩かないわけです。
こうしたリスク計算に基づく行動様式は、計算している自覚すらないほどに、人の慣れ親しんだものですが、当然に、人によって異なる帰結を生んでいます。それは当たり前で、人の経験量の違いによって、リスク計算に用いる情報量とリスクを制御する技術が異なり、人の性格や生きている環境の差などによって、リスクの許容度が異なるからです。そして、リスク許容度の差が人の個性であり、リスク計算とリスク制御の高度化が人の成長なのであって、両者が相俟って人の生活様式を規定しているのです。
企業が経営するとは
企業とは、ある事業の利益機会に意図的に参画するために組織されたものですが、利益機会の裏には、当然至極のこととして、リスクが存在するわけですから、ある事業のリスクを意図的にとるために組織されたものといっても同じことです。さて、どの事業リスクをとるかは企業固有の意思ですから、どの事業リスクをとろうとも、その事業が社会の必要性に立脚している限り、事業に貴賤、優劣、良悪の差があるはずもなく、企業の優劣がいわれるのは、意図的にとられたリスクについてではなく、それに付随してくる諸リスクを適切に制御して管理下に置く技術においてなのです。
そして、そのリスク管理のあり方については、単に技術の優劣の差があるだけではなく、企業の経営哲学によって規定されるリスクの許容度の差があります。例えば、手元流動性を厚く保有する、あるいは負債比率を低くおさえることは、リスク管理技術の問題というよりも、資金効率よりも危機耐性を重視するというリスク許容度に関する経営哲学に基づくことです。こうして、企業においても、人の行動様式と同じように、企業の個性、即ちリスク許容度に関する経営哲学の差と、企業の経営力、即ちリスク管理技術の差が経営行動を規定しているのです。
リスクとの付き合い

リスクが変化すれば、そのリスクに対する人や企業の行動も変化する、それが進化です。
昔、停電が珍しくなかったときは、誰もが停電リスクを想定し、蝋燭の準備を欠かさないなどのリスク対策をして暮らしていました。その後、停電が稀有なことになり、停電リスクはリスク計算から外れていくわけですが、福島の原子力事故後、改めて停電リスクが意識されました。しかも、昔と異なり、多くのものが電化されていて、電気の必需性は著しく高くなっていたために、停電リスクも著しく大きなものとして再登場したわけですが、それから9年もたち、再び停電リスクはリスク計算のなかで小さな比重を占めるようになりました。それは発電と電気利用のあり方が変化したからです。
こうして、人や企業は、自分を取り巻く無数のリスクについて、外部環境の変動に伴ってリスクが変化すれば、その評価を変更して制御方法を改め、新たなリスクを認知すれば、その評価と制御の方法を開発し、そのたびに生活様式や経営行動を調整してきたわけです。人類の歴史は、こうしたリスクに対する対応技術の変化と進化の歴史、あるいはリスクとの付き合い方の変遷の歴史であるといってもいいでしょう。
リスクに慣れる
あるいは、付き合い方というよりも、慣れ親しみ方というべきかもしれません。
火山の噴火、津波、洪水、土砂崩れなどの被害があるところは、過去においても、繰り返し被害のあった記録が残っているわけですが、それにもかかわらず、人は住み続けています。それは、天災が甚大な被害を起こすたびに、防災対策が講じられて、経験の蓄積によってリスク制御技術が高度化していくからでしょうが、それだけではなく、リスク制御技術の高度化によって、リスクが制御されているという安心感、あるいは災害を克服できるとする自信が形成されていくからでもあるに違いありません。
そして、この後者の心理的側面は、経験、あるいは経験の伝承によって一種の慣れが生じ、リスクに対する許容度が大きくなっていく、あるいはリスクに対する心理的耐性が強くなっていくことを意味していると考えられます。心理的耐性とは、パニックを起こさない冷静さです。
取付けの心理

深刻な金融危機において、銀行の破綻が現実味を帯びることは、誰にとっても極めて重大な財産上のリスクの顕在化であって、破綻前に預金を引き出そうとする行動を広く誘発します。それが取付けですが、取付けは銀行の破綻の可能性を一気に現実化させるわけです。なぜなら、銀行は、預金総額のほんの一部に対応する手元流動性しか保有していないので、一時の大量な払い出しには対応できず、取付けが起きれば直ちに支払い不能に陥るからです。
しかし、実際には、現在の銀行規制の仕組みと金融行政および金融政策のもとでは、仮に取付けが起きてもおかしくない状況が生じたとしても、中央銀行が大量の流動性を供与する、あるいは政府が財政資金を投入するなどの方策により、預金者に実損害が発生する可能性を最小化しています。つまり、リスクは適切に制御されているのです。
ただし、取付けにより一つの銀行が破綻し、それがパニック的状況を発生させて更なる取付けを誘発し、銀行の連鎖的破綻という破滅的な状況が発生すれば、リスクの制御能力の限界を超えてしまいます。つまり、制度上のリスク制御のあり方からして、銀行破綻により預金者が損害を被る潜在的なリスクは極めて小さいにもかかわらず、パニックが起きてしまうとリスク制御の限界が破られてしまい、損害を被るリスクが顕在化してしまうのです。
取付けと報道
さて、パニックは、自分の不安に基づく行動が他人を不安に陥れることを通じて、不安が連鎖的に拡大することに起因しますから、それを防止する方策の一つとして、不安が拡散しないように情報の流通を統制することが考えられます。実際、報道界においては、取付けの事実は報道しないという暗黙の了解があると推測されています。
しかし、それでは、真実を報道する責務との関係で、難問を生じます。そこで、その難問を解くためには、預金者のなかにパニック的状況を起こさないだけの心理的耐性を作るしかありませんが、そのためには、国民のなかに、制度の仕組みについての理解と政府の危機対応能力への信頼を定着させるだけでなく、経験による慣れを生じさせる必要があるのです。
日本では、前世紀末、深刻な金融危機のなかで戦後初めての銀行の破綻をみて、いくつかの銀行で実際に取付けがあったのだと推測されていますが、その報道はなかったようです。しかし、当時の経験は日本人の心理的リスク耐性を強化したに違いありませんから、今ならば取付けを報道してもいいのかもしれません。
ただし、危機の記憶は、すぐに消えてしまいます。故に、防災訓練があるのではないでしょうか。防災訓練は、危機時の対応に慣れさせるためになされるのでしょうが、より根源的に、危機の記憶を蘇らせて、危機に慣れさせることが重要なのではないでしょうか。実は、金融教育というのも、その機能の一つは、取付けを起こさせないことであり、為替や株式市場の暴落等、金融市場の混乱のなかで、心理的パニックに起因する投資行動を起こさせないことでしょうから、もっと金融危機の歴史に重点を置いた内容にすべきだろうと思われます。
情報操作と危機管理

それにしても、新型コロナウイルス感染症対策における危機の強調は興味深いです。取付けの場合、人々が小さな潜在的リスクに対して過剰に反応することで、取付けの連鎖を発生させ、リスクが一気に飛躍的に増大して顕在化するわけですが、感染症の場合は、全く逆で、人々が大きな潜在的リスクに対して過小に反応することで、感染の連鎖を発生させ、リスクが一気に飛躍的に増大して顕在化するわけです。そこで、新型コロナウイルス感染症対策においては、政策的に、危機感を煽るという極めて異例な対策が必要になるわけです。
これは、取付けの報道と見かけは逆ながら、情報操作の構造は同じです。取付けの場合は、報道しないことが賢明な策と考えられたのに対して、感染症の場合は、感染源を公表して二次感染を防止する目的もあって、全く逆に、徹底的に過剰なまでに政策当局が詳細を公表し、それが広く繰り返し報道されています。仮に誇張があったとしても、それにより感染症の拡大が阻止されれば、それでいいわけですが、情報開示と報道における中立性と政策意図との関係について、多少は考えるべきことがあるかもしれません。










