「皇室ショー」からのLet It Go──『トゥルーマン・ショー』としての皇族

ホンネは「セレブの色恋沙汰」
11月14日、小室眞子さん・圭さん夫妻が、日本を離れアメリカ・ニューヨークに到着した。この3カ月あまりの狂騒はやっと一段落すると見られる。
9月末の圭さんの帰国以降、日本のメディアはネットも電波も紙も大騒ぎだった。10月末のツーショットでの結婚会見と、その直後の圭さんのニューヨーク州司法試験の不合格、そして出国直前の圭さん母親の元婚約者との和解と、話題が供給され続けた。
コロナ禍が収まる過程でもあったこの間、女性週刊誌やスポーツ紙、情報番組だけでなく、ニュース番組や新聞などもこの一件を報道し続けた。タテマエとしての「皇族の御成婚」と、ホンネとしての「セレブの色恋沙汰」──そうした両面があるからこそ、このネタは日本社会で広く訴求した。
そこでは、ふたりを過度にバッシングし続けるオーディエンス(視聴者・読者)もいれば、その逆に自由な門出を祝う者も散見された。SNSでは否定と肯定が入り乱れるバトルロワイアルが議論の体を成さずにいまも続いている。
それは、近年まれに見るゴシップ以外のなにものでもなかった。

大ヒットとなった象徴天皇
今回のゴシップに大興奮していたのは、最近は「ワイドショー」と呼ばれなくなった地上波の情報番組だ。時の政権よりも芸能プロダクションからの圧力を怖がる近年のテレビ局は、芸能人についてのゴシップにはかなり及び腰になっている。そんななかで、小室夫妻は気兼ねなく取り組める絶好の素材だった。
皇族に対するゴシップが目立ち始めたのは、80年代後半からだ(※1)。具体的には、小室眞子さんの母親である現・紀子妃と現・雅子皇后の結婚報道だ。当時それを主導したのは女性週刊誌だった。
それは平成が始まったタイミングとほぼ同期している。振り返れば、これは天皇に対するイメージが大きく変わっていくプロセスの最初期でもあった。
戦前に「現人神」として君臨した昭和天皇とは異なり、平成の明仁天皇(現・上皇)は最初から象徴天皇だった。そのことで天皇に対する意識は大きく変わった。NHK放送文化研究所が5年おきに行っている意識調査では、天皇に対する尊敬と好感の感情は、昭和時代には足して50%前後だったが、2018年には80%近くにまで上がっている。

それは天皇や皇室が戦前のイメージから脱却し、実質的に「象徴」として機能し始めたことを意味するのかもしれない。多くのひとが軽々しく言及するのも、親密性が強まっていることの反映と捉えられる。しかも右派の「皇室離れ」もあって「不敬だ!」と怒鳴られる心配もない(むしろ一部の右派は小室夫妻に批判的だ)。
実質的に、皇族はスターやアイドル(芸能人)、あるいはセレブレティのように受容されるようになった。それゆえそこには通俗的な言及も大量発生する。ゴシップのビッグウェイヴは、こうして久しぶりに到来した。
婉曲的な自己主張のためのゴシップ
欧米では、ゴシップの役割の多くをいわゆる「セレブ」が担っている。具体的には、映画俳優やモデル、歌手のプライベートに関する報道が中心だ。彼らについてのネタは、パパラッチなどから日々供給され、オーディエンスはそれについて言及することで消費する。00年代以降は、アメリカではゴシップ雑誌やゴシップサイトが大きく成長した。
ゴシップは、赤の他人(セレブ)についての情報のやり取りだ。その情報をただ受容するだけでなく、家族や友人など身近な存在とそれについて話したり、ニュースサイトのコメント欄などネットに書き込んだりすることが目立つ。つまり、コミュニケーションのネタとして消費する。
ゴシップとして効果(価値)が大きくなるのは、そのネタを知るひとが多く、かつその評価が大きく二分されているときだ。今回の小室夫妻ネタは、まさにそうしたものだ。逆にコミュニケーションのネタにならないような情報は、ゴシップとしてあまり機能しない。
こうしたゴシップによるコミュニケーションには、ある程度の機能もある。それは、第三者(ネタ元)を介した個々人の意見表明だ。(その場に不在の)共通の知人に対する否定は悪口になるが、赤の他人に対する否定は婉曲的な自己主張となる。
小室夫妻を否定するにしても肯定するにしても、そこでは間接的に自身の道徳観や倫理観、あるいは政治意識などが表明されている。重要なのは情報そのものではなく、受け手(オーディエンス)がそれをどう評価するかにある。SNSによくいる“正義マン”がたいていゴシップを大好物とするのは、より簡便に自身の道徳観を顕示できるからだ。
アメリカのゴシップサイト・”Lainey Gossip”を運営するエレイン・ルイは、そのことを重々承知だ。彼女は言う。
「ゴシップについての会話は、私たち自身についての会話であって、対象についてではありません」「ゴシップトークは、自分が何者で、なにを信じているかを映すものです」(※2)
そして、こうしたゴシップについての互いの意見表明──道徳観などの確認によって、コミュニティにメンバーを招き入れたり、維持したり、あるいはそこから排除したりする。
日本では「井戸端会議」なる日常があったが、あれは典型的なゴシップトークだ。とくにふだんからはっきりと自己主張をしない傾向の強い日本人にとっては、ゴシップは意見表明のための重要な機会なのかもしれない。
しかも赤の他人が対象だから、自分自身は安全地帯にいて責任も及ばない。逆に、自己表現できる立場を確立していて責任感が強いひとにとっては、ゴシップはあまり必要がないのかもしれない(※3)。
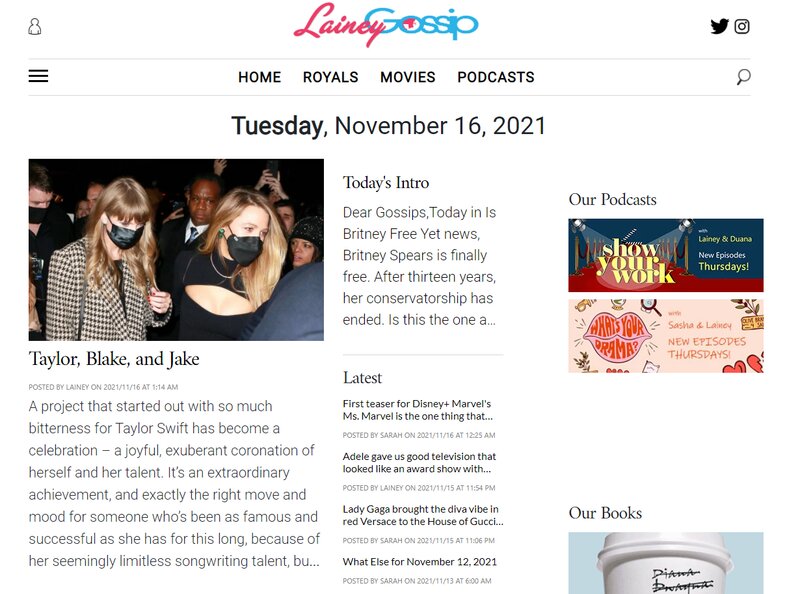
台本やカンペがないショー
小室夫妻についてのゴシップは、日本の芸能人やアメリカのセレブなどのそれと受容は似ているものの、決定的に異なる点もある。それが皇族という要素だ。
今回のゴシップが盛り上がった要因のひとつには、ゴシップ対象(小室眞子さん)からの反論や釈明が極めて少なかったこともある。いくらバッシングしても、(皇族時代は)公人なのでマスコミやSNSユーザーにとって訴訟リスクは低い。しかも明確な反論と釈明は結婚記者会見までほとんどなかったので、オーディエンスは一方的に言いたい放題だった。10月はじめに眞子さんが「複雑性PTSD」だと発表されても、報道が沈静化する様子はさほど見られなかった。
この皇族だった眞子さんの立場で思い起こすのは、1998年に公開されたハリウッド映画『トゥルーマン・ショー』だ。この作品は、生まれたときからその生い立ちをテレビのリアリティ番組でずっと放送されている青年・トゥルーマン(ジム・キャリー)の物語だ。
サラリーマンの彼は、生まれたときから離島の街・シーヘブンから出たことはない。だがこの島は、実は巨大な人工のドームに造られた仮構の街だ。トゥルーマンは、いたるところから小型カメラで撮影されており、その姿が24時間放送されている。周囲の人物はすべて仕込まれた番組の出演者で、彼の妻もわざとらしく商品名を連呼する。しかし彼は、自分の人生そのものが番組であることを知らない。
このリアリティ番組のプロデューサーであるクリストフ(エド・ハリス)はこう述べる。
「俳優の作り物の感情はもう飽き飽きだ。派手な爆破や特殊効果も。このショーでは、世界そのものは作り物だがトゥルーマンは偽者ではない。台本やカンペはない。シェイクスピアには劣っても、本物の人生だ」
ここからは映画『トゥルーマン・ショー』の結末に触れます
「皇室ショー」からのレリゴー
昨年イギリス王室から離脱し、メーガン妃とともにカナダに移住したヘンリー王子は、激しい報道に晒された自らの立場を「『トゥルーマン・ショー』と動物園を混ぜたようなものだ」と例えた(※4)。どこに行っても注目され、その一挙手一投足がゴシップの燃料となる。
小室眞子さんも同様だ。特権的身分の皇族や王族に生まれるのは、自由がまったく保証されない不運を持ち合わせることも意味する。生まれたときからその成長のプロセスを追われ、しかも結婚以外では皇族からは離脱できない。たとえ離脱しても日本に留まれば、今後も好奇の視線を送られ続ける。まるでトゥルーマンだ。
映画『トゥルーマン・ショー』の主人公は、徐々に自分の生きている空間の奇妙さに気づき、島から脱出することを模索するようになる。視聴者はそれが30年続いた番組の終了を意味することを理解しながらも、彼の決断と勇気のある行動に心動かされそのプロセスを見守る。
眞子さんの今回の結婚とニューヨーク移住が一部から高く称賛されるのも、彼女がこの「皇族ショー」から離脱する英断をしたからだ。そこでは、眞子さんに『アナと雪の女王』のエルサの姿を重ねるひともいる。つまり、レリゴーである、と。
そして眞子さんの出国を見送るひとびとと、『トゥルーマン・ショー』で番組を観ながら涙を流すひとびとがオーバーラップする。

が、映画『トゥルーマン・ショー』の真のラストは、そうした感動的なシーンではない。
さきほどまで同僚といっしょにピザを食べながら、トゥルーマンの脱出を見届けてハイタッチをしていた警備員ふたりは、番組が終わった瞬間にこう言う。
「ほかの番組は? テレビガイドはどこ?」
みんな、次のビッグウェイヴを待っている──婉曲的な自己主張をするために。
- ■注釈
- ※1:終戦から間もなくは、雑誌を中心に昭和天皇についてのゴシップ表現も多く見られたが、1961年の「風流夢譚」事件をきっかけに弱まっていく。
- ※2:Jessica M. Goldstein 'Gossip explains our culture. And nobody explains it like Lainey Gossip.' 、The Washington Post' 2018年5月11日。
- ※3:メディア研究者のエリン・マイヤーズは、「ゴシップは、自分自身の社会的立場や関心をもとに、情報を位置づけ、解釈し、変換することに関係する日常的なコミュニケーションのインフォーマルな様式」とまとめている。Erin A Meyers 'Gossip Talk and Online Community: Celebrity Gossip Blogs and Their Audiences'、2010年。
- ※4:「王室で育つのは『動物園』のようなもの、英ヘンリー王子が生い立ち語る」、『CNN.co.jp』2021年5月15日。
■関連記事
・出演者の“人格”がコンテンツ化するリアリティ番組が生んだ悲劇(2020年5月27日/『ハフポスト日本語版』)
・「怒り」を増幅させるSNSは、負のスパイラルを描いたまま2020年代に突入した(2020年5月25日/『Yahoo!ニュース個人』)
・保守派を困惑させた天皇陛下の「おことば」──二度目の「人間宣言」が巻き起こした波紋(2016年8月12日/『Yahoo!ニュース個人』)
・「残酷ショー」としての高校野球(2014年8月31日/『Yahoo!ニュース個人』)
・リアリティショーとしてのAKB48:峯岸みなみ丸坊主騒動の論点〈1〉(2013年2月5日/『Yahoo!ニュース個人』)










