大阪桐蔭の初代部長が明かす草創期。目指したのはPL学園に負けないチームだった

前身は大産大高の大東校舎
言わずと知れた高校野球の強豪-。大阪桐蔭高校の名は、野球にさほど関心がない層にも浸透している。甲子園での優勝回数は春4回、夏は5回。現在行われている春の選抜でも優勝候補の一角に挙げられている。
ただ、創部の経緯や、草創期についてはあまり知られていない。
大阪桐蔭に野球部が誕生したのは1988年だ。この年の2月に、大阪産業大学高校(現在の大阪産業大学附属高校)の大東校舎(臨時分校)が大阪桐蔭高校として独立したのを機に創設された。野球部のメンバーになったのは、大東校舎に在学していた大産大高の部員であり、一期生には元中日ドラゴンズ投手で、NPB通算91勝の今中慎二らがいた。
初代監督を務めたのは長澤和雄。関西大学では中軸打者で全国優勝を経験し、社会人・大丸(81年限りで活動停止)時代は全日本で四番を打った。
そして、長澤とともに草創期の大阪桐蔭を支えたのが、初代部長を務めた森岡正晃である。今年1月に「日本一チームのつくり方:なぜ、大阪桐蔭は創部4年で全国制覇ができたのか?」(あさ出版)を上梓した森岡は、近畿大学2年時(82年)より、PL学園高校時代の恩師でもある大産大高の山本泰監督(旧姓は鶴岡)のもとでコーチをしていた(近畿大学卒業後は教諭として大産大高に赴任)。

文字通り、ゼロからのチーム作りとなったなか、まず力を入れたのが、生徒募集である。練習グラウンドや遠距離通学者のための寮など、施設は用意されていた。野球道具は大産大高が所有していたものを半分、譲り受けたという。
生徒募集を委ねられた森岡が求めていたのは、ランクでいうなら「S」クラスの選手。PL学園出身の森岡は、柱となる選手がいなければ、超激戦区・大阪は勝ち抜けないことをよくわかっていた。新設校の野球部ではあったが、最初から視座は高かったのだ。
とはいえ、当時の大阪桐蔭はまだスタートしたばかり。初めて出場した夏の大阪府大会では初戦(2回戦)敗退だった。実績もない新しい学校に行きたい、という有望選手はなかなか現れなかったようだ。「中学野球の指導者に挨拶をしても、大阪桐蔭?ああ、(大産大高の)大東校舎の学校ね、という感じでしたね」(森岡)。
難航していた生徒募集に光が差す
それでも、リクルートの方針がぶれることはなかった。母校・PL学園に負けないチームを作りたい―。大阪桐蔭が創立された前年(87年)、PL学園は甲子園で春・夏連覇を成し遂げていた。
森岡自身の想いもあった。PL学園3年時(80年)は主将兼投手だった森岡は、高校時代に甲子園の土を踏んでいない。
在学当時のPL学園も強かった。2学年上の代は西田真二(元広島東洋カープ、現・セガサミー監督)と木戸克彦(元阪神タイガース、現・阪神タイガースWomen監督)のバッテリーで夏の甲子園で優勝。主砲・小早川毅彦(元広島東洋カープ)を擁した1学年上は春の選抜でベスト4に進出し、吉村禎章(元読売ジャイアンツ)らがいた2学年下は選抜で全国制覇を果たした。
甲子園で勝つのが半ば当たり前だった時代に、名門・PL学園の主将を任されながら、甲子園に導くことができなかった…。その悔しさ、挫折感は深く胸に刻まれたという。
「いまでも残ってます。近大2年の時にケガで選手を諦めたとき、松田博明監督(当時)の後押しもあって、指導者の道を選んだのも、それがあったからです。指導者になって甲子園に行きたい、と」

生徒募集が難航していたなか、初めて大阪桐蔭を志願したのが、井上大(東洋大学監督)だった。井上は大東畷ボーイズに所属していた中学時代からスラッガーとして名を馳せていた。実家は大東市にあり、大阪桐蔭が地元の学校であるのも決め手になったようだ。森岡は「井上が行きたいと意思表示をしてくれたことで、生徒募集の潮目が変わりました」と言う。
井上が行くならと、小、中でも一緒だった萩原誠(元阪神タイガース)が続き、その噂を聞きつけた玉山雄一も志望校を大阪桐蔭に変えた。京都ファイターズでプレーしていた玉山は大阪桐蔭では主将になるが、もともと他の学校を希望していた。
気持ちが強い選手が集まった
中学硬式で活躍している選手は横のつながりが強い。まだインターネットは普及していなかったが、大阪桐蔭という新しい学校に全国レベルの選手が行くらしい…という情報はどんどん広まっていった。森岡の自宅近所に住んでいた投手の背尾伊洋(元近鉄バファローズ)、捕手の白石幸二、遊撃手の元谷哲也も後を追うように、当時創立1年目だった大阪桐蔭に進路を定めた。
「この3人が入学を希望したことで、守りの要であるセンターラインが揃ったのは大きかったです」
森岡がPL学園時代に叩き込まれたのは守りだった。「逆転のPL」が代名詞のPL学園には強打のイメージがあるが、「打ち勝つのではなく、守り抜く。目指していたのは負けないチームでした」。

大阪桐蔭が第一希望ではなかった選手も少なくなかったが、創立2年目の「89年度入学組」は多士済々であった。まだ無名だった大阪桐蔭で甲子園に出る、という決意を持った選手たちが集まったのである。井上、萩原、澤村通の3人が1年夏からレギュラーで出場するなど、「3年計画」で育成されたこの代は2年後、91年春の選抜初出場(ベスト8)と、同夏の甲子園大会初出場初優勝の担い手となった。
もし生徒募集の方向性が途中でぶれていたら、91年夏の快挙は成し得なかっただろう。
彼らのほとんどは気が強かった。それは森岡が望んでいたことでもあった。
「向こう意気が強く、折れない自信を持っている選手が来てくれたら、と。そういう子は試合でも物おじしないので、力を発揮できるのです。夏の甲子園で初出場初優勝ができたのも、気持ちが強い選手が揃っていたからかもしれません」
創部4年目での全国制覇から30年以上の時が流れたが、大阪桐蔭はいまも、気持ちが強い選手が多いと聞く。
そういえば、昨年まで侍ジャパンU-18日本代表でヘッドコーチだった岩井隆(花咲徳栄高校監督)は、同チームで指導した大阪桐蔭の前田悠伍投手(当時3年、今年よりオリックス バファローズ)をこう評していた。
「いつ状態を聞いても『任せてください』と言うんです。自分なら絶対にできるという、根拠のない自信があるのでしょう」
母校に対するプライドが歴史を作る
森岡は部長ではあったが、ヘッドコーチの役割も担っていた。当時は20歳代と若く、選手とともにグラウンドで汗を流した。89年度入学組の選手にも兄のような感じで接し、グラウンド以外でもコミュニケーションを取った。特に心を砕いたのが、大阪桐蔭の選手である誇りを持たすことだったという。
「これはなかなか難しかったですね。PL学園なら、歴史と伝統があるので、自然とその一員であるプライドが養われるのですが…折々に、君たちが歴史を作るんだ、ということは言い聞かせました。それと、野球だけではダメやぞ、と。学校生活など、当たり前のことをきちんとやりなさいと、これも口酸っぱく伝え続けました」
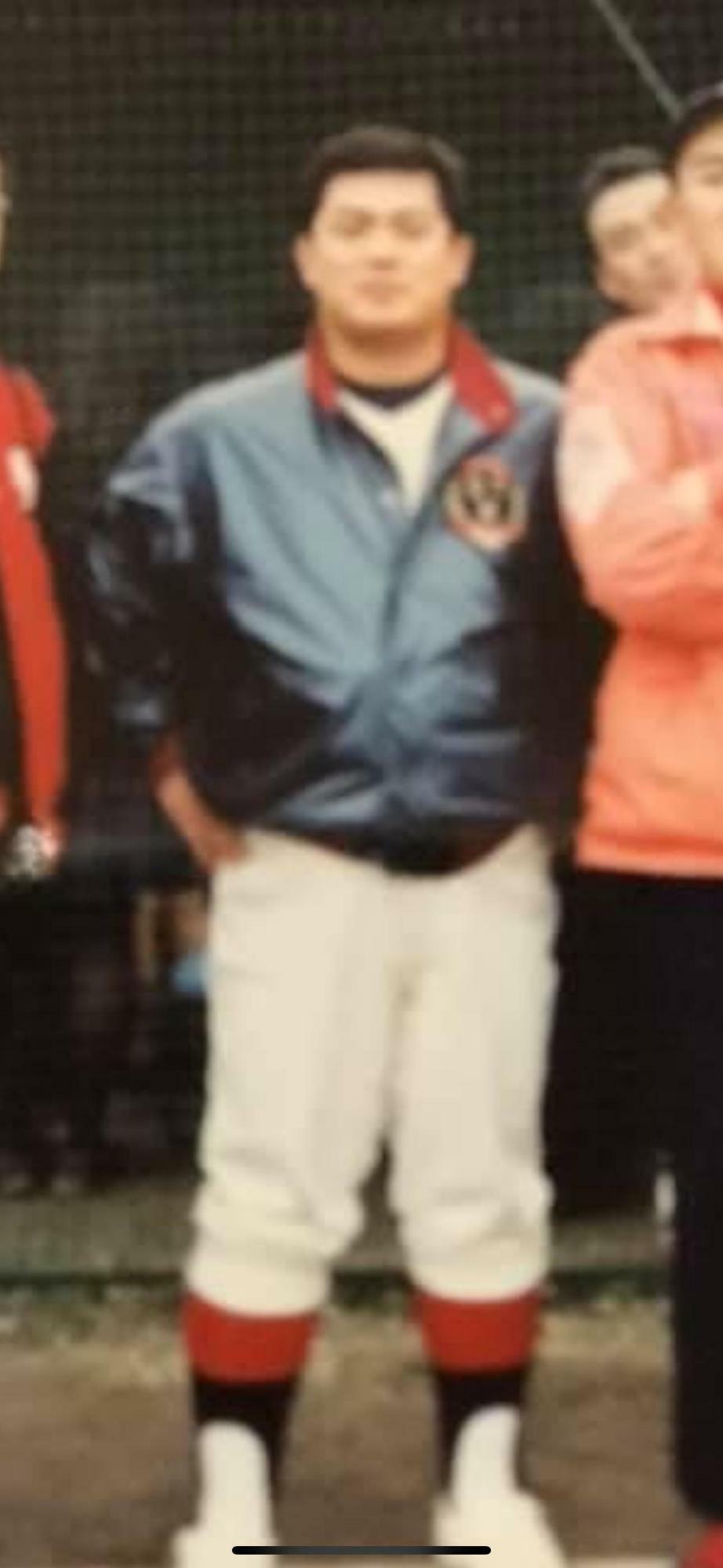
一方で、「89年度入学組」の選手にレギュラーの座を奪われた上級生もいた。もとは大産大高の野球部員だった生徒たちである。チームに不協和音が生じないよう、彼らに対しても心を配った。
「上級生は(89年度入学組の)実力は認めてましたが、胸中は複雑だったと思います。新しい歴史を作るには1年生の力が必要だから…という話はよくしましたね」
途中から環境が変わった現実に向き合っている気持ちも察した。森岡も立場的には近かったからだ。もともと、PL学園時代の恩師・山本のもとでやりたいと大産大高の指導者になった。大阪桐蔭への異動が決まった当初は、受け入れ難い心境だったという。
「3年計画」が実を結び、91年夏の甲子園で日本一になったとき、森岡の心を占めたのは達成感ではなかった。
「やった、という喜びもありましたが、むしろ、明日はもうこの子らと甲子園で野球ができないんだな、という寂しさのほうが大きかったですね」

森岡は、大阪桐蔭が創部4年目での快挙を果たした翌年から、同校のラグビー部の指導に携わった。異種競技でも指導手腕を発揮した後、2009年より履正社国際医療スポーツ専門学校野球部のGM兼監督や、大阪学院大学の野球部総監督などを歴任。現在は、行政や公的機関が主催するイベントのアドバイザーや、ベースボールアドバイザーとして、小、中、高の学生に対する指導などを行っている。

「いまも甲子園に来るたびに、ここは(試合を)観るためではなく、出るために来る場所だと思うんです」と語る森岡。その目には現在の大阪桐蔭がどのように映っているのだろうか。
「かつてのPL学園がそうだったように、周りから“勝つのが当たり前”と見られるなかで、勝ち続けるチームになりました。これは並大抵なことではありません。監督である西谷浩一先生と、創部時からコーチとして指導していた有友茂史部長の尽力の賜物だと思います」
草創期にPL学園に負けないチームを目指した大阪桐蔭。歴史を上書きするための戦いは続いている。
(文中敬称略)










